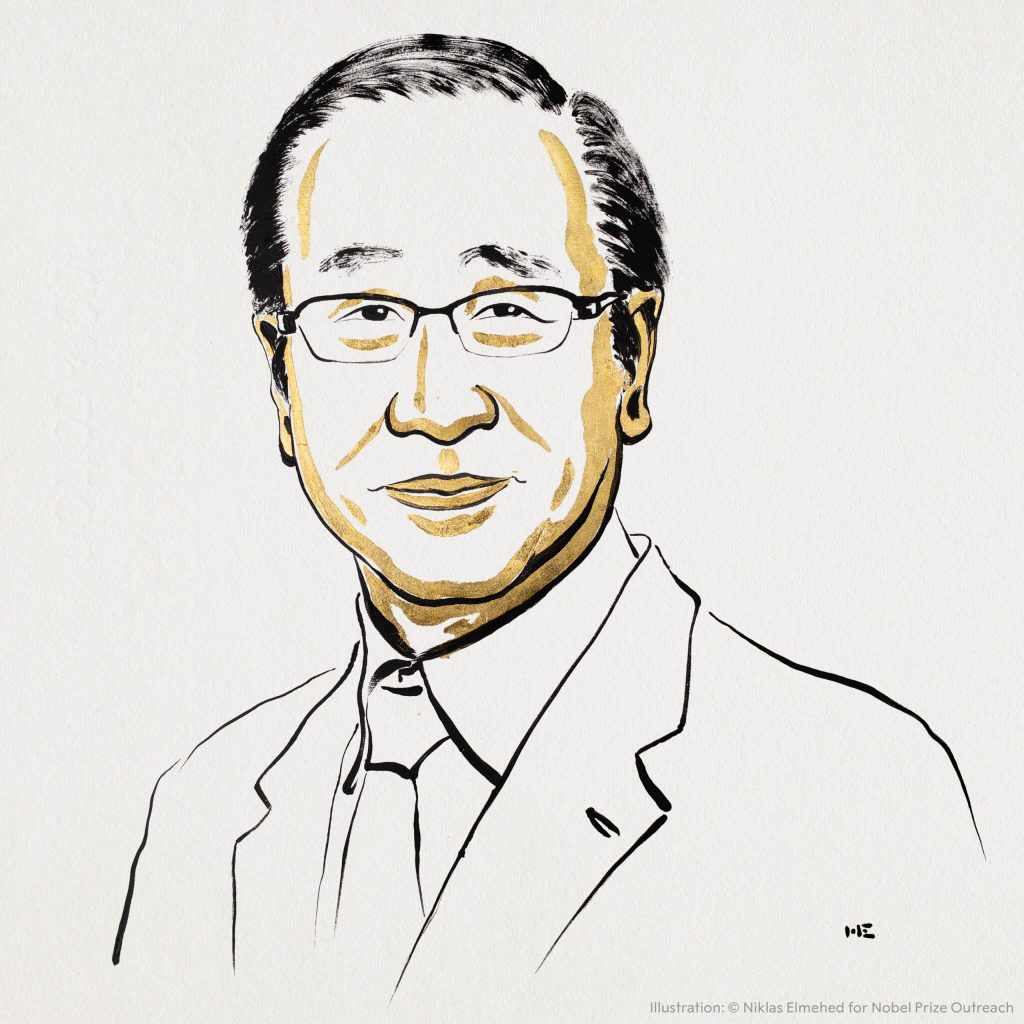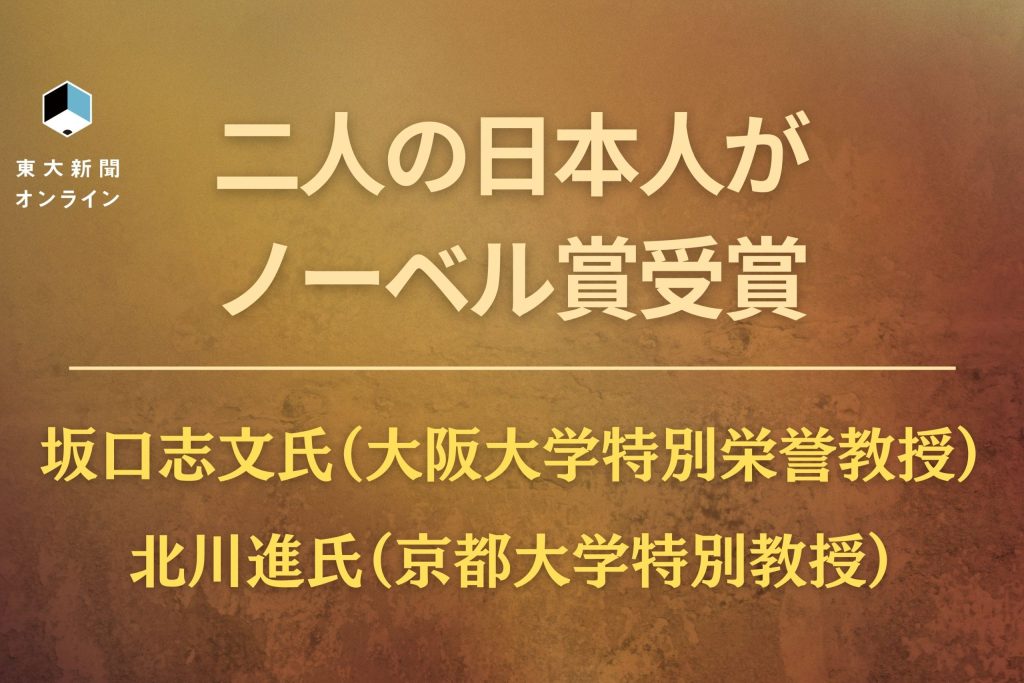
10月にスウェーデン・カロリンスカ研究所とスウェーデン王立科学アカデミーが今年のノーベル賞受賞者を発表し、2人の日本人が栄誉ある賞に選ばれた。坂口志文(しもん)氏(大阪大学特別栄誉教授)は制御性T細胞の研究の功績でノーベル生理学・医学賞を、北川進氏(京都大学特別教授)は金属有機構造体の研究の功績でノーベル化学賞を受賞することが決定した。ノーベル生理学・医学賞の日本人受賞は18年の本庶佑氏以来7年ぶり、ノーベル化学賞は19年の吉野彰氏以来6年ぶりの快挙となる。授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われた。(執筆・吉田直記)
ノーベル生理学・医学賞
坂口志文氏が免疫の「ブレーキ」解明で受賞 制御性T細胞が開く未来
人間の体は常に微生物からの侵入にさらされているため、複雑な免疫システムが生体防御の大切な役割を果たしている。免疫には自己と非自己を見分けるシステムが備わっていて、病原体や異常細胞は排除するが自己の細胞は攻撃しない。このおかげで私たち人間は健康に生きていくことができる。しかし、免疫系が自分自身の細胞を敵とみなして攻撃して起こる自己免疫性疾患や、特定の抗原に対する過剰な免疫反応であるアレルギー疾患も存在する。免疫学においては免疫を促進するだけでなく抑制する仕組みの解明も重要な課題だった。
今回ノーベル生理学・医学賞に選ばれた坂口氏の研究によって、1980年代から90年代にかけて免疫制御の研究分野が活気付いた。免疫細胞が分泌する情報伝達物質にインターロイキンというタンパク質があるが、坂口氏は95年にインターロイキン2受容体のα鎖であるCD25を発現するT細胞が免疫抑制機能を持つことを明らかにした。これはCD25が制御性T細胞の特異的なマーカーになるという重要な結果を示している。制御性T細胞という用語は70年代から使われていたものの、坂口氏らの研究成果によってその実体と生理的役割が確立したことで、広く受け入れられるようになった。免疫学の根幹にかかわる免疫寛容(自己の細胞や病原性を持たない異物に対して免疫反応を抑制すること)の問題に新たな展望が生まれ、世界中の科学者たちがこの分野に参入するようになった。
01年には2人の研究者が特定の遺伝子に変異を持つマウスが自己免疫疾患にかかりやすいことを発見し、この遺伝子をFoxp3と名付けた。この2人の研究者こそ、坂口氏とともにノーベル賞を受賞するメアリー・ブランコウ氏とフレッド・ラムズデル氏である。坂口氏はFoxp3が自身の研究につながることも証明し、免疫学における重大な発見を見事に結び付けた。これらの功績をたたえて、坂口氏らに今年のノーベル生理学・医学賞が授与された。

ノーベル化学賞
北川進氏が金属有機構造体の研究で受賞 多様な用途で広がる夢
20世紀に入ると構造化学の分野は大きく発展し、多くの新しい構造が研究されるようになった。70年代になると、後に北川進氏とともにノーベル賞を受賞するリチャード・ロブソン氏が革新的な立体化学構造を考案した。それは、ダイヤモンド構造(各炭素原子が4つの原子と結合して四面体をなす構造)のような、正に帯電した銅イオンとニトリル基で構成される立体構造であった。この時点ではもろく不安定な構造だったものの、内部に多数の大きな空洞を有する点で将来性があるものだった。
90年代には北川氏やオマール・ヤギ氏がより安定な立体構造の作成に成功する。北川氏らが考案したこの構造物は、金属イオンを利用して、有機化合物が3次元的に組み上げられて構成されるため、ナノメートル単位の微小な多孔構造を無数に有するという重要な特徴があった。これは柔軟性があるだけでなく、その間隙に気体を吸着・貯蔵できるなど多彩な機能を持ち、金属有機構造体(MOF, Metal–Organic Frameworks)と呼ばれるようになった。
この画期的な研究の広がりを受けて世界中の科学者たちが研究を重ね、現在までに数万種類以上もの金属有機構造体が開発されている。これらの中には、水から有機フッ素化合物(PFAS)を分離したり、環境中の微量医薬品を分解したりするほか、二酸化炭素を回収したり、砂漠の空気から水を採取したりするといったさまざまな用途がある。人類が直面する環境保全やエネルギー問題への貢献も期待されている。これらの功績をたたえて、北川氏らに今年のノーベル化学賞が授与された。