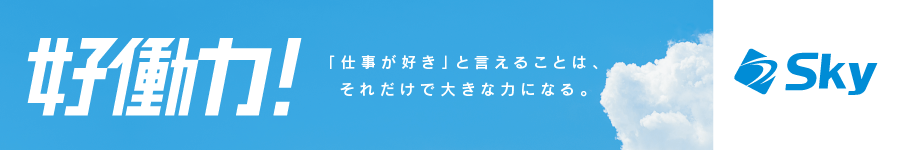「この世界において、すべては、一巻の書物に帰着するために存在する」。19世紀フランスの詩人ステファヌ・マラルメの言葉だ。この一文でさえその真意を理解しようとすれば万巻のマラルメに関する研究書や論文が必要だろう。だが紙幅と何よりも能力の問題から、ひとまず学生が教科書の偉人の肖像に落書きをするような気ままさで、この言葉を次のように読み変えながら本の世界の広がりについて考えてみたい。「一冊の書物すら、達するためには世界の全てが必要だ」と。
(構成・渡辺明日翔)
本から本へと「渡り読む」ことの意味
外国語の書籍を考えるのが最も分かりやすい。今、目の前に戯曲『リチャード三世』の原書があるとしよう。この15世紀イングランド宮廷の、権謀術数が張り巡らされた政争を題材に採り1世紀後のシェイクスピアが執筆した作品を、21世紀に生きる日本人がそのまま理解できるだろうか?
いや、まずは辞書が必要だろう。それも、シェイクスピアの時代の英語は今日の英語と大きく異なるため一般的なものよりも詳細な辞書や文法書が望ましい。坪内逍遥、福田恒存(つねあり)、松岡和子といった先人がどう日本語に訳したかを参考にするのも重要だ。さらに当時の文化、社会、政治など作品の背景も知る必要がある。だが複雑なことに、ここでは少なくとも作品の舞台と執筆時という二つの「当時」の背景が問題になる。シェイクスピアに限らず、作品の舞台や主題の持つ背景とその執筆者の背景は多くの場合、単に時代だけでなく社会のシステムや状況、文化、地理などさまざまな基準において遠く隔たっているからだ。このように考えると1冊の本を理解するにあたっても、参照すべき他の本は際限なく挙げることができると言える。
このような読書を煩わしく、シェイクスピアを専門にする研究者など限られた人にのみ必要なスタイルだと考える人もいるかもしれない。だがまずは同じシェイクスピアからでも別の一冊を読んでみよう。例えば『冬物語』を読み、彼が現実では内陸の国であるボヘミアを海に面した国として描いていることを知っていれば『リチャード三世』が正確に歴史を描いた作品であると誤解してしまうリスクを回避できるし、シェイクスピアほどのビッグネームも誤ったことを書くという教訓も得られる。またリチャード三世を戦いで破りイングランド王となったヘンリー七世の孫がシェイクスピアの時代のイングランド女王エリザベス一世であることを踏まえていれば、こうした執筆時の政治状況がリチャード三世とヘンリー七世が登場する戯曲を書くシェイクスピアにとって大きな制約であったと推測し、作品の裏側にもドラマを想像することができる。このように1冊の本も、他の本を通じて得られる知識のおかげでより正確に、あるいはより楽しんで読むことができるようになる。
一冊の本についても他の本や批評を通じてより多くの知識や視点を持つことで、その本の世界は「巨人の肩の上に立つ」ように見通しが良くなる。このことを基本とすることで初めて自分なりの独自な読み方ができるようになるとする北村紗衣『批評の教室-チョウのように読み、ハチのように書く』(ちくま新書)は間違いなくあなたの本の読み方自体を変える一冊だ。
武蔵大学准教授としてシェイクスピア受容やフェミニズム批評を専門に研究と教育を行う一方、文学や演劇、映画などさまざまなメディアの作品について豊かな知識を持ち批評を実践している著者ならではの視点で、シェイクスピアの演劇から映画マーヴェル・シリーズ、ロック・バンドのザ・ローリング・ストーンズの歌詞まで幅広い対象を例に精読、分析、批評の執筆のステップについて紹介している。
これに加え、本書の最大の特徴は著者と著者が大学で教える学生が同じ映画についての批評を書き、互いにコメントを加え、対談を行っていることだ。この箇所は同じ作品に関しても批評者の切り口や視点によって全く違う批評が生まれることを示しており、本書で紹介されている批評の技術を押さえればいかに自由に批評を書くことができるか、格好の例となっている。
北村の本が具体的で、より実践的な技術やノウハウを中心に紹介している一方、批評という営みがどのように多様に理論化されてきたかという、より抽象的なテーマについて俯瞰(ふかん)した一冊が廣野由美子の『批評理論入門-『フランケンシュタイン』解剖講義』(中公新書)だ。本書では登場人物の視点の焦点や作品内の時間の流れ方といった小説の技法と伝統批評、精神分析批評、ジェンダー批評、文化批評といったさまざまな批評理論の歴史と概要を整理している。
副題が示している通り、本書では『フランケンシュタイン』という一つの作品について、異なる批評理論を用いた多様な解釈や批評がなされてきたことが紹介されている。200年前の小説が読者の視点次第で当時の知識体系や社会状況を色濃く反映した作品、今日的なジェンダー、フェミニズムに関する論点を含んだ作品、あるいはその後のハリウッド映画といった大衆文化にさまざまな影響を与えたインスピレーションの源と、大きく異なる姿を見せることが分かる。
ちなみに本書のあとがきで触れられているように、この書籍の執筆の着想の一つはBedford/St. Martin’sという出版社から刊行されたCase Studies in Contemporary Criticismというシリーズに得ている。英語の書籍に挑戦したい方やシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』、ジェイムズ・ジョイスの『若い芸術家の肖像』など『フランケンシュタイン』以外のさまざまな文学作品を通じ多角的な批評を知りたい方には、このシリーズもお薦めだ。
世界の中の書物、書物の中の世界
ところで本記事では書物や本といった言葉を平然と、繰り返し用いてきた。が、当然ながら書物は歴史上のある時点で発明されたもので、また発明時から現在に至るまで古今東西の社会でその形態や機能を変えてきたものだ。そうした書物の歴史と現代における意味を問うたのが、社会のデジタル化が加速していた2005年から東京外国語大学で開講されたゼミナールを基に書かれた『身体としての書物』(東京外国語大学出版会)だ。
著者の今福龍太はその豊かな学識とともにさまざまな視点から書物へアプローチしてみせる。例えばフォント。中世ヨーロッパの書物において用いられていたのは中世ゴシック体というフォントで、極めて読みにくい。それは、聖書のような宗教テクストは神聖なものであり、気軽に読むべきものではなかったということ、またフォントの重厚さが教会の権威を示していたためだった。一方、従来に比べ運びやすい小型本とともに登場したイタリック体は中世ゴシック体に比べ読みやすく、かつ同じ紙の分量により多くの文字を印刷することができるフォントだ。この小型本と新たなフォントの登場により書籍はより安く便利なものとなり、より多くの人のもとへ本が届くようになった。社会が書物に求める機能や意味の変化が書物というメディアの形の変化にいかに現れ、書物というメディアの変化が書物の社会的な意味をいかに変えるかが示された例である。こうしたメディアとその内容の複雑な相互関係に対する視点を本書は全編を通じ与えてくれる。電子書籍へのアクセスがより簡便になった現在、たとえ同じ文字列を載せた本であっても紙で読むことと電子化されたデータを読むことで得られる経験が大きく異なるものであるという可能性を本書とともに考えたい。
今福は書物それ自体をテーマにした作品が多い作家であるアルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの小説「バベルの図書館」と「砂の本」の読解を上に紹介した書物で行っている。
「バベルの図書館」はアルファベットとピリオド、コンマ、スペースを合わせた25文字で可能な組み合わせの全てを本にすることによって、現存しないはずのテクストを含め過去に書かれたものから未来に書かれるはずのものまであらゆる言語で表現可能な書物の全てを所蔵する図書館を描き、書物の中に世界そのものが吸い込まれるような世界観を示している。これと対象的に「砂の本」ではたった一冊の中にページが無限に存在し、まさに砂にのみ込まれるような本の世界を描いた。
こうした、短編ながら難解で複雑な示唆を含む作品を多く残したボルヘスが、古今東西の文学について語っているのが『七つの夜』(岩波書店)だ。本書は講演が基となっているということもあり、彼の作品とは対象的に暖かく平明にダンテの『神曲』、『千一夜物語』、仏教といったテーマについて語る。が、各講演でボルヘスは「今、思い出しましたが……」といった口調でテーマから脱線し、例えば仏教と聖書の逸話、プラトンら古代ギリシア哲学を縦横無尽に結び付けていく。『語るボルヘス-書物・不死性・時間ほか』(岩波文庫)という別の講演録で、彼は「古い書物を読むということは、それが書かれた日から現在までに経過したすべての時間を読むようなもの」と言っている。これらの講演録でボルヘスが披露する知識の該博さは、ボルヘスこそが、ちょうど彼の作品が主題としたように、これまで書かれた膨大な数の書籍のしるしが刻まれた一冊の本であるかのように読者に錯覚させる。
20世紀フランスの批評家ロラン・バルトはこう書いている。「ある作品が『永遠』であるのは、それがさまざまな人間にたった一つの意味を課すからではなく、(中略)たった一人の人間にさまざまな意味を暗示するからなのだ」と。廣野の『批評理論入門』が示すように、『フランケンシュタイン』のような優れた作品は批評理論に応じて異なる姿を見せる可能性を秘めている。これに付け加えるならば作品、すなわち書物とは孤高の存在ではなく、むしろ他の書物との関係においてこそ新たな意味を絶えず獲得し続けており、故に永遠であるとも言える。読者がそれまで読んだ本によって新たに読む本の意味を変え、新たに読んだ本によってかつて読んだ本の意味が変わることもある。今回紹介した本は全ていわゆるフィクションではないが、読む人によって感銘を受けたり興味深いと感じたりする点は異なるはずだ。今回紹介した本を、読者それぞれの興味関心から新たな本とつなげ、本の世界を広げてみてほしい。
読書マップ