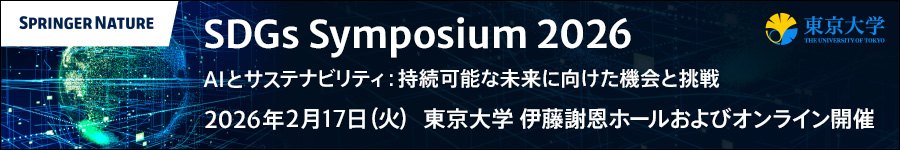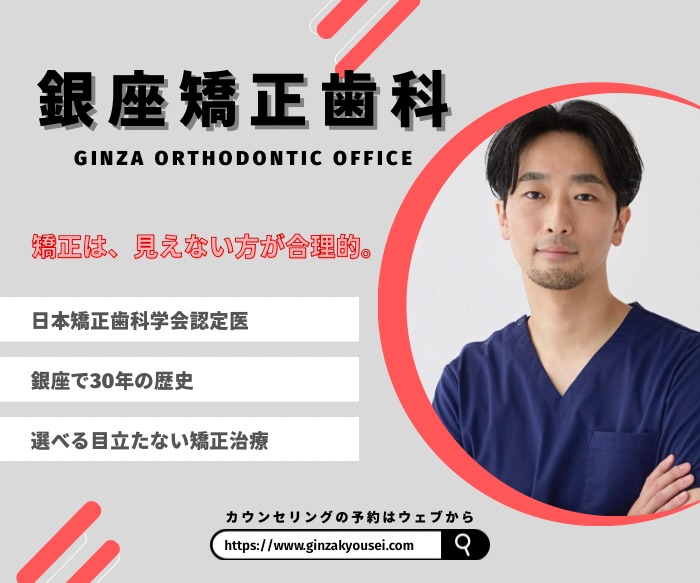東大先端科学技術研究センター(先端研)は6月10日、フィンランド大使館と共催で、フィンランドのアレクサンデル・ストゥブ大統領を迎えた公開シンポジウム「地政学と多国間秩序の変容」を開催した。
会場の駒場ⅡキャンパスのENEOSホールは、定員172名に迫る来場者で埋まり、日英同時通訳付きで進行された。井形彬・特任講師(先端研)が司会を務めた。開会にあたり、藤井輝夫総長と先端研の杉山正和所長が挨拶。その後ストゥブ大統領が基調講演を行い、質疑応答が行われた。

ストゥブ大統領は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで博士号を取得した研究者でもあり、欧州議会議員やフィンランドの首相・財務大臣などを歴任。フィンランドは2023年4月、第二次大戦後続けてきた中立の方針を転換し北大西洋条約機構(NATO)に加盟したが、大統領はNATO加盟の初期段階からの支持者であり、ロシアによるウクライナ侵攻にも強く反対の立場を取る。講演では自由民主主義と人権を重視する日・フィンランド両国の連携強化の必要性が強調された。講演の翌日の6月11日には、ストゥブ大統領と石破茂首相との間で「日本国とフィンランド共和国との間の将来における協力強化に関する共同声明」が署名されている。

「転換点」としての「2月24日」 1945年ではなく2025年の現実を反映した秩序を
ストゥブ大統領は、第二次世界大戦後のリベラルな多国間秩序が大きく揺らぐ現状を「転換点」と表現。その象徴的な出来事として、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻を挙げ「国連安全保障理事会(安保理)の常任理事国が、国連の理念を真っ向から否定する行為に出た」と語った。
世界情勢はウクライナに留まらず、ロシア・ウクライナ戦争への北朝鮮兵の参戦、中東の混乱、南シナ海での対立など、世界全体が分断と対立の様相を強めていると指摘。こうした状況のなか、新たな多国間秩序の構築が不可欠であり、それは「1945年ではなく、2025年の現実を反映したものであるべきだ」と提言した。
多国間秩序の再構築へ:秩序・バランス・ダイナミクスの三本柱 安保理の常任理事国追加にも言及
講演の中盤では、現代の多国間秩序の構造を「秩序(order)」「バランス(balance)」「ダイナミクス(dynamics)」の3つの観点から整理。冷戦時代の二極構造、そして米国主導の一極体制を経て、現在は多極的な競争と地域紛争の時代に移行していると解説した。
特に「バランス」に関して、国際社会を「グローバル・ウエスト」(米国、欧州、日本、豪州など約50カ国。現秩序の維持を目指すが、米国のリーダーシップの不透明さが懸念材料。)「グローバル・イースト」(中国寄りの25カ国。イランやロシアなど、価値観よりも利害関係を重視し、現秩序の変更を志向。)「グローバル・サウス」(インド、ブラジル、ナイジェリア、サウジアラビアなど約125カ国。人口増加と経済成長により、今後の秩序を左右する鍵となる存在。)の3つに分類。ストゥブ大統領は、これらの勢力バランスを調整するため、国連安全保障理事会における常任理事国の拡大が必要だと主張。具体的には、ラテンアメリカ1枠、アフリカ2枠、アジア2枠の追加を提案した。
競争から協力へ ダイナミクスの転換
国際関係の力学については、「競争」「紛争」「協力」という3段階を示した上で、現在は紛争のフェーズが拡大していると指摘。イスラエル・パレスチナ、ロシア・ウクライナ、スーダンなどの地域紛争が、国際秩序を脅かしているとした。
こうしたなかで必要なのは、国際機関を軸にした「協力」へのシフトであると訴えた。「いま世界は協力しているとは言いがたい状況だが、それでも制度的信頼を回復し、衝突を抑制するためには、協力が不可欠だ」と締めくくった。
フィンランドと日本 協力の実例として
講演の最後には、1919年に外交関係を樹立した日本とフィンランドの関係を引き合いに出し、教育・技術・安全保障の分野での協力関係がいかに重要かを述べた。藤井総長も冒頭の挨拶で、東大のVTTフィンランド技術研究センターとの連携を含む共同研究の取り組みを紹介し、両国の協力の意義を強調していた。

質疑応答 観客との対話も活発に
講演後には約30分間にわたり質疑応答が行われ、ストゥブ大統領は学生や記者からの六つの質問に回答。通訳を担当した井形特任講師との掛け合いのもと、国際関係から具体的な制度改革案にまで及ぶ活発な議論が交わされた。