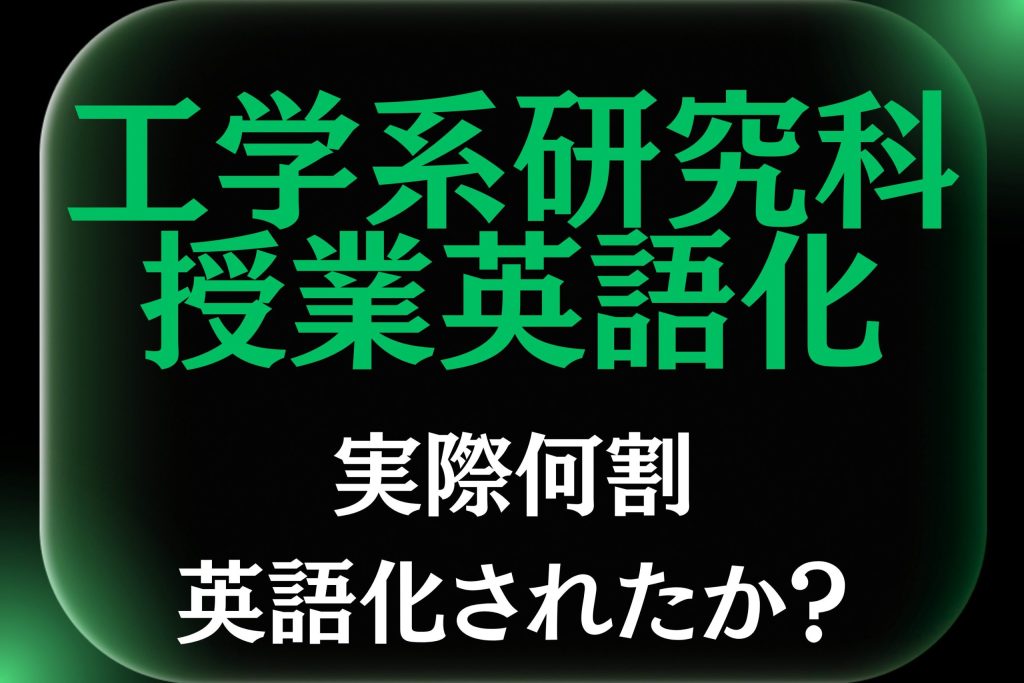
東大大学院工学系研究科は、英語で実施可能な授業について、2025年度から段階的に英語化し、26年度には原則英語で行う方針だ。なぜ英語化が必要で、歴史的にはどういう意味があるか、考える。(執筆・溝口慶)
英語化はなぜ必要になったのか
東大が育てる人材に求められる能力は、社会の変化に応じて変わってきた。そして今、工学分野では広く国際性が求められている。例えば工学の中で基礎科学に近い物理工学や計数工学などの分野では国境を越えた学術的な競争が展開されている。気候風土が重要な社会基盤学や都市工学などでは、アジアの研究ネットワークを通じた国際協力が重視され、システム創成学分野はグローバル社会特有の問題に取り組む。工業の応用に近い機械工学や電気電子工学などの分野では産業としての国際競争力も求められる。分野で事情は違えど、工学分野の国際的競争では英語が標準語だ。工学系研究科は「工学系から出されている原著論文のほとんどは英語です。日本人向けの総説・解説などの記事が日本語で執筆されているものが多い」という。
大学院で養われるのは専門分野の知識だけではない。英語で議論し、英語で研究発表し、英語で論文を執筆できるだけの能力が培われれば、研究職や専門職以外に就職しても将来役に立つ可能性が高い。
工学系研究科は英語化の理由の一つに学生の4割近くが留学生であることを挙げる。この数字は東大大学院全体の留学生率の平均が30%程度なのを上回る水準であり、工学系研究科は授業の英語化で留学生への教育効果が高まることが期待されるとしている。しかし、工学系の留学生の約9割はアジア出身だ。アジア出身の留学生の多くにとっては日本語も英語も母語ではないため、英語化が教育の向上につながるとは限らない点で課題が残る。ただ、日本人も留学生も同じレベルで議論ができるようになれば、多様な考えが交わりやすい環境が形成される。そして何より授業の英語化によって、アジア以外の、英語をよく話す国からの学生が増えれば、学生の複数性も高まることだろう。
英語化の現状
英語だけで学位が取得できるコースを全国で先駆けて設置したのも工学系研究科である。1982年には土木工学専攻(現・社会基盤学専攻)で英語の留学生特別コースを設置。アジアの開発途上国から多くの留学生が東大に来たことで、アジアにおける土木工学分野の人的ネットワーク形成に貢献した。こうした取り組みにより、社会基盤学専攻の博士課程では留学生が全学生の約4分の3を占めるほどに国際化が進んでいる。現在、工学系研究科は英語だけで学位を取得できるプログラムを9つ設けており、似た分野の東大大学院新領域創成科学研究科などでも同様のプログラムがある。
授業の英語化についても、工学系研究科では2010年頃より「バイリンガルキャンパス」の確立を掲げ、20年をめどに大学院の授業の5〜7割を英語とする構想も存在した。この方針を更新し、25年からは「授業の英語化をスタート」した。26年には「より多くの英語化が可能な授業について原則として英語で行う予定」だ。
では25年度の英語授業の割合はどの程度だったか。下の(表)にまとめた。

授業の使用言語の情報は、工学系研究科が各専攻の教員に対して行った調査に基づく。
(定員15名で留学生のいない原子力専攻は除いた。語学科目を含む工学系共通科目と社会人向けの都市工学専攻都市持続再生学コースの科目は含んでいない。)
工学系研究科によると、授業の英語化は専攻ごとに進められており、英語授業の割合の差は専攻ごとの「今までの取り組みの違い」だという。専攻ごとに英語が必要な事情は異なるため、数値に差が出るのも当然だが、ほとんどの科目が日本語で開講されている専攻もある中で、英語化の実現には困難が伴う。1年や2年の期間で拙速に授業を英語化して、授業の質が落ちては本末転倒だ。ある東大教授は教育や研究の質を維持するためには、教員も学生も、授業や発表のみならず、生活の場でも英語を使い能力の維持に努めることが大切だと指摘している。
日本の工学は全面英語で始まった
明治期の近代化にあたり必要な高度人材を確保するため、当初は外国人技師が雇われた一方、外国人教師による日本人学生への技術教育も図られた。東大工学部の前身の一つである工部大学校は、幕末に伊藤博文ら長州藩士が英国に留学したつながりで、スコットランド出身の英国人教師たちが基礎を築いた。ゆえに授業は全て英語で行われ、実験や寮生活でも英語が基本だった。日本の工学教育はそもそも全面的に英語で始まったのだ。
『東京大学百年史』は、東大が富国強兵政策と密接な関係にあったと記す。東大は官庁や産業界、陸海軍に指導的人材を送り込んできた。特に工学部門では、まずインフラ整備のため官業に人材・ノウハウを提供し、ついで鉱工業の発達に寄与した。例えば鉄道や電気通信、鉱山の近代化、造船、産業用の工作機械、工業製品の品質基準の制定などで大きく貢献した。当時の東大は海外から仕入れた先端知識を国内に普及させる役割を担っていた。そして教育から研究、実装まで全て国内で完結させたいと考えるのが自然だった。
そこで明治政府は、東大の前身の一つ、東京開成学校の卒業生を選抜し海外へ留学させた。この21人のうち、帝国大学工科大学(現・東大工学部)初代学長の古市公威を含む6人が後に東大教授となった。こうした人材により、日本の工学分野では外国人教師が日本人教師に置き換えられ、英語による教育も段階的に日本語へ移行していった。戦前の内は論文を英語で書く慣習は残り続けたものの、次第に工学部の卒業論文の英語のレベルは低下していった。

東大の役割がブレない英語化を
日本は欧米を追う形で近代化を進めてきた。これまでの東大は海外の知識を日本語に翻訳・吸収し、国内産業を発達させ、日本語で研究できる環境を整えてきた。日本語だけで博士号まで取得できる体制を構築した先人の功績は大きい。だからこそ長年日本語に置き換えてきたものを自ら捨て去るようにも映る授業の英語化は、確かに大きな歴史的変化に見える。こうした変化について、これまで東大が担ってきた日本の知を開く役割が縮小されかねないと批判するメディアもあった。
東大が育てる人材の持つ能力は、社会の変化に応じて変わってきた。かつては軍事技術の発展にも大きく貢献したが、東大はいずれの時代でも一貫して社会を率いる人材を送り出してきた。21世紀に授業が英語化されても、東大の役割が大きく変わることはない。以下は03年制定の東大憲章前文の言葉だ。
|
[東大憲章前文(一部抜粋)] 今、東京大学は、創立期、戦後改革の時代につぐ、国立大学法人化を伴う第三の大きな展開期を迎え、より自由にして自律性を発揮することができる新たな地位を求めている。これとともに、東京大学は、これまでの蓄積をふまえつつ、世界的な水準での学問研究の牽引力であること、あわせて公正な社会の実現、科学・技術の進歩と文化の創造に貢献する、世界的視野をもった市民的エリートが育つ場であることをあらためて目指す。 |
東大が育てるのは「世界的視野をもった」市民的エリートでなくてはならない。研究活動や経済活動のグローバル化に伴い、東大が育てる人材もそれに適した能力を備える必要がある。
授業の全面的な英語化が進むのは大学院の工学系研究科だ。大学院は、学部よりもさらに高度な、主に研究者や専門職となる人材を社会に送り出してきた。東大の大学院であるからには、世界の最先端を歩める人材を育てなくてはならない。そうでなければ、先端知を社会に実装するどころか、追随することすら困難になる。場をつくり、知をきわめ、人をはぐくむ。これが東大の基本方針、UTokyo Compassの3本の柱だ。 授業を英語に切り換えたら直ちに国際化が進むわけではない。日本語で行うべき授業もあるだろう。英語化が自己目的化するのではなく適切に行われ、将来的に東大生の複数性向上につながると期待したい。
東大の大学院生の約4分の1は工学系研究科に所属している。この変化が東大内に与える影響は決して小さくないだろう。
※2025年12月9日22時9分、(表)を差し替えました。差し替え前の図では工学系研究科便覧に依拠した情報を掲載していましたが、差し替え後の図では、工学系研究科が各専攻の教員に対して行った調査結果に依拠しています。











