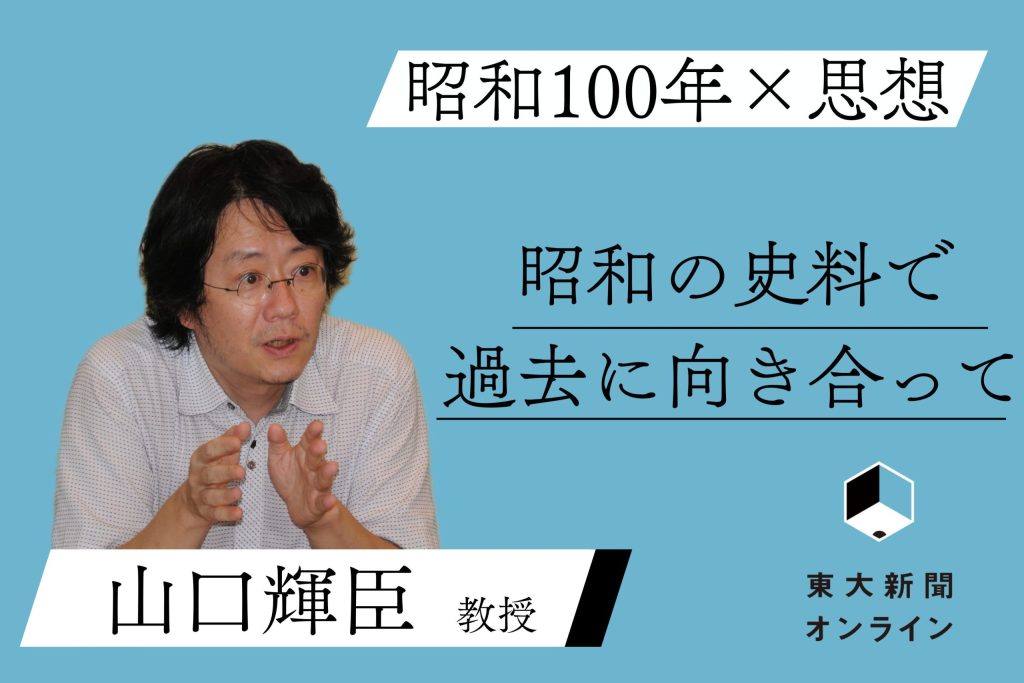
この100年、世相は劇的に移り変わり、主流の思想も同様に変化してきた。歴史学者はどのように過去を捉えてきたのか。我々は「昭和」をどう捉えれば良いのか。思想史を専門に研究してきた山口輝臣教授(東大大学院総合文化研究科)に話を聞いた。(取材・田中莉紗子)
変わる思想のトレンド、変わらぬ思想の形成プロセス
──昭和は激動の時代でした。そんな中思想の変化は
トレンドの思想は、時期によって大きく変化しました。例えば歴史学で戦前に華々しかったのは、後に皇国史観と呼ばれる、平泉澄(ひらいずみきよし)らが唱えたとされる見方です。元々明治時代の歴史学は、史料に書いてあること以外は一切認めない、厳格な史料実証主義でした。しかし、史料の背後にある人間の精神についても扱うべきだとの考えが強まり、さらに肥大化した結果、皇国史観がうまれてきます。精神について考える過程で、日本的な精神を見出していく。それが極端な形で発展した結果、不変の日本精神がずっと昔からあったかのようになってしまった。史料との整合性に難のある皇国史観はやがて、日本精神のために自分は戦争をしているんだという、真面目な学生が戦争で死んでいく理由の提示につながってしまいます。それが理由で皇国史観は戦後徹底的に批判され没落しました。
それに取って代わったのが戦後歴史学と呼ばれるものです。その中心にあったのは、マルクス主義的な歴史観、ちょっと古めかしい経済史でした。人間の行動は経済に規定され、それは階級を通じて現れると考え、事象の説明に応用する。戦後歴史学は、まだソ連が存在し、革命を目指している人も多かった時期に興隆した思想です。よって、ソ連が崩壊すると影響力を失いました。戦後日本の高度経済成長による変化は、革命なしでも社会は劇的に変わると示しました。革命を目指し戦後歴史学に取り組んでいた人たちは、その目標を失ったという見方もできるでしょう。
しかし、皇国史観、戦後歴史学などの思想を持つ人は全滅したわけではない。トレンドが変化して主流から外れても細々と形を変えつつ存続する。思想の面白さですね。
──逆に、一貫していたことは
思想の形成される過程は、大正の末から昭和の戦前期頃に本格的に始まった形が、昭和の間一貫して続きました。例えば総合雑誌で大学の知識人などが中心となり議論しトレンドが形成され、それが新聞などのメディアでも報道され、定着していく。これは、昭和より前や現在には見られない昭和に特有の形です。
思想の内容で言えば、昭和の間は一貫して、多くの思想家はマルクス主義を念頭に置きながら、それとの差異を通じて自分の思想を定位していました。例えば、マルクス主義は経済中心主義なので、精神や思想を研究対象とする皇国史観はマルクス主義に対する批判を含意している。リベラリストと呼ばれた丸山眞男(まさお)らも、共産主義者ではないがリベラルだという形で主張をしました。これまたソ連が崩壊して、平成以降はこの傾向は廃れますが。
宗教の概念は変化するも、その拡張は一貫
──宗教に関する変化は
神社神道は、戦前は宗教ではないと扱われていましたが、戦後は宗教とされました。宗教という概念は、明治時代にReligionという外来語を翻訳して生まれました。憲法で信教の自由を規定するため、当時の日本人は宗教とは何か、何が宗教で何が違うか考えました。その時、キリスト教や仏教と違い、わかりやすい教祖や教会組織、教典のない神道は、宗教ではないと考えられました。19世紀には、神道は宗教ではないという考えに、多くの人々が納得していたのです。
それに目を付けた神社関係者が、宗教ではないから皆が信じなければならないとの主張を普及させていきます。20世紀前期には、日本人なら仏教やキリスト教に加えて神道に敬意を払うものだという主張がほとんどの国民に受け入れられていきました。
しかし19世紀末から20世紀初期にかけて、宗教学が成立してくると、宗教についての考え方が変わります。個人の内面に基づく信仰が外に現れたものは宗教だと考えた宗教学者が、神道も宗教だと主張し、宗教の概念が広がっていくのです。すると、政策と宗教学者の主張との間にズレが生じ、さらには宗教ではないからこそ皆が崇敬しなければいけないと主張する神社と、それに抗う仏教の運動などさまざまな主張が混ざり合う複雑な状況が生じました。宗教として認められないと合法的に葬式ができなかった戦前において、既得権益を守りたい仏教側にも神道を宗教としない論理もありました。結局、政府は決断をつけられず、戦前は制度上神道は宗教ではないままでした。
例えるなら、自衛隊も法的には軍隊ではないと扱われていることと似ていますね。戦後ようやく、GHQの神道指令により神社も宗教法人化するんです。
──宗教に関して一貫していたものは
宗教の概念の拡張は一貫していました。戦前は宗教の概念が狭かったから、新宗教はなかなか宗教としての地位を得られなかった。仏教やキリスト教などの伝統的な宗教と比べ、一段格が低く怪しいものと見られ、やや差別的に新興宗教と呼ばれました。
1940年にようやく、宗教に関する法律(宗教団体法)が施行されます。実は、19世紀末にも宗教関係の法律を作成したけれど、仏教側がキリスト教と同列に扱われることへの嫌悪感から抵抗したため、成立しなかったんです。仏教側は特別扱いを求めていました。そこで1940年には、昨今まで問題になっている宗教法人の税制優遇措置を定め、それと引き換えに仏教と他の宗教の同列扱いを了承させました。ただ、税制優遇措置を与えるには相応の規制が必要とされ、新宗教は仏教などと同じ待遇を得られませんでした。
戦後になると宗教団体法は信教の自由を束縛しているとGHQから指摘され、廃止されました。そして、新たに宗教の枠組みを考える必要が生じ、神道も新宗教も宗教団体として認めました。信教の自由をできるだけ広く取ったんです。こうして、世界的に見ても非常にゆるい規制の宗教法ができました。
しかし1995年にオウム真理教事件を引き金に、宗教法人の運営面の透明化を図るべく法律が厳格化されました。最近は旧統一教会の問題を受け、事情によっては政府が介入しても良いと考えられるようになりました。
──昭和と現在の重なりは何ですか。昨今の既成政党への不信感には、戦前期と共通点がありませんか
戦争への警鐘を鳴らそうと昭和戦前期を思い出させるやり方は、そろそろ耐用年数が切れかけているのではないでしょうか。1945年に終わった戦争は日本人が体験した最後の戦争だとはいえ、100年近く前の戦争です。言い方を変えると、その戦争を軸に現代を語るのは、更新されていない戦争観を用いることになる。次に来るかもしれない戦争は、太平洋戦争からは大きく変化している公算が大きい。戦前の時期と状況が重なるからと、必ずしも戦争と絡める必要はないと思います。既成政党への不信感は確かに戦前には政党政治の終焉(しゅうえん)を導いたわけだけれど、政党は大政翼賛会を経つつ、最終的には戦後復活するわけです。その時もそうした政党に対し、期待しきれないとの感覚が実はあって、戦後間もなくは多党化が進むんです。女性が参政権を得たのもあり、特に参議院では無所属の議員もたくさん誕生して、二大政党制からはほど遠い形でした。戦後初期の政党史を思い返すと、連立政権が続きますよね。それほどの多党状態だったんです。それもやがては解消し55年体制に収まります。
だから、既成政党への不安や多党化は、戦前期だけではなく終戦直後にもあるんです。そもそも、戦前以外の状況を参照しても良いわけで。必ずしも戦争につながるとは言い切れない、むしろ、戦争を数十年しなかった社会体制の形成と関連しているかもしれないとの見方もできますよね。だから、例えば警鐘を鳴らすような、定型化した過去との向き合い方に拘泥せず、自由に過去を参照して良いと思います。
自由に歴史と向き合って
──今昭和を振り返る意義はどこにありますか
昭和は今とよく似たところが多くあり、さまざまな点で今にも生きている時代なのは間違いないです。でも、違うところももちろんある。例えば東大の進学選択自体は昭和に作られたシステムですよね。だから確かに昭和の仕組みが生きている。でも当初は志望順でマッチング率が悪かったのですが、その後複雑なアルゴリズムが導入されました。これを昭和の仕組みだというだけではダメですよね。これは一例ですが平成の間にも社会は大きく変わりました。その両方を念頭に置くのが、過去から現在へのつながりを考える上で重要なことです。
我々は、現在のことについて考える際、役立つかもと思って過去を参照するわけですよね。その時に、参照する過去として、特定の時代にこだわる必要は正直ありません。でも、昭和などの近い過去を参照するのは、過去と接し考えるちょうど良い訓練になります。昭和は過去で、現在とは違う。でも言葉が現代語に近いため、文献を読むのは他の時代よりずっと簡単ですから。
──どう学ぶのが良いのでしょうか
昭和について書かれた本を読むよりも、昭和に作られたものに触れることを意識してほしい。総合雑誌、小説などの出版物だけでなく映像や音声も立派な史料です。私たちは実際にそう苦労せずアクセスできるんです。国立国会図書館デジタルコレクションを使えば、ウェブ上で多くのものを読めます。それに明治の文章は古文っぽくて難しいけれど、昭和だとほとんど現代と同じ文章になります。三島由紀夫のように文章の難しい人でも、音声や映像が多く残っている。三島が駒場の900番講堂で学生と交わした議論の一問一答も、『討論三島由紀夫vs.東大全共闘』という本のほか、映像もある。それだと迫力があるし理解しやすい。何でもいいから興味があるものを探し、当時の人のコトバに耳を傾け、考えるのを楽しんでください。昭和についての本は、旅行のガイドブックみたいなものです。ガイドブックからも知識は得られるけれど、実際に現地を歩いて初めて分かることは多い。例えば自分の地元に友達が遊びに来る時、観光地のほかに、ローカルなご飯屋さんとか、土地勘を生かした案内をするでしょう。この土地勘はガイドブックを100冊読んでも得られないですよね。同様に、昭和当時のものからしか分からないこともたくさんある。当時のものを直に参照すれば、過去との向き合い方がより広がっていくでしょう。
──「昭和100年」特集に対し、思うことは
似たようなもので、明治100年の記念行事がありました。これは佐藤栄作内閣の時期に、明治維新から高度経済成長真っ只中の当時までを単線的に成長・発展の物語として捉えて大々的に式典や記念事業を行いました。例えば千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館はその一環として造られました。実は当時の歴史家の多くは、政府の歴史観は成功の物語を仕立てることで戦争から目を背けるものだと反対したんです。しかし明治100年を批判した歴史家も、明治維新が現在の起点であり、1868年から1967年までを1つの時代と捉えられるという考え方は共通して持っていた。しかしながら昭和100年はだいぶ違う。例えば、現在の起点が昭和の元年にあると考える人はまずいない。それどころか、昭和の64年間でさえ1つの時代と考えるのは難しいほど大きく変化しています。「昭和かよ」というツッコミも最近は聞きますが、もう昭和は現在とは違うという感覚が浸透していますよね。
──元号から歴史を捉えることに意義はありますか
明治より前までは、吉事や凶事があるとすぐに改元しました。明治以降は一世一元となり、元号が変わることは天皇の死を表すようになりました。しかし、平成の生前退位でそれが変わり、元号に関して新たな時代に入りました。一世一元の時代は元号と天皇の生涯が重なるので、元号の時代を語る時、人の生涯のイメージを投影しやすい。例えば明治なら、明治初期は近代の礎を築くまさに青春のようなイメージになる。その後は壮年期、右肩上がりで成長して日清戦争にも日露戦争にも勝った。日露戦争をもって日本社会が変わっていくという司馬遼太郎らの歴史観も、明治の終焉を意識しているイメージがあります。しかし今後はそのセットが切れるんです。それが向き合い方にどんな変化をもたらすのか。その時に元号を使い続けていることにどんな意義を見出すかですよね。例えば今回昭和100年をやっていて、では次に平成100年ってやるんだろうか、と想像してみるとう思いますか。100年続いた元号はないので元号100年というのは、さまざまなものから何周年という、さらに知的でモダンな発想を加えて編み出した知的創造力の産物です。時にはこうした形で歴史を捉え直すのも良いかもしれませんね。











