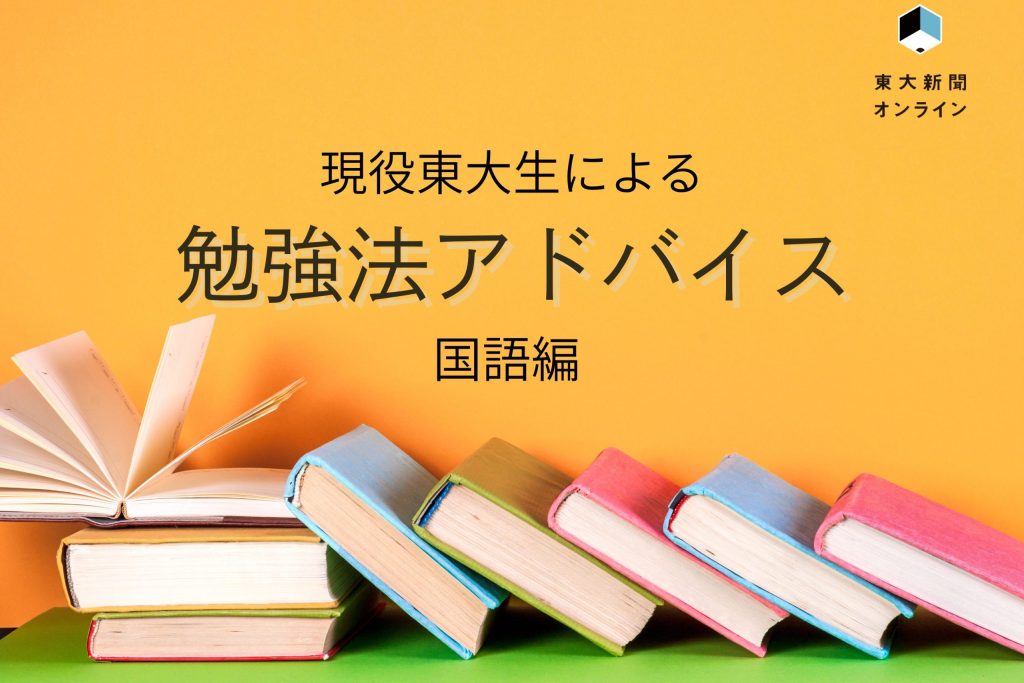
東大に合格した人はどの時期にどのような勉強をしていたのだろうか?読者の中には東大を受験しようと思っているものの、身近に東大受験について相談できる相手や仲間がいないため自らの勉強方法に確信が持てず、このような悩みを持つ人もいることだろう。そこで本記事では、東大生による国語の時期別の勉強方法をはじめ、東大入試の基本情報や入試本番での時間配分や注意点などを科目別に掲載した。ぜひ受験勉強の参考にしてほしい。
現代文 言葉に対する感受性と表現力を磨いて
理科は評論が1問、文科は加えて第4問に随想(2025年度は小説)も出題。全て記述式で、古文・漢文と合わせて国語全体の試験時間は理科100分、文科150分です。そのうち現代文にかける時間は、理科50分、文科80分程度が目安となります。
全体を通してまず大事なのは時間の使い方です。国語は一つの解答をいくらでも追求できるため、時間配分に失敗すると最後に少ない時間で焦って解答することになり、高得点を取ることが難しくなります。完璧な解答を作ろうと1問にこだわり過ぎてしまうと命取りになります。まずは大問ごとにかける時間をある程度決め、それを大きく逸脱せずにその中でできる最大限の解答を目指すと良いでしょう。
文理共通問題である第1問の評論では、解き始める前に全文を一読し、出題文全体の構造や流れ、論旨をつかみましょう。その後、各問題に対してどの部分を参照するか見極め、遺漏や重複に注意して全文を傍線部とそれに対応する部分に切り分けていきます。しかし、ただ文章中の表現をつぎはぎにするだけでは突破できません。何を答えれば良いかはっきりさせ、短い解答欄の中で問題に対応した解答になるように、重要な要素を漏らさず、無駄を削ぎ落とし、自分の言葉で表現しきりましょう。ぼんやりした当たり障りのない答えでは決して高得点にはなりません。採点者にも分かりやすく、ひねりのない解答を目指します。最初に何を主語にするか決めるとすっきり書きやすくなります。文科第4問の随想や小説で大切なのは、感受性・想像力を十分に発揮することです。その上で、傍線部に出てくる言葉が選択された意味、その細かなニュアンスを感じ取り、それを自分の解答に映し出す表現力を身に付けましょう。
過去問演習では、解答例を複数比較・参照し、この解答が最良だったのだ、という結論を自分で出してみましょう。そしてどこまで自分の言葉で表現すればいいのか、どのような言葉選びが適切なのかのあんばいを習得しましょう。(文III・2年)
古典 徹底した基礎基本でセンスを磨け
古文・漢文は、それぞれ大問一つずつの出題で、1〜2行の短い記述式問題です。各設問では単なる現代語訳だけではなく、場面や人物の心情まで深く読み解く力が問われます。高度な知識がなくても、基礎を固めておけば確実に得点源にできます。
高2のうちに、遅くとも高3の夏までに、古文の文法・単語、漢文の句形を完璧にしておきましょう。こうした基礎知識だけで解答できる問題も少なくありません。分からない言葉は安易にインターネットで調べるのではなく、辞書を引く習慣をつけるのがおすすめです。辞書を引くことで、言葉の複数の意味や用例、語源まで体系的に学べるため、知識が定着しやすくなります。
本格的な演習に入る前に、これまでに読んだ古文を品詞分解して精読したり、漢文の白文に返り点を打つ練習をしたりすると、土台がより強固になります。授業で習った文法を起点に、関連する古典常識や時代背景まで掘り下げると、文章全体の理解が深まり、記述問題のヒントになります。
高3の夏から過去問演習に本格的に取り組みましょう。入試本番では、文章中の全ての単語や文法が分かるとは限りません。初見の文章に早い段階で慣れ、文脈から意味を推測する力を養うことが重要です。1年分の過去問を最低でも3回解き直すことで、解法や文章への理解が格段に深まります。答案は必ず学校や塾の教員など信頼できる大人に添削してもらい、改善点を言語化して整理しましょう。復習の効率を上げるためにも、新しく得た知識や発見は全て復習ノートに書き込み、情報を一つの媒体にまとめておくことを推奨します。
限られた時間内で要点を押さえた簡潔な答案を作成できるか否かが鍵となります。求められているのは難解な知識ではなく、落ち着いて設問の意図を正確に読み取る力です。現代語訳の問題は特に確実に解いて、合格に近づきましょう。(文III・1年)











