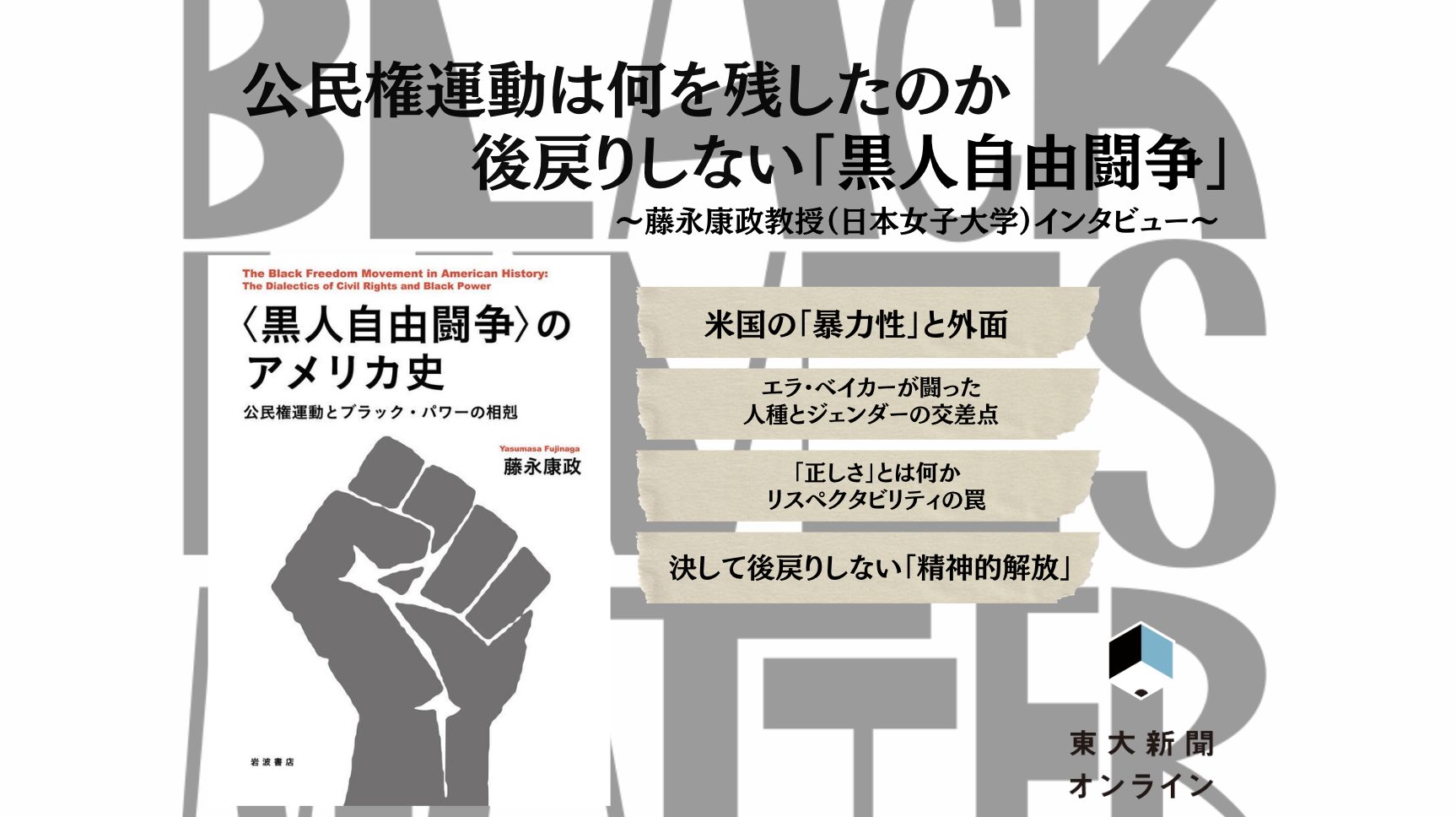
「公民権運動」と聞くと、何を想起するだろうか。一般的には、「キング牧師」として知られるマーティン・ルーサー・キングが率い、1964年の公民権法、65年の投票権法の成立をもって「終わった」とされる。このような見方に対し、多くのものを見落とす危険性や、公民権運動前後の道のりを過度に単純化する恐れがあることを指摘するのが、黒人自由闘争の歴史を「ブラック・パワー運動」(公民権法成立後も続く差別に対する非暴力のみに限らない形での抗議活動)を中心に描き出した、2024年12月刊行『〈黒人自由闘争〉のアメリカ史公民権運動とブラック・パワーの相剋』(岩波書店)だ。24年11月にトランプ氏が米国大統領選で勝利し、今年の1月に就任したばかり。トランプ大統領は、かつてブラック・ライブズ・マター運動をテロ行為と呼ぶなど、米国の人種差別問題の解決には後ろ向きだと言われている。そこで、本書の著者である藤永康政教授(日本女子大学)に話を聞いた。(取材・峯崎皓大)
米国の「暴力性」と外面
━━そもそも人種差別が始まったきっかけは何ですか
人類の奴隷制の中でも特異な近代の人種奴隷制がきっかけに始まったと言えます。19世紀後半に、西欧、北欧系白人を頂点として序列化された社会構造が形成される中で、人種差別が始まりました。
━━とりわけ米国における黒人差別の歴史には白人による暴力的な行為が数え切れないほどあります
公民権諸団体が公民権を求める最中に白人による暴力は多くありました。例えば1963年のバーミングハム闘争では人種に拠(よ)らない雇用機会の平等を求めるデモ行進やシットイン(座り込み)が行われたのですが、バーミングハム警察は、抗議活動を終わらせるために、子供を含むデモ参加者や無関係の見物人に対して高圧放水や警察犬を用いました。また白人に対する黒人へのリンチや殺人事件は数多く発生しており、多くのケースで白人は何も罪に問われないということが起こっていました。
━━白人はなぜここまで黒人に対して暴力的になれたのでしょうか
今の感覚からするとこの暴力性に対して理解できないものがあると思います。暴力を行う白人にとって、このような暴力は、自分たちにとっての「米国」を守るための「正しいこと」だったでしょう。そもそも米国は「建前の社会」であり、その建前の起源は米国の国の成り立ちにまでさかのぼることができます。独立宣言にはall men are created equal(全ての人は平等に創造された)とあります。一方で黒人を奴隷として扱い、女性には権利すら与えませんでした。この米国が建前の上で語る国の像と実情との矛盾を抑え込むために暴力性が出てきたと考えることができます。米国はこのような暴力性を多く抱えているにもかかわらずその暴力性を見ようとしてこなかったことに問題があると思います。ドナルド・J・トランプが登場する前の米国は理想主義的で、世界中に「人権」や「自由」を語る説教臭い国でした。しかしその理想主義的な姿勢では米国が内包している暴力性を見ることができず、米国社会の持つ問題とその理想主義と現実との矛盾にふたをしてしまうことになります。米国はマイノリティーの人権に関する法整備を行ってきましたが、それは外面を気にしながら行ってきたという側面がありました。実際にトルーマンによる軍での人種隔離の撤廃や、ケネディ、ジョンソンによる公民権法・投票権法制定の動きは心の底から人種差別をなくすためというよりは自由主義諸国の盟主を自認する米国の冷戦下での覇権を考えての動きであったと考えます。近年のトランプ大統領の当選に見られるように、もはや外面を気にしなくなり「自分たちのやりたいことをやる」ようになった米国はそれの持つ暴力性を隠さなくなり、かつては考えられなかったことが次々と行われるようになっていきます。
━━人種奴隷制がリンカーンにより廃止された後も人種差別が続いた理由は何でしょうか
奴隷制の廃止後にも、南部では白人と黒人の人種隔離政策「ジムクロウ」が行われたため、人種差別的な構造は存置されたままでした。1896年には「隔離は差別ではない」という最高裁判決が出たほか、「黒人は暴力的で性的野獣だ」というステレオタイプを作り出すことによって「安全を守るために黒人を隔離しなければいけない」としてジムクロウは正当化されました。人種奴隷制の下では「黒人は弱く女々しい」というステレオタイプがあったにも関わらず、です。また、女性に対しても、人種奴隷制の時代には「男性に従順なマミーのような存在」というステレオタイプだったのが、ジムクロウ以後には「尻軽な売春婦」というステレオタイプに書き換えられた、ということが起こりました。
エラ・ベイカーが闘った人種とジェンダーの交差点
━━本書にはエラ・ベイカーがマーティン・ルーサー・キングの存在は社会運動の障害になると批判していたことが描かれていました
ベイカーは、キングが議長を務めていたSCLC(南部キリスト教指導者会議)のキングに対する「個人崇拝」の組織風土を、「強いリーダーは弱い運動を産む」として批判していました。カリスマ的なリーダーがトップダウンで物事を決める中央集権的な組織ではなく、分権的な組織における自由な議論とコンセンサス形成の過程の苦闘こそが運動を推進させるのだというのがベイカーの考えでした。このようなベイカーの信念をもとにSNCC(学生非暴力調整委員会)が創設されました。また、SCLCは公民権に関することでは改革派であっても、社会的な価値観においては保守的な、男性牧師を中心とした組織でした。その中で女性であるベイカーは黒人としてのみならず女性というインターセクショナルな部分でも闘っていました。
━━SCLCには伝統的な価値観を重視し、ミソジニー(女性に対する嫌悪や蔑視)がありましたが、SNCCにはミソジニーはなかったのでしょうか
SNCCのミソジニーについて一つ有名な話がありますが真偽は定かではありません。それは、1966年にSNCCの議長に就任しブラック・パワー運動を提唱したストークリー・カーマイケルが、女性のメンバーにWhat is women’s position?(女性の立場(=ポジション)は何か?)と聞かれた際に「正常位だ」(性行為の際のポジションのこと)とジョークを言った、というものです。この話は当時SNCCの会議に参加していた複数のメンバーから出てきた話です。カーマイケル本人はその発言をしていないと否定していますし、その時会議にいた数人も否定しているほか、ベイカーがSNCCに常に大きな影響を及ぼしていたため「そんな発言ができるわけがない」とも言われます。真偽は不明ですが、このようなうわさがまことしやかに語られる時代であったことを考慮すれば、ミソジニーがなかったと言い切ることは難しいと思います。

「正しさ」とは何か リスペクタビリティの罠
━━代表的な公民権諸団体の一つであるNAACP(全米黒人地位向上協会)を本書は批判的に描いています
NAACPは主に裁判やロビイング活動を通して黒人の権利を勝ち取った団体です。例えば1954年には教育における人種隔離は違憲であるというブラウン判決を勝ち取りました。一方で、NAACPはリスペクタビリティ(直訳すると「尊敬できるさま」。具体的には、犯罪歴がなかったり、大学教育を受けることができたりした人のことを指す)を重視し、立派な人格を形成する機会に恵まれなかった人たちに手を差し伸べない傾向がありました。例えば、ノースカロライナ州の街、モンローで7歳の少年が同年代の白人の少女と遊んでいた時のこと、おままごとをする中でこの少女が少年の頬にキスをしました。それが明るみになり、少年は警察に拘束され、少女に対する性的虐待という罪状で21歳まで少年院に収監するという判決が裁判により下されました。この事件が起こった直後からNAACPの腰は重く、上層部は少年を見捨てるような動きをしました。その要因として、その少年にはかつて万引きなどで補導歴があったこと、その母は福祉手当を受け取っていたことなどが考慮されたと指摘されています。当時のNAACPの執行代表は「どうして福祉に世話になっている人間のクズをわれわれが代弁しなくちゃいかんのだ」と内々に述べていたといいます。つまり、犯罪歴が一つもない、その犯罪がたとえ貧困によるものであったとしても、リスペクタビリティを涵養(かんよう)できた人しかNAACPは助けなかったのです。
━━一方でSNCCの執行代表を務めたジェイムズ・フォアマンは「大多数の米国黒人が人間としての可能性を発展させる機会に恵まれていなかったことを理解してはいる」と述べていました。それにもかかわらずどうしてNAACPはそのような恵まれなかった人たちに手を差し伸べなかったのでしょうか
指摘の通り、もちろんNAACPの上層部も、恵まれなかった環境ゆえに貧困に苦しみ、殺人や強盗、窃盗を行う黒人がいることは知っています。しかし、リスペクタビリティを涵養(かんよう)できた黒人としては、そのような恵まれなかった黒人と自らを同種の存在として見ることができなかった、「同じにされたくなかった」のだと思います。一つ自分の経験から言うと、私は米国の大学院に進学しましたが、キャンパスは黒人ゲトーのど真ん中にありました。大学の黒人の友人がお店の中で地元の黒人の友人と話しているのが聞こえてきて、それはいつも私と話す英語とは違う訛(なま)りの入った英語でした。その友人は私に気付いた時に、いつもと様子が異なり、決まりが悪いような笑顔を向けてきました。もしかしたら彼は、黒人コミュニティの中で使われるいわゆる「黒人英語」を話しているのを私に聞かれたくなかったのかもしれません。
━━不当な拘束を行う警察や不当な判決を下す司法に頼ることができない黒人たちは何に頼っていたのでしょうか
何も頼ることができず、避けて生きるしかなかったというのが現実でした。当時の黒人たちにとってはトラブルに巻き込まれないように生き、もし巻き込まれた場合は自分で何とかするしかありませんでした。
一方で「何もできない自分たち」ということにも怒りや屈辱を抱いていたと考えられます。1950年代にフロリダ州やアラバマ州で黒人女性学生が白人男性にギャングレイプされるという事件が多発していました。その時に黒人男性は「女性を守れない自分たち」といった烙印を押されたような気持ちになっていたといいます。また、このような事件にまではならないにしろ、黒人男性が彼女と歩いているときに街角で彼女に対して卑猥(ひわい)な言葉を浴びせられても何もできない、ということが多々あったということは容易に想像できます。
決して後戻りしない「精神的解放」
━━リスペクタビリティを重視したNAACPが社会に残したものとは何でしょうか
NAACPがエリート主義的な組織であったことは確かです。しかしながら、NAACPがリスペクタビリティを追求していたことは、社会運動の中で「正しさ」を追求したという姿勢につながった点で、黒人自由闘争の歴史の中で大きな意味を持っていることも事実です。一方、「正しさ」を追求するあまりに運動の中での言葉遣いやマナーについてセンサーシップが働き、NAACPやキングのような「リスペクタブルな人たち」があまりにも寿(ことほ)がれることに対して、実際に運動を行っていた人たちは息が詰まるような思いをしていたと考えられます。ブラック・ライブズ・マター運動を歴史的な視点からではなく、現場の中から記録した研究者の一人としてキーガン・ヤマッタ・テイラーという人がいます。彼女の記録によると、中で運動をしているアクティビストは「公民権諸団体の人たちは私たちのところに来て説教しかしない。説教しかしないんだったらもう来るな」と声をあげていたそうです。代表的な例として挙げられるのが、公民権弁護士として活動していたオバマです。「他に方法がある」と公民権諸団体は言うが、現場で、特に激しく運動を行っているアクティビストたちからすると「他に方法がないからこれほどまで激しくやっている」という歯がゆい思いをしていたそうです。
━━トランプ大統領の就任以降、不法移民の国外追放などを目の当たりにすると、権利とは「脆(もろ)い」ものであると考えてしまいます
NAACPは、「政治家は自分の票しか考えないため当てにならないし話が通じないが、司法は法律を基に説得することができる」という考えのもと、政治に参加するという方法ではなく司法の場で黒人の権利を勝ち取ることに集中していました。また、公民権運動は「既存の社会の中での法的権利の獲得を目指すこと」に執心していました。それが1964年の公民権法、65年の投票権法につながりました。しかしながら、法的権利を獲得したからといって社会から差別は無くなっていないし、トランプ大統領のような人が誕生すれば権利が保障されるかどうか分かりません。その一方で、その公民権運動の中で人々の「精神的解放」は進み、黒人は自分自身を抑圧していたものからだんだんと解放されました。自由な髪型ができるようになったのはその一例です。また、不当に暴力を振るう白人や警官に対して、かつては何もできなかったのが、「精神的解放」によってやり返せる可能性が芽生えたことは、その後のブラック・パワー運動につながりました。ブラック・パワー運動では、職やヘルスケア、教育などの「内実がある権利」を要求するために社会構造そのものに挑みかかりました。2010年代以降に大きくなっていったブラック・ライブズ・マター運動に関して、私はよく「彼らは何を提案しているのですか」と聞かれます。その答えは「彼らは何か提案をしているというわけではない」です。何か具体的な言葉で表せない抽象的なものだけれども、リスペクタビリティを涵養(かんよう)する機会に恵まれた人だけでなく、恵まれなかった人も多く参加し、具体的な言葉ではないにしろ社会構造そのものに挑む運動でした。
権利がたとえ奪われたとしても、公民権運動によってもたらされた「精神的解放」やそれが可能にした社会構造への挑戦は決して後戻りすることはありません。
━━今後の米国における人種差別問題はどのように展開していくのでしょうか
就任早々トランプ大統領は選挙運動中に語っていたことを実際に行動に移しています。その中には黒人奴隷の歴史を軽視するような動きも見られ、また、指摘があったように、マイノリティーに対しての権利を脅かすような動きも見られます。しかしながら最後には司法がトランプ大統領の行動が適切かどうかを判断します。心配ではありますが、司法には期待しています。
また、私の世代は「理想主義を体現する米国」として米国に対して夢を抱いており、それをどうしても捨てきれず、ついつい米国が内包する暴力性を無視して外面のみを見てしまう側面があります。私自身も、どれほどひどい米国を見てしまっても、研究をしながら「俺はやっぱり米国が好きだ」と思ってしまいます。しかしながら、今の若い世代は10代の頃から1期目のトランプ政権を見ており、「理想主義を体現する米国」ではなく自国の利益を追求する「普通の国・米国」というように米国への見方が変化するのではないかと考えています。私は米国の研究をしている中でどうしてもフラットにものを見ることができないなと自分で感じることがあり、これは私が米国に対して抱いているイメージに起因していると思います。外面を捨てた米国をまざまざと見てきた若い世代の人たちがどのような米国をこれから描くのか、非常に期待しています。

ふじなが・やすまさ/99年東大大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(文学)。山口大学准教授などを経て18年より現職。









