
東大の藤井輝夫総長は、就任直後の2021年の入学式の式辞で、最先端の工学研究を社会と結び付けるには「『デザイン』からのアプローチが必要不可欠」と語っていた。総長任期6年の集大成として69年ぶりに東大に新学部が開設される。その名もUTokyo College of Design(CoD)。複雑化する社会問題を前に、東大はデザインを「地球と人類社会の未来の構築に必要な新概念」として、社会システムの変革を含む広い意味で再定義し、デザインを軸にした新たな教育を模索する。学生は秋に入学し、前期教養課程を経由しない。開講されるのは英語での授業だけ。進学選択もなければ、半分が留学生という、既存学部とは一線を画した構想だ。とはいえ、どのような計画も突然降って湧くものではない。小宮山宏・元総長や濱田純一・元総長以来のプランの結実としてCoDを捉えたとき、どのような未来や課題が待ち受けているか、考える。(執筆・溝口慶)
小宮山宏・元総長時代(05〜08年度) 知の構造化でデザインする社会

藤井総長が掲げる基本方針、「UTokyo Compass多様性の海へ」では「人類社会が直面する地球規模の課題(健康、経済格差、ジェンダー平等、紛争や分断、エネルギー、資源循環、気候変動等)に関し、東京大学が有するあらゆる分野の英知を結集してその解決に取り組む」とされている。「デザイン」による多様な知の融合により社会課題に取り組む人材の育成を目指すCoDは、課題解決の中心的存在になるだろう。
こうした地球規模での問題意識は小宮山元総長と共通するところがある。小宮山元総長は人類史的な転換期に直面している現代社会において、学術界には「知の構造化」が求められていると考える。知の構造化とは、無数の分野に細分化された知識を相互参照可能な形で整理し、最先端の学問と社会を結び付ける営みで、小宮山元総長は05年に、前期教養課程向けに学問領域の全体像や学問領域同士の有機的なつながりを学ぶオムニバス授業の「学術俯瞰講義」を開始した。
CoDでは、1年次の必修科目として開講されるIF(Interdisciplinary Foundations)で、既存の10学部の学問知を紹介する。そして2・3年次の必修科目として、IP(Interdisciplinary Perspectives)を開講。各学部の教員による約100科目もの分野横断的なこの授業を、CoDは独自のカリキュラムだと誇っている。小宮山元総長は東京大学新聞社による昨年9月の取材で、社会人を対象としたエグゼクティブ・マネジメント・プログラムと比べ、知の構造化という点では、今の藤井総長が掲げているCollege of Designの方が良いかもしれないと評価。「小さい組織ではあるけれど、そこを起点に学問分野を横断した知の構造化を全体に波及させることができるのではないか」と期待を述べる。
昨年2月に東大が発表した資料には、「コア」たるCoD学生のデザイン授業に、既存学部からの他学部履修生を「アフィリエイト学生」として参画させることで、相乗効果の拡大を狙うとある。既存部局との兼任教員を採用し、教育研究改革の全学への浸透を図る。CoDの学生は、他学部履修で、自分のデザインするビジョンの実現に向けて必要な専門知識を学ぶことができる。逆に、既存部局の学生も、デザインの手法を学ぶことで専門知の社会実装を進めることができるだろう。今年4月の会見で藤井総長は「デザインをベースにした学びの環境で、こういった非常に広い範囲の学問分野にアクセスが可能となっているようなプログラムというのは、世界を探しても他に類を見ない」と誇らしげに語った。
濱田純一・元総長時代(09〜14年度) よりタフに、よりグローバルに

濱田元総長は就任後「森を動かす」と宣言し、その後も行動指針「FOREST2015」を示したが、藤井総長は、行動指針「UTokyo Compass多様性の海へ」を発表した。「森」と「海」と対照的な2人だが、目指すものでは通じている。濱田元総長は「よりグローバルに、よりタフに」をスローガンに、国際流動性の促進、主体的な学びの向上、学部4年間を通じた高度教養教育を三つの柱に、教育プログラムの開発に挑んだ。
秋入学は何をもたらしうるのか
|
<秋入学のポテンシャル> ①欧米や中国の大学では学年を秋季に始め、学期末と進級の間に夏休みを置くのが主流。国際標準の学時暦を採用することで留学生の流動性が高められる。 ②入学前の半年間のギャップタームで、まとまった体験学習の機会が生まれる。 ③秋入学で年末年始の1カ月と夏の3カ月を長期休暇に充てる学時暦を組むと、夏休みが長くなり、研究活動や体験学習、短期留学などのまとまった機会とできる。 |
濱田元総長は、秋入学の全学での導入を検討した。高校卒業後から大学入学までの半年間のギャップタームの設計から、卒業後の就職時期や国家試験の時期の再検討などを含む巨大な構想だった。しかし学内での強い反発もあり、全学での秋入学は見送られ、代わりに「秋入学への一歩」として現在の4ターム制が導入された。また、学部で初めての秋入学となる教養学部英語コース(PEAK)が開設された。26年をもって募集停止となるPEAKを統合してCoDは発足し、秋入学を実施する。
入学時期をそろえれば、国際的な学生の流動性も高まるだろう。しかし長期休暇の時期や学期の組み方まで海外と共有できるかも、短期留学などの流動性を左右する。濱田総長は秋入学を目指すと宣言した12年の会見で、秋入学は社会の変化を促すこととセットでないと実現できず、変化を促すことにも意味があると話していた。
高校卒業から半年間のギャップターム
濱田総長時代に秋入学が頓挫した背景には、学内からの批判もあった。しかしCoDは実際に秋入学を導入する。3月の合格発表から入学までの半年間、日本人学生の学習体験や社会活動などに東大がどう関与するかは注目すべきだろう。例えば濱田元総長時代に藤井総長(当時は総長補佐)が立ち上げに関わった、FLY Programや体験活動プログラムのようなものが考えられる。特に前期教養課程に入学直後の1年生が休学し、東大の外で社会体験活動に挑戦するFLY Programを半年間に限って導入する方策は濱田元総長在任中の秋入学検討時にも考えられていた。ギャップタームが基礎学力に与える影響も懸念される。CoDでは全面的に英語で授業するため、今年7月に東大は、英語力強化のためのプログラムを検討していると言及した。
東大からの学習・体験機会の提供が十分でないと、所得や地域差がギャップタームでの体験格差を生むことも危惧される。PEAKを管轄する教養学部が濱田総長時代の秋入学の検討に対して示した、産業界や学習塾、旅行業者などの「ギャップビジネス」により、入学予定者間の格差が生じ、経験の差として現れる可能性がある、という指摘を今回も忘れてはならない。
CoDは他の海外大学を志望する受験生の併願先として利用される可能性もある。合格者の1〜2割が入学を辞退する米ハーバード大学などの海外大と比べ、東大は合格者のほぼ全員が入学する。CoDは海外大の競争相手として「蹴られる東大」の先駆けとなり、さらには海外大を「蹴って」まで選ばれる存在になれるか。真価が問われる。
多様性を確保するグローバル入試目指す
濱田元総長が残したものとして学校推薦型選抜もある。CoDもこれまでの東大の2次試験とは異なる独自入試を実施する。昨年2月の発表では「国際AO入試のプロ集団を配置」し、「多様性を最大限反映」した「グローバル入試」を目指すとした。今年7月の発表によれば、CoDには二つの入試方式が設けられ、共通テストか国際バカロレアなどの国際試験の成績と、出身高校の調査書と評価書、英語のエッセイ、英語面接で評価される。秋に出願を受け付け、2〜3月に合格が発表される。学部で唯一秋入学のPEAKでは、11〜12月の出願から2〜3月初旬の面接を経て、3月末に合格が発表されていた。CoDの入試の詳細は、26年7月までに発表される。
グローバル化の期待と課題
CoDでは英語での授業を全面的に展開する。IF・IPで既存の学部からの出講があるが、そもそも全ての教員が英語授業に慣れているわけではない。PEAKなどでは、これまでも日本人教員の英語力が低いため英語開講科目の質が低いという指摘があった。山下彩香特任助教(CoD企画調整室)も、就任前の昨年2月に、東大の学部も院も英語の授業が日本語の授業より低レベルというSNSの投稿に対し本当のことだと投稿しており、CoD企画調整室の教員も同じ問題意識を共有しているようだ。
すでに発表されたCoDの教員は、学部長予定者のマイルス・ペニントン教授(東大大学院情報学環、英ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ修了)だけだ。今年8月末時点で企画調整室に所属しているのは、西澤利郎特任教授(米ウィスコンシン大学マディソン校で修士課程修了)、田川欣哉特任教授(英ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ修士課程修了)、山下彩香特任助教授(米ハーバード大学デザイン大学院修士課程修了、現在博士課程4年)の3人と、いずれも英米での学位を持つ。多くの授業は既存部局の教員が兼任で受け持つが、デザイン科目に携わる教員などは新規で雇用する。今年度は任期無しの教授(8-10名)と、任期3年の准教授(10-12名)、任期3年の講師・助教(5-8名)を募集している。 外国人学生向けの日本語の語学科目の有無は未決定で、語学学習アプリを運営する企業との連携も検討中という。サークル活動が活発な駒場ⅠキャンパスにあるPEAKでさえも、他の教養学部生との交流が薄いという指摘があった。浅野キャンパスのCoDで、日本語の語学授業の実施が不透明となると、地理的にも言語的にも他学部生との日常的な交流は難しいとも考えられる。
スタジオ教育の試み
CoDではスタジオが学びの中心となる。二つの大きなオープンルームを設け、全員が作業できるスペースを与えられ、チームでプロジェクトに取り組む予定だ。ペニントン教授は「アイデアを交換し、より多くの人々と知り合うための、面白くて落ち着ける場所になるようにしたい」と語る。CoDで使われる予定の情報基盤センター別館には、スタジオとして用いられるかは不明だが、「学生室」として1階を全て使用した400平方メートルほどの部屋が一つ作られる見込みだ。
学生の1人(工学系・博士課程)は、スタジオ型は美術大学的なものであると語る。スタジオでは、学生は作品やプロジェクトを前に、実践的に手を動かしながら学ぶ。学生だけでなく教員とも日常的に意見交換やフィードバックが行われるため、形式ばらない議論や偶発的な交流から新しいアイデアが生まれやすいという。
CoDが対象として示す社会課題には「法制度のイノベーションと司法デザイン」などもある。果たしてそれにスタジオの形が適しているのだろうか。かつてマルクスは図書館にこもって資本主義システムに変わる社会のあり方を構想したが、CoDには部局図書館が設置される計画は聞かれない。果たして若者がスタジオで交わす会話は、社会システムを描き直すアイデアを生めるのだろうか。藤井総長は「いわゆるモノのデザイン」を超え、「広い意味での社会システムの変革、あるいは未来の社会そのものを作」る意味でのデザインを目指すという。しかし21年の入学式の式辞では、デザインを「工学の最先端の研究を実社会と結び付けるため」のアプローチだと記したように、どうしても「ものづくり」から離れられていないきらいがある。
デザイン授業のカリキュラム
CoDでは、1年次で、8つのデザインの手法をワークショップ形式で学ぶ。
|
<8つのデザインの手法> ・Human-Engaged Design ・Interaction Design ・Critical Design ・Design with Data ・Design Ethics ・Exhibiting ・Storytelling ・Prototyping & Making |
そして2・3年次では、Viewpoint Seriesという、社会課題やデザインに関するセミナーを受けながら、社会課題に焦点を当てて高度なデザインの手法の習得を目指しChange Maker Projectsが開講される。CoDの講師募集では、社会課題の例として右のものが挙げられている。
4年次では1学期間の学外体験(Off Campas Experience)としてインターンシップや、交換留学、フィールドワークなどを必修とする。留学生は日本企業、日本人学生は国際企業のインターンに行くなど、未経験の体験をすることを重視するという。UTokyo Compassは「パートナー企業やベンチャー企業等との連携による場を構築し、学生との交流やアントレプレナー教育を実施する」としている。CoDでは人材育成や社会連携の可能性について、7月に2回企業向け説明会を実施した。企業関係者の出前授業もあり得るかもしれない。学外体験について、当面はインターンを中心に検討しているというが、フィールドワークや交換留学も検討されている。
|
<CoDが対象として示す社会課題> ・ウェルビーイングと健康デザイン ・フードシステムと持続可能なイノベーション ・気候変動対策と環境デザイン ・災害対策とレジリエントデザイン・デザインにおける文化遺産と地域アイデンティティ ・創造性のための新興技術(AI、AR、VR) ・インクルーシブデザインとアクセシビリティ ・社会的起業家精神とインパクト主導型デザイン ・法制度のイノベーションと司法デザイン ・教育デザインと生涯学習 ・都市のモビリティと持続可能な都市 ・エコシステムデザインと生物多様性 |
問われる多様性
ペニントン教授は今年7月の東京大学新聞社の取材に「東大にさらなる多様性をもたらすことも私たちの使命」と述べているが、グローバル化に向けた道のりは険しい。CoDは1学年100人の定員のうち約半数を外国人学生とする計画だ。しかし昨年度の東大の外国人学生の内87.3%はアジア出身で、世界中から学生を集められているとは言い難い。CoDの外国人学生を仮に50人とし、この国籍の割合を当てはめると、44人がアジア出身で、その内39人が中国・韓国・台湾の出身となる。そもそも定員が50人では、作り出せる複数性にも限界がある。もちろんCoDは海外やオンラインでの説明会も重ねる。一方で、東大はインドに林香里理事・副学長を長とする事務所を持ち、8月19日にはインドでのイベントに矢口祐人副学長が参加するなど、インドを拠点にグローバルサウスへの進出を目指している。これらの取り組みを強化し、欧米の大学と一味違う、東大独自の多国籍な環境が生まれることに期待したい。
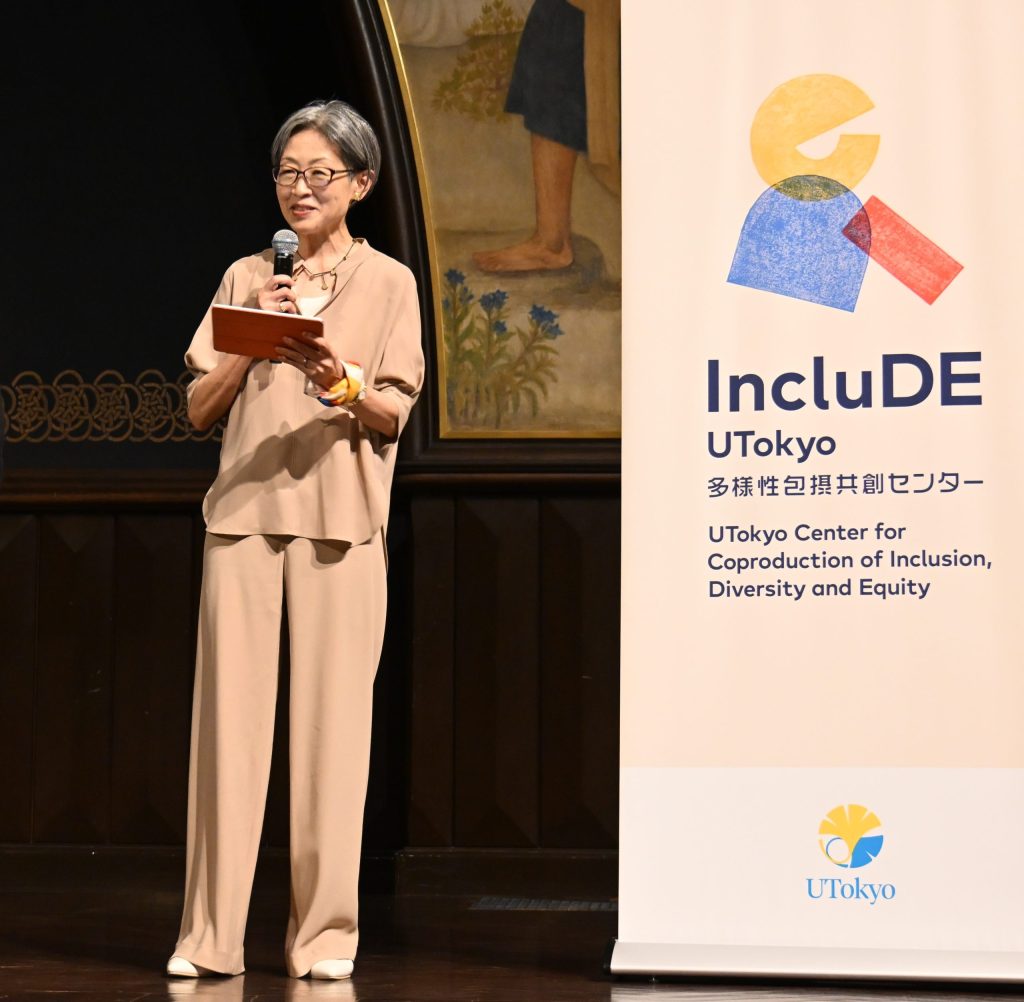
生産研出身 藤井総長とペニントン学部長生産研からの潮流
かつて藤井総長やペニントン教授が共に働いた東大生産技術研究所(生産研)は、「もしかする未来の研究所」を掲げて社会とのつながりを重視する。所内の研究室同士のグループ研究や他部局との連携も活発で、CoDが目指す学際的な雰囲気を思わせる。全学部から離れた駒場Ⅱキャンパスにある生産研だが、その前身で、戦時中に東大に設置された第二工学部は本郷から離れた千葉に存在した。吉見俊哉名誉教授は著書で、本郷の第一工学部(現在の工学部)で既に安定的地位を持つ教員はわざわざ千葉に行こうとしなかったことも影響し、本郷の価値観では収まりきらない教員が第二工学部に集まり、本郷の第一工学部では考えられない空気が広がっていたと記す。第二工学部も、CoDも、工学部出身の総長のもとで設置され、社会への知の実装を重視する。第二工学部と同じく、CoDも初年次は全寮制の予定だ。本郷から離れ、CoDが置かれる浅野キャンパスは、かつて小宮山元総長が武田先端知ビルを「出島」とみなして挑戦の地としたような場所だ。
ペニントン教授は英国でデザイン会社を設立した経験がある。今年8月時点でCoD企画調整室に所属する3名の教員も、全員が実務経験を持つ。これは第二工学部の教員に本郷と比べて実務経験が多いメンバーがそろったことに重なる。第二工学部では専門の異なる教員同士が食堂で親近感を高め、異なる専門領域間での高度な技術交流を生んだという。卒業生も研究職に限らず広く多大な功績を残したといい、第二工学部の卒業生で、戦後復興期に都道府県の土木部長を経験した者は17人いるが、これは全都道府県の3分の1以上だ。藤井総長はCoDを「次世代のリーダー、あるいはFuture Shaper、未来を作っていく人を育てる」ための「挑戦」と語る。果たして第二工学部のように後から評価される存在になれるか。藤井総長の力量が試される。











