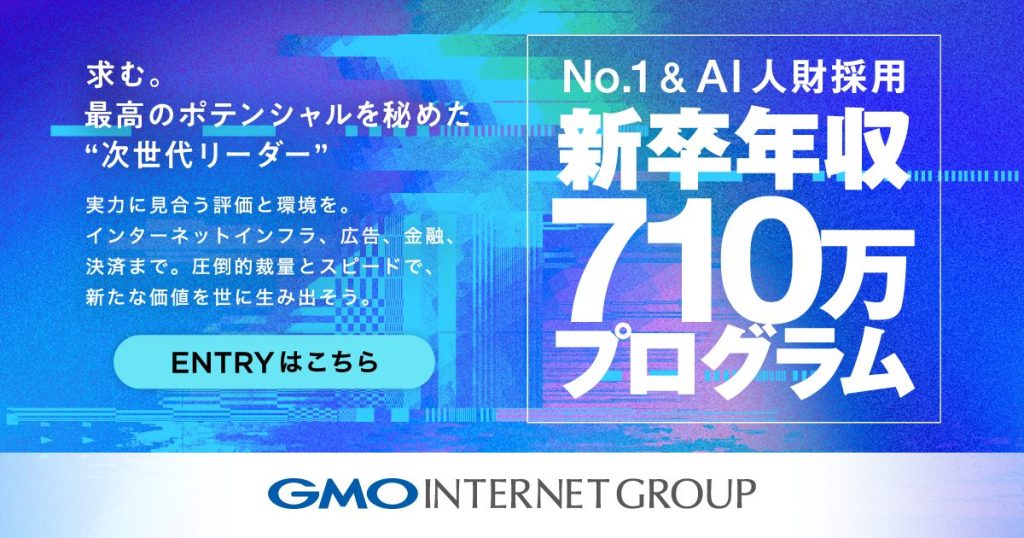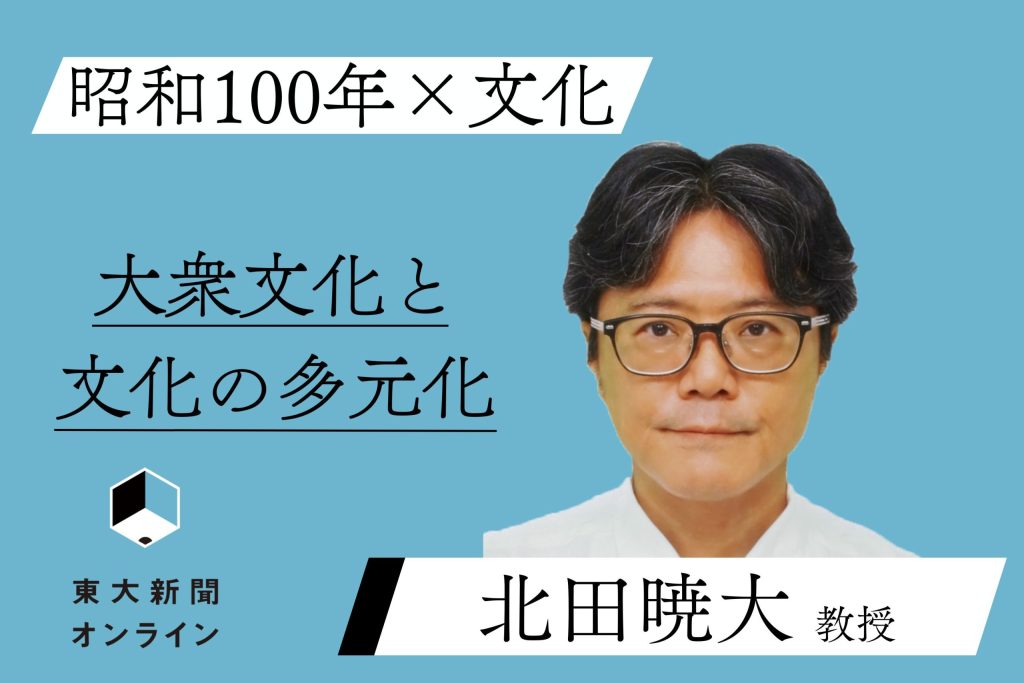昭和100年と文化 変容する文化のあり方と私たち
テレビの全盛期であり、文化の大衆性が強調された昭和。しかし時代の流れとともに文化は多様化し、生み出され方も大きく変わった。この間状況はどう変わり、そして私たちはどう文化と向き合うべきか。メディアの社会学を研究してきた北田暁大教授(東大大学院情報学環)に話を聞いた。(取材・茂木和葉)
大衆文化とその裏にあるもの 昭和文化の様相と社会
──社会学では「文化」をどのように捉えていますか
難しい問いですが、まず私たちが普段、生活世界のなかでにおいて行う趣味(ホビー)などと絡んだ実践を文化と呼びますよね。一方「日本文化」「米国文化」と言うように、共同性を可能にする意味的資源というイメージで語ることもある。このように具体的な趣味と関連した事象と、共同性を担保する意味媒体という二つの方向性で考えられている気がします。この両面を踏まえ、どの立ち位置で文化という言葉を使っているかを自覚して分析を進める必要があります。
──昭和の文化の様相について、どう捉えていますか
いわゆる「昭和」とは、皆が共有する情報の発信方法があると信憑(しんぴょう)されていた時代といえるでしょう。やはりマスコミが中心となって大衆を生み出していた。一方で「昭和」は、単層的な大衆文化を内から突き崩し、文化の多層性を生み出す大衆の抵抗も生み出した。サブカルチャーですね。大衆への抵抗自体が大衆化される、そういう時空間だったように思います。
──大衆文化の黄金期でありながら、それに対抗する動きも生まれたわけですね。
サブカルチャーは、ハイカルチャーに対して抵抗しつつ、マス文化の単層性を批判するものとして、60年代以降知識人の注目を集めました。日常実践として文化を捉え、政治的抵抗の可能性を見出したわけですね。マスコミ的な大衆文化と、非マスコミ的な大衆文化としてのサブカルチャーとは表裏一体なわけで、大衆社会批判とサブカルチャーへの着目とはいずれも大衆社会の所産といえます。抵抗が無意味ということではなく、抵抗それ自体も抵抗の対象に飲み込まれてしまう、それが大衆社会・文化のしたたかさだと思うんです。その構造が確立されたのはやはり「テレビの時代」である60、70年代だったのではないでしょうか。
──大衆文化の席巻が社会に与えた影響はありますか
政治的には自民党の支配体制が安定的に展開された時代でもあります。また、家庭ドラマの中で描かれる家族モデルが理想化されたのもやはり「テレビの時代」でした。幸せの55年体制とでもいえるものが、高度経済成長のもとで確立されていった。大衆文化は、私的生活をモデル化する社会的な規範の増幅装置として大いに機能したといえるでしょう。
──子どもや若者は、そうした大衆文化からどのような影響を受けていたのでしょうか
私自身明確な記憶にあるのは70年代末から80年代ぐらいからなので、60、70年代のあり方を実体験しているわけではないのですが、80年代に文化消費の「差異化」をめぐる議論が多く出てきたことは象徴的だと思います。上野千鶴子さんの『〈私〉探しゲーム』などが典型ですが、記号論の枠組みを用いて文化や趣味の細分化が盛んに論じられました。おそらく80年代に入ると、テレビを軸としたマスメディアの統合機能が失われつつある、という認識が共有されるようになったのだと思います。それまでの大衆社会論や文化論が画一化や単層化を問題化していたとすれば、80年代の消費社会論は、「私らしさ」を担保する他者との差異化のアイテムとして文化をとりあげました。社会学者のブルデューは70年代末に、文化を他者に対する差異化のゲームの資本として捉える『ディスタンクシオン』という本を出しましたが、そうした議論に説得力を与える状況が生み出されていたのだと思います。差異化のアイデンティティーゲームという論点は、90年代以降の文化論においてさらに深められていきます。
──文化の多様化・多元化が始まったのですね
自分の立ち位置を探るときに何か皆の共通したコンテンツや準拠点を基にする必要がなくなり、アイデンティティーを構成し他者との差を示すための基準そのものが多元化しているのが90年代以降とまずはいえるかもしれません。「昭和」の象徴としてテレビと相撲と巨人がありますが、巨人に関してはテレビと相まった求心性が強かったからこそアンチも多かった。しかし80年代の記憶と照らしてみても、アンチ巨人というのは今はそれほど強くない気がします(笑)。何に対してアンチとなるかもまたきわめて細分化されている。「テレビの時代」の終焉(しゅうえん)は、差異化ゲームのルールそのものの細分化をもたらしたわけです。
文化の多元化がもつ両義性 現代文化との向き合い方
──現代の文化の様相についてはどう捉えていますか
やはり何を自分の軸として文化を介したゲームをするか、準拠点が多元化しているのは事実だと思います。それはコンテンツ上の多元主義、民主主義を可能にする一方で、細分化されたムラ同士の交流を難しくしている。よく言われることですが、SNSでは、文化をめぐってつながる相手とは盛り上がるけれども、他のムラの住人とは没交渉だったり、あるいは没交渉であるがゆえにいざ抗争となると激化したりする。私はそれを否定的に捉えているわけではありませんが、難しいですね。先日選挙もありましたが、マスメディア主導のアジェンダ設定が難しくなり、世論の全体像がますます掴みづらくなっているのを感じます。
いや、昔の人は視野が広かったのかといえば決してそんなことはないと思いますよ。マスコミ研究では、だいぶ以前から先有傾向の強化ということがいわれます。マスコミ情報が強力な威力で人々の意見を変えてしまうというよりは、各々(おのおの)がもともと持っていた傾向を強化する機能がある、ということですね。そういうのはマスコミの時代からずっとある。ただ、SNSや動画サイトなどで、自分の先有傾向に合致する情報源へのアクセスが容易になったとはいえると思います。視野が狭まったというよりは、つながりへの欲望を実現するハードルが低まっている、という感じでしょうか。
──そうした現代の状況を否定的に捉えていないというのはなぜでしょうか
人間の思考や価値観が限られた準拠点に枠付けされるより、準拠点そのものが多元化することは好ましいと思います。いろいろな表現や価値観への接近可能性が技術的に担保された現代の方がやはり「自由」ですし、社会の成熟のためには多元化は欠かすことはできません。ただ同時に、それは異なる価値観を伴う人達の没交渉や、ムラ内でのつながりが優先された帰結として対立の激化も生み出すでしょう。その両義性に耐えていくことが、現在求められていると思います。
──私たちはどう現代文化と向き合えばよいでしょう
まずは閉じたムラの乱立や、ムラ同士の没交渉・対立は簡単には解決できないと自覚するのが大切なのではないでしょうか。どこかにきれいな正解があるわけではないことを前提とした共生の技術ですね。多元化する社会では、文化に対する曖昧な寛容ではなく、ある種の忍耐力が問われるのではないでしょうか。
──現代はSNSの発展もあり、コンテンツの発信手と受け取り手の境界が曖昧になり文化の生み出され方も変わってきているように感じます
境界が曖昧になっているというのはその通りですし、さらに加速していくでしょう。そういう時代だからこそ、逆にマスメディアのあり方について改めて問うていく必要があるのではないのでしょうか。なんのかんのとテレビを中心としたマスコミが作り出す情報空間、コンテンツは頑強です。「マスゴミ」と馬鹿(ばか)にしたところで、その相対的な文化ヘゲモニーは簡単には揺るぎません。あらためて「マスコミ的なもの」との付き合い方を丁寧に考えていくことが、現在において発信者・作り手となるうえで重要なのではないでしょうか。同時に、マスメディア側にも、自らの強みをどう再編成するかが問われていると思います。
──大衆文化はこれからも存続していくのでしょうか
大量の人々が共有する文化が立ち行かなくなるのは確かで、そういう意味での大衆文化は弱まっていくでしょう。一方で、全ての文化が大衆的なもの、つまり高級だ/高級でないという水準が消え、誰もがアクセスできるものになるという意味で、大衆文化が拡充していくともいえる。かつて高級文化と言われたものも、一種のサブカルチャーと捉えることができる時代です。そういう意味では全てが大衆文化になるとも言えるし、大衆文化がなくなった時代だとも言える。それは同じ事態の表裏を指しているのだと思います。