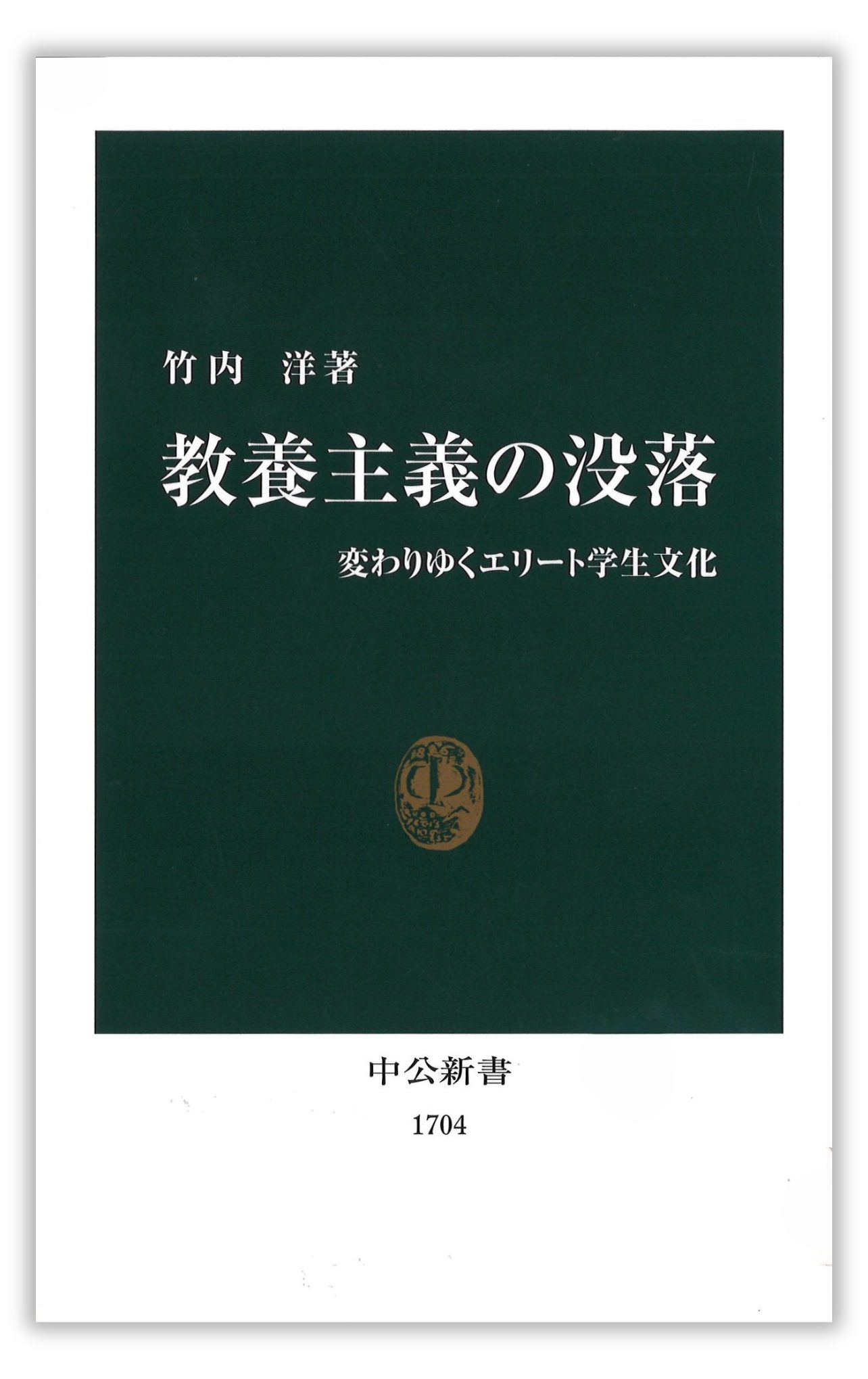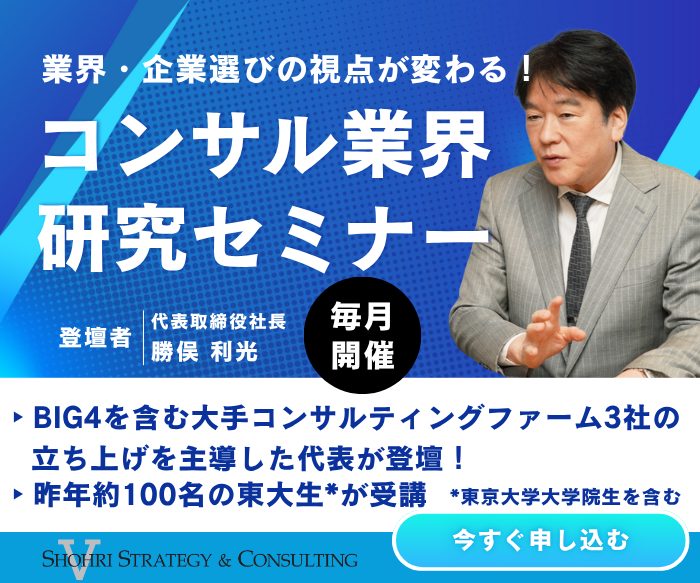教養が輝いた時代をたどる
東大生にとって「教養」とはなんだろうか。東大の学部の新入生が全員所属する学部の名前は教養学部となっているし、一般的に東大生は教養を持ち合わせているものと期待されているだろう。東大生と教養とは、切っても切り離せない関係にあるものであることは間違いない。
しかし、教養学部前期課程で東大生が学んでいるものは本当に教養と呼べるのだろうか。必修にあたる基礎科目と、7系列にわたる総合科目(いわゆる選択必修科目)をつまむように履修したところで、学生に教養が宿るというわけではないような気がする。教養とはもっと、長期的知に向き合うことで身に付けるもののはずだ。
実は、読書などを通して教養を身に付けることが学生の間で規範文化とされていた時代があった。2003年に刊行された中公新書『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化』では、大学における「教養主義」の起源と、それが学生文化として繁栄した歴史が語られる。
教養主義とは、「読書をつうじた人格形成主義や社会改良主義」(p.25)とされている。日本における教養主義はまた、西欧志向の主義でもあった。本書で語られるその歴史は戦前から始まる。
戦前の学制では、帝国大学へ入学するためには一部の例外を除いて旧制高校を卒業することが求められ、学生は現在の大学の教養学部の前期課程にあたる教育を旧制高校で受けていた。著者によれば、教養主義は旧制高校が発祥であり、これを「旧制高校的教養主義」と呼んでいる。「昭和戦前期の(旧制)高校生や大学生の教養は、高校や大学の授業などの公式カリキュラムだけではなく、総合雑誌や単行本、つまりジャーナリズム市場をつうじて得られていた」(p.14)とある通り、学生が読書を通じて積極的に教養を追い求めていたことがわかる。著者は、学生の愛読書に関する調査などを引用しながら、当時の学生文化の様相を明らかにしている。戦前の調査によると、帝国大学生のおよそ3人に1人が『中央公論』『世界』をはじめとした総合雑誌を購読していた。人文学の古典やマルクス主義に関する書物もよく読まれていた。
戦後すぐの学制改革によって旧制高校が廃止された後も、教養主義は存続した。著者で社会学者の竹内洋は61年に京都大学に入学しているが、旧制高校的教養主義の雰囲気が学内にはまだ残っていた。教養主義は70年頃まで大学生の規範文化として繁栄し、その後没落していったというのが本書による筋書きだ。
教養主義の威光を支えたものはなんだったのかという点も、本書の主要なテーマだ。教養主義は、大学生をエリートたらしめていた低い大学進学率や都市と農村の格差、「文化装置」として教養書や欧米書籍の翻訳書出版を行った岩波書店などに支えられていたことが明かされている。学生文化の枠を超えて教養主義の物語が階層論や社会史と結びつく面白さが本書の最大の魅力かもしれない。
帝国大学の文学部は、教養主義に魅了された学生にとって憧れだった。しかし、教養主義が威信を持っていた時代の文学部は、進路が教員に限られ、卒業後の経済的な利得という点で他の学部に劣っていた。経済的ハンディをわかっていながら文学部に進んだ学生たちは、教養主義に深く傾倒し勉学に励みながら、他学部の学生を高踏的に見下す一方で、相対的に農村出身者が多いという傾向があったとされている。過度な一般化であるような気がしなくもないが、こうした文学部生像が学生生活調査などのデータをもとに描かれている。文学部生にこのような傾向があったのは偶然ではない。都市と地方の格差が今よりはるかに大きかった時代、地方人や農村出身者にとって、教養主義は知識人の洗練されたイメージと結びつき、文化的に成り上がるための装置として機能していた。
戦前からの帝国大学としての歴史を持ち、独立した文学部を擁する数少ない大学として東大のデータや逸話が多く引用されているため、東大生の文化史としても興味深い内容が多い。
1970年代以降は大学進学率が上昇し、大学生のエリート性が薄れたことで学歴エリートの文化である教養主義は没落した。大学生の主な進路は「ただのサラリーマン」であり、彼らに教養知は求められていないという。
学生文化としての教養主義は没落したかもしれない。また、難しい本を読んで人格形成を図るという考え方に今どき存在感があるようにも思えない。しかし、刊行から20年が経過した現在でも、「教養」という言葉は本の表紙に記してあるだけで手に取ってみたくなるような、妖しい魅力を放っている。著者はその種の一般常識としての「キョウヨウ」には重要な要素が欠けていることを指摘し、今こそ教養とはなにかを考える機会であると問いかけている。戦前からの教養主義の歴史と、著者の洞察から得られたいくつかのヒントとともに。【日】