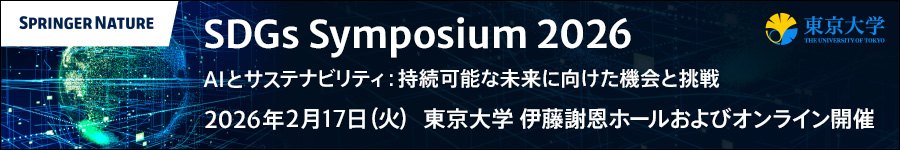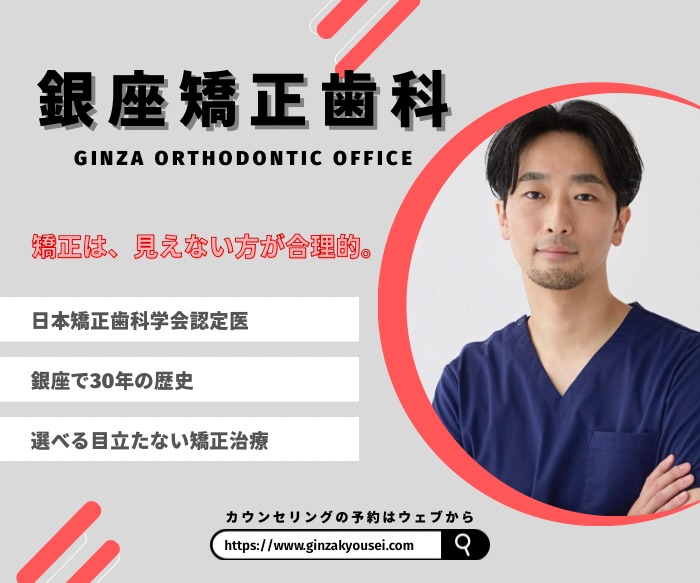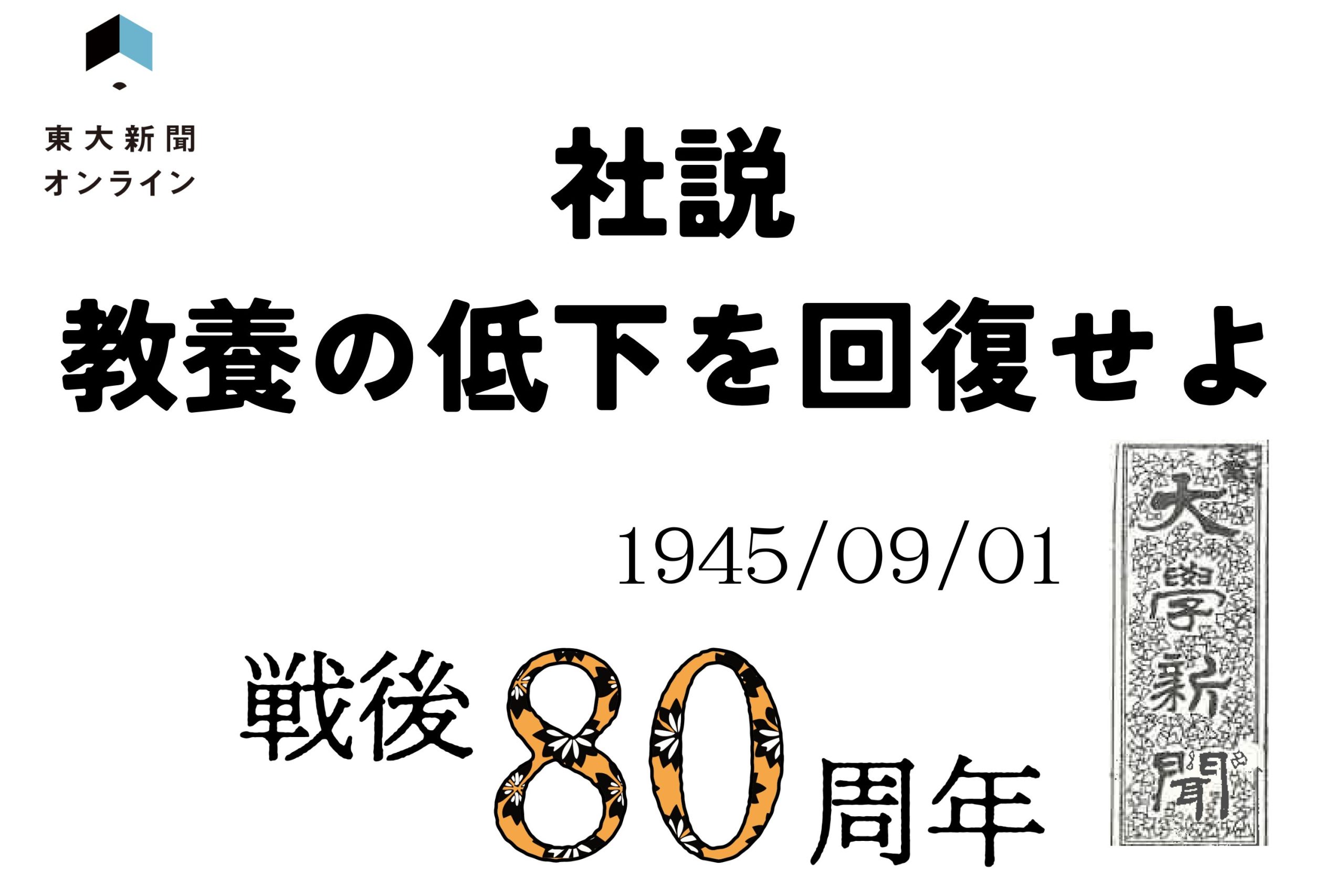
学徒兵や勤労動員の「生産戦士」たちも、敗戦で大学に戻ってくる。戦時中、十分に教育を受けられなかった学生たちについて、敗戦のその時何が問題とされていたか。
今回は1945年9月1日発行の「大學新聞」より社説「教養の低下を回復せよ」を転載する。終戦直後の検閲なき期間の本記事をして、「当時」について考えるきっかけにしてほしい。(構成・溝口慶、◯は印刷不良により判読できなかった文字、その他改行や句読点など一部改変)
社説 教養の低下を回復せよ
よしや戦には敗れたりとも、最後の瞬間まで学徒は或いは軍人として、或いは生産戦士としてよく戦った。無論学徒と雖も国民として敗戦の大罪を 陛下に謝し奉らねばならぬが、戦争末期に至り様々の不愉快な事象が国内に次々と生起しつつあった中に、よくその純真な祖国愛を維持して戦ったことに認められねばならぬ。一般工員も徴用工も殆ど姿を見せぬ工場に学童を含む学徒のみが作業を継続していたという事例は少なくなかったのである。
大東亜戦争を通じて学徒が名実共に国家の中堅たることは厳たる事実として国民に銘記せしめられた。このことは先般公布せられた戦時教育例の上諭においても、畏くも 陛下の嘉し給うた所であり、学徒は十分の自信を以て戦後の再建に奮闘するであろうことを深く期せしめうるのである。
しかしながら学徒が戦争中吾々の賞讃に値する敢闘を見せたということが直ちに戦後の再建に無条件的に之等の学徒を社会人として受入れ得ることを意味しないのである。思うに戦いは敵を斃す一事に一切を集中すれば足りるのであり、学徒は所謂行学一体の理念に徹することを要求されたのであったが、斯の如く単一化された目的に邁進することは一切の利害を超越する学徒にとっては言い得べくんば比較的容易であったのである。のみならず、過去に於て不当に圧迫せられた学徒は行の中に自己の活路を見出し得たとさえ観ぜられたのである。
しかし事態は今や急転回した農耕動員その他の一部を除いて男子は学園に、女子は家庭に、一応復帰することとなった今日そして同時に学徒の力が国家として十分の認識を以て見らるるに至った今日、学徒は自らが国家の中堅として立つには適(かな)わしい十分の教養を保持しえているか否かに再思三省を要すべき時は来たのである。
人間は往々にして過去に於る力量を認められた場合、それが未来に於ても無条件的に認められるという錯覚に陥り勝ちである。或いは年限短縮により或は出征により、将又勤労動員により、日本の知性として社会に立つべき十分の基礎を得られなかった学徒が、急転回を遂げた現在の日本において深刻な自己批判を敢行しないなら、それは学徒諸君の自殺にも等しいのみならず、日に月に困難を加えるであろう来るべき時において、往年の学徒にも優る苦痛を味わねばならぬであろうことを深く憂えざるを得ないのである。
率直に云って学徒の教養の低下には著しいものがある。戦争終結直後に於て、あらぬ流言に惑わされた、理性的判断力を全く欠如しているとより考えられる大学生をすら見るに至ったほど学徒の教養は低下しているのである。この教養の低下を回復すべく自らに十分の鞭を加えることは今や学徒に課せられた責務であるとともに、文教当局の責務でもあらねばならぬ。
前田文相はその就任に当って、国民に思考力を養わせねばならぬと述べた。この文相の言は第一に過去の教育に対する批判であり、第二は現在の学徒に対する批判であり、第三は未来の教育の目的を示しているのであって、文教責任者の覚悟を語るとともに自己批判の言葉として受取らねばならぬのである。
学徒は今日までに得た行動力と、生産現場の貴重なる体験を基礎として自らの足らざる所は率直に之を認め、些かも国家社会に甘えることなく偉大なる生産力はやがて偉大なる治世治世であることを─否、更には偉大なる知性こそが、偉大なる生産力として発現しうるものであることを今後に実証することを期待してやまぬものである。
※1944年7月から1946年4月の間、全国の学生新聞は『大学新聞』に一本化され、本紙の前身『帝国大学新聞』の編集部が編集を主に担っていました。終戦から80年の節目を迎え、戦争の当時を語る人々は減る今、遠い存在となりつつある「当時」を考える一助になれば幸いです。また『帝国大学新聞』や『大学新聞』、『東京大学新聞』の過去の記事は、駒場や情報学環・学際情報学府の図書館で閲覧できます。