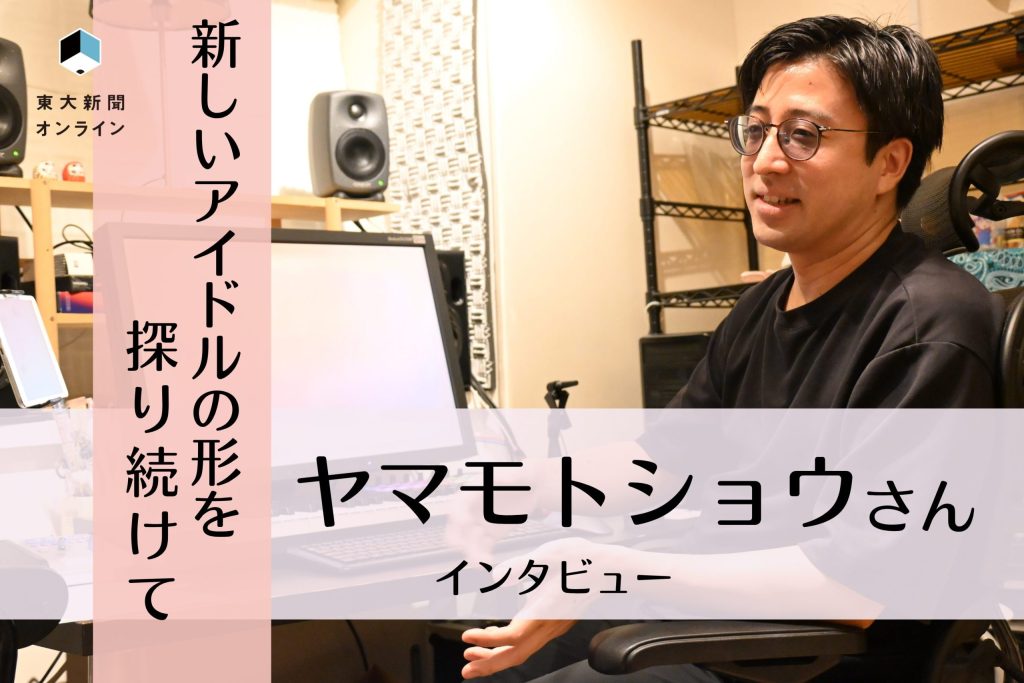
「わたしの一番かわいいところ」や「NEW KAWAII」などヒット曲を多く手掛けるヤマモトショウさん。東大では理Iから理学部に進んだのち文学部に転学部するという異色の経歴を持つ。バンドとしての活動中にアイドルの曲を作るように。コロナ禍では時代の変化に合わせて新たなアイドル像を、現在では地元の静岡県で今までとは異なるローカルアイドルの仕組みを創出。常に新しいアイドルの形を探り続ける原動力に迫る。(取材・山本桃歌、撮影・宇城謙人)
数学から哲学の道へ
──東大の理Iを志望した理由は
公立高校の理数科に所属していて、理数系に進む人が多かったことに加え、高校で学ぶ科目の中で数学が一番パズル的な要素があり楽しかったためです。通っていた高校では必ず部活に所属しなければならず、一番暇そうだという理由で数学部に入ったところ、数学が好きになりました。学問の深淵を見たというよりは、楽しいという気持ちが強かったですね。今でも数学は好きです。
東大を志望した理由は進振り(当時、現・進学選択)があったからです。大学進学時点では行きたい学部・学科が決まっていなかったので魅力的でした。
──その後理学部数学科に進学します
理Iのカリキュラムでは実験が必修科目となっていたのですが、長時間実験をすることに耐えられませんでした(笑)。数学など理論を学ぶ学科か、情報系の学科への進学を考え、時間の融通が利きそうな数学科にしました。今では全然そんなことはないと思うんですけど(笑)。
──数学科から文学部思想文化学科哲学専修課程(当時、現・人文学科哲学専修課程)に転学部しています
理由は二つあります。まず、僕が数学科で学問的関心を持っていた分野が数学基礎論という分野で、哲学に近かったことです。例えば、1+1=2という式は左辺と右辺が等しいことを表していますが、もう少しメタ的な視点に立つとこれは本当に成り立つのか。2を見た時に誰もが1+1だと思うなんてことはない。認識していることと数学として表現されていることとの間にはギャップがあって、それまでかなり厳密に定義されていると思っていた数学にも、実は全然そうではない部分もある。1+1を見たら2と操作するということを前提として数学的な営みを行っていることが、僕にとっては面白かったのです。
二つ目は、数学科に進んで初めて、僕が絶対に持っていない才能を持った人を見たことです。自分には思い付かないような発想を持つ人を見る中で、努力の必要性を認めつつも、努力では埋まらない差を感じました。
教員に相談する中で転学部できる制度があることを知り、学年は一つ下がることになったのですが、文学部に転学部しました。
──哲学専修課程に転学部した後に学んだことは
それまで一度も人文系の学問に真剣に取り組んだことがなかったので、どのような考え方をすればよいのかさえ分からないというところからスタートしました。言語を学ぶのも大変で、ドイツ語を一回もやったことがないのにいきなりフッサールのテキストを読むこともありました。ドイツ語の原典と、日本語訳と辞書を机の上に置いて、ドイツ語の勉強をしながら読み進めました。1日に3行読み進められれば良い方、という生活を半年くらい続けました。今考えると、人に何か言われることもなくそういうことをできるのはあの時期だけだったなと思いますし、この経験は今でも役に立っています。哲学は他の学問に比べて、明確に今役に立っている、と思える瞬間が分かりづらい学問ですが、哲学専修課程での学びが歌詞に反映されていることもあると感じているので、勉強して良かったなと思います。
プロのアーティストを目指して
──大学生の時に音楽と関わることは
所属していた軽音サークルとは別にバンドを組んでいました。きっかけは当時下北沢に住んでいたことです。駒場Iキャンパスに徒歩で通えるという理由で下北沢に住んでいたのですが、せっかくなら近くにあるライブハウスや劇場に行ってみようと思いライブや演劇を見る中で、サークル以外にもバンドを組んでプロを目指してみよう、と思うようになりました。そして哲学専修課程3年次にバンドを結成しました。僕は院進を考えていたものの、周りの人は就活を始めるタイミングで、挑戦できるとしたら最後の機会だと考えていました。
──周囲が就活をする中で、音楽の道に挑戦することに対する迷いや葛藤は
迷いは全くありませんでした。大学院でも引き続き哲学の勉強や研究は続けていたので、バンドが僕にとって主な活動、というわけでもありませんでした。音楽の道と音楽ではない道の2択で音楽を選んだという感覚ではなく、本当に「自分がプロになれるのか試したい」という気持ちで活動していました。
──バンドを組んだ当時から作詞作曲を行っていたのですか
バンドを組む以前も趣味程度の作曲は行っていたのですが、本格的に始めたのはバンドを組んでからでした。僕以外に作曲できる人がいなかったからです。知り合いに頼んでライブハウスでライブをさせてもらったり、レコード会社にデモテープを送ったりしました。徐々に曲に手応えを感じられるようになり、24歳の時にレコード会社と育成契約のようなものを結ぶことになりました。プロの入り口のようなところまではたどり着くことができ、大学院に通いながら音楽を続けようと思いました。思い返すと結構行き当たりばったりでしたね。
アイドルとの出会い 新たな方向性を探って
──今ではアイドルの曲を作曲しているイメージが強いです。バンドからアイドルの曲を作るようになったきっかけは
初めに組んだバンドのボーカルが1年ほどでやめてしまい、その後レコード会社からボーカルを紹介され、バンドを組むこととなりました。これが「ふぇのたす」の始まりです。このボーカルが、今でいうかわいい声をしていたので、売れるための戦略として、それまで作っていたロックな曲というよりは、この声を生かした曲を作ることにしました。
ちょうどその頃、アイドルがライブハウスでライブを行うようになりました。衝撃だったのは、ライブをたまたま見た時に、自分たちのライブよりも盛り上がっていたことです。そこで僕たちのバンドの客層として、新たにファンをライブハウスに呼ぶよりも、ライブハウスでアイドルを見ている人たちをつかんだ方が早いと感じました。それでふぇのたすを、バンドだけでなくアイドルとも共演できるような方向にシフトさせることにしました。僕は全くアイドルに興味がなかったのですが、そのようにしてアイドルとのつながりが一気に増えたことで、作曲を依頼されるようになりました。
──バンド曲とアイドル曲はかなり異なるという印象がありますが、変わらない点や意識的に変えた点は
共通しているのは「歌っている人をプロデュースする」という感覚です。ふぇのたすはボーカルが1人で、アイドルは複数人という違いはありますが、いかに歌う人の個性を生かすかを考えて作曲するかという点は変わりません。一方でアイドルならではと感じるのは、多くのクリエイティブな人たちが関わる点です。音楽以外の分野の人もいますし、当時は僕のようにアイドル曲を作ったことがない人が作曲に携わることもありました。そのような人がとても面白い曲を作って、それが結果的に10年くらい経った今のアイドル曲のフォーマットになっている部分もありますね。
アイドル曲とはいっても、当時ライブハウスで活動するアイドルの曲は、テレビに出て大人数で歌って……というアイドルの曲とはかなり異なるものでした。前日ライブハウスでお客さんが熱狂的に盛り上がっていた、あのアイドルに曲を書くならもっと「やばい」曲を書かなければならない、という感覚でしたね。既存のアイドル像ではない新しい方向性を提示することを目指していました。
──ライブハウスはテレビよりお客さんとの距離が近いように思います
ライブハウスでお客さんから受けた影響は大いにあります。おとなしめのイメージで書いた曲が、ライブ会場に行くと大きいコールが入って超盛り上がっていることもあり、お客さん含めてクリエイティブな感じでした。とても感動したエピソードがあります。ソロアイドルをやっている方が、洋楽のカバー曲を初披露した時のことです。その曲をやることをお客さんは知らなかった。ものすごく盛り上がる曲ではなかったんですけど、2番に入ったあたりでお客さんが自然とコールをし始めました。静かめの曲にコール入るんだ、と思ったのですが、いつもと何かが違う。よく聞いたら発音がかなりよくて英語っぽい。それに気付いたとき、ぞわってして、なんで僕が感動させられているんだ、と思った。お客さんよりも面白い発想で曲を作っていかないと負けてしまうという感覚を持ちました。
──今ではライブハウスだけでなくテレビに出るアイドルの曲も作っています
もともとテレビに出ていたというより、結果的にテレビに出るようになったという感じですね。2013年くらいからアイドルの仕事をしていて、だんだんフォーマット通りに作れば盛り上がるという感じになってきて、ワクワクしなくなりました。それで18年ごろからTikTokでどのようにしたらバズらせられるか、という研究を始めました。これを実践したのがコロナ禍です。ライブを大々的に行うことができないスモールスタートの中でどこまで売り出せるんだろう、というチャレンジをしてみたかった。その手法が受けて、多くの方に聞いてもらう機会が生まれました。狙い通りという感覚ですね。
──今までのアイドルの曲というと、恋愛の曲が多いイメージがありますが、ヤマモトさんが作る曲は自己肯定感を上げる歌詞が多いと感じています
FRUITS ZIPPERの初めの曲の一つである「わたしの一番かわいいところ」はコロナ禍におけるアイドルの活動の変化に沿っています。会いに行けたのに、会いに行けなくなった。ライブでも声を出せない。「目の前のあなたを見つめる」などの今まで歌ってきた歌詞に対するリアリティーがなくなってしまった。それと同時に、それまでの「対面で応援するファンと応援されるアイドル」という構図も難しくなった。そうした状況でどのような曲がヒットするかを考えた時に、曲によってテンションが上がるようにしようと思い付いたのです。例えば、TikTokでは再生されることではなくて拡散されることが目的。踊って口ずさむ中でテンションが上がる歌詞として、自己肯定感というテーマが出てきた感じです。
加えて、アイドルは自分で曲を作るわけではないですよね。だから本人が歌っているけど本人の言葉ではないんです。みんなそれを受け入れて楽しんでいたのですが、コロナ禍でアイドルと会えなくなる中で、ますますその感覚が強くなり、アイドルの存在が遠ざかってしまう。それよりは、ハッピーな歌を歌って、みんな同じようなことを感じているのかもね、という気持ちになる方が良いのかな、ということも自己肯定感をテーマとした理由です。リアリティーを追求した結果とも言えますね。
──「自己肯定感」を表現することで、それまでのアイドルよりも若い女性に受け入れられやすくなったのではないでしょうか
アイドル業界ではこれまでも女性ファンを獲得する重要性が指摘されてきました。一方で、アイドルに対する応援の構造は自分より力のないものに対して応援してあげている、というものでした。しかし、「それをやったら、私もかわいくなる」というものを提示することで、アイドルとファンが横並びになった。ファンが自己肯定感を上げることが、自動的にアイドルの応援になる、という構造を作りました。これに乗りやすい世代は同じ世代の女性などの、アイドルと同じような感覚を持っている方なのかなというイメージはありますね。
新しいローカルアイドルの形を目指して
──出身地である静岡県にローカルアイドル「fishbowl」を作ろうと思ったきっかけは
地元のテレビ局に勤める知り合いと話したことです。コロナ禍で、テレビにできることは変わりました。地方のテレビ局だと東京で作ったものを流すことも多く、これをあと30年くらい続けることは本当に可能なのだろうか、といった話が上がりました。それで新しいコンテンツを作るのがいいのでは、となり僕ができるとしたらアイドルに関することなのではないか、とざっくりと話したのがきっかけですね。当時の静岡県にはアイドルの成功例がたくさんあるわけではないこと、自分は東京でいろいろなアイドルに関わってきて、特別考えもなしに新しいものを作っても意味がないなと感じてきたころであったことから、地方であればこれまでのローカルアイドルとは異なる形のアイドルグループを作るという挑戦ができるのではないかと思いました。
アイドルを目指すとしたらローカルアイドルとして地元で地道に活動するか、東京を目指すかのどちらかのストーリーに乗っかるしかないという雰囲気の中で、どちらでもないアイドルを作りたかった。それで、ずっと地元にいるけれど地元以外でも評価される、というアイドルを作ろうと決めました。
──fishbowlには「応援企業・団体」がついています。地方での企業や自治体との提携の意義は
東京でアイドルのスポンサーをつけるといった話はフットワークがあまり軽くないんですよね。でも、地方だと東京より気軽な取り組みをいっぱいできたり、東京の企業でも地方だったら少しはフットワークを軽くすることができたり……地方のアイドルにはいろいろな可能性があります。静岡県は約350万人の人口がいます。350万人もいたら、できることも経済的なチャンスも多い。だから、売り上げにこだわったり、CMを一つとるなどと目標を設定したりしてしまうと、それが達成できるか否か、ということに活動が縛られてしまいます。そうではなく、とてもゆるいけど良いつながりみたいなものを生み出して、静岡県をみんなで盛り上げていくという感覚を持てるかが大事だと考えています。この考え方で活動をしていくことで、他では起こりえないような、新しい取り組みの事例がどんどん生まれています。
──地元を中心として多くの企業や自治体が「応援企業・団体」として名を連ねています
「応援企業・団体」は一般的なスポンサーとは異なり、お金のやり取りをしていません。だから自治体も名義を出すことができる。1回パートナーシップみたいなものを結んだ後に、もし一緒にやれることがあったら実際にお仕事として行う、という仕組みです。だから競合他社であろうが関係なく、広く応援してもらうことができます。ただ再現性が高い仕組みではありません。というのは、東京だとかなりのお金を絡ませなければなりません。地方ならではのエピソードですが、応援企業・団体は企業の代表の方と直接お話して決まったり、メンバーの家族と知り合いだったり……ということもあります。
自治体や教育委員会との提携はお金をもらっていないからこそ実現できたことですね。静岡県の教育委員会とは一緒にお仕事をすることもあり、学生や子どもたちとの取り組みも行っています。昨年の県知事選挙では啓発サポーターを務めました。
──グループ全体だけではなく、各メンバーにも応援企業・団体をつけた理由は
今のアイドル文化といえばやはり推し活が一般化してきていますよね。だからむしろ企業であってもその方が自然なのではないかというのが最初から構想としてありました。グループ全体にするか各メンバーにするかは企業側に選択してもらいます。例えば自分と同じ出身、会社の所在地の出身のメンバーを応援するというケースは多いですが、それに限らずメンバーの特技が理由で応援している企業・団体も存在します。
──ローカルアイドルだからこそ実現可能なことも多いんですね
fishbowlならではの背景を持ったメンバーもいます。齋藤ザーラチャヒヨニは地元でアルバイトをしていた時にお客さんからfishbowlの存在を聞いて、ダンスの経験があったこともありオーディションに応募しました。芸能事務所の方にもよく見つかったね、と言われるような人材なんですよ。地方のつながりがあったからこそ見つかった逸材ですね。
同じ時期に加入した佐佐木一心はかつて東京でアイドルをやっていて、解散して地元に戻ってきたもののアイドルをもっとやりたいという気持ちを持っていました。静岡に住みながら東京でも活躍する、ということは今までだったら不可能だったけれど、fishbowlなら可能性がある。才能を持つ人が地方でも活躍できる場を作っていくことが大切だと思いますね。
──fishbowlは東京など静岡県外でも活動していますが、県内での活動と意識的に変えていることは
最近ではTOKYO IDOL FESTIVALに参加しました。東京でも活躍するローカルアイドルが静岡の人にとっても自慢になる――例えば富士山やお茶と同じように、自分たちの町のアイドルが全国的に人気らしいよ、となるのが僕の理想です。だから、東京をはじめとして県外で行う活動は静岡県の人から見てある意味憧れのようなものに見える状況を作りたいです。
──ローカルアイドルを地元以外で売り出すとなると、地元を前面に押し出しそうですが、fishbowlの活動はそうではない印象を受けます
よく考えたら静岡県の色が出ている、というラインにしています。ファンの方が自慢したいのって、誰がどう見ても静岡県のこと歌っています、というよりは実は静岡県のこと歌っているんですよ、という方だと思います。
だからファンの中で考察が盛り上がってくるといいなと思いますね。fishbowlの曲の中にも、実在の景色に関する歌詞が存在します。このようなものをみんなが話して、地域の活性化につながっていくのがいろいろな場所で起こるのが理想ですね。本当に小さなことですが、地道にやっていかなければと思います。
──アイドルは今後地方でどのような役割を果たしていく可能性があると考えますか
fishbowlはいろいろな人のハブになれればと思っています。fishbowlを通じて知り合った応援企業同士がfishbowlとは関係のない新しい取り組みをしたり、新たな採用が生まれたり、ということが起こり始めています。アイドルは目立った広告塔でみんなが憧れたり理想に思ったりする存在のままでよいのです。それを目指した結果いろいろな効果が生まれていくといいですね。
──常に新しいものを追い求める原動力は
音楽を作ることは当たり前にやりたいと思っているし、音楽が大好きであるということを大前提として活動しています。
新しい才能に出会いたいというのも原動力ですね。そういう人が出てくることで、音楽が良くなっていきますし、本当に良いミュージシャンが出てくるかもしれない。音楽って、自分の想像を超えたことが起こるんですね。そういった期待感を持ちながら仕事をしています。











