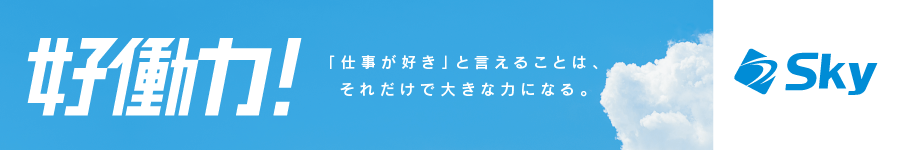2012年夏、日本各地から集まった人々が、福島第一原発事故後の原発政策に抗議するために首相官邸前で大規模なデモ活動を繰り広げた。約20万人もの人々が集まり、「脱原発」と「民主主義の危機」を叫びながら道路を埋めたにもかかわらず、そのデモはテレビや新聞といった主要メディアによって報道されることも、注目を集めることもなかった。
9月2日より渋谷アップリンクにて上映が開始される映画『首相官邸の前で』は、2012年のデモを、ネット上の映像と関係者6人のインタビューから再構成したドキュメンタリー作品だ。監督を手がけたのは、社会学者の小熊英二さん。
後編の今回は、デモを記録するに至った経緯や、アカデミアが社会変革において果たす役割などについて、インタビューを行った。(前編はこちら)

2011年から変わり始めたデモに対する意識
―2014年には、香港と台湾で大規模なデモが起き、そこでは大学生がデモを先導してSNSで積極的に広報を行ったり、大学教授が街頭講義を行ったり、といったアカデミア方面からの介入が目立ちました。小熊さんが取材したデモでは、大学や大学生が特定の役割を担っている場面などはありましたか。
2011年から2012年頃の、私が取材したデモで大学生の団体が目立って活動していたということはなかったと思います。少なくとも私の知る限りでは、特にありませんでした。
そもそも、「学生」という1つのまとまりとして、大学生を見ることにどこまで意味があるのだろう、と私は思っています。進学率が低くて、「学生=エリート」という図式が成立していた時期には、学生がある1つの社会集団でした。限られたエリートとして社会に責任を負い、悪い面があれば変えていかなければならない、という意識があったわけです。大学進学率が15%を超えるとそういう意識はなくなるといわれます。日本なら1960年代まででしょう。いま、学生を一枚岩として捉えることはあまり意味がないと思いますよ。
たしかに2014年には、香港の雨傘運動、台湾のひまわり運動のように、学生主導のデモが大きく報道されました。しかしあれは、また別の背景があります。台湾や香港の雇用状況は日本と比べてずっと厳しいので、大学を出ても安定した職などほとんど得られない。自営業か非正規雇用しか将来像がないのに、地価や物価がどんどんあがっていく。そして、その背景にあるのが中国から流入したお金であり、中国政府は経済力や政治力で自分たちの自由を奪おうとしている、という認識が広まっているようです。そういう状態だから、台湾では中国との貿易協定をめぐって、香港では選挙制度をめぐって運動がおき、学生の参加が多いのは分かります。日本の学生は、まだそこまで追い詰められてはいませんね。ただし、学生全員が政治に強い関心があるというわけではないのは、香港も台湾も同じでしょう。
―2015年現在では、安保関連法案に反対する学生の団体SEALDsが、大規模なデモ活動を行って注目を集めていますよね。
彼らはよくやっていると思いますが、いわば象徴です。国会前の抗議に行ってみればわかりますが、学生が大部分というわけではない。学生グループが主催の抗議に、老若男女のいろいろな人が集まっているわけです。自治会の組織動員とかではないわけだから、学生だけ集まってくるなんてことはありえない。それでも、学生グループが主催しているということで、「学生が立ち上がった」とマスメディアが描きやすいということでしょう。
むしろ2011年や12年に比べて変化があるとすれば、デモに対する一般的な認識がだいぶ変わったのと、ああいう抗議が政治文化として定着したことでしょう。何かあったら官邸前や国会前の歩道に集まって抗議する、というのは、明らかに2012年以降にできた政治文化です。しかも、あんな形態の抗議は、日本以外にはないと思いますよ。
私は2005年に客員教授としてフランスに滞在したのですが、フランスでは高校3年間のうちに1度や2度はデモに参加して、先輩からデモのノウハウを学ぶ、ということがカルチャーとしてありました。学園祭のやり方が、先輩から後輩にうけつがれるみたいな感じに、プラカードの作り方とかが伝授されていく。
日本では1960年代にはそういったノウハウの継承がされていましたが、先ほど述べたように、その素地が一度消えてしまった。それを作り直すことになったのが、2011年以降の出来事だと言えるでしょう。今ではその蓄積のお陰で、主催する側も一からやり方を考えなくてもよくなったし、参加する側の敷居もかなり低くなったと思います。

―とは言え、政治や社会的な問題について公の場で議論したり主張したりといった行為はまだ一般的ではないですよね。『首相官邸の前で』は、そういった議論の場・機会を提供するという意味でも、貴重な作品だと思います。
そうですね。映画を観た後に、観客どうしで話し合ってほしいと思っていますし、映画館にはその時間を設けてもらうように頼んでいます。
ただ、『首相官邸の前で』を観て、政治的なことだけを議論してもらえればいいと思っているわけではありません。あの音楽が良かったとか、あのシーンが良かったとか、そういう感想を話し合うのでもいいと私は思っています。自分としては、あの映画は力のある美しい映像を集めて編集したつもりです。政治的な目的で映像を選んだというよりも、人間の生き生きとした表情や、インパクトのある声が入っている映像を、アーティスティックな感性も重視して選びました。ですから、ある種のインパクトを多くの観客に与えられると思っています。その上で、何を考えるかは人それぞれです。異なる立場から、好きなように議論を重ねてほしいと思っています。
そもそも、人間は色々な話題を、自由に話し合って然るべきです。政治の話題だけを話してもらうことはないけれども、政治の話題を避けるのも不自然です。「これは政治的な話だからやめよう」とかいうのは、実はとても政治的なことですよ。例えば映画祭や講演会などで、主催者が「この作品(議題)は政治的だからやめてほしい」と言ったら、そのこと自体がすごく政治的なことだと思いますよね。政治というのは、人間の営みの自然な一部ですから、自然に話せばいいことだし、特別視されたりタブー視されたりするものではないはずです。
「政治」と「研究」は区別できない
―映画の中では、デモの政治的な側面だけでなく、カラフルな洋服を着たり音楽に合わせてスローガンを叫んだりといった、参加者の祝祭的な雰囲気まで捉えられていましたよね。
ああいうのは不謹慎だ、真面目じゃない、という人もいます。しかし私は、政治的なものと祝祭的なものを区別する必要はないと思っていました。もしも政治と祝祭、あるいは政治と文化を分けるのだったら、その「政治」とか「文化」は一体何なのか、と疑問に思います。歴史家の立場でいえば、そういう発想は、政治的弾圧が厳しかった戦前の時代に、「これは文化ですから弾圧しないでください」という行動をとった「文化人」が多かったことのなごりですよ。
関連していうと、私はときどき「どういった立場からデモに参加しているのか?」と聞かれることがあります。政治的な目的で参加しているのか、それとも研究のためなのか、と疑問に思う人がいるわけですね。しかしこれも、区別する意味はないと私は考えています。たとえば、ラッパを吹いてデモに参加している人は、アーティストとして参加しているのか、政治的目的で参加しているのか。それを無理に区別するなんて、ナンセンスでしょう。
私自身についていうと、スローガンを連呼したりするのは、自分の性に合いませんから、抗議に参加していてもやったことがありません。それでも、参加しているつもりです。そして同時に、色々なものを見て、その運動がどういった方向に進んでいるのかを普段から考えている。そして場合によっては意見を求められたり、メディアの取材に答えたり、人を紹介したり、運動と政治家をつないだり、本を作ったり映画を作ったりする。
ではそれは何なのかといえば、自分は研究者であるとか、映画監督であるとか、一市民であるとか、そういうこと以前に、一人の人間として参加しているわけですよ。また「これは政治活動への参加だ」とか「社会活動への参加だ」考えてやっているわけではない。たとえば、お店でものを買ったり、コンサートに行ったりするときに、「これは経済活動への参加だ」とか「これは文化活動への参加だ」とか考えないでしょう? ずっとそういう形で参加してきたので、スローガンを叫んだりしなくても、主催の人たちなどからは「あの人はああいう参加の仕方をする人なんだ」と認識されていますね。

―大学・大学院では、研究者が「政治的」な発言を避けることが度々見られます。それも、職業的・立場的な理由からだけではなく、「客観的な視点を維持するために、政治的な話題はタブーである」と考えている人が少なくないように思われます。
「客観的な視点」というものが純粋に成り立つのかといえば、私は社会科学では難しいと思いますね。私は物理学を勉強していたこともあるので、観測問題についての議論は知っています。物理学でも純粋な客観など原理的に無理だとされているのに、社会科学でそんなことは不可能だと思います。例えばインタビューをしても、録音機のスイッチを入れただけで、とたんに相手の話す内容や、全体の雰囲気に影響を与えますよね。調査者は透明人間になれ、なんて言いますけれど、それは不可能ですよ。
そういう意味で、「純粋な客観性」を志向しすぎても、実現不可能だと考えています。もちろん、研究とスローガンを区別するのは必要です。しかし例えば、活動家や政治家であっても、冷静に情勢分析をしていることと、強い熱意を持っていることは矛盾しない。私は抗議活動にずっと参加していて、先に述べたようないろいろなことをしたけれども、研究者としての客観性を保持することと、矛盾するとは思わない。少なくとも、「政治的」な発言をしないでいれば、それで自動的に客観性が担保されるというのは、ナイーヴな発想だと思いますね。
―参加者として、また研究者としての立場に立ちながら、デモに参加していたのですね。2012年のデモの重大さについて、当時から意識していたのでしょうか。
私は歴史学者・社会学者として、戦後のことも1960年代のことも調べていましたし、同時代の世界の潮流、例えばスペインやニューヨーク、中南米で起きた社会運動もフォローしていました。だから、それらと比較することで、2012年当時からデモについて「稀有なこと、大きなことが起きている」と認識出来ていました。それがあって、映画制作に繋がった訳です。
しかし、マスメディアの人々は、そういうことが認識できているとは思えなかった。また今回の映画でインタビューした方々や、参加者の多くも、何がどういう規模で起こっているのか、私が考えていたような文脈では理解していなかったのではないでしょうか。今になって振り返って、「2012年の抗議はこういうことだったのか」というふうに、当事者たちにも見えるようになりつつあるようです。当時からある程度の距離を持って、全体像を掴むというのは、なかなか難しいことだったと思います。

参加する学者の重要性
―1つのムーブメントを歴史上の文脈から読み解き、同時代の他地域の運動と比較して位置づける。人文系の研究が「社会的ニーズが低い」と見なされつつある中ですが、歴史学、社会学の重要性が改めて見えてきますね。
運動に参加している当事者はむしろ、今日どういうことがあって、どんな人があんなことをして、どんな試みがあって……というようなミクロな見方になりがちです。ある程度距離が取れている人にしか、歴史的・世界的にどんな意味があるのかということは、なかなか分からないでしょう。またそういうことは、主催者や参加者の第一の役割であるとは思いません。
そういう意味では、私が論文を書いたり映画を造ったりしたのは、まさに学者の役割だったと思っています。けれども、継続的に参加していないと分からないことが多かった。また、ずっと現場にいたからこそ、主催者や参加者から信頼を得て、インタビューをさせてもらったり、映像を提供してもらったり出来たと思います。
映画を作ったのは、論文を書くのと同じように、自分が得てきた学識や持っている視点などを活用して、自分に出来ることは何だろうと考えた結果です。この出来事はきちんと記録しておくべきレベルのものだし、映画として記録することは、国内だけでなく世界の他の国々にとっても有益なことだと思いました。そしてそれは、「人間として」やらなければいけないという意識であって、その結果として「研究者」とか「監督」と呼ばれるのなら、そう読んでくださってもけっこうです、という感じです。そういう経緯で作られた映画を観て、自分がどう思ったか、考えたか、誰かとぜひ話し合ってみてほしいですね。
(取材・文 後藤美波、写真 須田英太郎)
映画『首相官邸の前で』は9月19日より渋谷アップリンク、
リンク:http://www.uplink.co.jp/
作品分数109分
毎回上映後、会場の観客で映画の感想などについて語り合う、