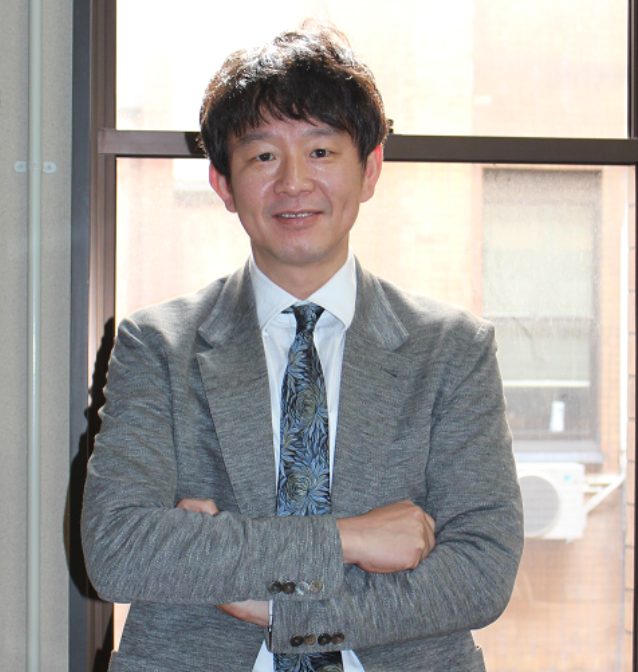大学院と聞いて何を思い浮かべるだろうか。日本では人文・社会科学系で大学院進学率が低く、また理系ではある意味「惰性で」大学院に進学するという学生も少なくはないだろう。大学院と学部の違いとは何だろうか。また、大学院で学び研究する価値や意義とは何だろうか。そこで東大文学部、人文社会系研究科で教鞭(きょうべん)を執る瀧川裕貴准教授(東大大学院人文社会系研究科)に話を聞いた。(取材・峯﨑皓大)
コアな問題意識を持ち研究を
━━学部教育と大学院教育の違い、また大学院教育の中でも修士課程と博士課程の違いをどう考えていますか
私の中では原則として学部でも院でも同じという認識です。確かに教育内容は異なりますが根本的なレベル、とりわけ広い意味でリサーチをするために教育があるという部分では同じだと認識しています。その中で私の専門領域の社会学に限ると、自立的なリサーチ能力が必要になります。もちろん教員のサポートもありますが、社会学は非常に広い分野なので自分の気になることを自発的に勉強する姿勢が必要になります。そしてその姿勢は院生のみに限らず、学部生の時から求められます。修士課程から博士課程に進学すると今まで以上にアカデミックな姿勢が求められますが、実践的なレベル、すなわち自立的なリサーチ能力が求められるという点では学部も院も変わらないという認識です。
その上で、私の研究室やゼミの教育内容の違いを述べるなら、学部生には社会学のオーソドックスな知識を身に付けることに主眼を置いています。それは基本的な幹になる知識が研究を進めていく上で重要になるからです。修士課程以上の大学院生に対しては私の専門領域である計算社会科学に関わる計算的なテキスト分析やネットワーク分析などを学ぶカリキュラムを設けています。
━━院進する学生に対して学部時代にどのような学びを期待していますか
一言で言うと学部生には小さくまとまらないでほしいです。学部生の期間ではある意味で自由に学ぶことができます。もちろん院生になっても自由に学ぶことができますが修士論文のプレッシャーに追われたり、専門的に深く学び、研究しないといけないことが多くなったりします。また、意図せずとも研究を進めていく上で研究内容がどんどん狭くなっていきます。そのようなことがない学部生だからこそできる学びがあり、知的なフットワークを軽くしてほしいです。修士課程以降の研究では自分にとってのコアな問題意識がないとなかなかモチベーションを保って研究することが難しいです。コアな問題意識というのは「地球温暖化問題」のような学問的なテーマではなく「なぜ世の中には権力の上下があるのか」といった、抽象的なもので構わないです。そのコアな問題意識を見つけるためにも広く学ぶことが必要です。その問題意識を一朝一夕で身につけることは難しいからこそ学部時代に好奇心を持ちながら知的なフットワークを軽く、広く学んでほしいです。
━━大学院で学ぶことの意味や価値は何だと考えますか
社会学の分野でいうと、社会学は学問分野が非常に広いため大学院で研究を進めれば進めるほど、より深く学ばなければいけなくなります。一方で社会学の最終的な目標は社会学の知を実際に現実社会に生かすことです。それが社会での証拠に基づいた(evidence-based)意思決定につながり、社会をより良くすることにつながると考えます。
また、東大では前期教養課程の2年間は教養学部に所属し、後期課程での専門的な学びは2年間しかありません。その2年間では理論を学び、それを実証して現実社会に生かすという方法論を身に付けることは難しいと考えています。そのためにも大学院に進学して修士課程でもう2年学び、研究することが必要だと思います。
研究に多様な視点 そして共同研究を
━━人文・社会学系の分野では修士課程進学率が他の専攻に比べて低く、博士課程進学率も減少傾向にあります。国際比較しても日本では人文・社会科学分野における修士号・博士号取得者の割合は低いです。この現状についてどのように考えていますか
これは由々しき事態です。最終的にアカデミアの世界に残らないにしろ、この現代社会で生き残ることは学部の学びだけでは不可能だと思います。大学院では学びを通して問題を設定し、解決のための道筋を立て、問題解決を自ら行えるようになりますが、これはどこで働くにも非常に重要な経験や能力だと考えます。特に、過去の研究を参考にしてデータに基づいた問題解決に取り組むというのは非常に重要な能力で、それを学部だけの学びで手に入れることができるとは考えていません。東大に限っていうと2年だけで身に付けるのは非常に難しいと思います。
━━東大大学院工学系研究科では2026年度から授業が原則英語化されるようになりました
東大の国際化の価値や流れは否定しようがありません。これだけ国際化が進み、学問の分野の垣根もなくなりつつある中で、日本だけで、日本に閉じこもって研究を行うことの意味はありません。その意味で国際化は非常に重要で、どうやったら世界中、とりわけアジア諸国から優秀な人を呼ぶことができるのかを考える必要があると思います。
授業を原則英語で行うことで国際化するという方法もある一方、明治時代にはドイツ語を学んでまでドイツに留学する日本人がいたように、日本語を勉強してでも東大で学びたいと思ってもらえるような価値のある研究を行う大学にならないといけないと思います。また、日本語で教育や研究を行わなければいけない分野もあります。例えば日本社会の分析だと日本語の資料が多く、最終的には日本語で研究をせざるを得ないのが現状です。英語での教育の必要性は分野によっても異なるということも踏まえる必要があると考えます。
━━現状の大学院教育について良い点や改善が必要な点があれば教えてください
東大の伝統として学生にファンダメンタルな知を身に付けることに重きを置いており、それはアカデミズムな思考性を持って研究する姿勢につながるので良い点だと考えます。
一方で課題として、理系の学生や社会人を経験した人ような、多様なバックグラウンドを持つ人が入れるような環境作りが十分とは言えないことが挙げられます。多様なバックグラウンドを持つ人が入りやすいようにして、研究室に多様な視点が多くもたらされるようになってほしいです。また、社会学に限っていうと、分野によりますが基本的には自立性を尊重する風潮があります。それは個人で研究を行う風潮があるということであり、共同研究のようにチームで研究を行うという風潮があまりありません。理系の分野では共同研究がベースになっていますが、社会学ではそうではありません。それは就職の時に共著よりも単著の論文を発表している方が好まれる、というような現状があったり、社会学の研究室は理系のいわゆる「ラボ」のような雰囲気はなく、教員と学生がそれぞれ別のことを行っている雰囲気があったりすることに起因しているかもしれません。研究室の中で教員と学生が一緒に研究をして、一緒に学会で発表することが社会学の分野でも一般的になればもっと共同研究が当たり前になってくると思います。