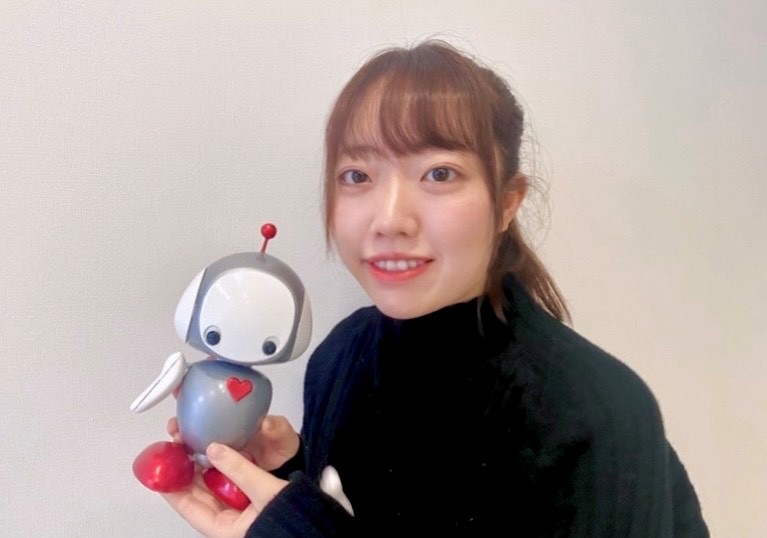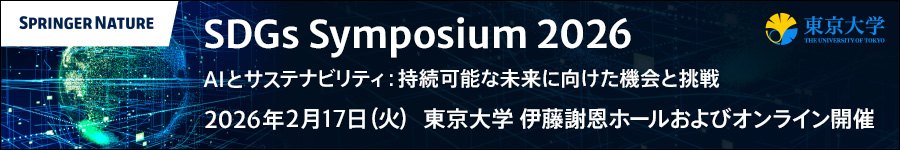2027年より東大に約70年ぶりの新学部「カレッジ・オブ・デザイン」が創設される。そのプログラムの柱となるのが、「東京大学の有する多様な学術知とイノベーション手法としてのデザインの学び」である。今回は「デザインを学ぶ」ことについて、学生に寄稿してもらった(寄稿=太田明理紗)
〜先端アートデザイン専攻の博士課程から見た、いま・これから〜
こんにちは。東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻アート・デザイン研究室博士課程1年に在籍している太田明理紗です。
「東京大学で“デザイン”を学ぶって、どんなことなんだろう?」
2027年から学士課程に「デザインプログラム」が新設される今、私は少し先んじて、博士課程という立場から東大でデザインを学び・研究しています。今回はその経験をもとに、東大におけるデザイン教育と、その中で私が感じていることを綴ってみたいと思います。
1. 東大に「デザインプログラム*」が誕生します
2027年、東京大学で本格的な「デザインプログラム*」が立ち上がります。これまで東大でも、工学系や情報系の中で設計やインターフェースに関わる授業はありましたが、「デザインを核に据えた」学びが本格的に展開されるのは初めてのことです。
プログラムの説明には、
ユーザー理解、コンセプトメイク、プロトタイピング、データ活用、ストーリーテリングなど、イノベーションのためのスキルと柔軟な思考力を磨く
とあります。
私はこの文章を読んだとき、東大が“デザイン”という言葉の本質に対して真摯(しんし)に向き合いたいという気持ちを強く感じました。デザインとは、ただの装飾ではなく、問いを立て、価値を形にしていく知的営みなのかなと私は考えています。その本質に深く入り込んでいく姿勢に、私はとてもわくわくしました。
そしてそれを、5年一貫で徹底的に育てようとする構想には、東大らしい大きなスケールと覚悟を感じました。どのような場になるのか、これからが非常に楽しみです!
2. 私の専攻の「デザイン」とは?
私が現在所属しているのは、先端アートデザイン分野です。アートとエンジニアリング、感性とテクノロジーの交差点のような領域で、人間とモノの関係性そのものに問いを投げかけるような研究が行われています。
この研究室では、美的表現の探求だけでなく、科学的検証、プロトタイピング、ユーザーとの対話、フィールドワークなどを通じて、「意味のあるものとは何か」を繰り返し考える日々があります。
私の研究は、かわいさや遊び心などの人間の知的な営みや、感情の進化的役割や認知の仕組みを、素材・形・動きといった物理的な要素から分析し、それをプロダクトの設計に応用する試みです。
私はもともと美術系でプロダクトデザイン(工業デザイン)を学び、東大のデザイン研究室へ進学しました。形や素材、製造の制約、触感やユーザビリティに向き合ってきた経験に、いま東大で、より深い意味づけや問いの構造を重ね合わせている最中です。
誰かの感情に届くかたちとは何か。問いの温度を、どのように形にするか。そんなことを考えながら、今日も手を動かしています。
3. 東大でデザインを学ぶということ
「デザイン」と一口に言っても、人によってその意味やアプローチは大きく異なります。だからこそ、工学・情報・アートといった多様な分野が交差する東大の環境は、デザインを探究するのにとても豊かな土壌だと感じます。
私が日々実感しているのは、デザインは単に「正解」を導くのではなく、問いを形として差し出す行為だと考えています。ときには違和感として、ときには希望や優しさとして、人の目の前に現れる。
そうした「問いを形にする」プロセスを大切にしている点が、東大のデザイン教育の大きな特徴だと思います。
4. 構造と余白──私が大事にしている2つの視点
良いデザインには、必ず「構造」があります。目に見えない論理や関係性、意味を支える骨格です。
私の研究でも、かわいさや遊び心という感情が、どんな形や素材、動きで喚起されるのかを論理的に分析し、感性の曖昧さに解像度を持たせています。
一方で、デザインには「余白」も欠かせません。
特に日本文化には、「間(ま)」やあいまいさを尊ぶ感覚があります。
私は、完璧で説明的なバランスよりも、少し抜けた“ズレ”に、人間らしさや共感の余地があると感じます。
構造が思考の軸を与え、余白が感情の自由を許す。
その間で揺れながら、「なぜこれをつくるのか?」という問いを自分に投げ続けることが、私にとってのデザイン研究の醍醐味です。
5. デザインの勉強って、どうやって始めるの?
「デザインに興味はあるけど、何から始めたらいいのかわからない」という声をよく聞きます。
私の場合は、高校生の頃に絵の予備校に通い、デッサンを学んだことがきっかけでした。目の前のものを「よく見る」こと、そして「違和感に気づく」こと。それは今の研究にも通じています。
とはいえ、絵が描けるかどうか、だけが本質ではないのかもしれません。
デザインとは、観察し、考え、問いを立て、誰かのために意味をつくる営み。そのために必要なのは、特別なスキルではなく、日々の気づきや、少しの遊び心なのかもと、私は考えています。
6. デザインにはどんな専攻があるの?
「デザイン」と一言で言っても、その中には多くの専門領域があります。
グラフィックデザイン、UI/UXデザイン、エディトリアルデザイン、建築デザインなど・・そして私の専門であるプロダクト(インダストリアル)デザインもあります。
プロダクトデザインは、私たちの生活にある製品——家電や家具、自動車、スマートフォンなど——の外見や機能、使いやすさを含めてデザインする領域です。
この専攻の魅力は、平面にも立体にも関わる「モノ」との対話があること。プロトタイピングを通じて、実際に触れられる“かたち”をつくれる点も、大きなやりがいです。
また、プロダクトデザインは美的センスだけでなく、ユーザー視点、製造の制約、社会的文脈など、非常に多層的な視点を必要とします。
東大の工学系との相性が良いのは、「美しさ」と「問いの構造」が両立している分野だからだと感じています。
7. 最後に
私がデザインを学び続ける理由は、とてもシンプルです。
「誰かの心に、そっと残るものを作りたい」
東京大学は、知の最前線でありながら、感情や曖昧さ、余白や問いといった、かたちにしづらいものに真正面から向き合える場所です。
もしあなたが、「文系か理系かわからない」「自分に何ができるかまだ見えていない」と感じているなら、その迷いは、デザインにとって何より豊かな出発点です。
自分の感性を信じて、問いを見つけ、かたちにする。 分野を超えて、意味を紡ぐ。
それこそが、これからの時代に必要とされる「デザイン」なのだと、私は信じています。