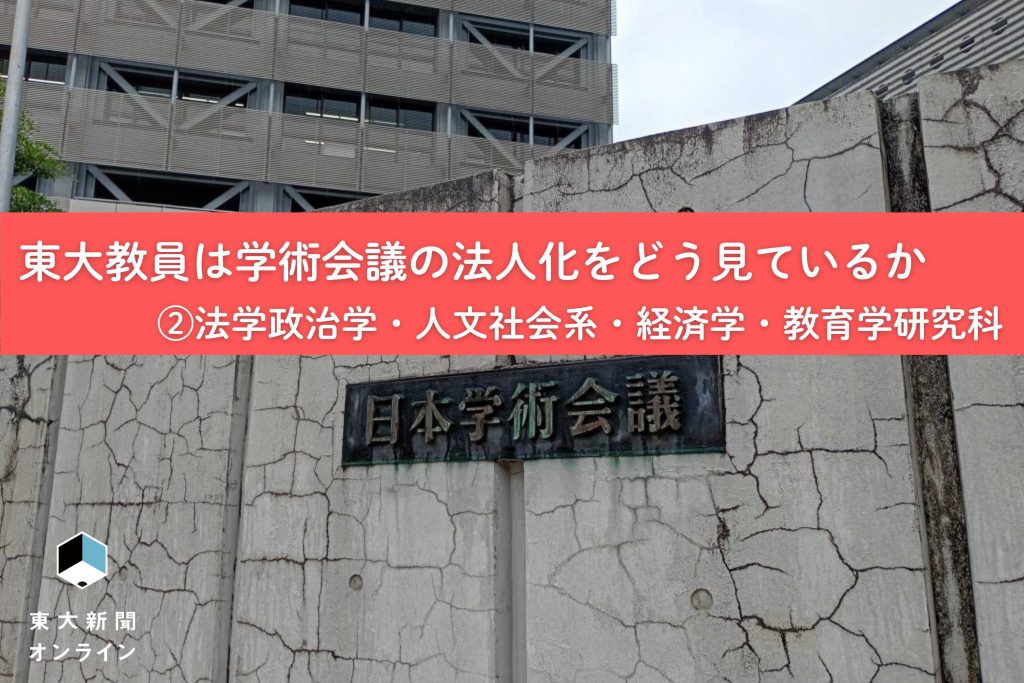
東大には多くの日本を代表する研究者が存在し、東大教員にも日本学術会議の関係者が存在する。5月に衆議院本会議を通過した政府による日本学術会議法人化法案は、6月11日に成立に至った。東大教員は今の情勢をどう見ているか、メールでアンケートを実施した(期間:5/7〜5/26、回答人数:163人)。
ここではアンケートに寄せられた自由記述のうち、大学院法学政治学研究科・大学院人文社会系研究科・大学院経済学研究科・大学院教育学研究科の教員によるものを原文のまま掲載する。他の部局については記事末尾を参照。
※学術会議の法人化に関しては、6月10日付で発行の『東京大学新聞』6月号に特集記事を掲載しています。そちらも併せてご覧ください。(お買い求めはこちらから)
・大学院法学政治学研究科 教授(過去に学術会議の会員または連携会員)
政府にとって、必要な=「耳に心地の良い」学術的助言は、他の審議会や機関で充分に得られている。もちろん、他の審議会での学術的助言を充分に活かす能力は、現在の日本政府にはない。日本学術会議は、政府にとって「耳の痛い」学術的見解を示せなければいけない。同様に、日本政府は聞く力がなく無能であるから、「耳の痛い」見解を発しても、何の役にも立たないが。
・大学院法学政治学研究科 教授
学界のサイレントマジョリティはあまり興味・関心を持っていないように感じられる。そのことが一番の問題なのではないか。自分もその一員なのではあるが。
・大学院法学政治学研究科 教授(現在学術会議の連携会員)
そもそも、政府や与党政治家は、学術アカデミーの存在意義を理解していない。学問の自由が脅かされた戦前のあり方に対する反省も理解していないと感じられる。学術会議のあり方に問題があるとしても、それは学術界が自ら対処すべき問題で、学術アカデミーの独立性や学問の自由の有名無実化を推進することは決して許してはならない。
・大学院人文社会系研究科 吉田寛教授
本件については、私が会長を務める美学会、および美学会を含めた藝術学関連学会連合でも声明を出しています。
・大学院人文社会系研究科 教授
不法な任命拒否に始まる政府による一連の介入は日本における学術研究を大幅に損なうものであり、反対します。また、政府の意向に沿った追従的な体制が構築されたとしても政府が得られるものは益よりも損失だとも考えます。
・大学院人文社会系研究科 教授(現在学術会議の連携会員)
学術会議そのものに問題がないわけではないと考えるが、今回の法案が提出される過程には大きな疑念を抱いている。
・大学院人文社会系研究科 教授
2020年以前の会員任命過程について、何人の推薦があり、何人任命されたかなどの情報を公開してほしい。
※現行法では、学術会議の推薦に基づき、内閣総理大臣が会員を任命する。現行制度下では、2020年に学術会議の推薦に対して菅首相が6人の任命を拒否した以外は、全て学術会議の推薦通りに会員の任命が行われてきた。学術会議の会員は、210人で、3年おきに半数が改選される。(注釈は東京大学新聞社が作成)
・大学院人文社会系研究科 准教授(現在学術会議の連携会員)
学問の自由を奪おうとする政府案には反対。だが、日本学術会議に対しての国民の支持が我々の予想(というよりも「願望」か)よりもはるかに少ない、という事実に向き合う必要もある。
・大学院人文社会系研究科 教授
私の専門は医学の歴史ですが、医学が軍事と結びついたことはナチスや日本のように非常に頻繁に起きてきました。一方で、医学が人類学のような別の地域の研究と結びついたことも数多く存在します。前者は悪いこと、後者は良いことというような単純な二元論は成立しません。医学と軍事と人類学などの境界は、曖昧なものがあります。これらを慎重に考える必要があります。現在の日本では、まだまだ議論が足りないように思います。
・大学院人文社会系研究科 准教授
菅首相による学術会議への会員の任命拒否は、それ自体が極めて重要な問題であるが、それ以降、学術会議への根拠不明のバッシングが日本社会に蔓延するのを放置したままにしたという点で、まことに罪深いものであった。教育に介入し続けた安倍政権によって培われた「リベラル」な学者叩きの傾向は、トランプのアメリカのそれとも通じる。ハーヴァードではないが、学術会議は政治権力に屈することなく、学問の自由を守るべく理念を掲げ続け、社会に訴え続けていくべきである。一人文学徒としては、学術会議もそこから生まれてきた、戦争の時代としての20世紀の経験を思想的・歴史的問題として考え続けていくことの必要性を再認識している。
・大学院人文社会系研究科 教授(過去に学術会議の会員または連携会員)
日本学術会議が80年前になぜ作られたか、その初心忘るべからずであり、学術研究者が進んで戦争に協力しないのはもちろん、政府が戦争に肯定的な政策を進めていたら諫言するという役割を今後も貫いてほしい。そのためには主権者(一般国民)に向けて積極的に情報発信して啓蒙すべきである。また政府当局者や国会議員は、自分たちが国家権力の執行を一時的に委任されているにすぎないということをしっかり自覚し、過去の人たち思いを汲み取り、「学問の自由」の重要性を学習しなおしてほしい。近隣某国でこの十数年来進行している主席崇拝と言論封殺の状況を反面教師とすべきである。
・大学院人文社会系研究科 教授(現在学術会議の会員)
私は日本学術会議会員です。日本学術会議は、政府からの適切な独立性が確保されていて初めて、日本のために有意義な活動ができると考えています。現在、国会で審議中の法案は、将来的に政府の介入を強める危険性を含むので、修正を求めたいと思います。
・大学院経済学研究科 星岳雄教授
学術会議が政府の機関である限り、政府の介入は避けられない。
・大学院経済学研究科 教授
学術会議は「我が国の科学者の代表機関」などとされていますが、実際は学者の代表でもなく、日本の学術界を代表してもいません。会員の選考に関する情報がまわってきたこともありません。ですので一部の学術会議の関係者が、学者の代表であるかのような行動や発言を行っているのは迷惑です。
・大学院経済学研究科 教授
私自身は6人の任命拒否の際などはぼんやりと問題だなとは感じていたものの、今は反対派の方々の活動の仕方や極端な言動・党派性を見て非常に疑問を感じ始め、このような人たちに勝手に「学術界の意見」を代表されるくらいであれば、政府のコントロールの方がよほどましだと感じるようになった。特に、弊学の一部教員については勝手に「東京大学教職員組合執行部有志」を名乗って勝手に組合の統一見解のように誤認されるような文章を同HPに掲載したり、Youtubeでのアジ演説のようなものを見て、この人たちや学術会議なるものの構成員というのはどういうレジティマシーがあって勝手に学術界を代表されるのか、そもそもこの組織の運営自体が極めて非民主的であり、それがゆえにこのような事態になっていると感じるようになった。米国の民主党左派の極端なDEI推進が逆向きの反動を生んでいるのに近い感じになっていることに近い感じで多くの研究者にある種のアパシーを生み出していると感じる。何故社会科学者(ではないかもしれないですが)であるのにもかからずこのようなことになぜ無自覚であり、党派的に極端な主張を前面に押し出して自分のイデオロギーを前面に出すのか理解に苦しむ。学会・研究者の世界のより多くの人の意見がきちんと集約されなにのであれば、そのような機関の独立性にどのような価値があるのだろうか。
※東京大学教職員組合は、5月7日、東京大学教職員組合執⾏委員会有志の名前で声明を発表した。(注釈は東京大学新聞社が作成)
・大学院教育学研究科 本田由紀教授(現在学術会議の連携会員)
学術会議を法人化しようとする現法案は、国立大学の法人化と同様の問題点を含んでいます。
※国立大学の法人化については、弊紙2024年10月号「学費問題&法人化20年特集号」で特集しています。こちらも併せてご覧ください。(注釈は東京大学新聞社が作成)
・大学院教育学研究科 隠岐さや香教授(現在学術会議の連携会員)
もしも日本が自由な民主主義的な国家としての矜持を持つのならば、学術会議を法人化するにあたり、ナショナル・アカデミーの五要件を満たさない制度設計をするべきではない。 自分が確認する限り、この五要件を満たさないアカデミーのある国では、政府による教育や研究へのイデオロギー介入が起こっている。 例外は現在のアメリカであり、全米アカデミーズは独立を保ちつつ沈黙している。また、学問の自由への抑圧は最初、政府からではなく、市民団体から起こり(大学へのカリキュラム介入など)、それがトランプの勝利により政府による弾圧という形をとった。アカデミーはその中で攻撃から免れてきた。おそらく今もまだ政権とトランプ派市民たちの視野に入っていないのだろう。アカデミーは独立性を保っているからこそ、いずれ米政府と大学を仲介できるかもしれないと考えているようだ。いずれにせよ学術会議も独立性を担保した形を保つことが重要である。
※ナショナルアカデミーの五要件とは
2021年に学術会議が提示した、(a)学術的に国を代表する機関としての地位、(b)そのための公的資格の付与、(c)国家財政支出による安定した財政基盤、(d)活動面での政府からの独立、(e)会員選考における自主性・独立性、の五つ。(注釈は東京大学新聞社で作成)
・大学院教育学研究科 教授(過去に会員または連携会員)
学術会議は原発事故やコロナ禍などで有効な対応ができなかったことや、研究者の非正規雇用などの問題に必ずしも十分な対応ができなかったことなどの問題があり、活動や外部への発信の在り方、会員の選任方法などの改善(中曽根政権以前の選挙による選任に戻すなど)が必要である。ただしそれは研究者コミュニティが自律的に行うべきである。今回は不当な任命拒否を正当化するための政治的介入という側面が強く、学術研究に必要な自主性・独立性を損ねる改革である。そのときの政権に親和的な研究者が権勢を振るう団体になることを危惧している。
・大学院教育学研究科 教授
国家権力が学術研究に介入し、研究者の自律性および研究の自由を著しく侵害する方向に向かっていることを強く危惧しています。
・大学院教育学研究科 教授(現在学術会議の連携会員)
学問の自由の大切さについて、もっとかみ砕いて説明していかないといけないと考えています。
【他の部局についてはこちら】










