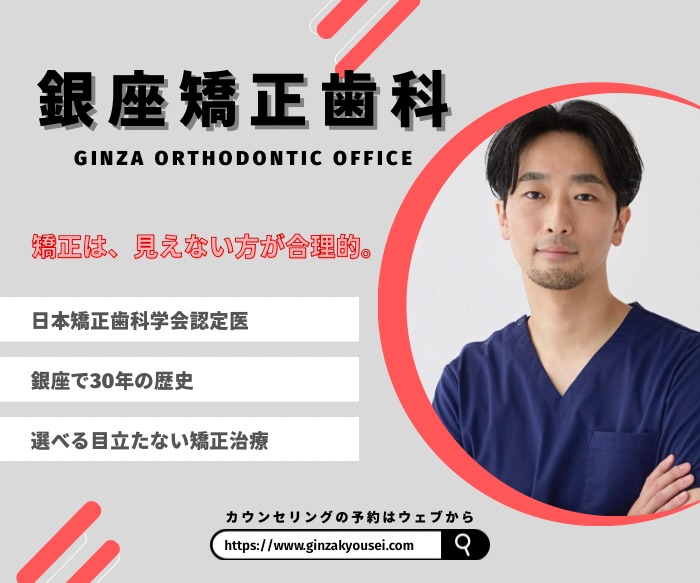少子高齢化や相次ぐ自然災害─現代日本は多重な社会課題を抱える。そして東大生は時としてそうした社会課題の解決の役割を求められる。しかし、そこにまつわる社会の観念は一筋縄ではいかない。「東大生ならばなんとかしてくれるだろう」という期待と、「東大生は何も分かってくれまい」という失望があり得る。特に地方において「東大」というブランドがある種神格化されているからこそ、社会と関わる東大生は複雑な二律背反性のはざまに置かれることになる。
石川県の能登町(のとちょう)は、2017年にフィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)へ参加して以来、9年連続で東大生を受け入れている。17年度に1期生が活動してから、今年度は9期生を募集するまでに至った。能登町で活動してきた東大生の姿とはどのようなものだろうか。そして、東大生と関わってきた地域社会の実像とはどのようなものだろうか。(取材・宇城謙人、吉野祥生)
(昨年度、本年度は地震の影響により、FSの枠組みではなく体験活動プログラムとしての実施となっているが、活動内容や趣旨が23年度以前とほぼ同一であるため、本稿では全てFSとする)
※FSとは…東大が学内生向けに実施する課外活動プログラム。学生たちが3〜5名程度のチームで国内各地を年3回程度訪問しつつ、提示された課題解決に現地自治体担当者とともに1年間取り組む。
【記事の前半はこちら】
「東大生はスーパーマンではない」 能登町役場・灰谷貴光さんインタビュー
東大生が社会と関わる上で無視できないのは、受け入れ側の地域の存在だ。2017年よりFSで東大生を受け入れてきた能登町の担当者である灰谷貴光さんは東大生の活動にどのようなことを思ってきたのだろうか。
━━東大生にはどのようなことを期待してFSに応募したのですか
能登町って5歳階級別の人口を見ると、20代が最も少ない人口構成をしています。大学は金沢近郊まで行かないとなく、高校卒業を機に町を出てしまう人が多いです。町でも大学生が歩いていることはないんですよ。人口減少社会でどのように地域づくりをしていこうかと考えたときに、大学生が能登町に来て、町民の方々と話し合う中で何かが生まれれば良いな、と思っていました。もしかしたら地域の課題が何か解決できるかも、というワクワク感が起これば良いな、と思っていました。
━━ワクワク感、ですか
そうです。皆さんはどんな時にワクワクしますか。私は「初めてのもの」に出会った時だと思うんですよね。そうそうできないな、ということができると思うと、ワクワクするじゃないですか。大学生がいない地域に大学生が来るだけでも、ワクワクするんじゃないかと。
━━能登町は9年連続で東大生を受け入れていますが、継続的に受け入れてきたことには理由があるのでしょうか
受け入れる側としては経験値のようなものが蓄積していくのは大きいですよね。
1年目なんかは、「大学生、めっちゃ何かしてくれるんじゃないの」みたいな期待が大きいわけですよ。でも、大変失礼ですが、1年の活動でそこまでできるはずがない。でも、活動の中でできるつながりがあるわけです。1期生が2期生と仲良くなったりだとか、能登町のお祭りに来てくれたりとか。地域の方ともつながったりするわけです。そうしたつながりが大切なんだなというのはすごく感じるところです。
━━東大生が活動するにあたって、期待通りだったこと、逆に期待通りにならなかったことはありますか
実はですね、良い意味であまり期待していなかったんですよ。地方では東大って看板、大きいですよね。それ、たくさん使ったほうが良いと思うんですよ。ただことによってはスーパーマンが来たと思われる。期待値のコントロールが難しいわけですよね。ものすごいギャップがあるわけです。
━━正直、「何もできない」というのが私がFSでの経験で感じてきたことです
玄田先生も1年では何もできないと言っていますよね。FSは、解決できないことがあると東大生に知ってもらうプログラムだって。
最初は私も、東大生は年齢が違うし、話が合うわけない、ギャップがあると思っていました。しんどいかな、と。でも、だんだんと関わっていく中で、私が飾る必要もないと思うようになってきたのです。そうすると、全然緊張感がなかったですね。
期待は、やっぱりさほどしてはいません。でも、つながりの中で何か生まれれば良いな、と思っています。
━━無理な期待は禁物ですよね
東大生という看板は大きいし、信用度も高いです。その看板は強い武器だし、だからフルで活用してほしい。でも、もろ刃の剣なわけですね。期待度から言えば、年度末の報告の時に最後にガクッときてしまうこともあり得るわけです。
このFSというプログラムで何が良いかって言ったら、日本海に突き出た能登まで来てくれることなんですよね。なかなか来られないところまで学生が来て、ここにある価値観を知ってもらうことに意義があると思っていて。
私たちが東京に行く時、高層ビルを見上げて首が痛くなったりするわけです。なんかうるさいし、みんな急いでいるし。数字を追っかけてせわしなく動く生活をしているわけです。
でも能登に来れば、田んぼが広がっていて、そこでカエルが鳴いていて、それがうるさくて眠れないという感じで、東京と価値観が違うわけです。数字で測れない良さですよね。学生にはそこを知ってくれるとうれしいです。
━━少しでも能登の価値観を知ってもらうことに意義があるということですか
能登町は2010年から人口が2割減少し、高齢化率は10%以上上昇して50%を超えています。数字でいえば無理ゲーで、かなり厳しいものがあるわけです。
でも、それは1年間365日能登町にいる人の話です。それにこだわらなくても良いのではないかと。「関係人口」であれば365分の1でも良いわけです。それでも何かが生まれると思うんですよね。
━━そこで能登町にインパクトが生まれれば、ということでしょうか
「希望」って大切だと思うんですよね。私は能登半島地震発災直後から避難所運営に奔走していましたが、そこで思ったことは、「希望」は作るものではなく、生み出すものだということです。誰かが作った「希望」はそれほどワクワクしないかもしれない、と。ワクワクする「希望」というものは自分から湧き出て、誰かに伝播(でんぱ)するものだと思うんです。学生たちも東京から能登町に来るとき、何かしらワクワクを感じていると思うんですよね。一人一人がどのようなことにワクワク感を持つかは違うかもしれないけど、それをミックスできたら良いかなと思います。ワクワクする「希望」を生み出すには、まずはワクワクを共有することが大切だと思うので、「中の人」と「外の人」が対話できる場は必要だと思いますね。
━━東大生が能登町に関わることによって、何か「希望」は生まれましたか
大学生がいない地域なので、大学生が歩いていたり、話せるだけでも地域がワクワクするんですよね。大学生は珍しいから、町の人もよく声を掛けます(笑)。それは私たちにとっては当たり前のことですが、そうやって私たちにとっての「当たり前」と東大生にとっての「当たり前じゃないこと」が出会って、東大生の「当たり前」になっていくのも面白いですよね。
昨年1月1日、午後4時10分に私たちの人生は一変し、多くの大切なものを失いました。でもそこから得られたものもあります。得られたものの一つが人とのつながりです。復興という道は、1人だけ、地域の中の人だけでは乗り越えられるものではありません。その点では、東大生が関わってくれるというのはとても意義があると思います。
地域とのつながりという話でいえば、8期生は小木中学校の「最後の登校日」に参加してくれました。これは中学校の閉校にあわせ、地域の方みんなに登校してもらうというイベントです。神田さんは建築が専攻なので、地域の方に建築についての授業をしたりだとか。能勢さんはお祭りの授業をしたりだとか。それぞれが得意なことを地域に還元する場になりました。私は「出番」というものが大切だと考えていますが、そういう機会になったと感じてもらっていればうれしいですよね。
━━大学生ではなく、「東大生」の出番とはどのようなものでしょうか
やはり「東大」という看板で人を引きつけて地域に飛び込むこと。そこから後は自分が試されるわけですが、東大生はツールの一つとして、東大の先生から得られる学びを持っています。そこは強みですよね。

はいや・たかみつ/能登町役場職員。2017年度よりふるさと振興課の一員とて、FSや体験活動プログラムでの東大生の受け入れに関わる。現在、復興支援課において復興支援計画の実装を担当。
記者の目
「東大生と社会」━━その関わり方には東大生一人一人、切り取る社会の一つ一つで異なるものがある。どれが正解か、というのは決め難いものであるが、9年連続で東大生を受け入れてきた能登町は一つのロールモデルとして良いだろう。
「東大生はスーパーマンではない」という灰谷さんの言葉が響く。受験戦争を経て国内最高峰の大学に入学した事実は背負う看板を大きくするが、それだけでは社会と関わるには不十分だ。肥大化した看板の余計な部分をそぎ落とし、謙虚に己に向かい合うという意識はいつも求められている。