
毎年多くの東大生が受験する国家公務員採用総合職試験。国家公務員を志す人にはもちろん、まだ進路に悩んでいる人にとっても国家公務員自らが語る職務の実情やその素直な感想は参考になるだろう。
今年は、総務省(事務系、技術系)・国土交通省・内閣府・文化庁・特許庁の東大出身者に取材。現在の省庁を選んだ経緯や担当する業務内容、省庁の魅力や就活生へのメッセージを聞いた。第1回では総務省と国土交通省を紹介する。
(構成・赤津郁海、取材・宇城謙人、赤津郁海、曽出陽太、田中莉紗子、岡拓杜、本田舞花)
国民生活の土台を支える 総務省(事務系)

| 受験区分 | 教養区分 |
| 学部/院卒 | 学部卒 |
| 入省 | 入省3年目 |
| 文理 | 文系 |
| 学部3年 | 春〜夏 |
教養区分の対策を開始、省庁・民間のインターンに参加 |
| 秋 | 教養区分の1次・2次試験合格 | |
| 12月 | 教養区分最終合格 | |
| 学部4年 | 6月 | 官庁訪問 |
| 2023年 | 入省 |
全国各地の人と土地の魅力を学びながら、国家としても大きな仕事ができるという点が総務省を志したきっかけだ。説明会やインターンシップに参加する中で、行政を住民に届け、幅広く日本全体に貢献できるというミッションに共感し、入省した。
東大入学時は理II。前期教養課程では教育や歴史にも興味を持ち、幅広く学んだ。理系の専門性を生かして国家総合職に就職することも考えたが、イメージしていた国家の中枢に関わる官僚像を体現でき、幅広い仕事ができると感じた事務系での就職を希望。後期課程は法学部第1類に進んだ。
法学部進学時には国家総合職への就職の意識が強く、将来の仕事に役立つと感じた法律と政治の両方の勉強に励んだ。中山洋平教授(東大大学院法学政治学研究科)のヨーロッパ政治史に関する授業を通して日本の政治制度の起源を探ることで、現代的な政治課題の解像度が上がった。法学部では友人と勉強に励む機会も多かったという。
試験勉強を始めたのは3年次の春。当時国家総合職に就くために最速となる、3年秋の試験を見据えていた。1次試験となる教養試験を突破しなければ論文やディスカッションが採点されないため、まずは教養試験の対策を進めた。6月頃からは1人で対策するのは難しいという考えのもと、国家総合職を志す友人らと勉強会を開いたことも。国家総合職を志しつつ、民間就職も視野に入れて就職活動を行った。
入省後は消防庁救急企画室に配属。3カ月間、消防や救急の現場を目の当たりにした後、愛知県庁へ出向。大都市からベッドタウン、山間部や離島までさまざまな行政のあり方を経験した。1年間の出向後に戻ってきた本省では自治行政局の地域情報化企画室で、特に地方部で不足しているデジタル人材の確保・育成に関わった。現在は大臣官房秘書課で職員採用に関するイベントの開催、職員の研修を担当している。
総務省の魅力は、地方行政を全般的に扱えること。「地方行政は住民の生活と直結していますし、そこが回らなければ省庁がどれほど良い施策を考えても、良い行政サービスとしてアウトプットされません」。霞が関での関係省庁や地方自治体との調整は大変だというが、そのぶん国民生活を支えているというやりがいは大きい。
国家公務員となるためには「素直な人」が向いているとのこと。日本を良くしようという目標のもと、他人の意見を聞き入れつつ向上心を持つことが必要だと力強く語った。
人と人、国と国をつなぐ仕事 総務省(技術系)
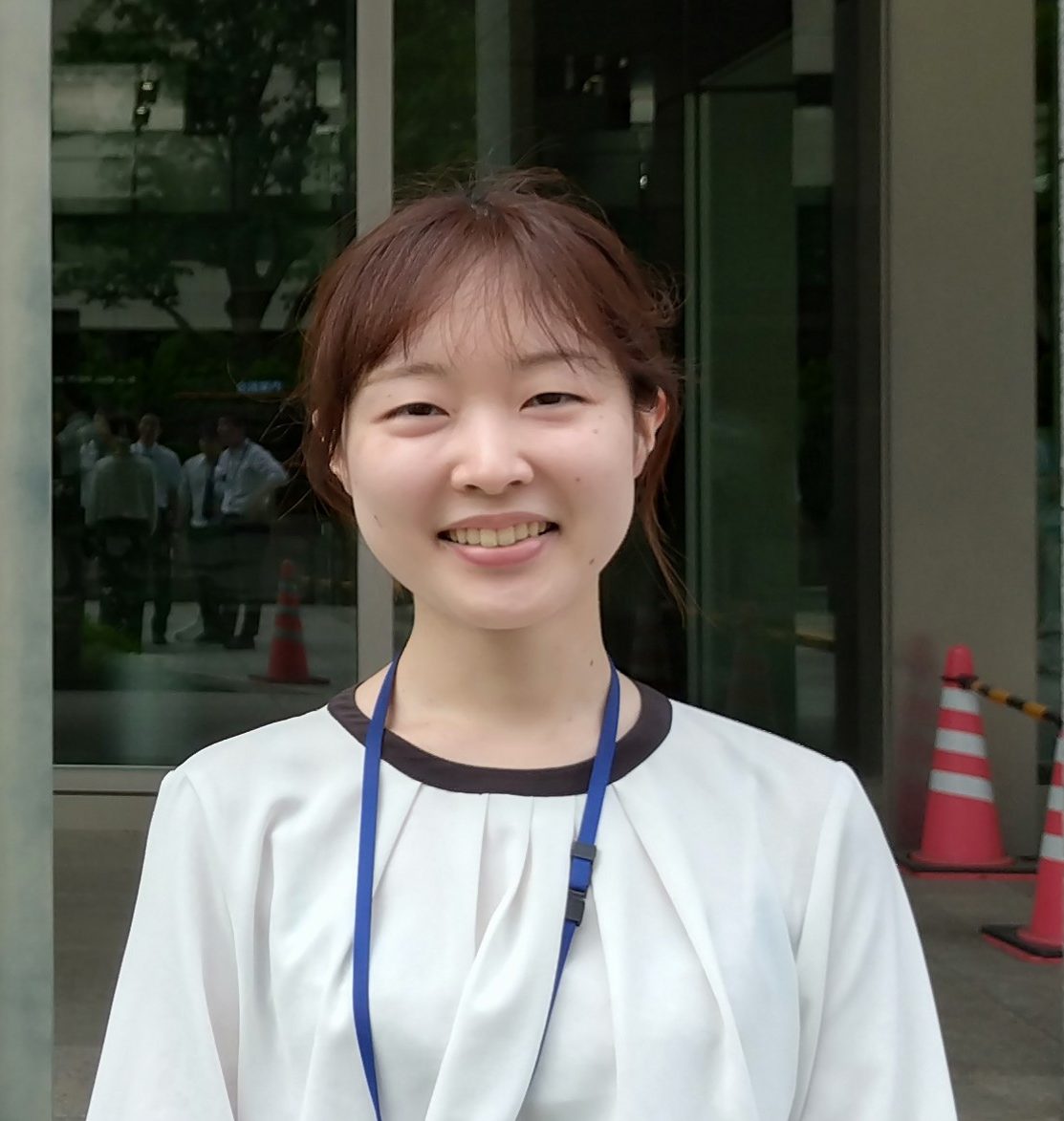
| 受験区分 | 森林・自然環境区分 |
| 学部/院卒 | 院卒 |
| 入省 | 入省2年目 |
| 文理 | 理系 |
| 修士1年 | 夏 |
民間・公務員のインターン、 説明会に参加 |
| 1〜2月 | 民間企業の就活を少しだけ行う、基礎能力試験の勉強を開始 | |
| 3月 | 森林・自然環境区分の勉強を開始 | |
| 修士2年 | 4月 | 試験受験 |
| 6月 | 官庁訪問 | |
| 2024年 | 入省 |
宮崎県出身で、地域に貢献したいという思いが強かった矢野さん。学生時代は農学部・農学生命科学研究科で、環境学を専攻していた。修士1年〜2年次にかけて参加したフィールドスタディ型政策協働プログラムでの活動は、国家公務員の仕事に近く、現在の業務にも直接生きているという。国家公務員への就職を強く意識したのは、修士1年次の前半。中でも情報通信事業を所管する総務省は、幅広い社会課題に貢献できる点で魅力的だった。
国家公務員試験は森林・自然環境区分で受験。研究の中間発表と時期が被っていたが、発表の準備は早めに済ませ、直前は試験対策に注力した。専門試験は院試に近い問題で、試験の1カ月ほど前から過去問を解くなどして対策した。出題範囲が広い基礎能力試験は、過去問から出題傾向を分析し、頻出の問題を重点的に勉強した。塾や互助会などには参加しなかったが、面接の対策に生協を利用していた。官庁訪問には苦手意識があったが、「相手の望むような回答を詰め込むのではなく、自分の意見を伝えることが大切だと思います」と話す。
入省後は国際戦略局技術政策課に配属された。主な業務は研究開発支援。日本の情報通信技術の社会実装・海外展開を目指し、革新的情報通信技術(Beyond5G(6G)基金事業を活用して民間企業や大学などによる研究開発を支援する。特に印象に残っているのはスペインで開催された「MWCBarcelona」への出張。国際共同研究として、国同士が連携し新たな枠組みを作る場に参加できたことは光栄だったという。「総務省は若手にも積極的に挑戦や経験の場を与えてくれる環境です」
人と人、企業と企業、国と国をつなぐ仕事に携われることは総務省の大きな魅力。一企業の利益でなく、国全体や数十年後の未来まで考えて仕事に取り組んでいる。「情報通信技術を生かして、国民が暮らしやすい世の中を作ることに少しでも貢献していきたいです」と話す。
総務省で働く上では、何事にも関心を持ち、疑問はとことん追求する姿勢が大切。「研究開発支援を進めるには、総務省としてもその研究内容の本質を理解しなければ議論や支援ができません。情報通信分野は技術革新のスピードがとても速いので、行政側もそれに対応する必要があります。実際に周りには、打ち合わせ中でも分からないことは積極的に質問する人が多いです」
国民生活を支えるインフラを担う 国土交通省

| 受験区分 | 経済区分 |
| 学部/院卒 | 学部卒 |
| 入省 | 入省2年目 |
| 文理 | 文系 |
| 学部3年 | 秋 |
試験の対策を開始、民間就活も並行して行っていた |
| 3月 | 経済区分で試験を受験 | |
| 学部4年 | 夏 | 官庁訪問 |
| 2024年 | 入省 |
学生時代はボランティアサークルに所属し、地域の小学生の休日の居場所づくりに関わる活動に取り組んでいた。経済学部を卒業後、国家公務員の道へ進んだ。
広く社会に貢献できる仕事がしたいという思いを胸に民間就活も行っていたが、社会を根本から支えているのはルールを構築する立場である国だと考え、国家公務員を選んだ。大学3年次の3月に国家公務員試験を経済区分で受験した。過去問や予備校を利用し受験勉強に取り組んだが、経済学部での学びが生きる部分も多かった。
数ある省庁の中で国土交通省を選んだ理由は、住宅や道路、鉄道など国民の生活に最も身近なところで、地に足のついた施策を立案できるから。持続可能なインフラの構築により、人口減少が進む中でも、国民が住みたい場所に住み続けられる社会を作りたいという思いも語ってくれた。また、官庁訪問で感じた職場の雰囲気も国土交通省を選んだ決め手になっており、入省後もギャップを感じずに働けているという。
現在は新幹線などの整備を管轄する幹線鉄道課に勤務している。日本の基幹的な交通ネットワークを担う新幹線の整備に向けて、多岐にわたる調整を進めることが主な仕事だ。入省2年目ということもあり、会議のセッティングや議事録の作成といった細かな仕事も担う。今後は、所掌の広さを特徴とする国土交通省の中でさまざまな部署に異動し、多様な経験を積んでいくことになるという。
仕事で印象に残ったことを聞くと、2022年に開業した西九州新幹線の沿線を訪れた時の話を語ってくれた。「出張の際に嬉野温泉駅という佐賀県内の新幹線駅を視察したのですが、地元のタクシーの運転おかみ手の方や旅館の女将さんにお話を聞くと、新幹線が開業したことでお客さんが増えたとおっしゃっていました。そのような声を聞いたり、新幹線の開業で街が変わり始めるのを目にしたりすると、やっぱり自分の仕事が人々の暮らしにじかに影響を与えているのだなと実感できます」
向いている学生像を聞いたところ、求められるスキルは民間企業とそれほど変わらないと感じるが、自分と同様に広く社会に貢献したいという軸を大切にしている学生にぜひ国家公務員を志してほしいと答えた。国土交通省は日常の当たり前なところから社会を支えたいという学生におすすめできるという。「世間でイメージされているほど待遇や職場環境は悪くないと感じます。入ってみて後悔することはないと思うので、ぜひ飛び込んでみてください」










