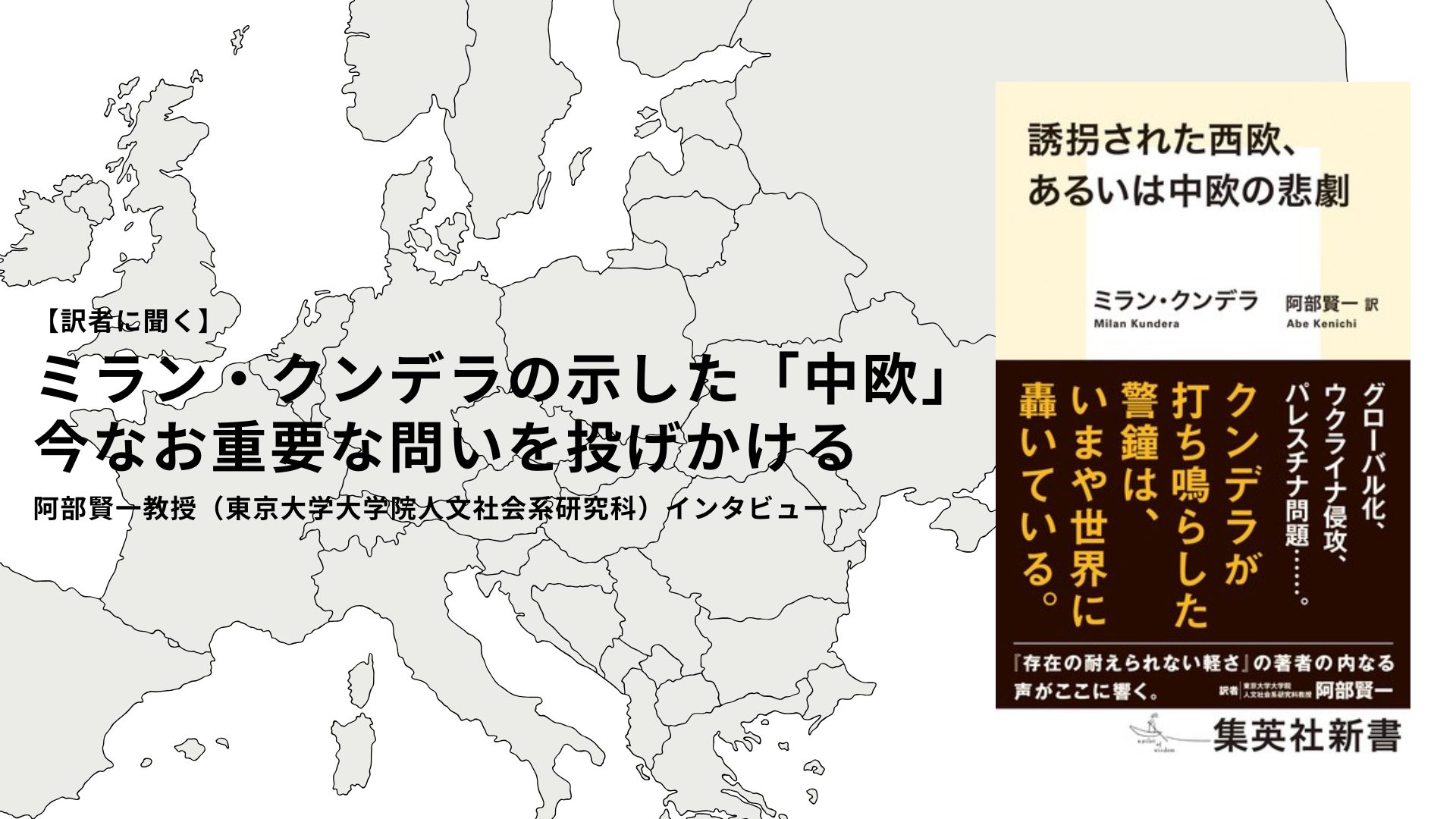
『誘拐された西欧、あるいは中欧の悲劇』(原題:Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale)は1983年にミラン・クンデラによって発表された評論だ。クンデラは中欧を「小民族」にという視点から定義し、文化的に西欧に属していたはずの中欧が第2次世界大戦後にソ連によって東側に編入されたことを「誘拐」としている。大国が幅を利かせるとき、翻弄される小国、小民族が存在するという図式は世界で長らく続いており、この評論は今なお重要なメッセージを投げかけている。そこで、『誘拐された西欧、あるいは中欧の悲劇』(集英社新書)を翻訳した阿部賢一教授(東大大学院人文社会系研究科)に話を聞いた。(取材・峯﨑皓大)
新たな「中欧」を提示 東でも西でもないオルタナティブ
━━この文章の著者ミラン・クンデラは『存在の耐えられない軽さ』などで知られる小説家です。彼はどのような小説家なのでしょうか
彼は旧チェコスロヴァキアに生まれ、1975年にフランスへ渡った作家です。チェコ語とフランス語で小説を書いた越境作家として知られています。小説の大きな特徴は「アイロニー」です。アイロニーは日本語では「皮肉」と訳されることが多いですが、字句通りの意味と話者の意図の不一致を意味します。初めての長篇小説『冗談』は、主人公がはがきに冗談のつもりで書いた言葉が周りからそのように受け止められず、深刻な状況を招いてしまうという物語です。このような「ずれ」は日常の一場面から歴史的な局面でも取り上げられ、一つの言葉や表現の多義性を手掛かりにして、小説の可能性を探究した作家だと言えます。
━━『誘拐された西欧、あるいは中欧の悲劇』が刊行されたのは83年ですが、同時代的な評価はどのようなものだったのでしょうか
この評論の影響は絶大なものでした。フランス語で発表されたこの文章はすぐに英語に翻訳されたため、西側だけではなく幅広い読者に読まれました。当時はまだ冷戦の時代で、多くの人が東西という対立しか意識していない中、中欧という選択肢を提示したからです。84年にはチェコの知識人による地下出版の雑誌『中欧』が刊行され、社会主義体制下の人々にも大きなインパクトを与えました。とりわけ、ハプスブルク帝国の下で共通の文化や制度を有していた歴史に光を当て、チェコ、ポーランド、ハンガリーの人々に対し、「中欧」だというアイデンティティーを提示し、自分たちは「東欧」ではないという意識を植えつける契機になったからです。
━━ドイツ中心の中欧統合を唱えたコンスタンティン・フランツのようにドイツの存在を前提として中欧が語られることが多かったと思いますが、この文章ではドイツを明言せずにあくまでも「西欧」と述べるにとどまっています。従来の「中欧論」とクンデラの中欧論の違いは何でしょうか
従来のドイツにおける中欧論とは小ドイツ主義(プロイセンを中心にドイツ統一を企図する思想・運動)と大ドイツ主義(オーストリアに中心にドイツ統合を目指す思想・運動)の対立の中で語られたものでした。この時に語られる中欧とは、ドイツ語で“Mitteleuropa”、端的に言えば、ドイツ主導の構想を示すことが多いです。
一方で、クンデラは「中欧」を“Europe centrale”とフランス語で表し、“Mitteleuropa”とは別の概念だと明言し、この「中欧」は多民族、多文化、多極的、多中心的なものであるとしました。特定の場所が中心となるのではなく、プラハやワルシャワなど力が分配された空間を想定していました。この概念の下敷きになっているのは、ハプスブルク帝国です。今日のオーストリアはドイツ語圏と捉えられがちですが、ハプスブルクのオーストリアは多民族、多言語、多文化な場でした。ですが、38年のミュンヘン会談を経て、ズデーテン地方がドイツに割譲された出来事など、ドイツに対する強い警戒感がチェコの人々には根強くありました。そのような中、自分たちの位置を措定しようとして、クンデラが依拠したのが中欧(Europe centrale)という概念でした。
━━この文章を通してクンデラは「東欧」に強い忌避感を抱いているように感じました。また、ポーランド人やハンガリー人などが自国を東欧とカテゴライズされることを嫌がることがあるという話を聞いたことがあります。「東欧」に対する忌避感はどこから来ているのでしょうか?
「西欧」と「東欧」のあいだにはイメージの非対称性があります。近年はウクライナ侵攻で、ある意味で脚光を浴びていますが、この地域に関する情報の発信は圧倒的に少ないです。そのため、多民族、多文化でありながらも、ロシアの衛星国というイメージが長年定着していました。言語的にはスラヴ語が多く話されていますが、セルビアなど、より東側ではキリル文字が使われ、東方教会が優勢であるのに対し、チェコやポーランドなど、より西側ではラテン文字が使われ、カトリックの影響が強く残っています。そもそも「東欧」は時代によって意味が異なりますが、20世紀後半、社会主義圏のヨーロッパと同義になりました。そのため、冷戦下では、ロシア的なもの、キリル文字、東方教会といったものと「東欧」が短絡的に結び付けられ、この地域の多様性が看過されていることに対する反発が根底にあると考えられます。
━━クンデラは「中欧」を文化的経験を共有する小民族と定義しましたが、この定義は同時代のユダヤ人にも当てはまると考えられます。当時の人々はユダヤ人を中欧の一部として捉えていたのでしょうか。それとも、フランツがドイツを中心に他民族を周縁に置いたように、ユダヤ人を周縁的に扱っていたのでしょうか
クンデラはユダヤ系住民を重要視していたと思います。ユダヤ系の人々はチェコ、ポーランド、ハンガリーの人々を結びつける接着剤であるという表現も用いています。フロイト(心理学者)、マーラー(作曲家)、フッサール(哲学者)といったユダヤ系の人々は、今日の国境で言えばチェコの生まれですが、ドイツ語を用いて、ウィーンなどで活躍していました。クンデラもチェコのブルノで生まれ、のちにフランスで、フランス語を用いて活躍した作家です。生まれた場所と言語に制約されない、また近代の国民国家という図式に制約されない代表的な存在として、ユダヤ系の人々を見なしていたのでしょう。そのため、多民族、多文化、多言語、多極的という中欧の特徴を体現する典型的な存在としてユダヤ人を強調していたと考えています。しかしながら、もう少し広い文脈で考えると、中欧の越境的な人々といえば、ロマやシンティの人々がいますが、クンデラは言及していません。同時代のチェコの作家ボフミル・フラバルはロマの人々を小説で取り上げるなどしましたが、クンデラにはそのような傾向はありませんでした。
外力としての「誘拐」 内なる声としての「悲劇」
━━この文章の原著はフランス語で書かれていますが、中欧における文化的アイデンティティの危機を述べる作品をチェコ語ではなくフランス語で発表することに、当時のチェコにおける出版等への弾圧やクンデラ自身がフランスで活動していたことを鑑みてもアイロニーのように感じます。クンデラはなぜフランス語で発表したのでしょうか。
チェコ語で書いた著作は翻訳されない限り、チェコ以外の人々に読まれません。また自身の小説が翻訳される際、過剰な変更や修正が加えられることも経験していました。しかしながら、何よりもチェコ語ではなくフランス語で書いた理由は、まずは西側の読者に届いて欲しいという思いがあったからだと考えます。つまり、フランス語での執筆を選択した段階で、対象読者を想定していたということです。その証拠として、この評論には注釈が多く付されています。クンデラの評論でこれだけの量の注釈がついているのは、この作品だけです。作者が注釈をつけるのは「本文だけでは伝わらないだろう」という意識があるからで、実際それらの注釈は中欧の文化や著作に関するものです。つまり、西側の読者を念頭に置いて、注を記し、本文も書いたと想定されるのです。
また、作中、「ヨーロッパ」が主語となることは何度もありますが、「チェコ」が主語となることはほとんどありません。また題名も、あくまでも『誘拐された西欧』であり、『誘拐されたチェコ』ではありません。ヨーロッパを主題に用いることで、チェコ以外の読者も共感しやすいようにしたと考えます。
逆に、この作品がチェコ語に翻訳されたのは、著者非公認の翻訳を除くと、発表から約四十年が経過した2023年のことでした。このようなことからも、クンデラは西側の読者を強く意識して、この評論を執筆したと言えるでしょう。
━━この文章中にクンデラがチェコで共産党政権による検閲で文芸雑誌が廃刊になったことを伝えてもフランス人が大した反応を示さず、「文化」が社会においてさほど重要なものでなくなったことを嘆くシーンが描かれています。一方で当時は文学や演劇だけではなくポップミュージックのような文化が力を持っていました。クンデラはそのようなものを文化として考えていたなかったのでしょうか。
その通りですね。大衆的なポップミュージックやサブカルチャーを文化として認めていない傾向はクンデラにはあると思います。ですが、芸術論として見れば、国境や言語を超えて横断的に論じる姿勢を貫いたことは評価すべき点です。中欧の芸術家だけではなく、時にマルチニックの作家を取り上げ、時にアイスランドの作家を称揚するという越境的な評論の姿勢は傑出していますし、音楽や文学、美術を、時にはヨーロッパという枠組みを超えて、大江健三郎を含めて横断的に論じた実践は、彼の不足点を補うには十分な営みだと思います。
━━この文章の題名にある「誘拐」「悲劇」を阿部教授はどのように解釈しますか
誘拐とは本来あるべき場所から暴力的に移動させられることを意味します。題名の「誘拐」は、中欧は本来西側にいるべきであるが、ソ連によって本来いるべきではない、いてはならない東側に強制移住させられたという比喩で使われています。「誘拐された西欧」というかつてなく印象的な題名を用いたのは、さすが小説家ミラン・クンデラといったところです。この作品が刊行された後、ユーゴスラビア出身の文学者マトヴェイェヴィチは「クンデラは文化のことばかりで政治のことについては全く触れていない」「政治あっての文化である」と批判しました。確かに「誘拐」という表現には、誘拐を防ぐ政治的な力がなかったという含意があるかもしれません。ですから、クンデラの議論には国際政治の観点が抜け落ちているという批判をすることは可能だと思います。一方で、少数民族という観点を用いて、文化が奪われてしまう危険性を指摘することで、国際政治の議論の場に文化あるいはアイデンティティーの問題を突きつけたとも言えるかもしれません。
一方で「悲劇」とはその文字通りの意味で使っていると考えます。クンデラの作品では、悲劇的な出来事が、時間や距離を置いてみると滑稽に見えることがしばしばあります。ですが、「誘拐された西欧」には喜劇的、滑稽な要素はありません。字句通りの「悲劇」として、著者が嘆息をしているようにも思えます。そのように考えると、「悲劇」という題名には、クンデラの内なる声が込められていると思います。
━━2000年代以降「中欧」のポーランドやスロバキア、ハンガリーでは極右政党の台頭があり、ポーランドにおける「LGBTフリーゾーン」やハンガリーにおける急進的な家族政策に見られるように伝統的な家族観といった「文化」を取り戻そうという動きに映ります。これはソ連による「誘拐」に対する揺り戻しのようなものなのか、冷戦後に進んだ急進的な改革(西側化、あえていうならば「第2の誘拐」)に対するバックラッシュなのか、またはそれらとは全く関連づけられない別の現象なのか、どのように考えますか
89年の東欧革命後、西欧への回帰、具体的にはEU(ヨーロッパ連合)やNATO(北大西洋条約機構)加盟を、この地域の多くの人が望んでいました。99年にチェコ、ハンガリー、ポーランドがNATOに加盟し、04年に中東欧諸国がEUに加盟し、表面的には「西欧に回帰した」と言えるかもしれません。ですが、さまざまな政策を決定するEUの官僚に対する不信感は以前から根強く、EU本部のあるブリュッセルに権力が集中し、自分たちの権利が尊重されていないと不満を抱く人は相当数いて、なかには共産主義時代が良かったと懐古する人々もいたのも事実です。ですが、このような動きは、ソ連による「誘拐」に対する揺り戻しというよりは新自由主義への警戒心や自分たちの声が埋没してしまうという不安感が大きかったように思います。また、フランスや英国などは国家としての連続性があるのに対し、チェコやポーランドなど、中東欧の国々は20世紀の間に何度も、体制、国境の変化を体験し、国や民族の連続性がしばしば疑問に付されました。当然ながら、政治、経済などさまざまな要因が複雑に絡み合っていますが、クンデラが強調した文化の連続性をめぐる議論が置き去りにされていたという側面はあるかと思います。そのため、経済的に豊かになっても自分たちのアイデンティティーを決定づける文化とは何かという議論が欠如しているか、あるいは短絡的な議論しかなされておらず、そのような状況が急進的な勢力の台頭を招いていると考えることもできるかもしれません。政治の場に「文化」をどのように接続するかという観点からも、クンデラの議論は今なお重要な問いを投げかけていると思います。











