
多くの受験生にとって受験はつらく、大変なもの。しかしだからこそ貴重な機会で、恵まれた経験だと語るのは、官僚、弁護士、米ハーバード大学ロースクールを経て東大大学院で博士号を取得後、家族法の研究者として研究する傍ら、コメンテーターや作家として活躍する山口真由特任教授(信州大学)だ。山口特任教授はさまざまな経験を経て自分が「読む人」であると気づいたと語る。今回はそんな山口特任教授へのインタビューを通し、どのようにして自分を知ることができたのかに迫る。(取材・峯﨑皓大)
自分を知ることで気持ちを切り替えて、前向きに
━━東大に進学した理由は何ですか
小学生の時に小和田雅子さん(現皇后さま)のご成婚のニュースを見て、外交官や官僚に憧れました。その時に父に「官僚になるなら東大、そして文Iに行けば間違いない」と言われ、東大を志すようになりました。
━━受験生時代に印象に残っていることはありますか
受験生時代の成績は良く、模擬試験でA判定や、低くてもB判定を取り続けていました。しかし、受験前の最後の模擬試験の判定がCに下がって非常に心配になりました。思い返してみると、高校受験の時も前日に過去問を解き、数学が100点満点中14点だったことがありました。直前になると必ずこのように不安になる出来事がある、今回も同様のことだ、と信じて不安な気持ちを乗り越えることができました。
勉強を始めたばかりの時は伸びるんです。その時期は本当に楽しいと心から思えるのですが、そこから頑張っても頑張っても伸びないという「平野」があります。その平野をやがて越えるとまた伸び、最後に一度ガクッと落ちて、そこから最後ゴールにたどり着くというのが私の成長曲線だということを私の中の経験値として持っています。高校の時の体育の先生が「みんながスランプだという時はスランプではなくプラトーである」とおっしゃっていました。スランプというのは一流選手が高いレベルを前提としてそこからパフォーマンスが落ちた時に使う言葉で、高いレベルを前提としているゆえにゴールはすぐそこにあります。その受験直前で不安になった時はこの言葉を思い出して「これだけ努力を重ねたからこれはプラトーではなくスランプだ、だからゴールはすぐそこだ」と気持ちを前向きに持っていくことができました。
━━勉強は好きでしたか
よくその質問をされるんですが、楽しいなんて感じることは全くなくて、私は「つらいつらい」と思いながら勉強をしていました(笑)。私は数学が苦手で、東大の入試の数学なんて訳が分からないと思いながら勉強していました。それでも、一周回ってつらいのも含めて楽しいのかもしれません。今42歳になって、あれだけ一つのことを頑張って、渇望感があって、体力があって、そして受験というものすごく大きな舞台で戦い、失敗してもまだ若いからいくらでもやり直せるという機会は年齢を重ねるとなかなかないです。もう一度経験したいとは思わないけれども、良い経験だったなと思います。
━━東大に入学後、印象に残っていることは
私は法学の授業はあまり好きではなく、駒場時代の授業が印象に残っています。大教室の講義形式の授業も楽しいですけど、先生が専門分野について熱意を持って授業をする少人数の授業はもっと楽しいと思いました。印象に残っているものに能の授業があります。『平家物語』を読むところから始まって能を学ぶという授業です。自分の全く知らない分野で、かつ受験生の時には「これは入試に出る、出ない」のように扱っていた古典ですが、その奥には非常に豊穣(ほうじょう)な世界が広がっていることに衝撃を受けましたし、そのことを知れたのは本当に良い経験だったと思います。
━━前期教養課程はまさにさまざまな知に触れる機会だと思います。しかし就活早期化や国家公務員試験の前倒しなど、「避難場所としての大学」という大学像が変化しつつあると思います
それはまさに私が危惧することです。大学が高い地位を保てなくなったことに問題意識を感じています。経済界などが大学にすぐに使える高度人材や、職業に直結するような教育を要求しています。個人的には、せめて東大くらいはそのような要求を「大学はそのような機関ではありません」と超然と跳ね返してほしいと思います。
一方、大学が経済界から評価されないのも問題だと思います。私は、大学時代の成績は非常に良かったんですが、就職する時にその成績があまり就活において意味を持たないということに驚きました。就職の時には大学で学んだことよりもアルバイトの経験や部活動でのリーダーシップの経験などを評価するようになっており、多くの人は大学時代に何を学び、何に感銘を受けたのか、ということを語らないんですよね。そのため、大学での努力が正当に評価されないようになっていると思います。
大学は「避難の場」であると開き直ってほしいと思う一方で、就職の際に大学における努力が正当に評価されないという現状において、そのままでは努力した学生をすくい上げることができない矛盾に東大も含めて多くの大学が難儀しているように見えます。
米国では学部で教養を学び、大学院でプロフェッショナルなことを学ぶという構成になっていると理解しています。日本は学歴社会と言いつつも大学院が正当に評価されないために学部での教育に職業訓練を求めてしまうという現状があるのだと思います。
ハーバードで家族法と出会い そして研究者の道へ
━━財務省、弁護士を経た後に米ハーバード大学ロースクールに進学しました。ハーバード大学在学中に印象に残っていることはありますか
ハーバード大学に在学していたときの少人数の授業が印象に残っています。私は英語が全くできず、授業でもほとんど発言しないため本当にいないもののように扱われていました。そんな中でフェミニストたちが家族法についてどのように解釈してきたかということを学び、議論する『Feminist Legal Theory』という授業を受けました。その授業では多くの疑問や問題意識を抱き、勇気を出して教授のオフィスアワーに質問しに行きました。オフィスアワーの前に自分の抱いた疑問点をメールで送って “Looks good” と返信が来たので、私の質問を理解してもらえたと思って満を持して質問に行きました。私は先生に送った質問を読み上げると先生はポカーンとした顔をしていました。忙しいから学生のメールなんて読んでいなかったんですよ。その時、先生が質問を理解している前提で質問したのに先生はメールを読んでいないし、私は英語力もないしどうやって説明しよう、と不安になりました。
しかししょうがないから私の拙い英語で説明するしかない、と思って説明したら先生がじっくり考えて“Beautiful”と一言言ったんです。そしてその後に「あなたの考えは非常に深く、文章の行間まで非常によく読んでいるわ」と言われました。その時に、社会に出て財務省時代も弁護士時代も厳しい経験ばかりだったけどようやく報われたな、という気持ちになれました。その時に、チャレンジしてみたら砕けることもあるけれど得られるものもあるということを学びました。それから先は恥をかいてでも何か言いたいことがあったら言おうと決めました。逆に、先生の方からもあまり話さない学生だけどしっかり意見を持っている学生だ、と扱ってもらえるようになりました。
━━家族法に興味を持ったきっかけは何ですか
元々は家族法に興味はありませんでした。ハーバード大学在学中にたまたま空いていたコマに家族法の授業を入れたのです。その授業が本当に面白かったと同時に、家族法は、これまで私が抱えてきたモヤモヤに答えてくれるような気がしました。例えば、「結婚適齢期になったら結婚すべきなのか」という悩みや、「結婚を前にして自分が選ばれないのではないか」というコンプレックスなどです。もちろん、そうしたモヤモヤがすぐに解消されるわけではありません。しかし、多くの人が同じようなことを考えてきた歴史があり、過去から私につながる緩やかな連帯があるのだと思うと、温かい気持ちになり、家族法に魅力を感じました。
━━米ハーバード大学ロースクールを卒業し、17年に東大大学院法学政治学研究科博士課程に進学しました。そのきっかけは何ですか
ハーバードで出会った家族法についてもっと研究したいという思いがありました。また、私は社会人になってから学生時代ほど打ち込めたものがありませんでした。その中で、ハーバード大学でもう一度勉強したら、勉強が嫌いだと思っていたけど、つらさや苦しさも含めて私は勉強が好きなんだということに気付きました。私が何か学問について書く時には、時間が許す限り調べ尽くしたいし、そうして作り上げた「作品」が批判されることは自分自身を否定されると感じるほどつらい、これが私のこだわりだと思うようになりました。この思いと学部時代の恩師からの後押しで博士課程に進学しました。
━━学部時代の学びと博士課程の学びはどのように異なっていましたか
全く違いました。学部時代にはある程度競争があるのですが、博士課程には競争というメルクマールがないことに最初は慣れなかったです。今まで競争がある中で勉強をしていたのですが、博士課程は本当に孤独な自分との戦いでした。特に博士論文を書いている時が顕著で、今日は自分のことを天才だと思って、次の日は自分のことをばかだと思うことの繰り返しでした(笑)。また、研究会等で発表するときも、一流の研究者である東大の先生方から容赦なく批判や質問が来て、返す言葉もないという時もありました。東大の先生方は一人前の研究者とみなしたら博士課程の学生であろうと、助手であろうと同僚であろうと遠慮なく疑問や矛盾を問うので、メンタルが崩壊しそうになることもありましたが、それこそが自分の研究をより良くするプロセスでした。
━━博士論文『合衆国における親子関係の決定 : 婚姻による推定、血縁の証拠又は養子縁組以外の可能性』(後にこれを基にして『アメリカにおける第二の親の決定』(弘文堂)を刊行)では米国における家族法やそれに関する判例というレンズを通して父、すなわち第二の親とは何かということを研究しました。現在はどのような研究をされているのでしょうか
博士論文の延長として、母とは何かという研究を行っています。「産んだ人が母である」という父よりも厳しいルールがある中に例外として代理懐胎と養子縁組という制度があります。その二つを探ると母の本質が見えて、母とは何かというのを理解することができるようになるのではないかと考えています。そして、母とは何か、父とは何かという二つの研究の延長線上に親とは何かという問いに答えることができるのではないかと考えています。今はアメリカでの代理懐胎の判例を研究しています。
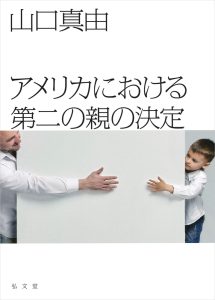
━━法という知見から社会を理解しようとしていると感じました
私は愚直に、判例をたくさん読み、それから何が言えるかというのを考えるのが得意です。また、判例の中にある一人一人の人間の物語を見るのがとても好きです。私は社会に興味があり、判例がたくさん積み重なっていった向こうに、法では捉えられない社会が浮かび上がると考えています。そのため、法のレンズを通して社会がどうなっているのか、そしてどのように変化しているのかということを捉えたいし、そうして捉えられた社会に法が対応していかなければいけないのではないかと考えています。
━━では法はどのように社会や人々の規範意識に影響を与えているのでしょうか
非常に難しい問いで一般的に何が言えるかは分かりません。米国ではアナウンス効果があると言われています。同性愛カップルに厳しい州憲法の改正に違憲判決が出た時は、同性愛カップルに対する差別を正当化し、差別しても良いというスティグマを助長するということが違憲判決の理由に挙げられました。日本でも先の国会で審議された特定生殖補助医療法案では第三者の卵子や精子の提供を受けられるのを法律婚カップルのみに限定しようとする動きがありました。これは結婚をしていない人は子供を持つべきではないというスティグマを人々の規範意識に植え付ける可能性があると思います。
恵まれた貴重な経験を大切に、大きな舞台に立って
━━研究者やコメンテーター、作家などさまざまな場面で活躍されていますが、どのアイデンティティーが最も大きいですか
私は「読む人」だというアイデンティティーを持っています。コメンテーターとしてもさまざまなものを読んで勉強しますし、研究者としても非常に多くの判例を読みます。多くの判例を読むことで、今まで読んできた判例が打ってきた点描がやがて絵を描き、五里霧中にいたのが、やがて理解できるようになるというのが私の信念です。
━━研究者やコメンテーター、作家などはアウトプットが多いと考えていたので「読む人」というアイデンティティーを持っているのは意外に感じました
私がコメンテーターをやっていて好きなことの一つは、その場で専門家に自分の疑問をぶつけることができるところです。コメンテーターとしてテレビでコメントする時に勉強をしますが、やはり専門家ではないので自分である話題について答えを出すということは難しいです。しかし、答えを出すことはできなくてもたくさんの疑問が見つかるので、実際に専門家に聞くということが自分の学びにもなっています。
━━今、受験勉強に励んでいる受験生にメッセージをお願いします
今は本当につらい時期だと思います。私は42歳になって振り返ってみたときに、受験生として過ごした時間は恵まれた時間だったと感じます。自分自身が可能性の塊で、自分の今持てる全てを費やして大きな舞台に立とうとするというのは、人生の中で恵まれた貴重な経験だと思います。当時は失敗が非常に怖いと思っていましたが、まだ若いのでいくらでもやり直しができます。その意味で、決して取り返しのつかないことにはならないというセーフティネットが用意された舞台に立っているということを忘れずに、思う存分やるのが良いと思います。そこで夢中になった経験というのが将来、自分自身の限界値を測るときのメルクマールになると思います。今はまずペンを握って大きな舞台に立ってほしいと思います。
━━進路を決める時には「何が好きか分からない」「好きなことが多くて分からない」「社会的にこれが良いとされているからこれにしよう」のようにさまざまな悩みを抱える人が多いと思います。進学や就職で悩んでいる人たちにメッセージをお願いします
とりあえずやってみるのが良いと思います。私はとりあえずはやりに乗ってみるタイプだったので、みんなが弁護士になりたいと言っているから弁護士になりました。官僚でも弁護士でも失敗して、30歳を過ぎてからようやく自分が「読む人」ということに気付けたので、何でも試してみるのが良いと思います。自分が「読む人」ということに気付けてもなお、多くのチャレンジが自分にはあります。人生は沈んだところが一番重要だと思います。「あ、うまくいっていない」という経験を溜めておかないとその後のバネにならないので、とりあえず何でも挑戦してください。就職でも最初に行った職場に100%合うなんてことはほぼないと思いますし、あったとしたら超ラッキーということだと思います。
東大を目指す受験生も東大生も、その環境にいること自体がまずは恵まれたことです。あなたたちのための扉はたくさん用意されているので、初めの扉で何か違うと思ったら引き返して次の扉を叩けば良いです。昔の私は、はやりに乗ろうとしていましたが、今、行き着いたのが王道ではない家族法でした。東大を卒業する22歳の私に「家族法をやったら良いよ」と言っても絶対に響かないと思います。それは色々な経験のもとに今の私があるからです。まずは自分がピンとくるものに挑戦してください。そしてそれで夢破れても良いんです。沈んでからが人生ですし、後退するところに人生の醍醐味(だいごみ)があると思います。沈んで、後退して、自分の生身を削ることで自分の本質が見えてくると思います。












