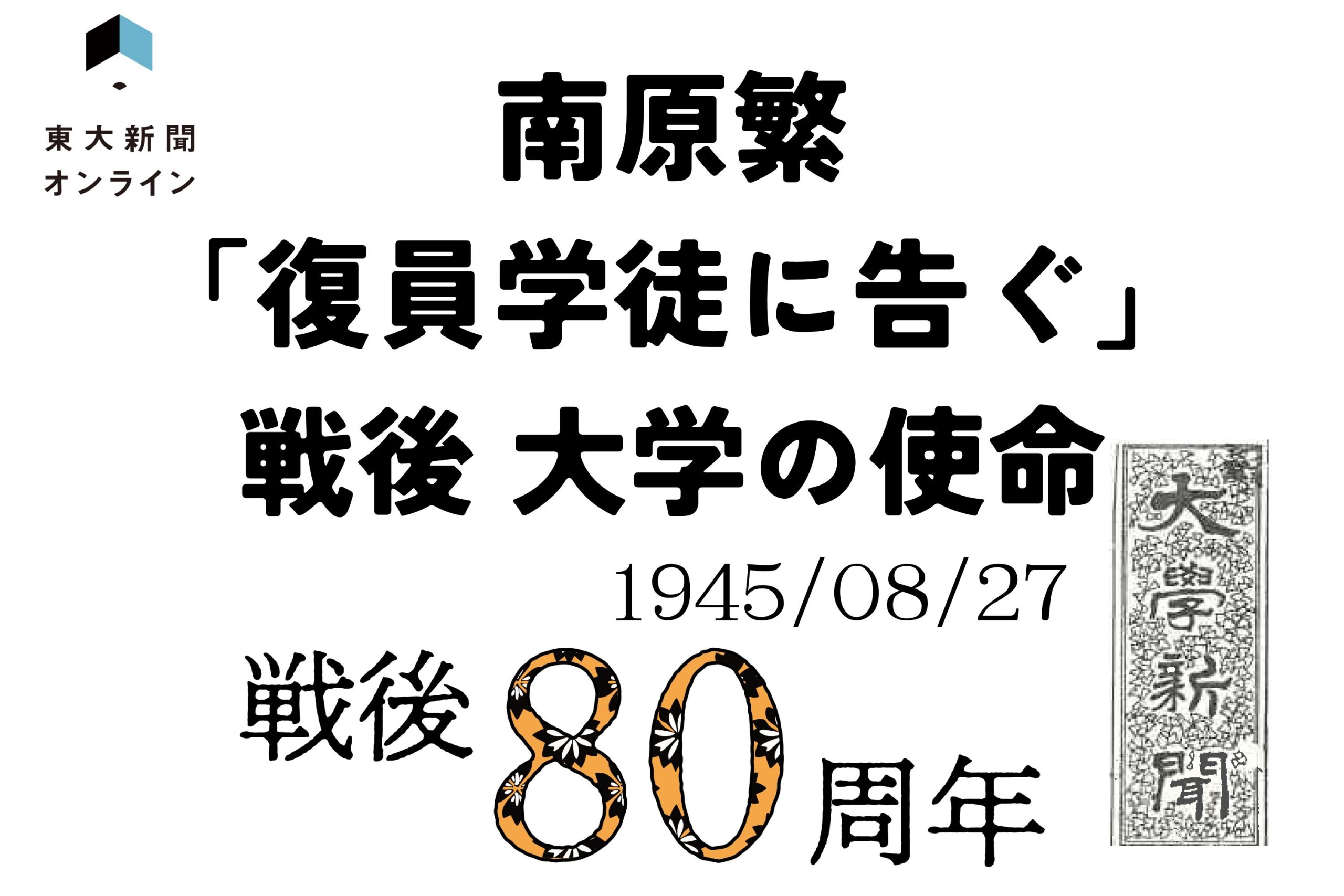
今回は、1945年9月1日発行の「大學新聞」より南原繁の記名がある「戦後に於ける大学の使命 復員学徒に告ぐ」を転載する。南原繁ら東大法学部の教授陣は終戦工作を行なっており、南原自身は45年末には東大総長に就任し大学改革に取り掛かる。終戦直後の検閲のない時期に、南原が終戦直後に復員学徒へ向けて残した貴重な本記事をして「当時」について考えるきっかけにしてほしい。(構成・溝口慶)
「戦後に於ける大学の使命 復員学徒に告ぐ」 法学部長・南原繁
一
昭和二十年八月十五日、それが我等の上にいかなる日であったか二千六百余年、光輝ある日本の歴史にとって呪われた「運命の日」であった。この日に生き残って我等国民の悲憤・痛恨、それを何に譬(たと)へることが出来よう。それは我国が嘗て知らなかった敗北と降伏の日であった。
吾々は先づこの現実を直視し徒に神秘の覆ひを以て包み隠すことなく、率直に事実を事実として承認しようではないか。我等の蒙(こうむ)った衝撃と痛手は余りにも深くして大きい。それは日と共にその全貌を明らかにし、吾々の知覚に感じ来るであらう。連合軍の本土上陸は開始されんとし、次いで帝都進駐も行はるべく、現実に敗北の事実のいかなるものかが、◯々と吾々の上にのしかかりつつある。彼等は日本民族に果して何を要求し、何を課せんとするのか。その結果、日本が遂にいかなる苦境と悲惨の極にまで突き落とされるのか。それは予測し能はざる程、深刻且苛烈なものであることを覚悟しなければならぬ。
それと同時に、たとひ吾々の受くる苦難がいかにあらうとも、その中から再び立ち上らねばならぬといふことも、吾々一同の新たな覚悟であり、祖国をして再び光栄ある日本として復興せしめなければならぬといふことは、我等並に子孫の課題であり、厳たる要請でなければならぬ。
然らば日本をして廃墟の中から復興せしめるものは何か。本来いつの時代にも然あるべき筈であるが、今や領土が局限せられ、軍備は撤廃せられ、産業また著るしく制約を蒙らんをする我国にとって特に学問と教育のほかにないことは、自明の理である。その場合、就中(なかんずく)、国家最高の学府として大学の意義と使命の重大なる今後の如きはないであらう。諸君が戦時中殊に最近は、全面的に授業が停止せられ、勤労に出動してゐた職場から、逸早く学徒本来の持場たる学校に復員せしめ、一日も速かにその態勢を整へしめんとするのもこれが為である。
軍人が剣を棄てた時、我等学徒の真の戦が開始せられるのである。それだけに国民学校から大学に至る斯の方面における連合国側の干渉極めて峻烈なるを予想しなければならぬ。吾々は只手を拱いて待ってゐるのではなく、当局と連繋して夫々の対策を講じつつある。我が大学が戦火を免れ、今後も亦たとひ外部的に何等の変化を受けずとするも、内部的に改変を余儀なくせしめらるることは、自然科学の部門を含めて、大なるものがあるであらう。
二
この間に処し、大学の使命は何であるか。何よりも我が国体の新たな自覚に出発しなければならぬといふことである。かの日大戦終結の詔書喚発の玉音を拝したる者誰か嗚咽感泣しない者があらうか。事ここに到ったは、一には我等に奉公の誠足らず、学徒として真理への勇気に欠くるところが無かったか。省みて忸怩たるものがある筈である。然るを唱へらるるが如き「一億玉砕」に到らしむることなく、我が「民族の滅亡」を聖断以て止めさせ給うた大御心、赤子と国家を振念させ給ふ叡慮の程只恐れ畏むのみである。
これひとへに上御一人の聖旨に出づるところと拝承して、かくの如きは洵に皇国にして初めて克く為し得るところ、正に世界の驚◯であり、或る意味に於て建武中興又は明治維新にも匹儔(ひっきゅう)すべき、否、それよりも更に大旦困難なる回転の偉業と申すべく、真の意味の昭和維新は茲(ここ)に出発点を求めねばならぬと思ふ。
人間はその住居が古くなれば、これを取り毀ち、往々土台石まで堀返して新に建造するものである国家についても同様、我等は現在惨敗の機会に遭遇して、国家の礎石を今ひと度吟味し、古くして常に新たる我が邦固有の国体の自意識の上に、混沌の中から、新日本と文化とを建設しなければならぬ。それが謂ふ所の「修理固成」の永遠の意味である。さうして之が自意識は、決して狂信的独断や唯我独善であってはならず、非合理性を裡に包んだところの、何処までも合理的なる理性の自覚でなければらぬ。
かやうなものとして、それは必然に特定の民族を超ゆる「世界精神」的理性でなければらず、いかなる国家もその前に謙虚にして、その声に聴かねばならぬ。それに依り、我が国に特殊なる民族宗教的神性たることを超えて、洽く世界に理解せられ、敬仰せらるべき人文主義的なる普遍的・合理的基盤を獲得し能ふであらう。
学問は由来、かかる理性の概念的思惟の業であり、必然に科学的認識と批判の上に立つものであるこの意味に於て、日本にとって緊要なる◯新に確然と学的基礎の上に据ゑられた世界観の樹立であるであらう。そこに「日本的」なるものの反省、真の「日本精神」の再認識が為さねれねばならぬと思ふ。かくして我が国◯最近呼号せられたる日本主義又は全体主義時代と、それに先だち一時氾濫したる自由主義乃至マルクス主義的時代の過誤を繰返すことなく、新たな第三の道を開拓しなければならぬと思ふ。
さやうな学的世界観の精密なる論理的構成は哲学者専門の業であるにしても、これが志向と内実はいかなる学徒も等しく懐抱し、自覚するところがなければならぬ。それに根拠してこそ、初めて文化並びに自然の語科学の任務も十全に達成し得られるであらう。今次大戦に於て、科学的知識が余りにも軽視又は無視せられ、学問的心理に代へて単なる信念が高唱せられ、或は学者自らがその真理性を強いても歪曲し、または放棄したることがなかったか。
真理は一時これを抑圧することも出来ようが、いかなる強権を以てしても遂にこれを蹂躙し能はないのがその特権である。哲学を初め諸科学の研究に従事する者ひとしく、今次敗戦の国家的一大「経験」を契機として、益々己が責務の重大なるを自覚し、真理を闡明(せんめい)し、真理を真理として主張するころの学問的精神を大いに振起しなければならぬ。
この点、大学学問研究の自由と自治の改めて確認せらるべき秋であると思ふ。そのことは学のあらゆる分野に於て相違はないが、就中文化科学についてさうである。文化諸科学の学徒は、戦時中、既に高校において定員が激減せられ、率先徴兵猶予の特典を停止せられて前線に赴き、また授業を廃止して勤労に挺進し来ったのである。然るに諸君の学修は今や自然科学と同じく、否、それにも勝って重要となり来ったのである。戦後複雑なる国家社会の難問は一に繋って斯学の解決に待ちつつあるからである。
三
若し夫れ、日本の完全なる復興の実現に至っては、恐らく今後「世紀」の事業たるべく、諸君はその基礎を築くに止まるであらうが、若しその基礎的工作にして失敗せんか、その後の凡ての構築は空しかるであらうそして前途は莉棘に満ちた苦難の道に相違いないが所謂「地下に潜る」といふが如き或は「臥薪嘗胆」といふが如き方法の克くし能はないであらう。須らく公明正大にして、対者の顔色を窺ふことなく、自主・自律、自ら為すべきを成すことである。飽くまで◯忍自重、寧ろ戦の勝敗を超えて、列国と協力、進んで世界平和の建設に積極的に寄与せんことである。詔書に『萬世ノ為ニ太平ヲ開カント欲ス』との聖旨は、かくて顕揚せられるであらう。
第二次世界大戦ほど、実に戦争の無道と暴虐の限りを尽したるは、有史以来未だ嘗て無かったことであらう。在来の戦争法規が蹂躙せられて怪まず、文明の発達を照らすべき科学がいかに人類の暴虐なる殺戮に使役せられたか。世界に革命的なる最初の原子爆弾の惨禍を思へ。我等は声を大にして世界の理性と良心に訴へ、人類を滅亡の淵より救はねばならぬ。その為、世界の公正なる与論の組織なくしては之を制御し、更にかやうな惨憺たる戦争の誘発を防止し得るものではない。また一国の完全なる自由と独立は、世界に普遍的なる国際的正義の樹立なくして実現し得るものではない。
この意味において世界秩序と国際組織の新な建設は、今後諸国民に課せられた大なる使命である。民主主義は十九世紀において発見せられた重要たる政治的真理ではあるが、これが政治学の最後の章ではあり得ない。これと世界理念とをいかに綜合するかは抑も今世紀を通じての人類の課題である。彼等は第一次国際連盟の失敗の原因を知悉せる筈である。若し戦勝国にして所謂強大国の利己的立場から此の問題が決定せらるるならば、再びその瓦解は火を睹るよりも明らかであり、その恐るべき結果はやがて彼等自身の頭上に加へられるであらう。我等戦敗国は捉はれざる公正の立場に於て、これらの問題について発言し、主張する義務と権利を保有しなければならぬ。
その場合、特に我等の側に於ては、古来我が国の大陸政策なるものを一擲し、真に支那の為の支那、其の近代国家の統一を庶幾し、これが達成に協力しなければならぬ。真の日支の協力なくして、東亜の安定と世界の平和は期し得るものでない。かくしてこそ一旦掲げた大東亜共栄圏の理念は勿論、進んで世界の新秩序は実現に向って大なる一歩を前進し得るであらう。
四
以上の如きは、吾々各人が一個の人間として高貴にして善良、正直にして親切たるとなくして期し得るものではない。吾々は猜疑と敵意を棄てて人間として信頼と尊敬を◯ち得ることから始めねばならぬ。今後、国家社会中堅たるべき青年知識人に於て、特にこのことが覚醒されなければならぬ。それは自己自身を断えず内面的に向上し純化する人間として、自らを形成することである。これ「教養」の真の意義であり、かかる教養を身に着けることが、諸君の大学生活のまたひとつの大なる使命でなければならぬ。それは一言にしていへば「人間性理想」(Humanitaetsideal)であり、祖国と人類の将来は、この理想に、かつて自らの未来を創造するところに成立するであらう。仮令今より後、いかなる最悪の情況に立ち到らうとも、その中に在って、我等はこれを放棄してはならない。これが放棄されることは、凡そ精神的なる人間の没落と文化の終焉を意味するからである。
諸君は長き戦争の時代と勤労生活を通じて、裡(うち)なる魂を或は脅かされ、汚されるところは無かったか。おしなべて内面的・精神的なるものの荒廃、ひいて道義の退廃、現代の如きはないであらう。索漠たる諸都市の惨状にも勝して、かかる精神の荒廃を憂ふる者である。戦争の敗因は幾多挙ぐべきものがあらうが、極言すれば我が国家社会の各階層に亘って精神の退廃が根本因をなしたことが指摘されなければならぬ。
最も厳格なる規律を要請さるべき国家浮沈の秋に、自己本位的快楽主義的風潮の普く浸透せる事実を認めざるを得ない。戦敗れた今日に於いて尚かつ、その傾向の瀾漫せるは何としたことか。かくてはいつまでも祖国は立ち直らず、永久に滅亡の一路を辿る外はないであらう。再び来らんとするアメリカニズムとマルキシズムは、この点において一唇の危険こそあれ、積極的に何等吾人に加ふるところはないであらう。
私は信ずる──日本をして真に復興せしむには、人間性理想を国民の胸奥に透徹せしむるに在ると。この見地から、我が国の文教は大学より国民学校に至るまで一大改革を為す必要がある。我が国体観念も、かやうな人間の全人的なる共鳴と協賛を得、それらに荷はれてこそ、初めて揺るぎなき堅固な支柱を見出し得るであらう。我が国に於て発展せらるべき所謂「民主政」体制も、かやうな人間によって構成されてこそ、その意義があると思ふ。若しそうでなければ、それが独裁制と少数の指導者政治に置き代へられても、単なる大衆による再び一箇の機械的強制と暴力とならないことを誰が保障し得るものぞ。
先づひとりひとりが自由なる精神的独立人となることである。かやうな人間の生くる所、国家の結合は内面的鞏固(きょうこ)を増し、国家の真の強大を齎(もた)らすであらう。かく観ずると気に、我が国家社会のあらゆる部面において、一大革新と合理化を図らねばならぬ多くの問題は山積してゐる。また外、世界はかやうな人間に対し、その門戸を閉して、これを拒む理由はあり得ない。我等は必ずしも領土の狭小と人口の過剰をを憂ふるに及ばぬ。精神的自律的人間の往く所、世界と自然はその力によって開拓するに委ねられるであらう。かくして海国日本の平和なる世界的発展は新な未来を約束せられてある。我等は敗れたりと雖も、聊(いささ)かも阿諛屈従するを要せぬ。毅然として立ち、面を真直に向けて歩かうではないか。
五
青年よ。学徒よ。希望を持て。理想を見失うな。かかる苦難の時代に戦い生きた祖先は未だ嘗て無かったと同時に、かかる光栄ある任務の課せられた時代も亦嘗て無いのである。
やがて大陸から、南洋の島々から、我等の仲間が還り来るであらう、そして再びこの講堂を埋めて、祖国再建の熱情に燃えて、学に精進する日も遠くないことであらう、唯そのとき永久に還らぬ幾多俊秀のあるを思うと限りなく寂しい。彼等は皆、武人として勇敢に戦ひ且死んだのである。併し、彼等は武人たると同時に、最後の日まで学徒たるの矜持を棄てはしなかった。彼等は国を興すものは、究極に於て真理と正義であると固たく信じて疑はなかった筈である。この日にも、早、彼等の魂は此処に帰り来って我等と偕に在り、諸君のこれからの新たな戦を祝福し、嚮導(きょうどう)するであらうと思ふ。
尚この機会に於て、◯に設置せられた戦時「特別学生」制度に就いて一言し度い。それは伝えらるるが如き◯才教育とは範疇を異にし、極めて少数ながら諸君の代表として、一般的には授業が停止せられたに拘らず、有形無形の大学生を守らんが為文政当局の了解の下に残留せしめたものである。これのみは授業を継続し、師弟相携へて酷暑の日にも学に励み来ったと同時に、或る時は吾々の研究室の貴重なる図書を敵爆撃の危険より疎開するために、連日渾身の努力を傾けた。決戦下、大学の伝統を護り続けたものとして、後年大学の歴史に特筆されるに値するであらう。
農耕に工場にその他の場所に、本来習熟せざる作業に、額に汗して黙々と働き来った一般学生に対しては、深くその労を多としなけれならぬ。今や任務を完了して全員恙なく復り来ったことを悦ぶと共に、諸君は以前のままの教室を講堂をそこに見出し、感慨無量なるものがあるであらう。吾々は長い間の諸君の緊張を知らぬ訳はない。だが、今は連合軍進駐の時である。現に友軍機ならぬ戦闘機が我等の頭上を轟々と飛翔しつつある。間近に彼等の戦車の響きを聞くのも遠い日ではあるまい。諸君は飽くまで沈着冷静、些の不安と動揺を戒むると共に、苟も軽挙盲動を慎まなければならぬ。進むも退くも一致団結、この厳粛なる歴史の時を、大学人として立派に行動しようではないか。それは先づ我等学徒の為すべき第一の義務である。(八月二十七日)(筆者は東大法学部長)










