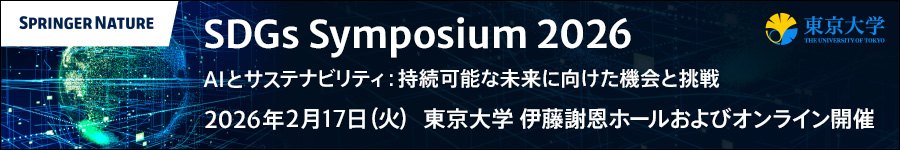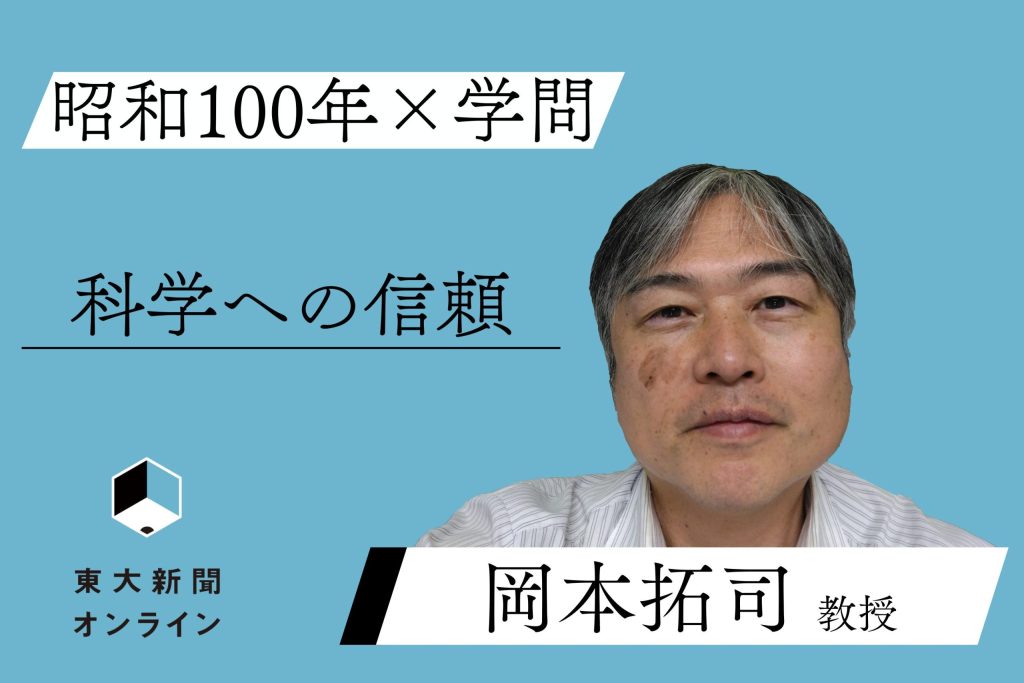
昭和100年と科学 通底する科学への信頼
第2次世界大戦、戦後の復興と高度経済成長、福島第一原子力発電所の事故、新型コロナ対策。この100年、科学技術は政治や暮らしに大きく関わってきた。科学者は社会に対して何を思い、そして社会は科学をどのように受け止めてきたのだろうか。近代日本の科学と社会との関係性を研究してきた岡本拓司教授(東大大学院総合文化研究科)に話を聞いた。(取材・岡部義文)
「科学する心」戦前・戦中期の科学と精神論の間で
──近代科学は主に明治期に海外から輸入されてきました。そこから昭和初期にかけて、日本の科学はどのように発展してきたのでしょうか
明治期はまだ国際的な地位が低く、だからこそ学問では海外に勝とうとする気概が見られました。単に欧米の研究を輸入していただけではなく、独自の優れた研究も行ってきました。1925年に量子力学が誕生して物理学の世界が大きな転換期を迎えると、そうした発展途上の分野では特に、海外に肩を並べる研究が目指されました。
──研究において、海外に「勝つ」という意識が根底にあったのでしょうか
全員とは言いませんが、例えば長岡半太郎のような明治の半ばごろに成人期を迎えた研究者には、特にそうした意識を持つ人が多いと言えます。必ずしも産業や軍事に結びつかない研究分野も軽視されていたわけではなく、特に西洋で話題になっていた問題に食らいついて成果を上げようとする意識が見られました。
──大戦期に入ると、国家や民族の精神性を重視する言説や政策が広がります。こうした中で、科学はどのように受け入れられてきたのでしょうか
満州事変以降には、国体の中心としての天皇の存在を強調する国体明徴運動が起こります。天皇の統治が神的なものに由来するのだという主張は、当然ながら当時の大人は本当に信じていたわけではありません。そもそも、進化論が日本にやってきたときでも、天皇制と進化論は矛盾なく両立していたわけです。戦時中も、軍部が士気を上げるために精神的な面を強調することはあれど、兵器や資源の面で、科学が突きつける現実を無視することはできませんでした。
一方、その中間にはいろいろな考えの人がいます。生理学者で第2次近衛内閣の文部大臣も務めた橋田邦彦は「科学する心」を唱え、「良い人間がやれば良い科学になる」とし、天皇に仕える日本人が行う良い「日本科学」で世界をリードすべきであると主張します。
精神面の過度な強調の例の一つが特攻兵器です。特攻は日本人でなくてはできないとする主張が見られた一方で「素晴らしい精神性を持つ日本人を兵器の一部として扱わなければならないことは、科学の敗北だ」という反省は、戦時中の学生や科学者の間でも見られました。
「科学で負けたからしょうがない」諦めから戦後の科学は出発した
──敗戦を経て、大戦への反省は科学や科学者にも向けられたのでしょうか
ポツダム宣言を受け入れる一つの理由として「戦いに負けたのは受け入れがたいが、科学で負けたのならしょうがない」という受け入れ方があったと言えます。科学が重要な戦争において、日本の科学は勝てる域にまで達していないので負けても仕方ないというわけです。日露戦争の頃には、日本は最新の技術の無線通信を活用していました。科学の重要性も認識していたはずですが、第2次世界大戦では、戦う意志などの精神性がより強調されました。しかし、相手国は科学を用いて勝利したわけです。原爆はまさにその象徴と言えるでしょう。
──「科学で負けた」ことが、科学者への強い風当たりを生まなかったのでしょうか
確かに科学者に対する批判や風刺も一部には存在しました。原子核の分野など、戦時中に優先的に資金を得て研究できた場合もありました。しかし、戦後科学者は非効率的な軍部や役人によって十分に研究が出来なかったのだと主張しました。こうした中で、科学への信頼が大きく失墜することはありませんでした。
──戦後まもなくノーベル賞受賞者が出るなど、特に純粋研究の分野で国際的な業績を上げていきます
戦前から、純粋研究の分野でも、長岡のように、新しい理論を積極的に取り入れるよう主張する科学者がいました。物理学の分野では、量子力学の誕生によって、新しい理論が良い成果を生み出しやすい環境がありました。これが素粒子物理学の理論研究や、加速機サイクロトロンを用いた実験物理学の研究を発展させ、ノーベル賞を受賞した湯川秀樹や朝永(ともなが)振一郎の業績につながっていきました。最先端の純粋研究を支える学問的な風土は戦前から整っていたのです。湯川のノーベル賞受賞は、科学界や日本にとって大きな励みになるものでした。日本は科学で戦争に負けたが、決して日本の科学が劣っているだけではないことが示されたのです。
揺らぐ科学への評価、揺らがぬ科学への信頼
──戦後社会の中で、科学はどのように受け入れられていったのでしょうか
科学と民主主義が手を携えて進展するという主張が生まれ、一定の支持を受けました。また、戦前と同様、産業の基礎としての科学技術の重要性も再度強調されました。戦前の東京帝国大学は、欧米に先駆けて工学や農学などの実学に他の学問と同じ地位を与えましたが、戦後、1957年には「科学技術者養成拡充計画」で理工系学生の増員が定められ、工学は新規の分野を取り入れながら規模を拡大していきました。
──こうした中で、国民の科学に対する意識は変化したのでしょうか
50年代末以降の理工系ブームの一方、公害問題やベトナム戦争を経て、科学が民主主義と共に進歩するという予測に対する批判が現れるようになります。60年代末の学生運動では、科学研究が人民を苦しめると指摘されるなど、こうした批判が顕著に表れます。
他に、日本の科学技術がそれほど進歩していないという主張も見られます。例えば湯川に次ぐ朝永のノーベル賞受賞はその16年後で、20世紀の自然科学分野での受賞者は6人のみです。日本人は科学を十分理解していないのではないか、といったことも言われました。
──近年では、福島第一原子力発電所の事故や新型コロナ対策など、科学技術を巡る政治的争点も現れます
東日本大震災の後は、そう大きくは科学への信頼は揺らぎませんでした。震災直後は様々な意見が見られても、しばらく経つと信頼は回復していきました。福島第一原子力発電所の処理水の問題を見ても、非科学的な主張は最終的には信頼を失うように思います。新型コロナ対策も、専門家に対して批判をする際でも科学的根拠に基づいて批判する姿勢が見られます。
──科学に対する意識は変わる一方、科学研究は戦前から脈々と続き、科学の信頼自体が大きく揺らぐようなことはなかったように思います。その背景にはどのようなものがあるのでしょうか
日本が世界に存在感を示そうとする中で、科学が公平なものだったということが挙げられます。科学の結果は公平に評価され、例え相手が日本を軽視していても無視はできません。議論が苦手でも、几帳面(きちょうめん)な努力で結果を積み上げていくことができ、実力を研究の成果で示せる領域なのです。そうした成果は文化や言語の違いがあっても否定されないものであったことが大きいのでしょう。