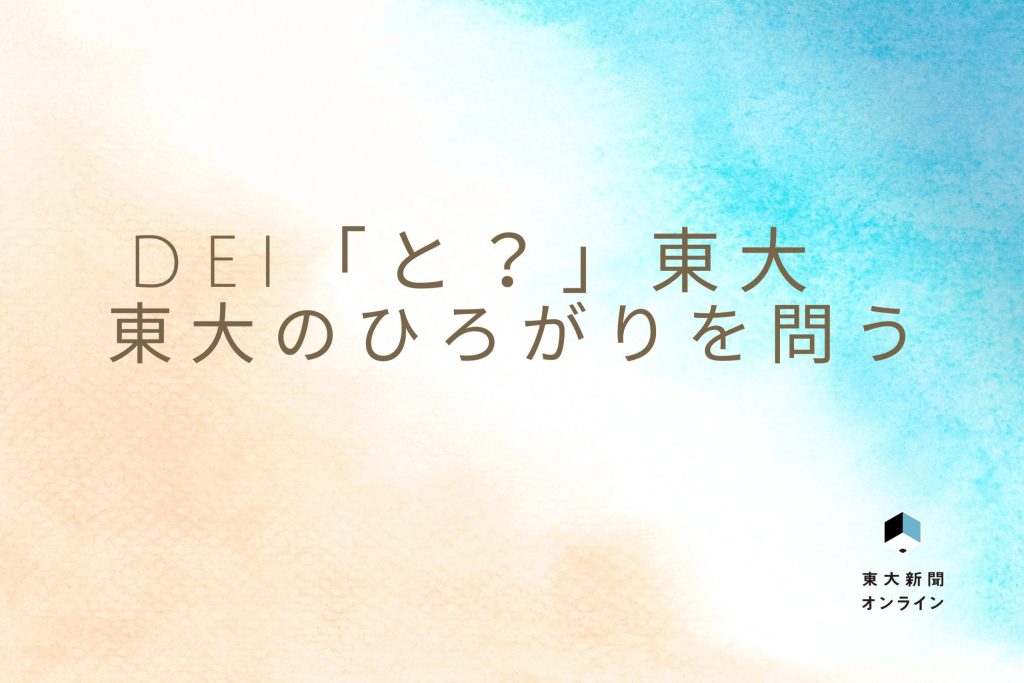
「DEI」とはダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包摂性)の略称であり、組織や社会の中でさまざまな背景を持つ人々が、平等に参加し活躍できる環境を整えることを理念とする社会運動である。特に、研究や教育で多様な視点からの、より深く新しい洞察を常に求める大学ではDEIが重要であることは言うまでもない。東大でも単なる理想論ではなく、社会的責務としてDEIを引き受け、推進している。2021年に示した基本方針「UTokyoCompass」が象徴的だ。そこでは【知をきわめる】【人をはぐくむ】【場をつくる】と三つのパースペクティヴを銘打ち、女子学生3割、女性教員25%、交換留学生の派遣・受け入れの拡充、修士・博士課程学生の支援などの具体的目標を掲げ「多様性の確保」を目指している。改修の終わった駒場Iキャンパスの1号館1階にオールジェンダートイレができたことも記憶に新しい。
一方で、現状の歩みはまだ途上と言わざるを得ないのも事実だ。今年度の一般選抜において、全合格者に占める女性の割合は20.0%(昨年度は19.4%)で目標には程遠く、女性教員比率は16%ほど。本郷キャンパスの建物には身体障害者の障壁になる構造物が多く存在する。さらに、これらの問題は考えれば考えるほど、東大一つではどうしようもできないように見える、根本的な社会構造が見え透けるような気さえする。
東大は、「安心して活動でき世界の誰もが来たくなるキャンパス」をいかにしてつくりあげることができるのだろうか。150周年記念連載第1弾では、「DEIと東大」と題して、東大の現状と抱える課題、その展望について探っていく。
DEIはなぜ重要か
冒頭に「DEIは重要だ」と書いたが、いま一度その理由を見極める必要がある。そもそもDEIとはなぜ必要なのだろうか。それは一つに歴史的な差別の是正である。例えば、歴史的な文脈において高等教育を受けるのに「男性」でなければならない時代があり、「健常者」/「障害者」であるだけで享受できる教育資本にはあまりに大きな格差があった。そして、当たり前だが現代はその延長線上に位置している。すなわち「あった」ではない。今も確かに「ある」。帝国大学の時代、女子学生を正規の学生としては受け入れなかった東大は、今でも男性中心的な構造を変革するに至っていない。現総長の藤井輝夫は麻布高校、前代の五神真は武蔵高校、その前の濱田純一は灘高校……と、名の知れた男子校出身者が続いているのは、象徴的と言っていいかもしれない。もちろん、先人の個々の輝かしい功績への評価を覆そうとは思わないが、その陰に、不当な扱いによって涙をのんだ人、ないがしろにされた人がいて、その大勢が現代も変わっていないことは、しかと認めなければならない事実だ.
また一つに、多様性の確保がより成熟した環境を育み、豊かな成果を生むようであるということも見逃せない。少々文脈は異なるが、マッキンゼーの調査によれば、性別・民族の多様性が高い企業は財務パフォーマンスが優れているというデータもある。高等教育や研究の分野においても、さまざまな視野や洞察がより深い成果を生むためには必要であることは明らかで、東大が世界で存在感を発揮していくためには、偏った出自・性別・民族の集団であることはあまり得策ではない。
東大におけるDEI推進の課題と限界
DEIが重要であり、それを東大自身も認識していることを整理した。では、なぜ東大はその目標を十分達成できていないのだろうか。何が問題となっており、偏った男女比や留学生の少なさ・出自の偏りを招いているのだろうか。
ここで指摘すべきは、まず東大(ひいては旧帝国大学全体)における理系学部の枠の大きさだ。東大の一般選抜における文科の募集は約1200人であり、理科は約1700人である。理系の募集人数が多く、主要な都内の私立大学と比較すると、その多さが目立つ(例えば早稲田大学は文系約3500人に対し理系約1500人)。そして、日本では理系を志す女子は男子よりも圧倒的に少ない。「自然科学・数学・統計学」分野の女子率は27%で、経済協力開発機構(OECD)加盟国全体の52%と比較するとその差は歴然だ。「工学・製造・建築」など加盟国全体でも26%と低い分野もあるが、その中でも日本は16%と加盟国中最下位だ。性差によって学力に差があるのかと言われると、それもまた違う。同じく15歳を対象にしたOECD内における調査では、日本の数学の成績は男女ともにトップクラスでその差は少ない。学力差というのも考えにくい。
ここに日本の固定観念の根強さが潜んでいることは見逃せない。「女性は理系科目ができない」と社会に半ば「常識」として植え付けられた偏見は今も根強い。また、男性に比べ、女性の上京をためらう家庭が多いことも見逃せない。浪人生の男女比も男子の方が高い。安定志向と言ってしまえば簡単だが、その「安定志向」には本人自身のそれよりも、外部から与えられたそれが無視できない程度潜んでいることに、注意しなければならない。
次に、留学生や障害者の受け入れにおいて深刻な課題の一つは東大の財政的基盤の脆弱(ぜいじゃく)さである。とりわけ留学生については、出身国や家庭の経済的背景によって進学先が大きく制約される。経済的に余裕のある学生は高額な学費・生活費を負担しても質の高い教育・研究環境を選択できるが、困窮する学生は奨学金や学費免除、住宅支援が充実した大学に限らざるを得ない。東大の受け入れ体制も、国際的トップ校としては発展途上だ。例えば、学士課程の英語学位プログラムはPEAKに限られ、英語で履修できる科目の選択肢も限られる。また、学費減免や奨学金制度はあるが倍率が高く、手続きも煩雑で経済的に脆弱な学生にとって大きな障壁となっている。さらに外国人教員比率が約14%と海外のトップ大学に比べ低い。
障害のある学生の受け入れも同様に人的・物的資源の不足が課題である。バリアフリー化、教材のアクセシビリティーの確保、試験・評価の合理的配慮など幅広い支援が必要だが、東大バリアフリー支援室の常勤スタッフ数は限られ、個別対応が追いついていないという声も見受けられる。人的資源の拡充や専門性の向上、部局間の連携強化が急務だが、財政的裏付けが不十分な現状では理想と現実の間に深い溝が残っている。
東大の「外縁的」多様性について
ここまでの考察を勘案すると、東大のDEI達成のための諸施策のままならない原因に、東大よりもはるかに大きな社会の構造が見え透けているのは確かだ。では、東大には何もできないか。そうではないだろう。日本トップクラスの教育・研究環境を東大が有していることは事実であり、これまで検討してきた問題の原因にメスを入れるのに、十分とはいえずとも、そのための力と責任を持っているはずだ。東大こそが先陣を切るべきではないか。
その考えの下では、これまでの東大の諸施策が、いかに東大内部の多様性--内縁的多様性、とでも呼ぼうか--ばかりを注視していたかが見えてくる。女子学生向けの理系進学支援や家賃補助、留学生への奨学金やPEAKに限られた英語学位プログラム、障害のある学生への合理的配慮など、いずれも学内の顔ぶれを整えるためにとってつけたような施策にとどまっている。対象も女子学生・留学生・障害者といった「分かりやすい少数者」に偏り、両親ともに高卒以下である大学第一世代や、経済的困窮者といった層への支援は十分ではない。東大のDEIは内に閉じ、そのまなざしが本来志向するべき社会との開かれた接点を欠いている。
つまり、東大が目を向けるべきはその中における内縁的な多様性だけではなく、むしろ社会との接続における「外縁的多様性」(内縁的多様性に対して外部構造の多様性を意味する)にある。「多様性」とは、決して構成員の属性に限られるものではなく、大学が誰と接続し、どのような関係性の中に位置するかという、より外縁的な広がりにも及ぶはずである。つまり「外縁的多様性」とは、大学が関わる機関・組織・社会的主体との関係における多様性、すなわち資金を提供する国家や財団、共同研究を担う企業、制度設計に影響を与える国際的パートナーなどとの連携のあり方を指す。
先に指摘したように、東大のDEI施策は、これまで主として学内構成員の属性の多様化、すなわち内縁的多様性に焦点を当ててきたと言える。女子学生・女性教員の比率向上、障害のある学生支援、LGBTQ+の権利保障、留学生受入の拡大といった施策は、いずれも東大という内部共同体の顔ぶれを多様化することを目標としており、外縁的多様性への意識は乏しい。
東大の「社会的責任」、背反する「内縁的閉鎖性」
具体的に見ると、第一に、連携・資金源の偏りが挙げられる。東大の研究・教育活動は依然として、中央官庁や大手企業、特定の財団など東大卒業生も多く関わってきた、伝統的かつ男性中心的な関係性に強く依存している。例えば、一つの指標として財務構造をうかがえば、東大は収益の3割ほどを国からの運営費交付金で賄っているが、米マサチューセッツ工科大学ではそのほぼ半分が受託研究費、3割以上が寄付によるものだ。資金源が多様であることは、当然その組織が接続する外部のコミュニティーの多様性を象徴する。
また、今年三菱商事との協業によりTech Incubation Paletteというスタートアップのプログラムが実現したが、東大発のスタートアップは、役員の多くが男性であり、東大の閉鎖的な内部構造を再生産しているように見受けられる。そして、この事例に象徴的なように、東大──とりわけ藤井総長らを中心とする現在の中枢──が想定している社会はスタートアップやテック系の産業界などに限定されていて、他方で例えばイスラエル・ガザ情勢やトランプ政権発足に伴う世界の混乱をはじめとする国際情勢や、アイヌ民族をはじめとする先住民族の遺骨返還問題などの社会に対する倫理的な責任について、日本を代表とする大学としては発言に乏しく、消極的である。多様性を標榜(ひょうぼう)しても、外部パートナーの構造は画一的であり、グローバルな市民社会組織やジェンダー平等・人権を基軸とする財団との連携は試みられているとはいえ前者に比較するといまだ限定的だ。東大は、全学として社会になんらかのメッセージを発信することに、もっと積極的であるべきだ。
第二に、広報活動の受け手も限られている。女子学生向けの家賃補助や理系進学支援セミナーなどの施策は存在するが、実際には情報が届く層には偏りがあることが多い。例えば文部科学省の2023年の「高校生の進路に関する保護者調査」では、世帯年収や居住地によって、保護者の情報収集能力や進学支援意識に有意な差があることが報告されており、都市部・高学歴家庭・進学校出身者の方が情報感度や進路選択の柔軟性で優位に立つことが明らかになっている。社会的に周縁化された層や、家庭の教育資本が乏しい層に向けたアウトリーチはまだ弱く、結果として学内の「多様化」は中高一貫男子校・首都圏進学校出身者を中心とした、文化的に同質なエリート層内の変化に留まっている。本来その施策が解消することを目指す(極端に分配された)教育資本格差について解消するに至っていない。
第三に、施策の対象となる「マイノリティー」の範囲が限定的である。東大のDEIは主に、女子学生・障害者・性的マイノリティー・留学生といった明確にラベル化された少数者に焦点を当てる。しかし、社会的階層・地域格差・世代間格差など、より構造的で重層的な差異への対応は後景に退いている。結果として、DEIが「分かりやすい少数者」に閉じた制度改善にとどまっている。
東大のこれから:大学を超えた「ひろがり」としてのDEIを
このように、東大のDEIは学内における属性多様化を中心とした内縁的取り組みが多く、外部社会との関係性や多様な価値圏への接続を意識した施策は乏しい。この内向き志向が続く限り、東大は「多様性を標榜するが閉鎖的なエリート共同体」という印象を拭えず、真に公共的な知の拠点としての正統性を強化するには限界があると言わざるを得ない。
もしも大学が、今見たように同質的な価値観と制度に基づいた限られた外部関係のみで成り立っているとしたら、その内部にいかに形式的な「内縁的多様性」が保たれていたとしても、その知的営為は閉鎖的な回路にとどまりかねない。逆に言えば、外縁的多様性を積極的に獲得し、多様な文化圏・経済圏・価値体系との対話を通じて自己を絶えず更新していく大学こそが、真に「開かれた知の場」としての公共性を担うことができる。そもそも、東大の構成員も東大には無関係の「外縁」だったものが、さまざまな機会を経て東大の「内縁」に参与するようになった人々だ。東大が社会の信頼を集める存在であり続けるためには、外縁的多様性への自覚的なまなざしと、それに裏打ちされた制度設計が不可欠である。
こうした社会とのつながりを多様にする施策が、留学生や障害者、女子学生の増加を促すということにピンとこない人もいるかもしれない。確かに、外縁的多様性の確保への取り組みは、女子学生や障害のある学生の数を直接増加させるわけではない。しかし、大学が閉じた内輪の論理にとどまる限り、社会全体に存在する多様な価値観や生き方と接続する機会が乏しく、結果として学内の多様性確保も限定的で形骸化しやすい。東大総長に結局のところ有名男子校出身者が続いているのは、その象徴だった。逆に、企業・地域社会・国際機関・NPOなど多様な外部主体と恒常的に連携し、共同研究や社会連携、多言語広報などの活動を通じて大学の知を開くことで、大学は自らの文化を更新し、異質な他者と共存する経験を蓄積することができる。こうした外縁的多様性の営みは、大学を「閉じたエリート共同体」から「開かれた公共空間」へと転換させ、ひいては多様な背景を持つ人々が安心して集う環境を整える基盤となるのである。
DEIの本質は、他者を見つめ続けることだ。自分の了見を疑い続け、理解できないものを拒絶するのではなく、受け入れ、そこに一緒にいるということ。絶えず私たちは異質なもので、それはつまりそれぞれが異質なのであってその誰もが一緒くたにならずに、個人としてそこにあるということ。その視座を持ち続けることはきっと私たちが他者とともに学び、考え、生きていくための根源的な倫理にほかならない。多様性とは、単に「違う人々がいる」ことではなく、「違うままにともにある」ことに向けた不断の実践である。
だからこそ、DEIとは一度実現して終わる政策ではない。それは、常に更新され、問い直され、対話されるべき「開かれた営み」であるべきなのだ。東大がそのような営みの先陣を切る存在であることを、私たちは信じたい。【乃】











