近世日本の地域社会や農業を多面的に研究する戸石七生准教授(東大大学院農学生命科学研究科)。もともとは歴史への関心から東大文学部で西洋史を専攻していたが、土地制度への関心から、文学部から農学生命科学研究科に進学した。異なる地域ごとの比較や長期的な視点から見えてくるのは、そこに生きる人々の「食のかたち」。現代における食のあり方を聞いた。(取材・木下太陽、撮影・宇城謙人)
歴史学からの出発──「土地制度」をめぐる探究
──東大入学までの遍歴を教えてください
広島で幼稚園まで過ごし、東京で小学校に通ったあと、中学校から父の仕事の関係でドイツに移りました。当時はまだ東西ドイツが統一する前でした。ギムナジウム(現地の中等教育機関)を経て、日本の高校に戻りました。幅広いことが学べると思い、東大を受験しました。
──前期課程はどのように過ごしましたか
ドイツに滞在していた関係で、ドイツ語の授業に多く参加しました。第一外国語がドイツ語だった人たちで構成されるクラスにも参加しましたが、周囲の語学への関心が高かったことも影響していると思います。また、当時は農学に特別な興味関心を持っていたわけではありませんでしたね。
──後期課程では文学部、大学院は農学生命科学研究科に進学します
もともと歴史が好きで、小学生のころから歴史を学びたいと思っていました。後期課程では西洋史を中心に、家族史や外交史など、まさに文学部的なことを学んでいましたね。
大学院では土地制度の歴史を学びたいと思ったのですが、人文社会系研究科よりも農学生命科学研究科のほうが向いているだろうと考え、そこに進みました。
──大学院での学びについて教えてください
日本の土地制度を学ぶなかで、土地所有のあり方が家族関係や村落コミュニティと密接に結びついていることを知り、家族史の研究に着手しました。修士論文では「養子」という切り口から、江戸時代の「家」と「村」の実態解明を試みました。
史料としては、現在の戸籍に近い性格を持つ江戸時代の宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)を活用しています。修士課程では、私の所属研究室が市史編纂(へんさん)に携わってきた神奈川県秦野(はだの)市の資料を調査し、論文を執筆しました。しかし、修士論文の段階では勉強が足りないと自覚し、その後、歴史人口学研究の第一人者であった故・速水融先生から新たなデータベースをお借りする機会を得て、博士論文を完成させることができました。
歴史を比較して得た、新たな視点からの研究
──現在はどのような視点で研究を進めていますか
研究には、通史的・比較史的な視点から、長い時間軸や複数の地域を扱ってアプローチしています。博士論文では、修士論文の延長として「養子」という切り口から家・村・土地などを研究したのですが、そこから日本近世の身分制度というテーマに入っていくことになりました。具体的には「百姓株式」の話を始めたのですが、これは村の寄合や祭りへの参加と、農業を営むために必要な屋敷地、田畑、山林を利用する権利のことです。この百姓株式が家だけでなく村でも管理されていたということが先行研究から明らかになっています。ただ百姓株式については日本近世史を専門とする人でも知らないことがあるほどで、当時は少し孤独感を覚えていました。
そんな時、本を読んでいたところ、インド史の小谷汪之先生の著書に出会い、日本の百姓株式と同じものがインドにあると知りました。そこから比較というアプローチで研究を始めたという経緯があります。
研究の世界では、百姓株式は近代との接続が意識されすぎる傾向が強く、「よくわからない慣習が残っているもの」として理解されがちです。しかし、中世から見ていくと、決してそんなことはありません。私の著書『むらと家を守った江戸時代の人びと 人口減少地域の養子制度と百姓株式』(農山漁村文化協会)では、インドとの共通点を示しながら、百姓株式は中世からの流れで説明すれば理解できるという話を詳しく書きました。
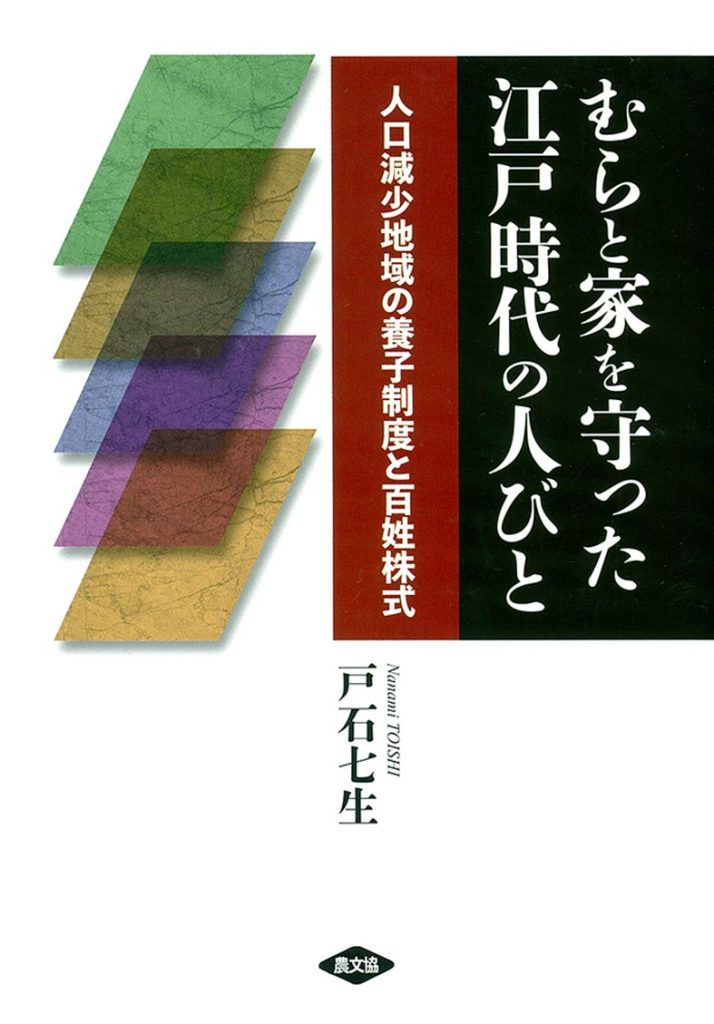
──百姓株式の研究がどのように食につながるのでしょうか
身分制の問題に取り組む中で、他の身分との違いを考える際にどうしても出てくるのが「食」や「穢(けが)れ」といった問題です。この点では、インドにも同様の問題があり、かなり共通する部分があります。例えば、穢多(えた)や非人(ひにん)など、日本近世史の用語では「賤民(せんみん)」と呼ばれる被差別部落問題にもつながる身分です。
一方で、穢多や非人と呼ばれる人たちは、農業に必要不可欠な「役畜(えきちく)」を扱っていました。戦後までそうでしたが、日本人はウシやウマをトラクター代わりに使っていました。こうした動物は必要不可欠であったにもかかわらず、動けなくなったり死んだりすると「穢れている」とされ、村の外れの特定の場所に捨てられました。それを回収するのが「賤民」と呼ばれた人たちだったのです。こうした構図は、1953年に「農業機械化促進法」という法案ができてトラクターが普及するまで続いていました。最近その法律が廃止されたと、教え子の農林水産省の職員が教えてくれましたが、背景にはこのような歴史があります。
江戸時代の農業は、士農工商という言葉が示す通り非常に重要な産業とされました。また、全ての価値を米に換算する価値観が社会の隅々まで行き渡っていました。その意味で、稲作は「光の当たる産業」だったのですが、同時にそれを裏で支えていたのは穢多や非人などの被差別身分だったという「影の側面」も存在していたのです。
この問題は現在も政治的な影を落としているため、日本近世史の研究者と話していても、インドの研究者とは違って「その問題はちょっと……」と避ける人が多いのが実情です。しかし、自分の史料を見ていると、日常的に彼らが登場します。そうした事実を直視し、研究と結びつけていきたいと考えています。
ここで話を「食」に戻すと、当時の農民は牛肉をあまり食べていませんでした。これは日本に限らず起きたことですが、実は江戸時代、「牛肉を食べない運動」があったことによります。獣の肉を食べないことで徳を積むという運動です。欧米でもこうした研究をされている方がいて、多くの本が出ています。私もキャッチアップが必要ですが、国際的にも、現在の動物愛護、環境保護運動に近いような「食べてはいけないものの序列」ができたのです。
そこで重要なのは、農民は牛肉を避けていた一方で、皮を取って生計を立てていた被差別部落の人たちは、残った肉も捨てるのではなく適切に食べていたということです。牛肉は意外と流通していたのではないか、という観点で学生が論文を書き、私も共著者として名を連ねたこともあります。
──食べてはいけないとされつつも、実際は異なる側面もあったということですね
現在の環境運動や動物愛護運動の中で「牛を食べるのは環境に良くない」といったことを国連が発表しています。温室効果ガスであるメタンガスを排出する牛を育てると、地球温暖化が進むというわけです。イギリスへ行った際に、このような食べ物の序列化はアジアにも見られ、そのルーツは18世紀までさかのぼれるという話もしたのですが、反応はあまり芳しくありませんでした。
しかし、食糧消費の大家であるベテランのクリストファー・リトソン先生(英ニューカッスル大学名誉教授)にお会いした際は、話が通じました。「役畜」である動物を食べることへの忌避感、つまり一緒に働いたり、冬に家の中に入れて保護したりした実体験に伴う感覚の話です。昔の人であれば、牛を食べることに対する「痛ましい」とか「血が出てくるのは……」といった感覚を共有できました。
リトソン先生がおっしゃるには、実は英国にも同じような感覚があり、「ウマは食べない」のだそうです。フランス人は食べますが、イギリス人にとって馬肉はとんでもないこと。それはやはり、第二次世界大戦後にトラクターが普及する前まで、ウマが主な役畜として農業に欠かせず、毎日一緒に畑で働いていたからです。
こうした比較をすると、一部の「自分たちが最新トレンドだ」と主張する先生方とは意見が合わないこともありましたが、戦後の食糧事情をどうにかしようというところから研究を始めたベテランの先生とは、不思議と意思疎通ができました。
今は、そうした伝統的な感覚と新しいイデオロギーをどうつなぐかを考えています。日本にも「肉を食べるのは環境に良くない」という新しい考え方が入ってきていますが、その発想がどこから来るのかという背景は十分に伝わっていないように思います。それは、もしかしたらリトソン先生が指摘されたような「伝統的な農業のあり方」との対比から生まれているのかもしれません。食における消費と生産は、そうした形でつながっているのです。
──農学部のフィールドが広いことに驚きました
もともと農業経済学の分野は文系色の強い領域であり、歴史学、農業政策学、農業経営学、開発経済学、さらには経済理論に至るまで、多様な学問領域を包含しています。また、森林経理学や農学国際専攻のように、文理融合的なアプローチをとる研究室も少なくありません。
日本の農業経営学のルーツを辿ると、食糧生産を総合的に研究する栽培学と経営学が未分化だった時代に行き着きます。その後学問の専門分化が進み、栽培学は理系、経営学は文系へと分かれていきましたが、今なお根本圭介先生(東大大学院農学生命科学研究科教授)のような文系の知見にも精通し、文理融合的な研究を実践されている先生もいらっしゃいます。
異なる立場から「食のかたち」を捉え直す
──農業政策などの面から、現代における食や農業をどう受け止めていますか
現代の環境に対する意識の高まりについて言えば、消費者が自分たちのイデオロギーで「頭でっかち」になり、生産者の実情を忘れがちであるという点が大きな問題です。そこをつなぎ合わせ、補強していくのが私の役目だと考えています。しかし、そのためには通時的、あるいは広域的な視点を持たなければならず、短期間のデータだけでは説明がつきません。
もう一点、「米」の問題についてですが、食の体系というのは地域や文化によって決定的に異なります。例えば、日本農業経済学会のホームページを見てみてください。トップページに出てくる画像は「イネ」です。一方で、ヨーロッパの農業経済や農学の教科書を見ると、そこには「ウシ」が出てくる。つまり、その地域や文化にとって何が最も重要な食物であるかという「当たり前」は、決して普遍的なものではないというところから問い直さなければなりません。だからこそ、地域比較的な視点が必要なのです。
日本人は米を中心に食生活や社会体系を築いてきました。米とは「カロリーベースで今日何キロカロリーのうちのこれだけ」と数値化できる存在ではありません。日本人の生活の満足度に最も直結している食料なのです。しかし、農水省の方々やメディアに出る有識者は、その実感を十分に理解していないように思います。
私は、こうした問題を解決するには「食糧管理制度(食管制度)」に戻すしかないのではないかと考えています。1995年に廃止されるまで続いた制度ですが、今の若い皆さんは生まれていなかったかもしれません。私はまさにその制度を肌で知っている世代です。
現在起きている「令和の米騒動」のような事態を前にして、消費者と生産者の双方が満足できる形を模索するのであれば、政府がその差額を負担して調整する食管制度のような仕組みを考え直すべき時期に来ているのではないでしょうか。
──「食」をどう捉えるのがよいと考えますか
「人間はその人が食べてきたものでできている」という言葉があるように、食は自分自身のことをより深く知るための手段だと考えています。
以前、3年生のゼミで最初にこのようなアンケートを配ったことがあります。「明日が地球最後の日だとしたら、何を食べたいですか?」「一生のうち、ある一つの食べ物が食べられなくなるとしたら、一番困るものは何ですか?」と。すると、地球最後に食べたいものは人によってバラバラなのですが、「これだけは断てない」という問いに対しては、ほとんどの学生が「米」と答えるのです。やはり、お米を中心に考えるというマインドは、日本人の中に今も深く根付いているのだと感じます。
例えば、パンくずやラーメンを残してもそれほど咎(とが)められませんが、米を一粒でも残すと怒られる、いわゆる「米警察」のような感覚が日本人にはあります。ところが、農家の出身でありながら、お弁当のお米を平気で残したりする一面を持つ人もいます。
そこには、生産者と消費者の間にある価値観のギャップ、あるいは作っている側だからこそのドライな距離感があるのかもしれません。こうした「食」を巡る認識のズレや、消費者と生産者の価値観のギャップを丁寧に埋めていくことこそが、私の仕事だと考えています。
──最後に一言お願いします
農学部にはさまざまな切り口から研究できる環境があります。今は男子学生の割合が圧倒的なのですが、ぜひ女子学生の方々にも来ていただきたいと考えています。
バイオテクノロジーだけではなく、食やガーデニングといった、日々の生活に直結する事柄も農学の大切な領域です。もともと「家政学」と「農学」は根を同じくする学問です。どちらも家庭や生活を支えるための知恵であり、それこそが農学の本質なのです。農学部で生活に根ざした学問を志す皆さんを、弥生キャンパスで心より歓迎します。

。











