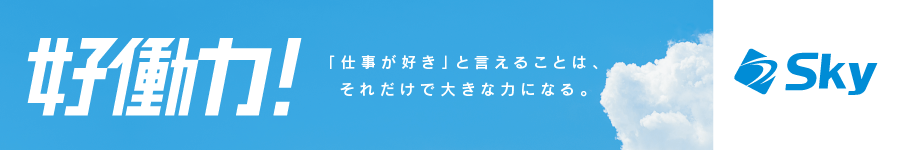「善意」「悪意」「マナー」をキーワードに16世紀から20世紀の英国と米国の文学を読み解く『善意と悪意の英文学史』。だが当初は『善意と悪意の文学史』というタイトルでの出版も考えていたということもあり、英文学に留まらない広い問題意識を持つ一冊でもある。今回は著者の阿部公彦教授(東大大学院人文社会系研究科)に本書と関連して文学以外の英国文化や日本の文学、また現代のコミュニケーションのあり方について考えを聞いた。
(取材・渡辺明日翔)
『善意と悪意の英文学史——語り手は読者をどのように愛してきたか』
阿部公彦著、東京大学出版会、2015
━━本書では、16世紀頃の英国で礼節への意識が高まりマナーブックが普及する一方、マナーを揶揄(やゆ)する風刺文化が生まれたことが指摘されています。こうしたマナーと風刺の関係は文学以外の現代英国文化にも通じるように考えられますが、いかがですか
過剰にマナーや形式を守ってみせることでマナー自体をひっくり返す。こういう力は『モンティ・パイソン』や『Mr. ビーン』のような現代のコメディーには確かにありますね。
また形式と文化ということでは、英国発のパンクなどはどこか冷めた「やけくそさ」が目につきますし、ポップなように見えるザ・ローリング・ストーンズなども、その魅力の芯の部分には独特な調子っぱずれさがあり、形式と上手に距離をとっています。
━━本書では日本語と英語を「敬語型」か「ポライトネス型」という枠で比べています。日本語は敬語のルールからも分かるように決まった「型」に依存する。英語はやり取りのたびにルールを新たに設定する、と。これは文化的な背景とも関係しますか
英国発の文化では、サッカー、ラグビー、テニス、クリケットなど世界に普及したスポーツが目につきます。これは、共通のルールを作り共有するのが巧みだということでしょう。米国文化にもそれは引き継がれました。ポライトネス型はルールがより柔軟で、何より文化的な背景が違う人が入ってきてもルールがオープンになっているところが特徴です。
━━明治維新後、全国レベルで言葉の統合が進んだことにも本書では注目しています。この時期、書き言葉としてどんな文体が標準化するかわからなかった。そんな中「ですます調」をうまく使いこなした江戸川乱歩と宮沢賢治といった書き手が取り上げられ分析されています。太平洋戦争も日本社会にとってもう一つの大変化と言えますが、戦後の作家の文体についてはいかがでしょうか
近著の『病んだ言葉 癒やす言葉 生きる言葉』(青土社)でも触れたのですが、太宰治と志賀直哉の対比は興味深いと思います。太宰の小説は二人称的で、ですます調で読者に語りかけるように書かれた作品が数多くあり、とても人間関係的です。その一方、志賀の小説は『城の崎にて』などが典型ですが、どこか無愛想。けれどもよく見るとそれは志賀なりに読者や自己に「誠実」な語りを追求した結果です。
太宰の作品は「読者よ」というように語りかけるシャーロット・ブロンテやチャールズ・ディケンズのような19世紀的な小説、志賀はアーネスト・ヘミングウェイがその典型である20世紀的な小説を想起させます。
━━本書では米国の作家ウィリアム・フォークナーが後者のタイプとして論じられていましたね
後者のタイプの小説には、感情表現が大げさでときに感傷主義的になる19 世紀小説から距離を置くようなスタンスが読み取れます。
志賀と太宰は読者との関係の取り方が異なるということなのですが、おもしろいことにこの二人は実際に衝突したことがあります。志賀は1947年の太宰の小説『斜陽』の敬語が不自然であると批判し、それに応じて太宰も『如是我聞』というエッセイで志賀に反撃したのです。たとえば1946年の志賀の短編小説『灰色の月』の冒頭は「冷え冷えとしているが、着てきた服で丁度よかった」と始まる。そこを、自分のどうでもいい事情に拘泥している、いったい何様だ! と太宰があざ笑うのです。
つねに聞き手への気遣いが表に出る太宰の文章に比べると、志賀はすごくぶっきらぼうで自己中心的。お偉そうだというのです。
━━確かに太宰の作品は読者を「笑わせよう」という意識が志賀よりも強く感じられ、二人称的に読者を意識しているように考えられます。これは一方で『人志松本のすべらない話』といったテレビ番組が代表するように、面白いネタで人を惹きつける最近のコミュニケーション文化にも通じる様に思われます
もしかしたらコミュニケーションのスタイルは循環していて、現在は感情表現が過剰気味だった以前のスタイルに回帰しているという面もあるかもしれません。
近代という時代を通し、善意は一種の貨幣のように機能し、善意を相手に多く与えることで関係を良好に保ったり地位を得たりということが意識されていました。
最近のSNSには「感涙」「爆笑」というような大げさな言葉が多く用いられる傾向がありますが、これも言葉を通じ相手に多くの善意を表現しようとする結果でしょう。善意の表現が一種のインフレーションを起こしているようにも見えます。社会に善意があふれること自体はとりあえず悪いことではありませんが、それが過剰になると息苦しさのようなものが生じたり、反動で攻撃的な言葉が増えたりするということは意識する必要があると思います。
━━本当に内面に善意があるかどうかはともかく、自分に善意があるように見せることによって相手から多くの善意を引き出すことを狙うコミュニケーションは、本書でも18世紀英国のマナーブック『チェスタフィールド卿の手紙』を通じて分析されていましたね
はい。現代社会ではこれはSNSなどメディアの性質とも関係しているでしょう。字数が限られたSNSでは、どうしてもメッセージは善意や悪意、賛成と反対といった二元的な価値観の中で極端に単純化されがちです。微妙なニュアンスが切り捨てられてしまう。そういうメディア環境では、善意を強調することによってトラブルを回避する予防線を張らざるを得ないのかもしれません。
━━対面でのコミュニケーションは録音や録画をしない限りその場で消えてしまう一回性の強いものですが、インターネット上の発言や投稿はテクストとなって残るということも背景にありそうですね
まさにそうで、コミュニケーションがテクスト化していることによって、ちょうど哲学者のジャック・デリダが文学テクストについて指摘したようにメッセージがどんどん読み替えられていく可能性が高くなっていると思います。コンテクストが切り取られて発信者の見えない所でメッセージだけが流通してしまう危険がある以上、事前に予防線を張ることがコミュニケーションの重要な戦略となっていると考えられます。
━━学生を中心に読者に何かメッセージをお願いします
人間関係の距離感を扱う学問があるということ、そしてその一つが文学研究であるということを知ってほしいですね。今日の若者は距離感について非常に敏感ですが、それがアカデミックなテーマとして扱われていることは十分に知られていません。
文学作品のテクストでは人間関係の機微や微妙な距離感が非常に精密に表現されます。現在は人間のコミュニケーションの全体がテクスト化している時代なので、こうした時代を生きる若者に、テクストを通し人間の距離感の神秘を解き明かす学問である文学研究にも注目してもらいたいです。
阿部公彦(あべ・まさひこ)教授(東京大学大学院人文社会系研究科)
97年英ケンブリッジ大学大学院英語英米文学専攻博士課程修了。Ph.D.(文学)。帝京大学文学部専任講師などを経て18年より現職。13年『文学を〈凝視する〉』(岩波書店)でサントリー学芸賞受賞。
【記事修正】2022年1月6日午後0時29分 リード文の「東大人文社会系研究科」を「東大大学院人文社会系研究科」に、経歴の「Ph.D」を「Ph.D.(文学)」に、『文学を〈凝視〉する』を『文学を〈凝視する〉』(岩波書店)に修正しました。その他表記を修正しました。