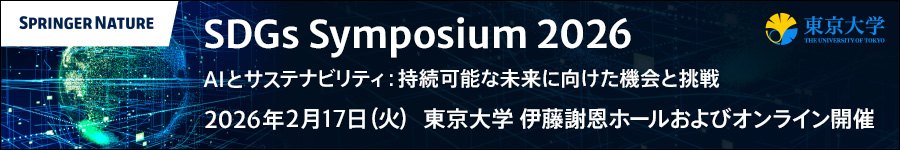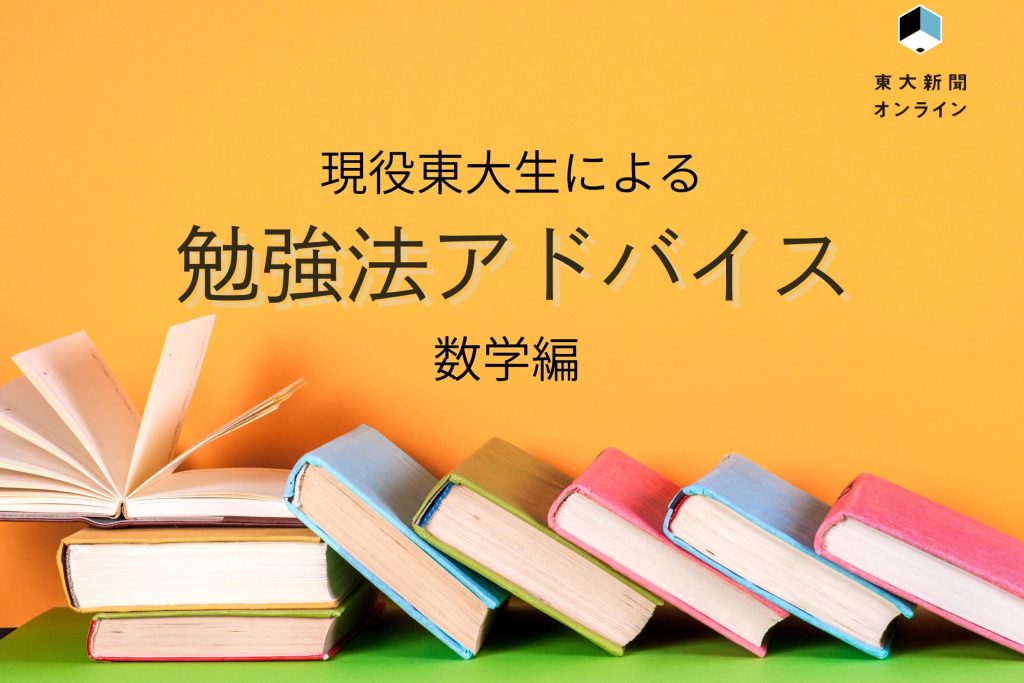
東大に合格した人はどの時期にどのような勉強をしていたのだろうか?読者の中には東大を受験しようと思っているものの、身近に東大受験について相談できる相手や仲間がいないため自らの勉強方法に確信が持てず、このような悩みを持つ人もいることだろう。そこで本記事では、東大生による数学の時期別の勉強方法をはじめ、東大入試の基本情報や入試本番での時間配分や注意点などを科目別に掲載した。ぜひ受験勉強の参考にしてほしい。
理系数学 基礎を固めてから使える解法を増やす
例年大問6問の構成で、高校数学の幅広い分野から出題されます。複数の分野が融合した問題も多く、満遍なく知識を身につけることが求められます。また、問題を解く過程で試行錯誤したり計算処理に時間がかかったりする問題が多く、時間配分も重要です。近年はおおよそ難化傾向にあり、数学の得点で周囲の受験生と差をつけるには相当の実力が必要になるでしょう。
高3の夏休みに入るまでをめどに、全範囲の基礎固めや難関大受験者向けの問題集での演習を済ませられると良いでしょう。知識の抜けや漏れをとにかくなくすことが非常に大切です。
可能であれば夏休みから、難しければ9月頃から過去問演習に入ります。過去問演習では本番の時間配分を意識するために、試験時間の150分を計り、記述も丁寧に行うなど、なるべく本番と同じ状況で取り組みます。150分経過後に解ききれなかった分があり、もう少し考えたいという場合はそのまま続けましょう。ただし、考えても分からなさそうなら無理に続ける必要はありません。また、解答用紙の使い方を練習しましょう。本番では、例年大問1、2、4、5はA4サイズ程度、大問3、6はA3サイズ程度の解答欄が与えられますが、案外不足しがちです。問題を解き終わった後は、漫然と解説の文章を読むのではなく、解説を見ずに答案を再現できるか、類題が出たときにその解法を使えるようになったかを意識し、実際に手を動かしながら解説を追います。別解がないか考えたり調べたりするのも良いでしょう。
高校数学では、基礎固めが終わってから、どれだけ多くの解法を覚えて使えるようになるかが鍵になります。「なぜこの問題ではこの解法が有効になるのか」という本質を理解して、偏りなく解法の引き出しを増やしていけば、安定して高得点を取ることができるでしょう。(理I・1年)
文系数学 自分に合った計画的な学習で余裕をもった対策を
試験時間は100分、大問は4題で、出題範囲は多岐にわたり、しばしば理系数学との共通問題が出題されます。配点は2次試験全体440点中の80点と、教科の比重としては英語や国語に比べて低い一方、差が付く科目ともいわれます。突飛な問題が出ることは少なく、典型問題にひとひねり加えられた問題が出題されます。多くの大問は複数の小問で構成され(1)で証明した式を(2)で生かせるような誘導が付いています。前の小問で得られた情報を利用して解く意識や、部分点を粘り強く勝ち取る姿勢、一つの問題に執着しすぎない柔軟な時間配分も肝要です。
高3の夏休み前までは、定義・定理・公式など基本事項を自ら導出・活用できるまで、苦手な単元を演習しましょう。『青チャート』や『フォーカスゴールド』などで典型問題に多く触れられる教材を用いたり、模試の復習を面倒がらずに続けたりすると効果的です。体系的に整理する必要はありませんが、ミスが頻発する箇所や覚えにくい公式などは、まとめノートに記すように習慣付けましょう。この時期から自分の得意/苦手の情報を積み重ねておくと、試験前の見直しの際に貴重な材料になります。
夏休み以降は、『良問プラチカ』などレベルを上げた問題集と並行し、過去問を積極的に進めていきましょう。過去問(特に25カ年のもの)は、質・量ともにこれ以上ない貴重な演習教材です。時間配分に慣れておくため、最初から本番の時間通りに演習に取り組むことを強く勧めます。初見で完答する必要はありませんが、1週間ほどの時間を空けて再び解き直しを行った上で、1回目の解法の欠陥をなるべく一般化した形でまとめノートに記入し、今後の解答の精度を高めましょう。
文系数学に割ける時間や苦手分野を踏まえて、早いうちから本番までの学習スケジュールを立てておくと、学習の各段階における目的が明確になります。自分に最適な学習方法を早めにつかみ、余裕を持って対策を行いましょう。(文I・1年)