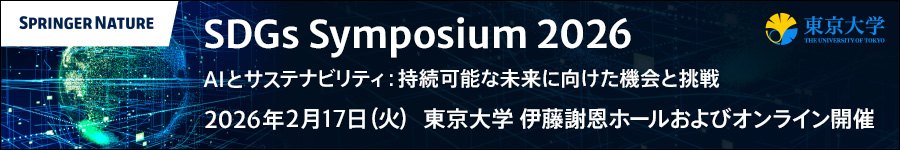「日本一」に向けて東大ラクロス部男子BLUE BULLETSがチーム一致団結で挑んだ2025年シーズンは、惜しくもプレーオフ進出へあと一歩届かぬ展開となった。しかし、部内から2人の日本代表を輩出するなど、その実力は確かなものとなっている。今年、ラクロス男子20歳以下日本代表に選出された川中康太朗選手(文・3年)と武田慶太選手(育・3年)に話を聞いた。(取材・丹羽美貴、写真は全て日本ラクロス協会提供)
日本を背負って世界の舞台へ 初めての連続と向き合う日々
今年1月に開催されたトライアウトで日本代表候補選手が選出されたのち、月に1〜2度の練習会を経て、最終的な日本代表のメンバーが選ばれた。7月の強化合宿の後に、本番の地、韓国・済州島で開催される2025 World Lacrosse Men’s U20 Championshipに臨む。
代表選手の選出過程は熾烈(しれつ)を極めるものだった。1月のトライアウトに合格した選手のうち、選考会で選ばれたさらに半分以下の選手だけしか大会本番の舞台に臨むことはできない。
その選考会最終日。代表選手の名前が呼ばれる瞬間、川中選手の胸中は期待と不安がせめぎ合っていた。「正直、自分が代表選手になれるかどうかの自信は五分五分でした。自分の名前が呼ばれた時は喜びと安心感からか、頭が真っ白になりました」と振り返る。
一方、武田選手は大会直前、出場選手の変更によって大会本番への切符を手にした。入部を後押ししてくれた当時のラクロス部男子の先輩も日本代表に選ばれた経験があった。入部すると日本代表などの大きな舞台に立てる機会もある、という話は当初から耳にしていた。しかし、一度選考会でメンバーに選ばれなかった後にメンバー変更で出場できることになったという連絡が届くと、「自分の人生において、本当にこんなことも起こるんだ」という思いが込み上がった。大会直前でのメンバー変更。直前に選ばれたからこその使命感や責任感は一層胸に湧き上がってきた、と語る。

東大では気心知れた仲間と共に挑む試合。毎日のように言葉を交わす部員同士ならではの息の合ったプレーも可能になる。一方で、日本代表のチームは結成から約半年後には世界を相手に戦わなくてはならない。最初は話したことのない選手もいて、コミュニケーションには少し苦戦した部分もあったという。2泊3日の強化合宿中、同じ部屋で過ごした選手とは親交が深まった。「日頃の練習や合宿期間だけではなく、大会期間中にもポジションごとに、練習や試合の後にミーティングを行い、積極的な意見交換を通して関係を深めていきました」と川中選手。また、約半年間という短い期間の中でチームワークを高められた秘策を、武田選手は「選手それぞれのフレンドリーさ」に見出した。関東ユースなどの大会で個々では面識のある選手もいた中、これまで会ったことのない選手がうまくチームに溶け込みプレーができたことは代表選手同士がフレンドリーにコミュニケーションをとれた成果だと振り返った。
そして臨んだ大会本番。2025 World Lacrosse Men’s U20 Championshipは8月15日〜24日に開催された。10日間で日本代表は6試合に挑んだ。
予選プール戦では、勝利数や得失点差などが決勝トーナメント進出への鍵を握る。点差をつけて勝利することが求められる試合において、日本代表はオランダ戦を18-5、香港戦を18-1と圧勝。プレッシャーのかかる初戦のオランダ戦でチーム初得点を挙げたのは武田選手だった。チームを勢いに乗せた先制点を武田選手自身も「大会期間中の自身の光るプレー」と振り返る。続く香港戦でも武田選手は得点を挙げてチームに貢献した。

大学のチームの一員としてプレーする中で、海外選手と戦う機会はそう多くはない。海外選手にはアメリカの強豪校でプレーをする選手や大学入学以前からラクロスの経験がある選手もいる。川中選手はオランダ戦が自身初の海外選手との対決だったという。言語も違う選手同士で、相手がどのような戦略をとるのかも分からない体験は初めてのことだ。だからこそ、やりたい放題のプレーになってしまう場面もあったそう。ゴーリー(ゴールを守るポジション)の川中選手は相手からかけられたプレッシャーをかわして味方にプレーをつなげたところ、相手選手が不服に思ったのか、思いっきり背中を叩かれてしまった。チーム内にも動揺が走り、こちらが何を言っても知らない、という相手の空気感に圧倒された。しかし、その後相手のボールを狭いところから受けて突破する、という場面では相手のアタックに抵抗することができた。この場面を川中選手は自分も海外相手にきちんと戦える自信になった好プレーだ、と語る。
大会終盤に対峙(たいじ)したジャマイカ戦が印象深いと話す武田選手。オフェンシブミッドフィールダーとして攻守両方をこなす武田選手はディフェンス選手の足の速さを振り返った。日本代表の強みは走り出す時の初速の速さだったが、足が非常に速いジャマイカ選手に追いつけず苦戦したそうだ。しかし、どんなに手強い相手でもチームのプレーコンセプトの“HIGH INTENSITY”(高強度)が心の支えとなった。一つ一つのプレーや得点の重みを大切に、着実なプレーで勝利を積み重ねた。

連日試合が続くこともある期間中、体力面はチーム全体の大きな課題だった。大会期間の8月は韓国でも酷暑に見舞われた。外で活動をするだけでも暑さが体力を奪う。大会前からチーム内でも体力面は課題の一つに取り上げ、期間中は食事の栄養バランスや体のケアなど対策を積極的に行った。決勝トーナメントは4日連続の試合となり、両選手にとって初めてのことだった。対戦する相手も予選を勝ち抜いた相手で手強いチームばかり。
大会期間中、何度も初めての経験に突き当たる日本代表チームの支えとなったのは「自分が日本代表として日の丸を背負っている」という感覚だった。観客席に日本の国旗が掲げられているのをグラウンドから見たときに、自分が背負っているものは日本なんだ、と再認識し奮い立つ感覚があった、と武田選手。川中選手は「試合が始まる前にチームメイトと肩を組んで国歌斉唱をする時、国を背負って戦うことの緊張感と気持ちの高ぶりを今でも鮮明に覚えています」と振り返った。
「自分が戦っているのは、未来のラクロス界の選手のためでもある」と両選手は力を込めた。日本代表は22年の前回大会では5位で大会を終えた。前回大会の順位により、今大会も引き続き全体5位のポジションから大会をスタートできた。今度は自分たちが後輩のために良い順位を勝ち取ってあげたい、という思いがチームを鼓舞した。4年に一度の本大会。「今はまだラクロスを始めていないかもしれない未来の選手のために、良い順位を用意してつなげたかったです」と川中選手は熱い思いを口にした。
準々決勝のオーストラリア戦では711と敗れ、惜しくも準決勝進出はかなわなかったものの、順位決定戦では気持ちを切り替えて全体5位で大会を終えた。日の丸を背負って感じた重責や、慣れない環境でのプレーの負荷は計り知れない。初めての経験が積み重なる本大会において、チームが一つになってつかみ取った5位には「未来のまだ見ぬ後輩」にバトンを託そうとする選手の思いが込められた何にも変え難い価値があるに違いない。
ラクロスに出会えた大学生活は財産 ラクロス部男子が歩む未来
東大ラクロス部男子では、部員のほとんどが大学に入ってからラクロスを始めている。川中選手、武田選手もその1人だ。これまでに経験してきたスポーツがラクロスに生かされるのが面白いところ、と川中選手は話す。例えば、野球をやっていた人はシュートで腕を振る動作に慣れていたり、バスケをやっていた人はステップワークに長けていたり、それぞれの経験を生かすことができるのだ。一方で、努力次第でいろいろなスポーツ経験を持つ人を上回るシュートやプレーができるようになる点にも面白さを感じているという。海外の代表選手は、大学入学前からプレーをしていたり普段はトップリーグの大学に留学してラクロスをしていたりする選手も多い中、日本では大学入学後にラクロスを始めても日本代表まで上り詰めることができるのも魅力だ、と武田選手は話す。また、国内でも他大学の選手とプレーでき、交友関係が広がることもある。
創部以来、関東学生1部リーグでプレーを続けてきたラクロス部男子。東大に入学するまでは勉強に長く向き合ってきた学生が、今度はスポーツで日本一を目指す、というストーリーにはロマンや夢が詰まっているのかもしれない。東大が日本一を獲得することに意味があるし、誰かに勇気を与えられるはず、と武田選手。「毎日朝早く練習して、一緒にご飯を食べて、次の日もまた必ず朝一緒に練習して……というように、同じ生活を過ごし共に日本一を目指す仲間と出会えたことは大学生活において大きな財産になりました」と川中選手は笑顔をこぼす。

来年は両選手にとって引退前のラストイヤー。「地上最速の格闘球技」とも呼ばれるラクロスは、体当たりのプレーやすさまじい速さで投げられるシュートが観客を魅了する。「ラクロスに興味を持ってくれる人が増えて欲しい」「僕たちが魅了されたように、見ている人に気迫を感じてもらうプレーをしたい」と次々に未来のビジョンがあふれ出す。今年は惜しくもプレーオフ進出を逃した東大ラクロス部男子BLUEBULLETS。しかしすでに見据えているのは未来のラクロスの道筋だ。「4年間が意味のあった時間だと思えるような戦い方をしたい」と決意をにじませる両選手のプレー、そして今後のラクロス部男子の活躍に注目だ。