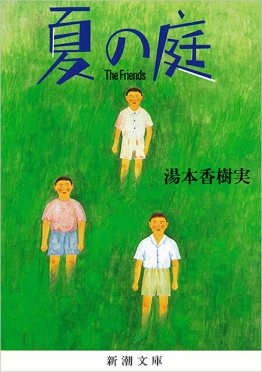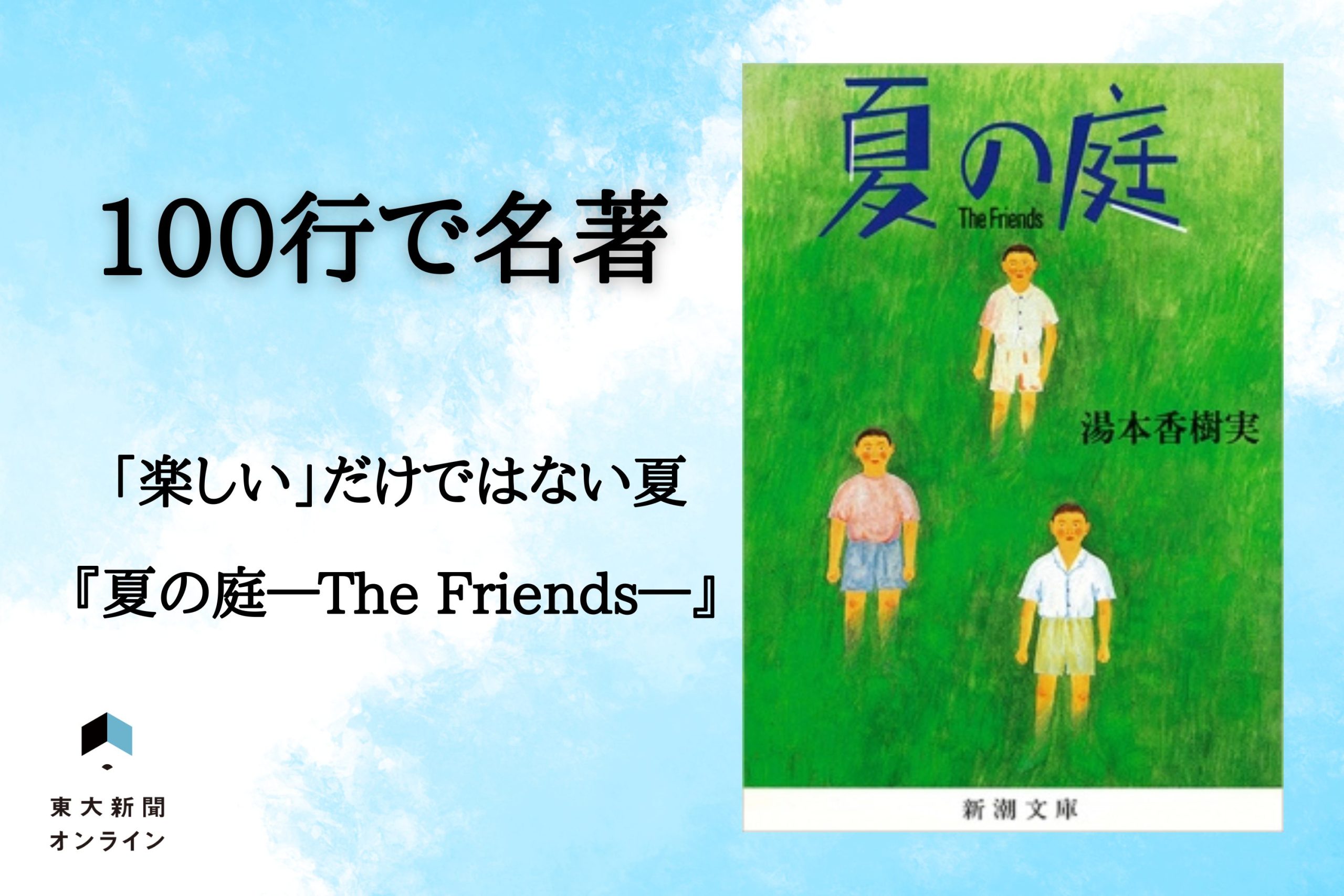
小学生の頃、夏休みを心の底から待ち望む自分がいた。早起きをする必要もないし、夜更かしをしても構わない。友達と毎日プールや虫取りに行き、日が暮れるまで熱中した。お盆には、夏祭りや祖父母の家への帰省、家族旅行など年に一度の楽しい恒例行事。後半に大量の宿題に慌てふためくのもその一つだったのかもしれない。そして最終日には、消えゆく線香花火を眺めて、夏休みの儚(はかな)さを子供ながらに悟った。明日からまた日常が戻ることを思うと、妙に胸が締め付けられるように感じたものだった。夏休みには、学校での勉強、習い事など同じことを繰り返す退屈な日常にはない楽しさを味わえる喜びがあった。
今回紹介する小説『夏の庭ーThe Friendsー』も、小学生の夏休みがテーマだ。しかし、先程のような夏休みとは少し、いやかなり異質なものだ。「人が死ぬのを見たい」という思いつきから、中学受験を控える木山ら小6の3人組は、近所のとあるぼろ屋敷に住む老人の観察を始める。老人には生気が全く感じられず、死は間近だと思われたが、彼らが観察を続けるにつれて妙に元気になっていく。やがて、遠くから見ているだけだった少年たちと老人の間には会話が生まれ、ひと夏の不思議な交流を深めていく。
木山らと老人が過ごすこの夏は、小学生だけでなく多くの人が想像するような「楽しい夏休み」には還元できない、複雑なものである。かといって、この夏は、木山らが中学受験に向けてひたすら勉強し、大変だが充実した夏を過ごしたという説明で表象されるものではない(もちろん多少の勉強はしていたが)。老人のつらい戦争体験。クラスメートとの仲たがい。微妙に複雑な家庭環境。観察対象だった老人にいつの間にか掃除や料理をやらされ、話をすることを通して、彼らは目を背けたくなるような問題に気付く。そして、彼らなりに全力で向き合ってみるのである。
もちろん小学生だから、解決できる範疇(はんちゅう)は限られているし、失敗もする。よかれと思って老人の家族を捜索した際には、逆に老人を怒らせてしまった。それでも、木山らは老人から、あるいは自分たち自身で何かを学び、得るのである。「何か」という曖昧な言葉には、机の前に座った勉強で得られる知識、娯楽を通じて得られる享楽的な幸福感を超越したものが詰まっている。肉体的、精神的な痛みを伴いながらも、今後の人生を確実に豊かにする、新鮮できらびやかな宝物。これらは、ただの「楽しい」夏休みを過ごすだけではなかなか手に入らないものに違いない。
しかし、夏休み後半、偶然遭遇した人との晩酌を楽しむほど元気になった老人は、3人のいない所であっけなく死んでしまう。あれほど仲良くなった3人と老人にはあまりにも似つかわしくない別れに思える。しかし、夏休みもいつかは終わるのだ。老人は残酷なまでに夏の儚さを象徴していた。しかも葬式の後、老人の生きていた痕跡が跡形もなくなり、この夏は完全に木山らの記憶の中だけのものになってしまう。いつかこの夏、そして老人に関する記憶は忘れ去られてしまうのだろうか?
いや、それは杞憂(きゆう)だろう。「オレたち、あの世に知り合いがいるんだ。それってすごい強くないか!」老人と過ごした小6の夏は、勉強や仕事に追われるこれからの人生や娯楽に興じるありきたりな「楽しい」夏休みに埋もれず生き続けるに違いない。さて、私たちは現時点で、人生において本当に特別な思い出を持っていると自信を持って答えられるのか。読後に、こんな質問が投げかけられたようにも感じる。
東大生の夏休みは約2カ月間。学業に追われるの日々からの解放感に存分に浸ることができる。忙しさを忘れ、家にこもって何もしないのが許されるのをありがたく思う人も多いだろう。あるいは、家族や友達との幼少期以来の久々の旅行や夏祭りに興じる人もいるかもしれない。しかし、この本の木山らのように、日常には起こり得ない出会いに思いをはせ、理想を裏切るような行動を起こしてみるのはいかがだろうか。ただ「ゆっくりできた」「楽しかった」の一言では言い表せないような忘れられない思い出が生まれるかもしれない。【加】