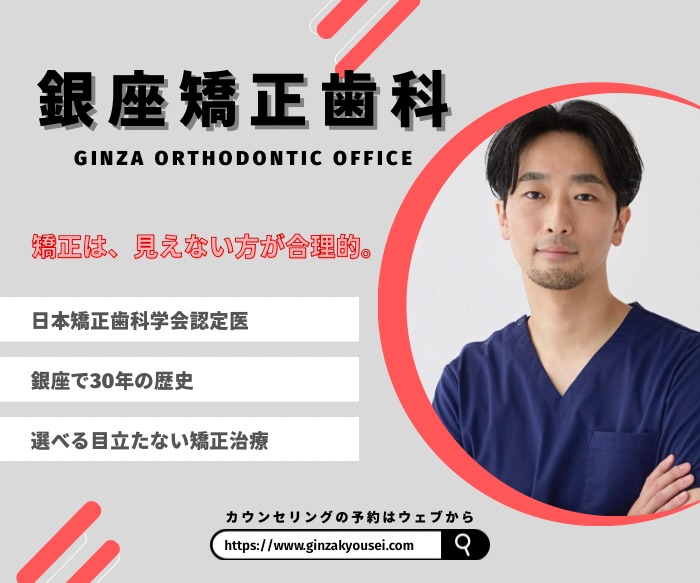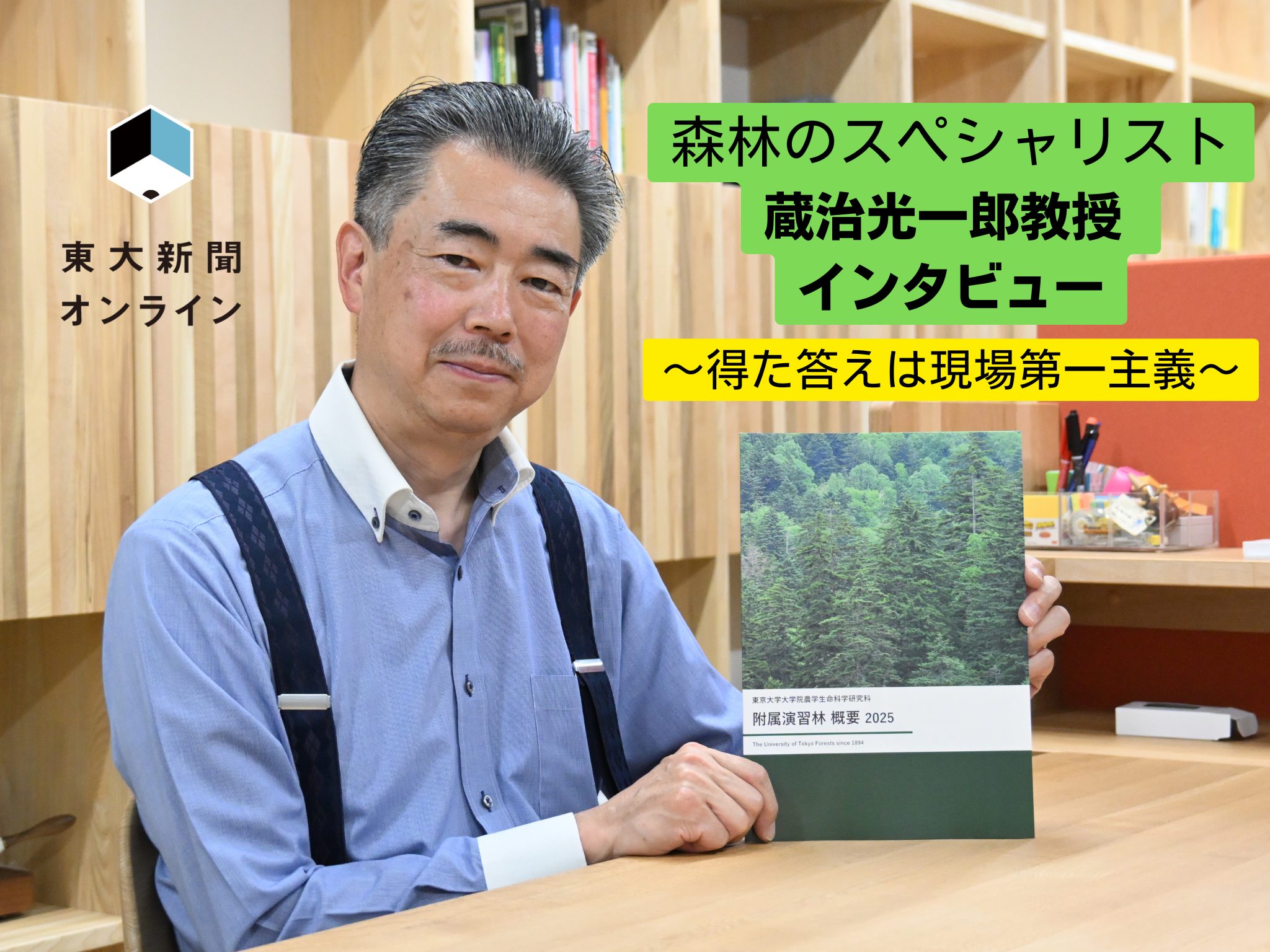
日本の国土面積の約7割を占め、私たちの暮らしに関わりが深い森林。しかし、その本当の機能について、私たちは本当に理解しているのだろうか。森林と水循環の関係を専門にしている蔵治光一郎教授(東大大学院農学生命科学研究科)に、森林と水の関係などについて聞いた。(取材・吉野祥生、撮影・赤津郁海)
森林と水の関係 東大が持つ「演習林」とは
━━現在の研究について教えてください
森林が持つさまざまな価値の中に、洪水を緩和し、私たちの飲み水の水源地を守る役割があります。私は、水が循環する空間的単位である「流域」の中で、森林をどこに位置付け、どうマネジメントしていくべきかを研究しています。
日本の木材自給率は近年高くなってきており、国産材の生産量も増えています。適度に切る分には良いこともたくさんあるのですが、経済原理に任せていると生産性と低コストだけを追求してしまいがちです。生産性が高く低コストの伐採は、健全な水循環を損なう恐れがあるので、木材生産と洪水緩和、水資源の涵養(かんよう)を両立できるような森づくりの在り方を追求しなければいけません。
━━森林と水の関係について教えてください
私たちが利用する水は、もともと雨や雪などの上空から降ってくる水で、それが集まって川の水になって私たちの手元に届きます。しかし、全ての降水が川に流れていく訳ではなく、降ってきた雨や雪に対して川に流れてくる水の量は半分程度しかありません。残り半分は全て蒸発して水蒸気となり、また空気中に戻っています。そこで私たちは、森林に保水力を期待します。つまり、大雨のときには下流への水の流出を抑える一方で、下流で水が不足しているときには、河川に少しずつ水を供給するという、二つの役割を森林に求めているのです。
━━一般的に木を植えると水が増えるという印象があります
それはむしろ逆で、森林というのは水を使って生きている生き物ですから、木のないところに木を植えると水をたくさん使ってしまいます。木を植えることで、森林が人間側に水を残してくれなくなってしまうという一般のイメージとは逆の関係もあるのです。乾燥地では、植林は水を枯らす行為だと認識されているところですね。
━━東大には演習林がありますが、演習林について教えてください
東大の演習林は北海道、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県の6道県にそれぞれ1カ所ずつと東京都に2カ所の計8カ所にあります。東大理学部の管理する小石川植物園の隣に、小石川樹木園という東大農学部が管理する森林があって、これが今年の4月から演習林の管理になり、合計8カ所になりました。総面積が東京23区の面積の約半分にもなる広大な土地を、東大が所有しているということです。
演習林は教育、研究、社会連携の三つの目的で使われます。教育利用では森林系の専修に所属する学部3年生、4年生向けの専門的な実習が行われています。実習は朝に山に出掛けていき、夕方に帰ってきて、演習林の宿泊施設に泊まるという形で、3~4泊で行われることが一般的です。前期教養課程の学生向けの主題科目や総合科目でも演習林が用いられており、こちらは1~3泊程度の実習が中心となっています。一方、研究利用では、学生の卒業研究、大学院での研究のフィールドとなりますし、教員も同様に演習林内に機器を設置してデータを取って研究を行っています。また、北海道演習林と千葉演習林を中心に演習林で生産した木材の販売を実施しています。

演習林はできてから130年ぐらい経っているので、実は100年前の先生が設計した研究もいまだに続けられています。森林の研究の難しいところは、木は植えてから大きくなるまでに50年、100年とかかるので、実際にここの土地にこの木を植えたら、経済的、生態学的にどうなのかという結論を得るのにも同様に50年、100年とかかるということです。個人の人生を超えた長さの研究を行える場所として、演習林は貴重ですし、私たちも先人の研究を引き継いで行っています。
━━農学部以外の学生も演習林を利用する機会があるとのことですが、学生には演習林でどのような学びを期待していますか
農学部の森林を研究する学生というのは1学年20人くらいで、東大の学生全体からすればほんのわずかです。しかし、実は森林はどんな専門分野に進んでも、また社会人になってからも、私たちの生活や社会の仕組みと切っても切り離せないものです。深い専門的なことを学ばなくても入り口の部分だけでもいいので、教室での座学や実際に現場に行って研究を見ることで価値ある学びになると思います。
森林には多様な機能があります。木材の生産や水資源の涵養だけではなく、二酸化炭素を吸収して温暖化を軽減し、生物多様性の源にもなっています。人がレクリエーションで実際に森林に行って癒やされるといった機能もあります。総合大学である東大に入った学生が森林のことを全く学ばずに卒業していくのはとても惜しいことです。私たちはより多くの学生が演習林に足を運んでくれることを期待して、教育にも力を入れています。

「好きなこと」を仕事にする
━━蔵治教授は前期教養課程の頃、どのようなことに関心がありましたか
実は前期教養課程は、自分がどんなことに興味があるかよく分からず試行錯誤していた時間だったように思います。映画研究会に入り、映画をたくさん見た記憶があります。それも自分探しの一部だったのかもしれません。ただ、高校の時に得意な科目や好きな科目はあり、その中でそもそも文理を区別することに違和感を覚えていました。私は理Ⅰで入学しましたが、文理融合型の分野にも関心がありました。進振り(当時、現・進学選択)でどうすれば自身の関心に合った満足のいく選択ができるか考えていました。
━━農学部林学科(当時、現・森林環境資源科学専修)に進学されたきっかけはありますか
ずっと東京に住んでいましたが、幼い頃から森林が好きで、中学生くらいのときはよく東京から列車に乗って山梨や長野といった中央本線沿線の山まで行き、山を歩いていました。八ケ岳山麓のような山の中で水が流れているところで「ぼーっと」するような時間が特に好きでしたね。好きなことが仕事とつながれば、それは幸せかもしれないってことも思っていました。当時の私は時代背景的なこともあったのか、人工物に違和感があったので、林学の分野は実習などで自然の中で学べる点も大きかったです。当時から地球環境問題があって、地球環境が破綻せずに持続するためには、人工物よりも自然物をベースとして持続可能な生産にシフトしていく必要があると考えていました。転換が進まなければいずれは地球全体が破綻するのではないかということは強く当時思っていましたね。文理の両方を学べるということも魅力的でした。
━━いま自身の進学選択を振り返るといかがですか
当時、林学科は比較的人気のない分野だったので、それが良かったのではないかと思います。入ってみて分かったのは、人気がないにもかかわらず、林学には社会的なニーズが常にあって、実は専門家が不足している分野だということでした。当時はそこまで考えていませんでしたが、今考えてみると、人気があるところで競争するよりもずっと得だったのではないかなと思います。そういう意味では林学科への進学は大正解と言えるでしょう。
━━当時、林学科では院進は一般的だったのでしょうか
当時は修士課程に進学する人は半分程度で、ちょうど院進が過半数となる過渡期でした。東大は前期教養課程があるので、専門的に学び始めるのが遅いですし、ちょっとしか学んでいないのに卒業研究をさせられても、という思いはありました。この程度しか知らないにもかかわらず、東大卒という肩書きで社会に出てもばかにされるのではという思いはありましたね。なので、モラトリアム的なこともあったかもしれませんが、修士課程には行こうと思いました。

━━修士課程を修了した後、マレーシアで青年海外協力隊として約2年間活動されています
当時はバブル経済で就職自体はものすごく楽に出来るという雰囲気が社会にありました。しかし、修士1年次の終わりから2年次にかけて、公務員試験を受けたり、就職活動して民間企業の人と話したりしても、全くピンときませんでした。何をライフワークとするのか判断するには早すぎる、みたいな印象がありました。
そこで、社会的な課題に直面している現場に行ってみようと考えました。当時は熱帯雨林の破壊がマスコミでよく報道されていたのですが、報道が本当かどうか自分の目で確かめてみたかったのです。いろいろ調べてみると、青年海外協力隊で森林保護の職種があることが分かりました。マレーシア・ボルネオ島のサバ州でイギリス植民地時代からの歴史がある森林研究所で働けるというものでした。学部や修士課程で熱帯の研究はしていませんでしたが、やはり森林の専門家として生きていく可能性があるのであれば、もっと現場のことを知らなければいけないという気持ちがありました。短期間ではなくて、地元の人たちと対等に話ができるレベルの滞在期間や語学能力を獲得したかったのです。

━━現地ではどのような学びがありましたか
現地で私は中間管理職だったので、大卒の上司と話をすることは多かったですが、中卒や高卒の部下とマレーシア語でコミュニケーションを取る必要もあり、慣れないうちは大変でした。しかし、部下たちは本当によく生活の知恵や、人間が生きていくための技能を身に付けており、幸せで健康に生きていました。彼らは大学を出てはいませんが、学術的な教科書には書いていないような種類の専門的知識を持っていたのです。マレーシアは多民族国家で、民族も宗教も違う人たちがうまく折り合いをつけながら平和に暮らしており、多様性についても勉強になりました。
この現場体験は私の価値観を根本から変えたかもしれません。それ以来「現場第一主義」になり、机上でコンピューターを動かす研究だけでなく、現場のコンテクストを踏まえ、社会を動かすことにつながる研究や活動にも取り組んできました。
日本は森林にどう向き合うべきなのか
━━日本の森林はいまどのような状態にあるのでしょうか
日本の森林の面積はわずかに減っている状況です。太陽光パネルの設置で発電のために土地を使っている影響もありますが、それを含めても減少率はわずかです。
木材生産のための森林の伐採も一部の地域では徐々に増えてきていますが、日本全体では、樹木が自然に成長するスピードに比べるとまだまだ少ない状況です。木を全く切らずに利用しないまま放置されている森林が多いので、どんどん木が巨大化しています。人間が植林したスギ、ヒノキなどで構成される人工林は、間伐をしないで放置すると、財産としての価値も下がり、災害の危険が高い森林になってしまいます。
━━歴史的に見て日本の森林はどのように利用されてきたのでしょうか
天武天皇が飛鳥の都の近くを流れる川の上流の森林伐採を禁止したと『日本書紀』に書かれています。飛鳥時代は都を移転して、そのたびに建築をするわけですから、大量の木材を使っていたことは間違いないです。そこで生きていた人たちも日々の暮らしの燃料やエネルギー源として、木を切って燃やしていました。そのたびに近くの森にある木を伐採するので、森から木がなくなってしまい、山から流れ出た土砂が川を埋めて洪水が起きていたようです。
江戸時代には木材の商品価値が向上して、江戸に幕府が置かれると東日本にも森林の過剰利用が広がりました。当時はかなり焼畑農業もしており、山の斜面を食糧生産の場としても利用していたようです。
このように日本人の森林利用は、古来から続けられ、場所によっては持続不可能なレベルまで行ってしまったのです。そして痛い目にあって、慌てて森林を伐採しすぎないようにルールを作ったということの繰り返しだったと思います。
━━それは知りませんでした
日本列島の土地は、人間の歴史と並行して、人間との相互作用の中で変化してきたはずなのですが、人間に主眼が置かれている高校までの日本史ではあまり学びません。地理と歴史の融合した分野だと思うのですが、縦割りの科目設定によって、抜け落ちている部分なのかなという気はします。
━━森林に対する誤ったイメージを持ちがちだという現状はどのような問題をもたらすのでしょうか
都市に住む人が増えて、森林が距離的にも心理的にも遠い存在になり、他人事になってしまったと思います。小中学校での自然教育も減ってきており、人間が森林の現物に触れる機会が限られてしまっています。その結果、正しい情報が伝わらず、偏ったイメージが流されていることによって、ゆがんだ認識が形成されていると思います。
例えば、「木を切るのは絶対的に悪だ」という意見が盛んに唱えられた時期がありました。しかしそれは、ずっと森林を利用して生きてきた日本人が作り上げてきた文化とは相反する考え方です。私たちの身近にあるものの多くは木からできていますが、材料として木を使う文化があることを、完全に忘れてしまってはいないでしょうか。人間として、ある土地で生きていく時に、樹木から生産できる木材ほど価値のあるものもなかなかありません。その価値を放棄すれば、森は放置されてやぶになり、野生動物が増えて、人間が近づくことさえ出来ないような土地になってしまいます。そのような未来を私たちは本当に望んでいるのでしょうか。
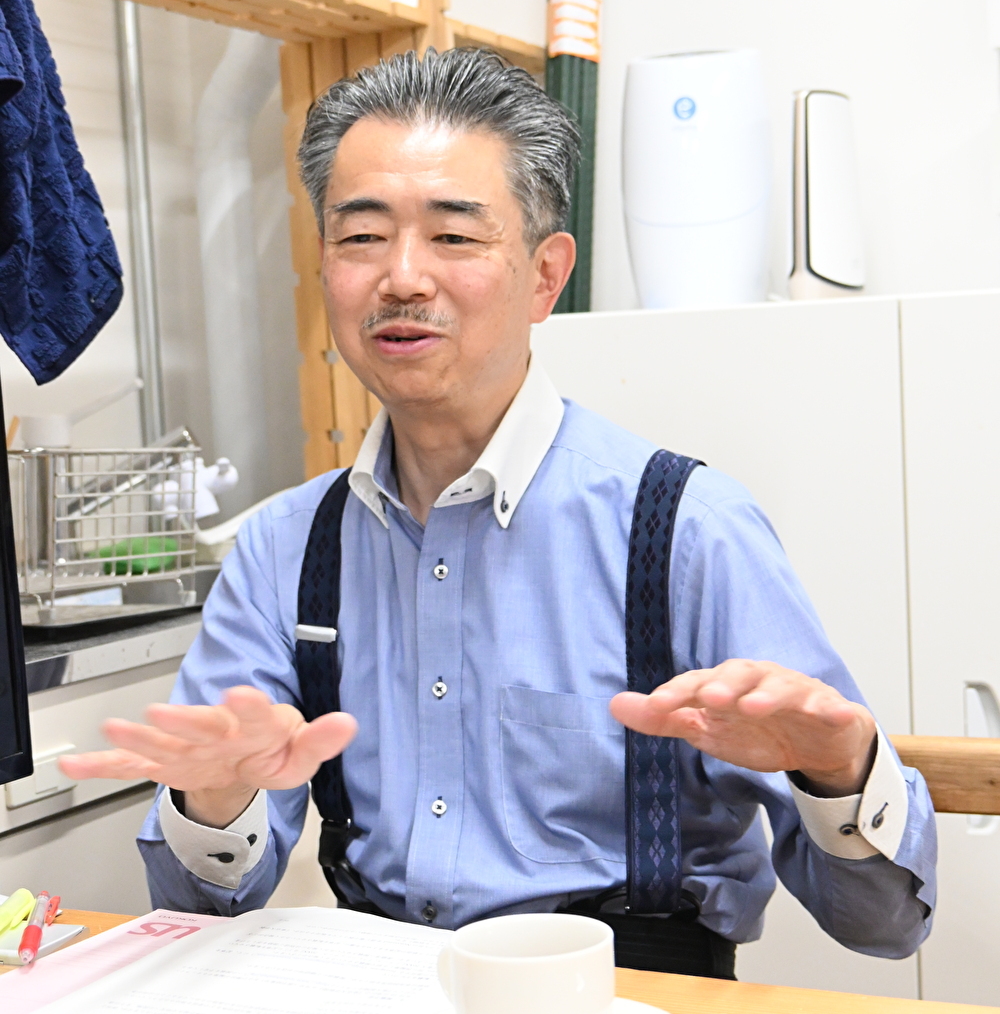
━━森林は激甚化する災害にも防災機能を期待できるのでしょうか
森林には土砂災害を防ぐという機能があります。しかし、最近の災害では、流木が橋に引っ掛かったり、倒れてきた木が電線を切ってしまったりするなど、木が悪さをする災害も起きています。それはやはり人間が森林をあまりにも利用しないで放置しているから起こりやすくなっていると思います。だから、人間がもっと森林に関心を持って利用することが必要で、それが防災上もプラスになるはずです。
地球温暖化によって雨の降り方が変わってくるからこそ、森林の持っている働きを強めることによって、災害の緩和に貢献できると思います。それは、今までの経験を超えた規模で発生しかねない災害を、少しでも和らげる働きという意味です。これまでは数年で計画的に作るダムなどの人工物に頼ってきました。しかし、これからは人工物に加えて森林も必要だというプラスの思考で考えないと、想定を超えた自然現象への対応は厳しいという状況になってきたと思います。
━━森林と水の関係は重要であるにもかかわらず、研究する人が少ないと聞きましたが、どうしてでしょうか
やはりデータを取るのが非常に難しいということが大きいです。例えば、私たちは森林の中を流れている川の流量を測るのですが、普段雨が降ってない時にちょろちょろ流れている水の量と、雨が降った時に増水して勢いよく流れている水の量が実は1000倍ぐらい違うのです。それを技術的に測定するのが難しいのと、洪水や渇水は雨が極端に多いときと少ないときに起こるので数年に一度くらいしか起きません。ですから、長期的かつ大規模な研究にならざるを得ず、現代社会の非常にスピード感を持って動いている世界と相いれないところもどうしてもあります。
━━大学の学問と科学的な知見が、日本の森林のためにできることはどのようなことがありますか
好奇心を原動力とした学術研究も必要だと思いますが、現場では役に立たないことが多いです。現場の事情は非常に複雑で、一つとして同じケースはないですし、それぞれの地域に歴史があって、それぞれ個別の事情を抱える中で課題に対応しようとしているからです。学術研究は、どちらかというと、そういった個別事情を全て切り捨てた理想的な状態を想定して行うので、役に立たないということになりやすいのです。
現場主義的な研究はスタートのところから違うと思いますし、そうした研究の成果は現場の状況を改善するのに役に立つと思います。さらに大きなレベルでは、専門家が集まって政策提言をして、今の制度を見直し、日本の森林をどうするかという議論に結び付けなければいけないと思います。民主主義という枠組みの中で、大学の学識者の責任として情報発信していく必要があると認識しています。
━━世論の形成には国民に分かりやすく情報発信することが必要ではないでしょうか
世論がどこを向いているかによって、国会にしても政府にしても方向性を決めるところもあるので、国民の認識が不確かなイメージに左右されている現状では、政策にしてもどちらに行けばいいのか分からなくなってしまいます。日本国民一人一人が森林について理解した上で、こうしてほしいという意見を持てるような状況を作っていく努力が必要だと思います。
分かりやすい情報発信は意識的にやらないと難しいと思いますが、「面白くて、楽しい」というキーワードも大事だと思います。いまは面白くなければ何も始まりません。いかにいろいろな人を森林に連れていくことができるか、そして森林で面白いことをして、「森林は面白いんだ」という世論を作っていくかという活動がこれから一層必要だと思います。