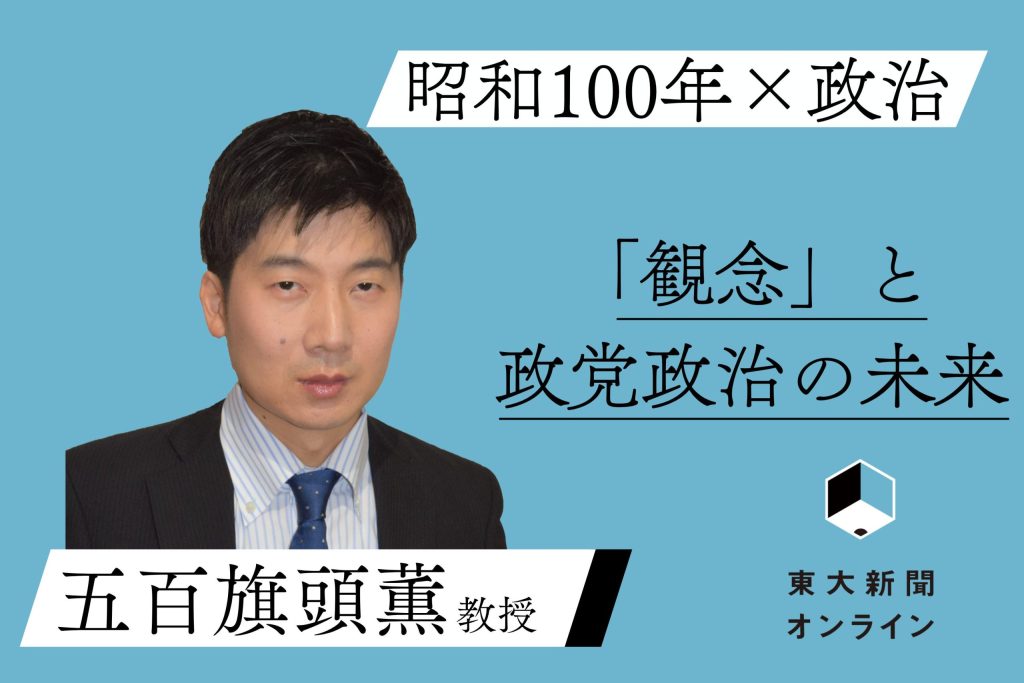
男子普通選挙の法制化から100年。昭和はまさにデモクラシーの時代として始まった。しかし、昭和の、特に戦前期の政治と聞けば軍部台頭の印象は強い。行き詰まる戦後政治の現状を前に、「昭和」から学べることはないだろうか。政党政治を研究してきた五百旗頭(いおきべ)薫教授(東大大学院法学政治学研究科)に話を聞いた。(取材・岡拓杜)
──昭和の政治と聞くと現代から遠い出来事のような印象がありますが、実際はどうでしょうか
昭和初期と今とを比べて、政治の状況は似ていると考えています。昭和初期の政党政治は明治・大正期の民主化の成果が花開いた時期であり、本来は明るい時代なのですが、暗いイメージが付きまといがちです。それは政策の選択肢が狭く、今と同様に政治が苦境に陥っていたからなんですね。バブル崩壊後に失われた30年が始まったように、この時期は第1次世界大戦中の大戦景気が終わって戦後不況の只中にあったので、まず財政面で政策に制約がありました。それから外交面では、中国のナショナリズム高揚やソ連の台頭、ワシントン体制の確立などを背景に窮屈さを感じていました。この戦争中に日本の大陸政策に対する欧州のチェックが弱まり、対華21カ条要求やシベリア出兵のような外交的な拡大期を経験したのとは対照的です。文脈は違いますが、今の日本も米国のトランプ政権、中国やロシアとの難しい関係、北朝鮮の核ミサイル開発などの安全保障上の懸念も大きく、外交的に採れる政策の幅は制約されています。
──当時の政治はその状況にどう取り組んだのですか
制約がある以上、一つの政策で決定的なことはできないので、複数の分野にまたがる様々な政策に、全体としてある角度を付けるんですね。当時の人々にとって魅力的だと思われるような「観念」によって粉飾すると言うべきでしょうか。当時は二大政党制が機能していましたが、一つには憲政会や後身の立憲民政党がよく使った「緊張」という観念があります。浜口雄幸内閣の金解禁などはそうですが、経済や外交、軍事で、痛みに耐えたり、欲望を自粛したりする。それを未来への準備だと思って、今は我慢しようという向きです。その対極にあるのが、立憲政友会系の「生命」で、自己主張を抑制せずに生命力のほとばしるように開放していきましょうという主張です。軍事的拡大や国威発揚、利益政治など中身は雑多です。この両者がせめぎ合う中で第三極として、天皇の臣民として頑張ろうという「国体」も出てきます。
政権交代も起こる環境で、二大政党が観念の角度をつけることで競争して、一方の政党が決定的に大きな誤ちを犯すようなことになりにくい仕組みが生まれました。観念の三国志みたいな感じなんです。
──それは保革対立とも異なるのでしょうか
共産主義と資本主義の対立のようなイデオロギーの衝突と違って、聞こえの良い観念の競争なので、ある政党が実現できなかった観念を、一方の政党が奪うこともできます。つまり誰かの専有物ではないので、三つの観念のうち二つ取れば天下が取れるみたいな感じです。資本主義政党が失敗したからといって、共産主義政党が資本主義のイデオロギーを奪って、自分の方が上手く資本主義経済を回せるとはなりませんよね。その一方で、観念は争奪の競争を生み出します。
──しかし昭和初期の政治は軍部の台頭を許しました
どの政党も天下を取ろうとして二つの観念に手を出したので、そもそも矛盾していたり、採れる政策に制約があるせいで達成できなかったりします。すると大きな痛手となって自分に返ってきて、他党にその観念を取られるというブーメランのような状態が現れていました。ブーメランが何巡かするうちに、立っていられる政党がなくなったのだと思います。浜口雄幸はそれを熟知していて、一度掲げた金解禁(金の輸出許可制を取りやめ、当時列強で主流だった金本位制に復帰すること)を貫き通しました。金の輸出を解禁した場合、金準備の不足を招く貿易赤字を回避しなければなりません。そのため、デフレ政策で国民の消費水準を抑えて輸入を抑制しつつ、不良企業を淘汰して国際競争力を高める必要がありました。これは国民の痛みを伴う点で「緊張」に当てはまる政策でしたが、世界恐慌と時期が重なり昭和恐慌にまで悪化します。これにより政党政治への信頼は地に落ちて、政党も萎縮しました。それ以来、政党は大日本帝国憲法で認められた最低限の権限は行使しても、「観念」を掲げて政権を奪取する気迫を失い、軍部の勢いに押され、迎合さえするようになりました。
──この時期は盛んに「国体」が論じられていました
「国体」という観念を採ったことで、政党内閣が国体に合わないという主張に政党は正面から反論できない場合がありました。それだけでなく、国体論は気に入らない内閣を倒すのに利用されることもあり、政党間で力を削ぎ合うような抗争が続く中で、満州事変や五・一五事件を経て、政党政治の理論的支柱であった美濃部達吉の「天皇機関説」を否定する国体明徴声明に至ります。そうした混乱の印象から、敗戦後、安定した保守政治を求める気分が、戦前からの政治家の中に強くありました。社会党や共産党の台頭も後押しして、今からちょうど70年前に戦前の保守二大政党の系列が一致団結して自民党が生まれます。強力な政党の誕生が、政権交代の定着を阻害し、これは今にも続きます。その上で、政策の選択肢が狭いという昭和初期の課題が再発しているのが現代の難しさです。
──憲法が改正されたことで、戦前と戦後との間には断絶があるという見方もあります
大日本帝国憲法と日本国憲法は、当時の水準では進歩的で、かつ条文が短い点で共通しています。大日本帝国憲法の起草を大きな役割を果たした井上毅は、国内が政治体制をめぐり争うことを危惧していました。そこで、予算審議や法案提出における強い権限を議会に与え、国民が満足できる進歩的な憲法を作ろうと考えました。それから短い憲法にすることで解釈の余地を大きくし、改憲しなくても運用できるようにしました。例えば、大日本帝国憲法に「内閣」という文字は出てきません。行政の中心すら規定しないことで、憲法解釈次第で政党政治も可能になります。井上にとって最悪なのは、憲法改正を求める声が上がって、明治維新のように政治の歴史がまた動き出すことだったのです。井上は「歴史」を終わらせるために短くて進歩的な憲法を作ったといえるかもしれません。
──政党政治を支える憲法解釈は最終的に否定されることになりました
憲政の常道の時代、政党はさまざまな憲法解釈を積み重ねて政党政治を正当化していました。しかし元の憲法から離れすぎると、憲法本来の精神に回帰しようという憲法原理主義的なバネが働きます。大日本帝国憲法が発布された1889年から47年後に二・二六事件が起きて、リベラルな憲法解釈を支持する重臣たちが次々と銃殺されました。「国体明徴」という形でデモクラシーを終わらせることになりました。
──日本国憲法の場合はどうですか
1947年に施行された日本国憲法も、短くて進歩的な憲法ゆえに80年近く改正せずとも運用できていますが、同じような原理主義の動きが見られます。日本国憲法は政権や議会の運営について詳しく規定していないばかりか、矛盾するような規定を含んでいます。まず日本国憲法では議院内閣制を明記していますが、これは英国のように下院の第1党が組閣することで、立法と行政を確実に押さえられるような強い与党を志向する制度です。一方、米国の影響で日本では衆議院と参議院の両院に強い自律性があるため、内閣や多数派の政党が国会の審議をコントロールしにくくなっています。日本はこの矛盾を長い間、自民党の長期政権によって克服しようとしてきました。国会で審議する前に自民党内部で与党議員の意見を調整することで、国会審議の予見可能性を高める動きです。しかし、この一党優位は政権交代を前提とする英国流の議院内閣制の精神に反するので、施行から47年後の1994年に選挙制度の改革で小選挙区比例代表並立制が導入され、政権交代が起きやすい制度の構築が進められました。戦前も戦後も憲法を改正せず柔軟に運用し続けて47年で憲法原理主義的な揺り戻しが生じたのです。
──憲法9条を中心に置く護憲派もいます
大日本帝国憲法の時と異なり、戦後の憲法原理主義は二つに分かれています。一つは安倍政権のような、強い与党が政権を運営する議院内閣制に立脚する立場です。「選挙で勝った与党が思い通りに運営するので、文句があるなら次の選挙で我々に勝って下さい。ただし選挙の時期は私が決めます」という姿勢が典型的でしょう。もう一つが、憲法9条の平和主義の精神に立脚して、安倍政治を危険視する立場です。戦前と戦後ではかなり共通する点もあり、憲法が短いからこそ、時の政権が責任を持って国政を運用する必要があります。運用者に憲法解釈の大きな裁量がある分、もっと慎重に権限を行使しなくてはいけません。そうでないと、半世紀ほどの試みを経て、原理主義が台頭する可能性がある、というのが歴史の教訓ではないでしょうか。
──憲法に関する議論の停滞も含めて、現代政治はますます近視眼的になっている気がします。観念すら生み出せていないのではないでしょうか
観念を作る能力の低下は心配です。もちろん国体のように観念にとらわれて人が間違いを犯すことがあるので、観念は恐ろしいものですが、ただ欲望のままに政策を実行しても、正しい判断はできません。現役・将来世代のために必要な改革をしたり、支出を抑制したりするのは、高齢者が多い中で、大衆の欲望のままに判断していてもできないと思うのですよね。外国人が入ってくるのは生活環境が変わって嫌だけど、世界中と仲良くした方がいいし、外国の人材も活用しないと日本の未来は厳しいと考えて、新しい環境に適応しようといった判断は欲望に従ったままではできないのではないでしょうか。観念を組み合わせて議論し、納得するプロセスが必要です。
──昭和初期が観念を生み出せたのはなぜでしょうか
大きな力を持つ論壇誌がありました。その中には50ページを超えるような今では考えられないくらいの大論文が掲載されていて、それを読める人こそエリートだという意識がありました。
──近年の政治では、裏金や格差、排外主義など、問題が噴出しているように見えます
これからの日本は三つのガードレールに衝突しないように運転していく必要があります。一つは利益政治です。そもそも財源がありませんし、海外の不正と比べたら額は小さいですが裏金問題などの腐敗の温床にもなります。日本は比較的クリーンな政治が実現できている国ですが、精神的な余裕がなくなっている分、一層クリーンな政治を追求していく必要があります。二つ目は新自由主義です。新自由主義はクリーンに見えますが、一部のエリートのエゴに歯止めが効きにくくなります。同時に格差を助長してポピュリズムの台頭を促していると思います。最後に排外主義です。「国体」と比べても、〇〇ファーストは、その良し悪しはさておき、観念の体をなしていないのではないでしょうか。ある美徳をもって日本人は素晴らしいと考え、その美徳を守ろうと呼び掛けられた国体論とも違って、「日本である以上は日本人がファーストなのは当然で、外国人はファーストではないが全否定もしない。他国ではそこの国民がファーストなのでお互いさま。だから、もう良いでしょ」と言ってしまうと議論が終わってしまいます。これは観念を作る能力の衰退を象徴しているようでもあります。
──これからの日本には何が必要でしょうか
こうした腐敗と格差と排外主義をなくすには、他者への想像力が必要です。その基になるのは豊かな言語世界で、その土壌から観念が生まれます。学生時代は言語世界を育むチャンスですが、今は何気なく本を読んで、ゆっくり考える時間が少なくなっている気がします。これは今の政治の問題と関係があるのではないでしょうか。












