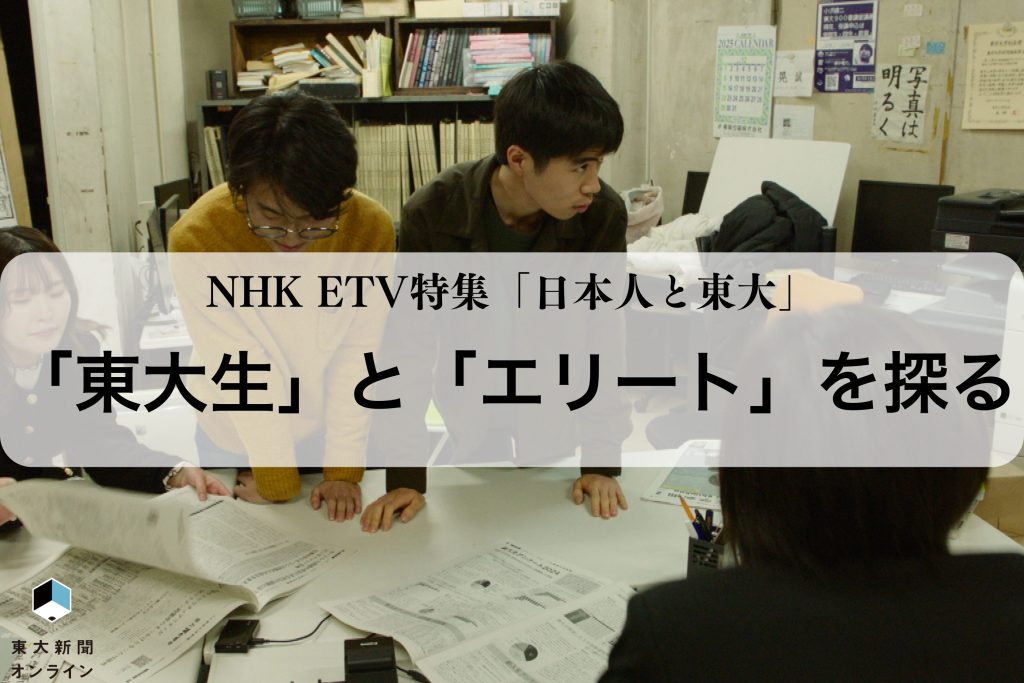
「東京大学」という言葉を耳にしたとき、皆さんはどのようなイメージを抱くだろうか。長い受験戦争を勝ち抜き、希望と高揚感を胸にこの大学の門をくぐった新入生は、未来に対する大きな期待を感じているに違いない。また、卒業生や在学生、そして関係者である私たちも、東大に対しさまざまな実地的イメージを持っていることだろう。しかし、社会で取り沙汰される「東大」というレッテルは、私たちの実際の経験や個別の背景とは必ずしも一致しない。すぐに思いつくものだけでも、90年代の官僚・東大法学部バッシング、松尾研所属の中国人留学生に対するバッシングなど、さまざまな事件を通じて「東大生」「エリート」という属性が、時に過大な期待、時に激しい批判の対象となってきた。そして、そうした「東大生」にまつわる世間と東大生自身との認識のギャップは、「一応、東大です」という言い回しに象徴的なように現代においても顕著に表れている。
本稿では、NHKのETV特集「日本人と東大」の取材や新入生アンケートの結果、そして東大生それぞれの実体験を踏まえ、私たち現代の東大生がいかにして社会に応答し、どのように自己を語るべきなのか少考する。また、東大の中における謙遜や自己卑下の傾向、東大というブランドが内包する重圧、日本独自の謙虚さの文化、さらにはメディアあるいはSNSの隆盛による固定的な東大生像の醸成、それと私たちの実像との乖離(かいり)……。この一連の論点は、東大生であるということが単なる学歴や肩書きに留まらず、個々の人生経験や社会参加のあり方に深く影響していることをも示唆している。東大生であるということは、考え出すと想像よりもずっとずっと難しい。それでも、東大生として、「エリート(?)」として、私たちはどうすれば地に足をつけていくことができるだろうか。この記事では、そうした私たちのありように迫っていこう。【乃】
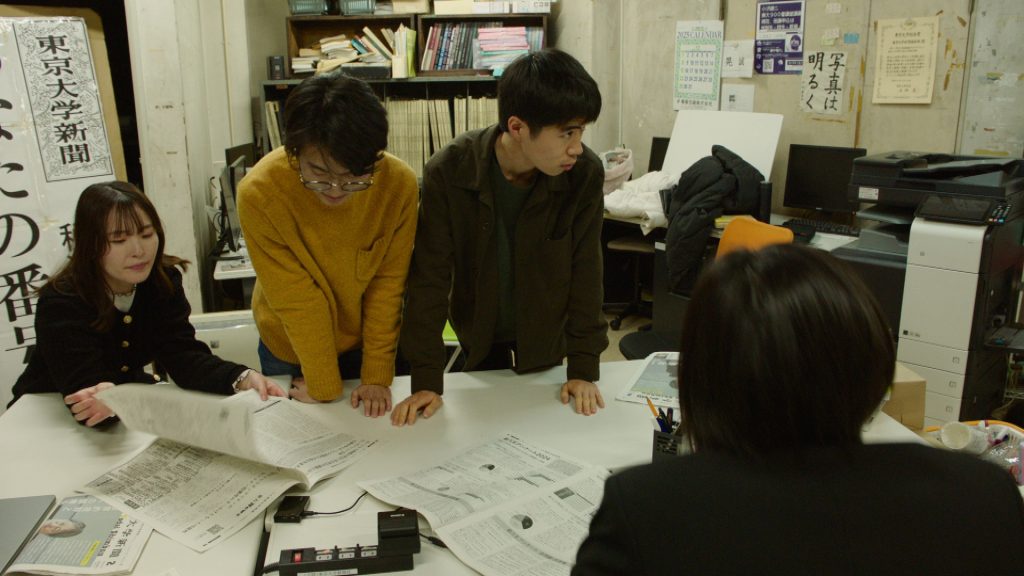
東京大学新聞社による2025年度の新入生アンケートにおいて、「あなたは、自分が将来、社会の未来を担うエリートになるという意識を持っていますか。また、エリート意識を持つことは良いことだと思いますか。」という質問に対し、実に3割以上の東大生が「エリート意識を持っていて、持つことは良いことだと思う」、1割ほどが「エリート意識を持っているが、持つことが良いことだとは思わない」と回答した。前年度の「あなたは、自分が将来、日本の未来を担うエリートになるという意識を持っていますか。」という問いに対しても、3分の2の新入生が「持っている」「少しは持っている」と回答した。これは、東大で曲がりなりにも2年を過ごした記者としては、意外な数字であった。東大生とは、東大の中においてはほとほと「普通」の人間だ。他愛もないことで盛り上がり、他のどのコミュニティとも同じように人間関係で悩んだり、将来に漠然とした不安を持ったりする人が大半だ。むしろ、そうした意味で東大ほど大変な環境もなかなかない。上は青天井だからだ。「自分の才能は東大の中でもごく普通かもしれない」と感じる中で、自分がいかに凡人であるかと何度思わされたことだろうか。
しかし、今回NHKの特集である「シリーズ 日本人と東大 第1回『エリートの条件』」の取材や番組を通して実直に語られた東大生像は、1877年の創設から現在に至るまで、さまざまなバックグラウンドを持った東大生が個別的ながらも切実な問題意識を背景に、社会に対して振る舞おうと、応答しようとする姿だった。映じられたそれは、過半数が肯定的に回答した先のアンケートの結果とも符合する。そのエリート意識は、バリバリ働いて出世して、といった古典的な「エリート」の像の反映ではなく、むしろ個々の苦労や問題、夢や情熱に裏打ちされた自分への期待のようにも映る。
思えば、先ほどごく「普通」だと論じた学生の一人一人にも、それぞれの生き様はあった。例えば地方から身一つも同然で東京にやってきたクラスメートには、東大で学びながらも、いずれは自分の地元をもっと良くしたい、変えたいという夢があった。東大生は、もちろん受験勉強の中で切磋琢磨(せっさたくま)し、比較的高い学力の中に置かれた人間の集まりであるが、それだけではなく、培った思考力の中に、自分の持つ個人的なバックグラウンドや属する社会への問題意識を内面として持っているのだと、アンケートの結果や番組の取材を通して改めて気付かされたものだ。
「東大生」であること、「東大生」と呼ばれること
ここまでで、指摘しておかなければいけない事実として、以下の2点があるだろう。「東大生の過半数は(少なくとも入学時には)社会に対してなんらかのプレゼンスを示せる存在でありたい、社会の未来を担うエリートでありたい」と感じていること。そして、「しかし、東大内での競争や社会における「東大生像」と自分との乖離(かいり)、文化的謙遜などのさまざまな背景により、それを十全に発揮できていない」ということ。これは、東京大学新聞社によるアンケートの結果からも読み取れる。2024年度のアンケートでは、東大生の過半数が何らかエリートであるという意識を持っていることが確認できた一方、25年度のアンケートではそうではなかった。目立ったのは「エリート意識は持っていないが、持つのは良いことだと思う」という選択肢が4割以上選択されたことだ。この回答に映じられているのは、東大生が持つエリート意識と、他の東大生や社会的な東大のイメージの中で板挟みにあう中で、エリートでありたいと願うことについて躊躇(ちゅうちょ)してしまっている姿なのではないだろうか。
先に言及した通り、東大生が直面する問題として、先に述べた「東大内における自分より遥かに優れた存在との邂逅(かいこう)」以外にも、「東大の外から下される評価との乖離」がある。
東大生として存在することは難しい。それは、単純に東大内で自分よりも遥かに優れた人間に出会ったことへの劣等感のほかにも、東大生として私たち自身が存在すること、まず何よりも生身の人間としてあることとは別の形で、世間において「東大生であるということ」についてすでにイメージが形作られてきたという事情がある。東大という名を冠した多数のテレビのバラエティ番組や、東大卒の天才がやたらと取り沙汰されるメディア媒体を目にしたことがある人は多いだろう。東大とは、良くも悪くも日本において最も話題に上がる大学である。「東大生」は、そうした話題や反響の中で、皮肉にも東大生の介在なしにイメージを形作られてきた。1990年代のバブル崩壊後に起きた官僚バッシング、それに伴う東大法学部バッシングも、その流れの一つだ。経済政策の失敗や相次ぐ不祥事の責任を問われた彼らは大きな批判にさらされ、それはやがて官僚を多く輩出する東大法学部にも向かい、「東大法学部の学生は使えない」といった言説にまで発展した。
「東大」という記号が世間において持つ意味は、ときとして極端に肥大化し、歪められ、私たち東大生の手から離れていく。「天才」あるいは「イカ東(「いかにも東大生」の略語、勉強はできるが身だしなみや対人関係について無頓着という、東大生のステレオタイプに対する俗称)」というように、いつの間にか私たちはさまざまなレッテルを貼られ、葛藤し、なんらかの機制によってそれに適応する。社会における東大生のイメージと自分とのギャップにもまれ、あるいはそれを他者に押し付けられて精神を擦り減らすことさえ珍しくない。あるいは、大学名を聞かれたときに「一応、東大です」「東京の大学です」と返答するといった様式などは象徴的だ。そこにおいて私たちは、もはや「東大生であること」を避けようとする。ここには、日本特有の謙遜の文化が通底していることも見逃せない。日常の対人関係において、「自分は東大生です」と明言することをためらう内因として、それが誇示と受け取られるのではないかという懸念が働くことは、一つ事実として考えられるだろう。さらに近年、東大生であること自体が優秀さの裏付けだけではなく、恵まれた環境の帰結という記号としても機能する中で、「東大生である」ことはますます難しくなっている。「周りの環境に恵まれた」と今の東大生はそろって口にし、「東大生」に対する社会的なイメージはますます固定化され、私たちはますます東大生であることを表明できなくなっている。
これで良いのか。東大生は、とても頭が良くて、論理的で、だけどコミュニケーションは苦手で人間として難がある存在なのだろうか。そうではない。東大という場所は、中国人留学生を不当に優遇してそれを正当化する場所でもないし(留学生それぞれだって、背景は違えど厳しい条件のもとで東大の門戸を叩くことを許され、同じ屋根の下で勉学に励む大事な仲間であることに疑いはない)、机上の空論を学ぶばかりで実際的な視野を持てない人間の集まりでもない。私たちにだって、ひどく個人的で、しかし切実な問題意識があるはずだ。世間で揶揄(やゆ)される「東大生」ではない、自分本来の姿を持っているはずだ。自分の持つ個別的な問題意識についてどうにかしたいという気持ちが、エリートとしてあろうとすること、社会の未来を担うエリートでありたいと願うことではないのだろうか。
東大生であることを避けることは、東大生の定義から自分自らを除外し、それを最早ごく一部の東大生あるいは外的な存在に託す行為に他ならない。私たちはそのことに目を背けているのではないだろうか。「周りの環境に恵まれて東大に入ることができたけど、東大にはもっとすごい人がたくさんいて、私はそれに比べたら全然ダメ」と言う人がいる。確かにそうかもしれない。単純な学力や機転、想像力などの能力で比べたって上にはいくらでも上がいる。しかしそれは、私たち東大生がどういった存在か考えること、伝えることを放棄する理由にはならない。その場しのぎの言い訳でしかない。地方から身一つで東京に来た学生は、故郷への恩返しや地域社会の発展を強く願い、東京でエリート教育を受けながらも、どこかで自分を育んでくれた地元において、市民的エリートとして存在感を示せるように、と自分のエリートとしての自覚を有しているのかもしれない。また、研究や学問の現場で日々挑戦を続ける学生は、単に自らの知識を磨くだけでなく、その成果を仲間や社会に還元するための具体的なプロジェクトやコミュニティ活動に積極的に関与しているという話を聞くことも多い。私たちは、ひどく切実な個を抱えたどこにでもいる人間の一人であり、そしてそれが故に「東大生」として「エリート」として生きていこうと願うのだと、私たちはそうした「東大生」なのだと示していく必要があるのではないだろうか。
第三高等中学校(三高)を経て1895年に帝国大学法科政治学科(当時)を卒業した浜口雄幸は、大蔵省を経て政界に進出、立憲民政党の初代総裁となり、1929年に内閣総理大臣となった。軍部が台頭しつつあった当時の日本において、ロンドン海軍軍縮条約などの締結など協調外交の路線を模索した浜口は、当時最新のメディアであったラジオにおいて国民に自身の政策を直接訴えた首相としても名高い。三高・帝国大学時代の盟友である幣原喜重郎は、外務大臣として浜口を支え、戦後には内閣総理大臣として、欧米との交渉の席で責務を全うした。彼の時代の「エリート」は民意を適切に反映させるという理念を掲げながらも、まさに国の上に立つものとして民衆を引っ張っていくような姿だったことは確かだろう。それが、彼の時代には求められていたのである。
かたや、現代はどうだろうか。資本を独占する資産家が政治にも跋扈(ばっこ)し、首長は対話とは言い難い別の要素――偽の情報や安易なポピュリズム、ルサンチマンにつけ込むレイシズムや憎悪感情――に決定を左右される。一度目をつけられた他者はもはや顔のない他者、記号として攻撃される。松尾研究室(工学系研究科)所属の中国人留学生が、真偽の分からない情報をもとにSNSでバッシングを受け、個人情報をネットに晒され、その批判の矛先が松尾研究室にまで向かったことは記憶に新しい。この問題の起因としてあったのは間違いなく外国人に対する(大抵は実態から乖離した)恐怖感情やミソジニーであったが、同時に東大という「エリート性」あるいは「主知主義性」に対する反知性主義の反発であったことも確かであろう。あるいは、いわば「国粋主義的な東大」と形容すべきような、これもまた外部から一方的に形作られた外国人排斥という全体性のうちに「東大」を取り込もうとする人々も見受けられた。さらにいえば、この構図において、東大や東大生それ自体がバッシングの標的にされることだって想像に難くない。他者は顔の見えないSNSのこの時代においては、簡単に記号となる。面と向かって悪口を言ったり殴ったりすることのできない他者に対してさえ、人々は攻撃を活発化させる。民衆の声の適切な反映を目指したはずの民主主義運動・社会運動は、その大きな一助と期待されたインターネットやSNSによって皮肉にも覆い隠され、それに乗じた資産家や権力者の支配する寡頭制にさえなってしまったように映る。そして私たち東大生もまた、浜口がまさにそうであったような「エリート」であるという自覚をもはや持てず、「東大生」であることそれ自体に困難を抱えている。「私たち」と「東大生」にはもはや断絶さえある。この場所では、すでに「対話」は死んだのだろうか。もはや、それは現代において何の意味もなさない過去のものになってしまった?
そうではないだろう。私たちは、社会に根ざす一人の人間として、そして東大生としてここにいる。存在が故に、他者と向き合い、お互いの剥き出しの顔を曝け出している。そこで私たちが発する言葉は力になる。社会は決して、少数の支配する場所でも、多数の一元的な価値観のみが信奉される場所でもない。現状の社会構造によっては救いきれない「他者」を救うための「来るべき民主主義」の行われる場所であるべきだ。そのためにも、私たちはまず何よりも、ここにいる存在として声を上げなければならない。そうやって他者の前に他者として立ち現れなければならない。「東大生」は記号ではない。個人的であり、切実であり、温かい血の通った人間だ。私たちは、東大という記号に縛られることなく、「東大生である」という事実を自分自身のアイデンティティの一部として受け止めると同時に、その枠を超えてそれぞれの自己表現を追求すべきだ。こうした実践が広がれば、社会は「東大生」という一枚岩的なイメージではなく、多様な価値観と個性を持つ「市民的エリート」としての東大生の姿を認識するようになるだろう。往年の浜口がそうしたように、私たちも対話を諦めてはならない。謙虚であることは大切であるが、それが過度に働き、自己を小さくしてしまうならば、真の意味での対話は成立しない。現代社会において、情報過多の中で多くの人々が顔なき批判にさらされる時代だからこそ、私たちは自分の声を大切にし、互いに向き合う姿勢を培う必要がある。
私たちは、自らの体験と苦悩、そして未来への希望を語り、個々の声を積み重ねることで、東大生という集団のイメージを再定義していく権利がある。私たちが、東大生と呼ばれる存在である限り。自分が「東大生」であるという事実を恥じるのではなく、それを出発点として、私たちがいかに社会に向き合い、他者と対話しながら前進していくかを示していく。そうやって、「ここにいる」存在として地面に立とう。
なお、今回弊紙が取材に協力したNHKの特集「シリーズ 日本人と東大 第1回『エリートの条件』」については、下記のリンクからオンデマンド配信が視聴可能だ。お時間のある際にぜひご覧になってはどうだろうか。
ETV特集 シリーズ 日本人と東大 第1回 エリートの条件 “花の28年組”はなぜ敗北したのか

【記事追記】
2025年5月2日14時00分 一部表現を修正しました。











