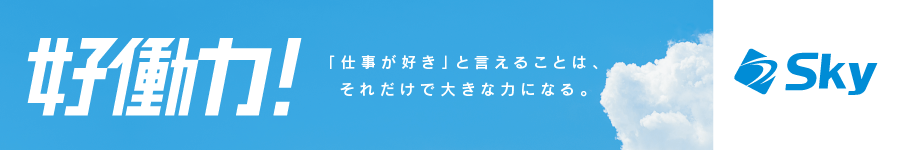今年7月に施行された性犯罪に関する刑法の改正法。従来の「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」は「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」に改められた。改正の意義は何か。改正法は性犯罪をどのように捉えているのか。刑法が専門の和田俊憲教授(東大大学院法学政治学研究科)による論考だ。(寄稿)
行為類型を列挙 処罰対象明確化
「性犯罪は被害者が抵抗しなかった場合には成立しない」「性犯罪は夫婦間では成立しない」といった「神話」がある。これらは、社会の一部で真実であると信じられているとしても、客観的には正しくない。今般の改正前の刑法の下でもすでに、これらの言説は裁判所によって否定されていたと考えられるが、それでも今回、性犯罪規定が改正されたのは、これらが神話にすぎないという認識を社会内でより広く共有する必要があったからであり、また、その神話の先で専門家の間でも残っていた解釈適用のばらつきを極力なくすことが目指されたからである。
刑法は、具体的な被告人に対する刑事手続において適用される裁判規範であるとともに、社会内で一般的に参照されるべき行為規範でもある。それゆえ、規範の内容を裁判所が理解しているだけでは不十分であり、検察官や警察官はもちろん、被害を受けたと感じる人、さらには潜在的な被害者や加害者を含めた国民一般に理解されるべきである。しかし、わが国の刑法は条文が簡潔にすぎ、解釈の余地が大きく、その正確な内容は条文を読んだだけではただちに分からず、関係する判例をも正しく理解する必要があって、それはじつは専門家でも容易でない。
今回の改正で、性犯罪の中核的な規定(刑法176条・177条)は、刑法の中では異例の文字数の多さとなり(改正により3倍以上に増加した)、規範の内容が従来よりも格段に詳細に表現された。改正前は「暴行・脅迫」の使用および「心神喪失・抗拒不能」の利用などの2類型にまとめて定められていた部分が、より具体的な9類型の行為として列挙されることになったのである。たとえば、予想と異なる事態に直面させ、恐怖・驚愕(きょうがく)させて性的行為を行う類型や、虐待したうえで性的行為を行う類型は、近年の心理学の知見に基づき、被害者が性犯罪の場面で短期的にフリーズしたり、長期的な虐待により通常の反応ができなくなることを明示したものである。改正前の規定でも「抗拒不能」の解釈により処罰が可能であったが、これらの類型が処罰対象であることは格段に明確になったといえよう。
人格的統合性を重視 最新の見方反映
今回の改正で、性犯罪の本質は「被害者がその時点で同意できないような客観的状況」で性的行為を行うところに求められた。従来の「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」に代わって新たに名付けられた「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」という犯罪名からは、「現に被害者の同意が存在しない状況」で性的行為を行う犯罪だと思われるかもしれないが、必ずしもそうではないのである。
この2つには重要な違いがある。もし「現に被害者の同意が存在しない状況」が本質だとすると、被害者の頭の中に同意が存在すると軽率にも勘違いして性的行為に及んだ行為者には、性犯罪の故意がないことになり、処罰がなされないことになってしまう。これに対して、「被害者がその時点で同意できないような客観的状況」が重要だとすると、そのような客観的状況であることの認識があれば性犯罪の故意が肯定できることになる。そして、同意があると勘違いしたという言い訳が通用するのは、上記のような客観的状況であるにもかかわらず被害者が例外的に同意することもありうると合理的にいえるような特別の事情を、行為者が誤って信じた場合に限られる。
それはたとえば、睡眠中の配偶者の陰部を触ったが、その配偶者間ではそのようにすることが習慣になっていたような場合である。たまたまその日は被害者は同意していなかったというのであっても、性的行為に及んだ行為者が相手方はいつもどおり同意していると誤って信じていたら、犯罪は不成立となりうる。
この前提として、夫婦間でも性犯罪が成立することを確認しよう。今回の改正で、性犯罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」成立するものと規定された。歴史的には、夫の妻に対する強姦罪は成立しないという理解が、洋の東西を問わず一般的であった。わが国もその例に漏れず、同様の理解がおそらく昭和後期までは通説であった。夫のいわば財産である妻の貞操を第三者が害するのが性犯罪であり、夫が妻と行う性的行為は、自分の財産をどのように使っても処罰されないのと同様、犯罪性が認められないと考えられていたのである。その後、性犯罪は、その身体を有する本人の性的自由を侵害する犯罪であると解されるようになり、夫婦間でも、妻の(あるいは夫の)意思に反する性的行為には性犯罪が成立するという理解が通説化した。今回の改正では、その通説が明文化されたことになる。
妻が夫の財産でないのはもちろんであるが、性犯罪はたんに性的自由を侵害する犯罪かといえば、それを超えて、行為者の支配欲に基づいて実行される点に着目すべきだという指摘や、被害者の性的尊厳や人格的統合性を害するところに本質があるという理解が近年は増えてきている。つまり、行為者が被害者を対等な人格的存在として尊重せず、被害者の性的利益を自らの財産であるかのように自由に処分できると考えて身体的侵襲に及び、その結果、被害者が心身の人格的統合性を揺るがされ、その影響が長期にわたって残るところを捉えるべきだというのである。
前述のとおり、今回の改正では、同意が存在せず被害者の意思に反するところを直接捉えて犯罪化するのではなく、被害者がその時点で同意できないような客観的状況で性的行為を行うところが性犯罪の本体であるとされている。それはすなわち、被害者が行為者と対等なコミュニケーションを図ることが困難な状況で、上位にある行為者が下位の被害者から性的利益を奪うのが性犯罪であるという位置づけであり、近年の新たな見方を反映させたものと評価することができる。
高い完成度も更なる改正の可能性
ところで、世界の性犯罪規定を見回したとき、とくに先進的であるとされるカナダ刑法では、重い処罰よりも広い処罰が優先され、同意のない性的接触が広く性的暴行罪として処罰対象にされている。しかも、同意は性的行為の時点で現実に存在しなければならないものとされていることから、睡眠中で意識のない人の陰部に触れるような行為は、事前に同意があっても、性的暴行罪を構成する。夫婦間でも同じである。これを正面から適用すると処罰範囲が著しく広くなるように思われるが、それが回避されているのは、犯罪が成立していないからではなく、被害者が被害を申告しないからであり、つまり、実際の処罰範囲の適正化は被害申告の有無に大きく依存しているようにみえる。
これと比較すると、わが国の改正後の性犯罪規定においては、睡眠中のわいせつ行為や性交等は原則として不同意わいせつ罪・不同意性交等罪を構成するものとしつつ、被害者の事前の同意を認める余地を残しているから、犯罪の成否のレベルで処罰範囲の適正化が図られる。その点で、カナダ刑法のような「先進的」な刑法が抱える難を逃れており、その他の点も含め、比較法的にみて、完成度の高いものになっているように思われる。
もっとも、性犯罪規定は5年後の見直しがすでに予定されており、さらに改正される可能性がある。たとえば、脅迫的要素がなく被害者の錯誤のみに基づいて性的行為を行う類型で今回処罰が明示的に規定されたのは、被害者が、実際にはわいせつ行為であるのに医療行為や宗教行為等であると誤信した場合と、性的行為の相手方について人違いをした場合だけである。これに対して諸外国では、実際には避妊していないのに避妊していると勘違いさせて性交を行う類型でも男性側を処罰する例が増えており、わが国でもこれを追加すべきかどうか検討する必要があるかもしれない。
公訴時効についても再改正の必要性が指摘されている。わが国では、時効の期間は犯罪の刑の重さに対応して定められており、その原則どおりであれば、不同意わいせつ罪は7年、不同意性交等罪は10年で時効となる。しかし、被害の認識や申告が困難であるという性犯罪の特性に鑑みて、今回の改正では特例が設けられ、それぞれ12年と15年を時効期間とするものとされた(さらに、被害者が18歳未満の場合は、18歳になるまでは時効が進行しないのと同じ扱いがなされることになった)。しかし、現実には被害から15年以上経過してからようやく申告が可能になるケースもあり、それに対応できるようにする必要があるというのである。
時効完成後の被害申告で問題なのは、検察官・裁判所による起訴・有罪認定・処罰ができないだけでなく、警察レベルでも被害者への対応や捜査がなされない点である。被害者が公的に被害者として受け止めてもらえないところに、1人の人格的存在として正当に扱われないという性犯罪の本質に係る2次被害が生じうるのであり、それを避けることがぜひとも必要である。とはいえ、個々の事件の事情を捨象して期間経過後は一律に起訴ができないようにする時効制度にも、それ自体として歴史的に認められてきた一定の合理性がある。そうだとすると、時効期間の延長とは別の方法として、時効期間経過後も被害申告を正式に受け止めて何らかの形で被害者に公的に寄り添う仕組みを設けることが目指されるべきではないかと思われる。