現在の日本では火葬が一般的だが、近年は宇宙葬や冷凍葬など新たな葬送の形も登場している。同じ日本でも時代によって葬送形態はさまざまで、縄文・弥生時代の葬送法の一つである再葬は、同時期の日本考古学を専門とする設樂博己教授(東大人文社会系研究科)の研究の一つだ。
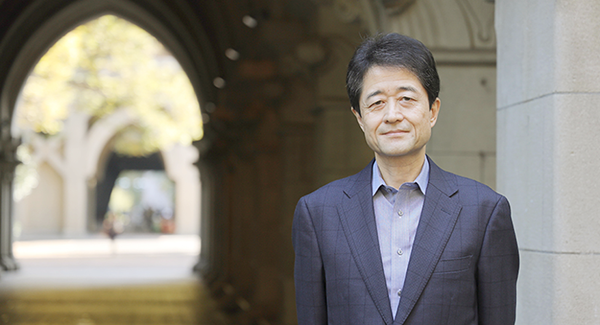
再葬とは土葬などによって骨にした遺体を土器に納め、再び埋葬する葬法をいう。縄文から弥生時代への過渡期に、東日本を中心に急増した。今でも沖縄の一部では再葬とよく似た洗骨葬という葬法が残っており「再葬を研究する上で大きな手掛かりとなった」と設樂教授は語る。洗骨葬は手厚く先祖を敬う習俗と理解されているため、再葬も同様に祖先祭祀を意味する習俗だと考えられる。再葬が急増した時期は世界的な寒冷期だったことからも、社会秩序の安定のため祖先祭祀である再葬が大流行したのではないかというのが設樂教授の考えだ。
考古学は人類誕生から現在までの数百万年間の、人類が存在した全ての場所が研究対象だ。文字のない時代も研究するため、遺物の年代特定が研究の基本だ。しかし設樂教授は遺物の背後にある文化や社会にも関心を持ち、再葬遺物の研究などに取り組んできた。
設樂教授が考える考古学の魅力は主に二つ。一つ目は、発掘調査という考古学独自の研究手法だ。発掘調査で遺物を見つけること自体非常に面白く、時代の変遷に伴う遺物の型式変化などを通じて歴史過程を解明する作業もやりがいがある。文字資料から歴史を解明する文献史学とは異なり、遺物から推測したことを基に歴史を再構築できる。二つ目の魅力は、多様な角度から研究できること。考古学は日本では歴史学に含まれることが多いが、米国では文化人類学の一部と理解されており、場所によって学問としての成り立ちや性質が違う。学問的位置付けの違いが、さまざまな研究の切り口を生む。
◇
「研究者人生を歩むことを決定づけたのは大学時代」と振り返る設樂教授。大学時代は研究室に友人たちと入り浸り、家ではなく研究室から講義や演習に出掛ける日々を送った。最初の発掘調査は静岡県袋井市での古墳時代の墓の調査で、日当は3000円。「報酬は安かったが、とても楽しかった」。大学の長期休みには群馬県に帰省し、縄文時代の土製耳飾りの発掘調査に参加した。「考古学漬けの大学生活が、自然と研究者人生に自分を導いた」と設樂教授は振り返る。
東大の考古学研究室は本郷キャンパス内の研究室と総合研究博物館に加え、北海道の常呂にも実習施設を持つ。研究室に所属する学部生は夏休み中の約1週間、ここで発掘調査実習に取り組む。学部生同士の絆が深まる機会でもあり、研究室最大の特徴だ。
考古学研究室に所属する教員の専門分野は、旧石器時代の日本や先史時代の東北アジアなどさまざま。研究室開設以来、東アジアと日本の先史時代の研究が継承されていることが特色の一つだ。学部生は1学年5人ほどで、院生と合わせ20数人の学生が研究室に所属している。
近年は熊本城再建に考古学者が関わるなど、考古学は「社会への貢献度が高く、現代の世界から隔絶した学問ではない」と力説する設樂教授。考古学研究を志す学生に向けては「考古学は人類が過ごした全時代と場所が研究対象になるので、将来は宇宙空間さえ考古学で扱えるかもしれません。考古学の膨大な研究領域の中から、きっと自分に合う研究テーマが見つかりますよ」と語った。(森永志歩)
※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。










