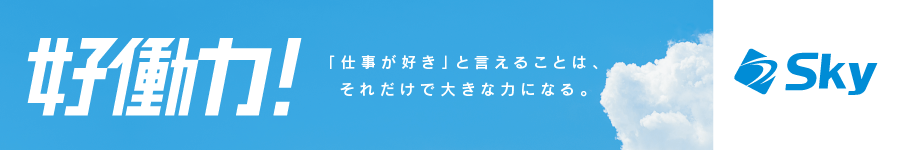「子(し)の曰(のたま)わく、学びて時にこれを習う、亦(ま)た説(よろこ)ばしからずや。朋(とも)あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや」
あまりにも有名なこの一節で始まる『論語』は、直接読んだことはなくとも、どこかで耳にしたことのある警句にあふれている。
「子の曰わく、故(ふる)きを温(あたた)めて新しきを知る、以て師と為(な)るべし」
「子の曰(のたま)わく、過ぎたるは猶(な)お及ばざるがごとし」
『論語』は、「仁(慈しみの心)」や「礼」「孝(親に対する尊敬の心)」といった「徳」の重要性、為政者や人としての「道」のあり方、そして修養の意義を説いているが、このような内容については少なからず知っている読者も多いのではないだろうか。また、内容について一つ一つ解説し、その道徳性を賛美していくのも本記事の役割ではないだろう。
だからといって、『論語』のマナーをビジネスシーンに役立てよう、だとか、翻って『論語』の前時代性を批判しよう、だとかを今さらうんぬんするのも陳腐極まりない。そこで、筆者の『論語』との出会いから述べていきたい。
筆者と『論語』との出会いは、高校1年生の時、『論語』が国語の授業で扱われたことに始まる。その短いながらも何か奥底に眠る感情をくすぐるような警句の数々に心を惹(ひ)かれ、書店で原典を購入してみることにした。『論語』の内容については、かねてよりなんとなく内容を知っていた(そして、その古臭い価値観に忌避感を感じていたことも事実だ)。読後、特に内容に心酔したといったことはなかった。しかし予想通りの嫌悪感に加えて、自らの価値観を再確認できた安心感や共感のような感情を抱いたのを不思議に思ったことはよく覚えている。
子は親を敬え、部下は上司に忠の心をもって仕えよ、礼儀はきちんとしろ、贅沢はするな、学問を修めよ…この警句の数々に、時代錯誤である、と冷笑の視線を送る現代人は決して少なくないだろう。「儒教的価値観」はネガティブ・ワードとして使われることも多い。我々は「儒教的価値観」を「自由な思考」をもって批判し、嘲笑(あざわら)うことができる。
しかし、それは本当だろうか。(流し読みでもよいので)一回本書を手に取ってほしい。そこには、必ずや共感や同調の念で受け入れることのできる一節が少なからずあるはずだ。今までそれとは意識せずとも心のうちにあった信条や信念、価値観などが、鮮やかに言語化されているのを発見する、いわば「価値観のふるさと」を見つける人もいるかもしれない。
我々の多くは日本で生まれ、日本社会の中で育ち、日本人と関わっている。そして、儒教と日本文化の関係は伝統的である。何も『論語』や日本文化の素晴らしさを見よ、というのではない。たとえ『論語』の価値観に、一種のうさんくささのようなものを感じている人間であっても、日本という共同体と何らかの関わりを保ってきた(いる)以上、「論語的思考」とは無縁ではないのである。我々の思考は全くもって自由ではない。たとえ我々が「自由」に何かを批判しようとも、当の思考は、教育され、植え付けられた文化や価値観にがんじがらめになっているものである。
古典に親しみ、自国文化を深く知るということは、けだしこのようなことなのだろう。つまり、我々の意識や思考はそれを好むとも好まずとも自国の文化に大いに束縛されており、いわば偏見と固定観念に満ちていると自覚する、ということ。自由な思考とは、そこから始まるのではないか。【三】