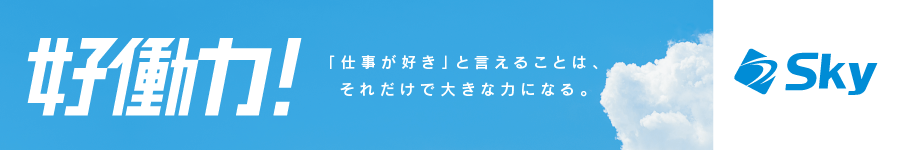生涯をジャーナリストとして尽力されたひとりの人物を紹介し、その足跡をたどることで、「ジャーナリストの仕事」について考えてみたいと思います。
工藤宜(くどう・よろし)氏は、1929年、山形県に生まれました。
東京大学教養学部フランス科を卒業後、朝日新聞社へ入社します。
学生時代からジャーナリスト志望だったというわけではなく、幼少のころは得意な絵をいかして画家になることを目指していたそうです。新聞社へ入社後も、絵画鑑賞やオペラ鑑賞など、芸術に関する興味関心は生涯にわたって続いていました。
工藤氏は、「週刊朝日」編集部に配属後、1971年に「週刊朝日」編集長に就任します。
その年、最高裁判所による宮本判事補再任拒否の判決を受けて、「週刊朝日」は同年4月23日号に「最高裁判官会議の全容 8対4でクビになった宮本判事補」という記事(右画像)を掲載しました。
ところが、この記事に対し、最高裁判所総長は「すべて推測に基づくねつ造」として、朝日新聞社に記事取り消しと謝罪を求めたそうです。

朝日新聞社による事実確認の結果、同社は4月28日付朝刊一面に「最高裁に遺憾の意を表明」という見出しとともに、「朝日新聞社は、週刊朝日については、事実に相違し、表現上も穏当を欠くものがあり、また本誌夕刊については誤りがあるので、遺憾の意を表明した」と掲載されました。
この事件を受けて、当時副編集長であった工藤氏が編集長に昇格することになりますが、大きな事件の後であるだけに、仲間うちからは編集長就任を心配する声もあったそうです。
少し話はそれますが、工藤氏は晩年、自身が執筆・運営するブログ「two dogs君のブログ」で当時のことを振り返っています。
そこでの記載によると、「この最高裁の記事は、当時の法曹界はもちろん、ジャーナリズム全体を騒然とさせた、いわゆる特ダネ中の特ダネというべきもの」(2010年6月10日付ブログ)だったそうです。
最高裁は宮本判事補の再任拒否の理由を「人事上の機密」として公表していませんが、よほどの理由がない限り再任されるのがそれまでの習わしである裁判官再任制度において、宮本判事補が再任拒否されたことは、世間の注目を集める結果となりました。
宮本判事補が特定の団体に所属していたことに起因するのではというマスコミの見解から、「週刊朝日」は最高裁判官会議の内容に迫ることで、再任拒否の理由を明らかにしようと試みました。
このあたりの心境について、工藤氏はブログで「最高裁に一週刊誌が挑戦すること自体が身の程をわきまえていないことだったが、あくまで事実を探求する姿勢は、ことにいわば権力側に問題があると考えられた場合には、ジャーナリストの血が騒ぐのだ」(2010年6月12日付ブログ)と記しています。
そんな状況での編集長就任であるため、工藤氏の仕事は、編集部内の立て直しから始まったといいます。
この一連の事件を受けてか「週刊朝日」の販売部数が減少したため、工藤氏は雑誌の大幅改造にあたります。グラビアの全面改造に向け、ファッションに森英恵氏を起用したり、従来の芸術好きを活かしてフランス児童文学を掲載します。
それまで主流であった女性の絵や写真を起用した表紙も中止し、事件性のある斬新なものに変えていきました。
それでも順調にはいかず、編集部員のなかには工藤氏に対してあからさまに反抗的な態度をとる人もいたそうです。
そんな工藤氏に、さらなる問題が起こりました。いわゆる中国問題です。
このころ、朝日新聞社は社の方針として、中国に関する記事の掲載を控えるようにしていました。社長みずから会議に顔を出し、出版局長、朝日ジャーナル編集長、そして週刊朝日編集長である工藤氏の前で、「中国の記事は書かない」旨を述べたといいます。
当時の中国は、報道に対して厳しく、たとえ正しいことでも国内的に問題があると中国政府がみなすと、その記者は追放されていました。中国から社の記者が一人もいなくなったという会社もあったそうです。
そこで、朝日新聞社がとった対応は、「今は書かず、時機を待って後で書けばいい。そのためにいまのうちに取材をしておく」というものでした。
その姿勢に対し、異論を唱えるものは誰もおらず、工藤氏もまたその指示に従ってしまいます。
それでも、内心腑に落ちないところもあったようです。
社の方針は、記者からペンを奪うものでありました。どうしてあのとき反論しなかったのだろうかと、工藤氏はそれから40年経ったあとも後悔の念を持ち続けています。
「記者というものは、思ったこと(それが何であるかは記者の資質による)を自分なりの書き方で記事にしたい人間だと思う。その欲望は容易なことで止められるものではない」(2011年11月6日付ブログ)。
煮え切らない思いを抱えながら、日常の仕事をこなすことになります。というのも、工藤氏のなかでは、ジャーナリズムは国家および国民を守る重大な役割を持っていると考えていたからです。
正しい報道がおこなわれなかったために、国民が大害を被るという事態が過去にもあったと述べています。
そんななか、ひとりの記者が工藤氏のもとに、ある記事を持ってきます。
その記者は朝日新聞社在籍中に江戸川乱歩賞をうけた推理作家でもあり、中国事情にも詳しい人物でした。
その記者が持ってきたのは、中国・林彪の動静についての記事でした。
これを「週刊朝日」に掲載してほしいといいます。当記者は中国の地方放送局、小規模な新聞社までを丹念に調べ、林彪が一切姿を現していないことから、林彪の身に異変が起きたことを推測していました。
というのも、その頃すでに、中国・毛沢東の後継者とされた林彪が、表舞台から一切姿を消していることについて、マスコミは不審に感じはじめていました。
工藤氏は、この記事を読んで、報道すべきと判断します。
当時の中国に関する記事は、中国政府に賛成するものばかりになっていました。なにより、この記事を掲載できることについて、工藤氏自身うれしく思ったといいます。
 そして、記者を匿名扱いにし、上層部の許可を得ることなく、林彪事件についての記事を「”林彪のナゾ”を追う/ここ三カ月の中国首脳25人の動静全調査」というタイトルで、1971年12月10日号(右画像)に掲載します。
そして、記者を匿名扱いにし、上層部の許可を得ることなく、林彪事件についての記事を「”林彪のナゾ”を追う/ここ三カ月の中国首脳25人の動静全調査」というタイトルで、1971年12月10日号(右画像)に掲載します。
はたして、この記事が世に出たその日、外国通信社によって林彪事件が明らかにされました。結果的に、この記事は一大スクープとなります。
これにより、工藤氏は「週刊朝日」編集長を解任されました。任期は一年あまりだったそうです。
工藤氏はそのまま、ニューヨーク駐在員としてアメリカに渡ることになりました。
元来の芸術好きが功を奏して、ニューヨーク滞在は刺激のある充実したものになります。
しかし、朝日新聞社では、ニューヨーク駐在員という職名は、あとにも先にも工藤氏だけだったそうです。
「ぼくはやっとこのごろになって、あれが左遷というものか、と考えている」(2010年8月22日ブログ)。
ニューヨークで2年あまりを過ごし、日本に戻った工藤氏は、空きが出るという噂を聞きつけて、みずから新潟・佐渡の駐在員を志願します。佐渡駐在とは、住居兼事務所の建物で、ひとりで仕事をすることになります。通常は、入社して間もない若手社員が経験を積むところでしょう。
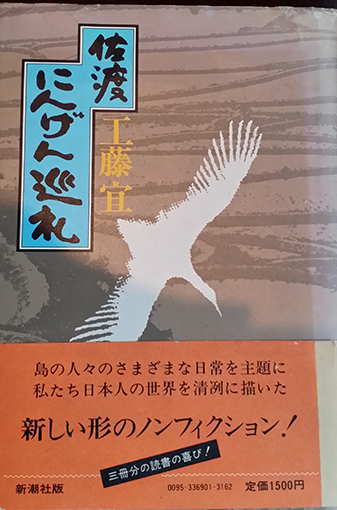 そこへなぜ工藤氏が志願したのか、詳細は不明ですが、佐渡駐在中に佐渡の文化や生活を取材したルポルタージュを新潟の新聞に掲載します。
そこへなぜ工藤氏が志願したのか、詳細は不明ですが、佐渡駐在中に佐渡の文化や生活を取材したルポルタージュを新潟の新聞に掲載します。
1980年、その記事は新潮社より『佐渡にんげん巡礼』(工藤宜著・右画像)として出版されました。
40万字にもわたって、佐渡の人びとの悲喜を記した本書は、のちに大宅壮一賞の最終候補に選ばれ、著名作家たちから高い評価を得ています。
この書籍には、工藤氏の人びとに対する愛情と、その実態を報道しようとする意気込みが余すところなくちりばめられ、ジャーナリストとしての本来の姿を実現しているものと感じます。
組織ぐるみの思惑に巻き込まれ、ジャーナリストとしての使命を抑圧された経験を持つ工藤氏にとっては、佐渡での取材と報道に明け暮れる生活は至福の時だったのかもしれません。
 工藤氏は2013年4月、83歳で他界されました。
工藤氏は2013年4月、83歳で他界されました。
今年、本書『佐渡にんげん巡礼』は、工藤氏の長男らの意向により、電子書籍化(右画像)され、あらためて出版されることになりました。
ひとりのジャーナリストが、生涯をかけて果たした使命。
それは肉体亡きあとも形を変えて、この世に現存し続けることになります。
時代を超えて生き続けるものを描く。
それこそがジャーナリストの本望なのかもしれません。
(取材・文 古関夢香)
※この記事は、東京大学大学院情報学環教育部の授業の一環で執筆されました。