親子心中を民俗学的に解明し、日本のみならず韓国や中国の民俗学界にも長年影響を与え続けてきた岩本通弥(いわもと・みちや)教授。このロングインタビューでは、本年度で東大を退職する岩本教授に、自身の研究のきっかけから日韓問題への見解まで幅広く聞いた。
(取材・円光門)
研究テーマの一つに親子心中がありますが、親子心中に関心を持つようになったきっかけは何だったのでしょうか
私は高校生だった頃、志賀直哉の『暗夜行路』や『和解』、島崎藤村の『夜明け前』や『破戒』といった小説に魅了されました。いずれも「家」から個が自立することを主題とする近代文学です。
「家」という法的な制度自体は戦後まもなく解体しますが、父権あるいは家父長制の強さは日本社会においてその後もしばらくは持続します。例えば私の家族の場合、父親が妄信的なカトリックの信者でして、大学受験の時は上智大学以外なら学費を出さないと宣告されたほどでした。父親の意識の中には、子の意志というのは二の次で、親の言う通りに子を従わせるといった家父長制の残滓(ざんし)がまだ残っていたのでしょう。
個の自立を主題にする近代文学に私が引かれたのは、このような個人的、時代的な背景に対する問題意識があったからでしょう。親子心中というのはまさに子の自立に真っ向から反対する現象ですから、こうした問題意識が後に親子心中への関心にもつながったのだと思います。
大学に入り親子心中を民俗学的に捉えていこうと思ったのはなぜですか
私が筑波大学に入った1974年というのは、親子心中などの報道数が例年以上に急増した年でした。発生件数はほぼ横ばいなのに74年と前年の73年だけ報道数が増えたのは、72年の8月に東京で開かれた国際心理学会議で、70年に東京で起きた殺人事件の被害者の20%が1歳未満の嬰児(えいじ)であり、かつその加害者が母親であることがコーネル大学の文化人類学者ロバート・スミスらの共同研究によって明らかにされたことを、マスメディアが「赤ちゃん殺しに仰天」とセンセーショナルに取り上げたからです。
一方、鉄道駅などに設置され始めたコインロッカーに新生児が遺棄されたという捨て子事件も、73年に前後して日本国内で同時多発的に発生し、社会問題となりました。村上龍の80年の作品『コインロッカー・ベイビーズ』はまさにこの文脈の中で生まれたものです。
そうしたメディア状況だったこともあってか、大学1年次の中国語の授業で、中国人の先生から「なぜ日本人は親子心中をするのですか? 中国ではありえないのに」と言われて、親子の捉え方に関するエスニックな文化差というものを意識し始めました。この問題を解明したくて、私は民俗学にのめり込んでいったのです。

民俗学というと、一般的には古い習俗や伝承を研究対象とする学問といったイメージがあるのですが、親子心中という現代的な事象を扱うこともあるのでしょうか
実際、そのような疑問を持つ学者も多くいて、私の研究は常にそれとの闘いでした。私が大学院を修了して国立歴史民俗博物館の助手に着任した時、日本民俗学会の談話会という若手研究者の登竜門のような場で自分の研究を発表する機会を得ました。私はそこで「近代家族と親子心中」と題した発表をしたのですが、質疑応答の際に最初に問われたのは、「今日のご発表、民俗学なのでしょうか?」というものでした。國學院大學にいらしたとある大御所から全否定されたのです。
しかし私が民俗学の定義として参照したのは柳田國男です。学部時代に柳田の本を読みふけり、私の学問観はこれらに決定的な影響を受けました。柳田國男は『民間伝承論』という本の中で、民俗学を「事象そのものを現象として、ありのままに凝視し、『わかつて居る』、『当り前だ』といはれて居る其奥の心理を洞察すること」だと規定しています。つまり親子心中という事象の背後に「当たり前」のように作動している、人々の「家」に対する認識を洞察する限りにおいて、親子心中は民俗学の対象たり得るのです。
親子心中の背後に作動する人々の「家」に対する認識とは何ですか
日本で親子心中が頻発し始めたのは大正末年ですが、それ以前は親子が困窮した場合、親が子を捨てたり親だけ自殺したりするのが主で、親子の死は必ずしも結び付いていませんでした。捨て子をしたら育ててくれる裕福な商家や豪農などが存在し、家が外部に開放されている構造があったからです。
住み込みの奉公人や下男、下女、書生など、多くの非血縁者が家の不可欠な構成要素でした。しかし商家の在り方が住み込み奉公人制度から通勤給与制に変化すると、非血縁者は家から排除されていくようになります。大丸や十合(そごう)といった呉服店が通勤給与制を採り始めたのは1908年ですが、この時期から捨て子を受容する基盤であった開放的な家の構造が崩壊していきました。統計を見ると、商家などによる捨て子の受容数と親子心中の件数は逆相関の関係にあることが分かります。
こうした変化は言葉の上にも表れてきます。「厄介」という言葉は、「家居(やかゐ)」と書いて、もともと「居候」と同義で、家長の直系ではないが扶養されている者という家族的続柄を表す言葉でした。しかし非血縁者が家から排除されるにしたがって、「厄介」は「面倒なこと」や「わずらわしいこと」といったネガティブな意味に転じていきます。また、親を失った子供が他人の家に引き取られ「厄介者」だといじめられるというプロットが昔話や児童文学などで定番だったのも、こうした時代を背景としています。
さらに、近代化にあたって義務教育が始まると、子供の養育責任が生みの親だけに限定されるなど親の扶養義務が強化されていきます。それ故に親だけが自殺したり捨て子をしたりすることは非情な行為だと見なされるに至ったことも、大正末年に親子心中が激増した理由と言えるでしょう。このように、人々の「家」に対する認識の転換と親子心中の発生件数を結び付けた仮説の提示と論証が、私が大学院で取り組んだ議論でした。
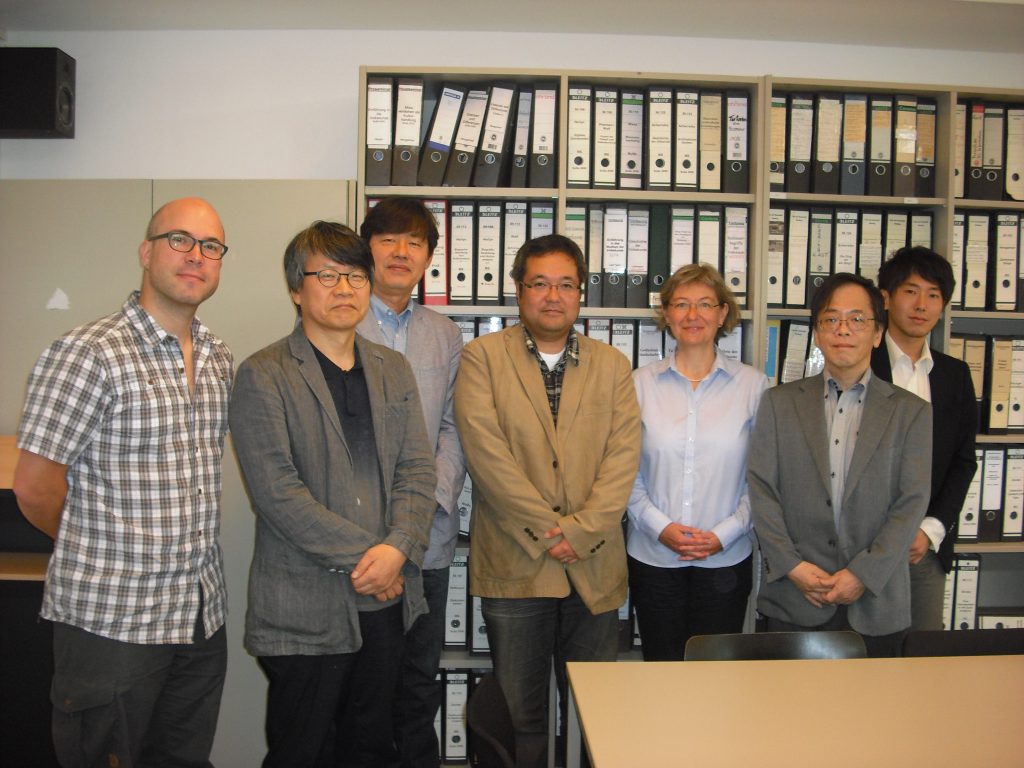
柳田國男の本以外に、学部時代に読んでその後の研究に大きな影響を与えた本はありますか
民俗学を専攻することを決めさせてくれたのは、千葉徳爾(とくじ)『切腹の話 日本人はなぜハラを切るか』という本です。千葉先生は私の学部時代の指導教官で、柳田國男の晩年の弟子でもありました。
この本は、マタギが熊狩りをするときに熊の腹部を十字に切り刻んで内臓を取り出すという儀礼と、侍の切腹の方法が文化的に連関しているのではないかという説を提示するものです。切腹も江戸時代になるとすぐに介錯で首をはねてしまうようになりましたが、もともとは横に腹を一文字に切った上で、上から縦に刀に力を入れて思いっきりかっさばかないと、絶命しなかったそうで。このように、学問的な本ながら内容が実に異様だったんですね。
文中には千葉先生自身が中学1年生の時に野良犬を弓矢で射殺して腹をさばいたという経験が書かれていて、内臓が飛び出すと思っていたところ大網膜の油がすごくて驚いたという、かなりリアルで衝撃的な表現が出てきます。果たしてこんな先生に付いて行ってよいのか、少し不安にもなりましたが、こういうことも民俗学の研究対象となり得るのだと了解したとき、私もゾクゾクとした高揚感を覚えました。
切腹というと、今では衝撃的なものに感じられますが、江戸時代までは侍には「当たり前」だったんですよね。柳田國男いわく民俗学は「当たり前」を研究対象にする営みとのことですが、その方法論について詳しく教えてください
「当たり前」を前提条件とする学問は、ほかにもありますが、民俗学の特徴は、そのプロセスを問うことにあります。つまり、奇異だったものや新奇だったものが「当たり前」になっていくプロセスと、「当たり前」だったものがそうではなくなっていくプロセスに民俗学は着目するのです。
「当たり前」のことは我々に内在化されているため認識困難性を伴います。「当たり前」だったモノやコトが稀少化し、「当たり前」でなくなることで、はじめてかつての「当たり前」が認識されるわけです。
さて、そのような「当たり前」を問う民俗学の方法論についてですが、本年度東大の前期教養課程で行われたオムニバス講義の中で、受講生を対象に次のような意識調査をいたしました。「電車やバスで車内の会話は禁じられていないのに、携帯通話は、なぜいけないのでしょう?」「例えば今後、車内通話解禁の議論が起きたとき、あなたはそれに賛成しますか、反対しますか?その賛否と、理由を簡単に述べて下さい」という2問を出しました。民俗学が得意とするのは、こうした問いに対する回答者の主観的態度とその説明付け、つまり回答者が問いに対していかなる言葉を用いて説明づけるのかを、そのナラティヴから分析することです。回答者297人のうち、賛成でも反対でも「迷惑」という言葉や言い回しを使って説明付けている人は、85人の29%、さらに「不快」「マナー」「配慮」という「迷惑」と連関する単語を入れて説明している人249人を含めると、何と84%に達しました。
これは何を意味するのでしょうか。人を「不快」にさせたり「迷惑」をかけたりしないよう「配慮」するような「マナー」が大事だという価値判断が大半の人に内在化していて、あたかも自分の頭で考えて意見を出したようでいても、実はそれが他の人々と同じ「語りのパターン」にはまり込んでいるものであるということ、これこそが「当たり前」とされる規範の在り方です。民俗学は人々の主観的な「語り」に着目することで、自分の行動や考え方が、はたして本当に自分が考えた結果なのか、それとも単に慣習的判断に従っているのかを見極める指針を提供する、つまり「当たり前」を認識可能なものにする営みともいえます。(「迷惑」規範について過去に岩本教授に取材した記事はこちら)

教授は韓国でも在外研究を行い、長年親子心中についての日韓比較研究を日韓両言語で発表してきました。近年日韓関係は最低と言われるまでに冷え込んでいますが、事態を改善するためには何が必要だと考えますか
私は1989年から定期的に韓国に行っていますが、そこで三一節や光復節といった、いわゆる「反日」運動の記念日に、日本に関する特集のドキュメンタリー番組をテレビで観る機会が何度もありました。その変遷を振り返ると、最初は表層的だった番組の内容がだんだんと深化していったという印象を受けます。例えば2004年になると、ある特集で、靖国神社を日本人は無意識も含めてどう考え、どう感じているのかについて、家の中の神棚との関連を起点に文化論的に深めた分析的な議論が放送されていました。先ほど人々の主観的な「語り」に着目するのが民俗学の方法論だと言いましたが、この意味において、韓国メディアのこうした実践は民俗学的な視点を持つものだと言えるでしょう。
ところが日本メディアの論調を見ると、韓国のトップがおかしいというだけで、過去数十年間そういう「語り」から一歩も外に出ていないように思えてなりません。韓国のテレビで日本についての討論番組が行われる際は、日本を研究対象とする文化人類学者を呼ぶことは珍しくありません。私が1990年に韓国で在外研究をしていた時は、文化人類学者がTV番組に出演することはありませんでしたが、2004年に在外研究をしに訪韓したときには、知り合いの文化人類学者や民俗学者が頻繁に登場してくるのにはとても驚きました。他方で日本はというと、「朝まで生テレビ!」などの討論番組で韓国が扱われる時は、呼ばれるのはもっぱら政治学者や経済学者ばかりで、文化人類学者や民俗学者は昔こそ呼ばれていたことはありましたが、近年ではめっきり姿を見せなくなりました。日本の報道で、なぜ韓国人は従軍慰安婦や徴用工の問題にこれだけこだわるのかといったことを、その意識まで掘り下げて分析したような、相手側の立場に立って考えた番組を私は見たことがありません。
つまり、韓国の側ではどんどんと、いわば文化論的=民俗学的に日本を捉えようとするのに対し、日本は韓国を政治的、経済的にしか捉えようとしてこなかったのではないでしょうか。もちろん政治的、経済的な視点も大切ですが、日韓関係を本当に改善しようとするなら、相手のことを深く知ろうとする勇気と知恵が必要でしょう。そのためには相手方の論理を、相手側の視点から説明付けしようとする文化論的な、生活レベルからの民俗学的な視点が求められると思います。
しかし韓国を民俗学的に捉えることは、「韓国人だから」という民族本質主義的な説明付けを生み出す危険を招くことにはならないのでしょうか
誤解しないでいただきたいのですが、現代民俗学、特に戦後のドイツ民俗学は、民族本質主義(ethnocentrism,自民族中心主義)を真っ向から批判する学問です。戦前、「ゲルマン民族の本質」などというものを論じてナチスに加担してしまったドイツ民俗学は、戦後激しい非難を浴び、一時は学問領域そのものの存立が危うくなりました。しかし1970年、喧々諤々(けんけんごうごう)の議論の末にテュービンゲン大学のヘルマン・バウジンガーらが、民俗学を現在の文化的社会的諸問題を分析の出発点とし、それらの解決を目指しながら、文化の「伝達」プロセスの解析から、現象の文化的拘束性としての歴史性を考えていく学問だと再定義したのです。日本では「民俗」と「民族」が同音であることから、一般の人からはよく民俗学というと「民族」とは何かを扱うものであると誤解されやすいのですが、本来の営みはその正反対であり、目の前にある現象を「民族」などという曖昧な記号に回収せず、それがいかなる文化的プロセスを経て形成されてきたかという歴史性を科学的に解明するものなのです。
なぜ韓国は日本のことを文化論的=民俗学的に捉えようとするのでしょうか
韓国のこのような傾向は日本に対してのみ見られるものではありません。中国やアメリカをはじめ世界に進出するにあたって、進出する相手国の文化や生活を知らないと上手くいかないということを、彼らは多くの失敗から学び、戦略的に経験、獲得していったのだと私は考えています。
こうした変化は、日韓の国際化・グローバル化・多文化共生のありようの違いに起因しているものと考えられます。特に三点目に関しては、2008年に多文化家族支援法が制定されるなど、韓国で「結婚移民」と呼ばれる人々や外国人労働者が急増したことが原因です。海外からの移民のみならず海外への移民数の変化も顕著で、1990年代以降、それ以前は単一民族主義的だった韓国のグローバル化は加速度的に進み、2019年の時点での在外同胞は749万人です。これに対し、海外に住む日本人(海外在留邦人)の数は139万370人に過ぎません。
人口が約3倍多い日本は国内市場も大きく、それほど海外に依存しなくても食べていける一方で、韓国は対外政策を米国やオーストラリア並みの移民国家に転換せざるを得なくなりました。その際、最初は相手国との文化摩擦が多かったものの、だんだんと相手国の文化や生活を知らないとその地に浸透、進出、定着ができないという認識を持ち始め、文化重視の傾向を深めてゆきます。
サムスンをはじめ、韓流ドラマやK-POP、さらにはアカデミー賞をとった「パラサイト 半地下の家族」やBTSなど、他国あるいは世界に通じるような戦略を徹底的に練るようにしないと、韓国は生きていけないのです。これらの点がガラパゴス文化といわれてしまう日本とは大きく違うところでしょう。

最後に、研究者の立場から悩める学生にメッセージをお願いします
学習にしても研究にしても、楽しまないといけません。特に研究者を目指す人に向けては、博士課程に進んでも研究者ポストに就けないかもしれないという近年の深刻な状況下で、あえてそう言いたいですね。私も研究が苦痛になりそうになることがよくありました。例えば大学院在籍時に、本来書くはずのなかった「中間論文」なるものを書かなければならないと急に言い渡されたのですが、その年には他にも原稿が溜まっていて、計算すると1日につき原稿用紙3枚のペースを1年間保持しないと書き終わらないという状況でした。千葉先生とは別の指導教官でしたが、「無理です」と伝えても「書け」と言われ、苦しみながら書いていたら、論文提出の3週間前にとうとう腎臓結石で入院してしまったのです。見舞いに来た後輩が、先生からのメッセージとして伝えてくれたのは、「健康より原稿」でした。半ばジョークだったんでしょうが。
でも研究というのは本質的に楽しいものです。本来楽しめるはずの研究が苦になるということは何かを間違えているということなので、すぐに軌道修正して、研究が常に楽しいという状況を確保しておかないと、たとえ研究者ポストに就けたとしても長い研究人生は維持できません。知的刺激で脳がまひするようなハイな感覚を大事にしてください。

85年筑波大学大学院博士課程単位取得退学。国立歴史民俗博物館助手などを経て、06年より現職。近著に共編『民俗学の思考法——〈いま・ここ〉の日常と文化を捉える』(慶應義塾大学出版会)など多数。









