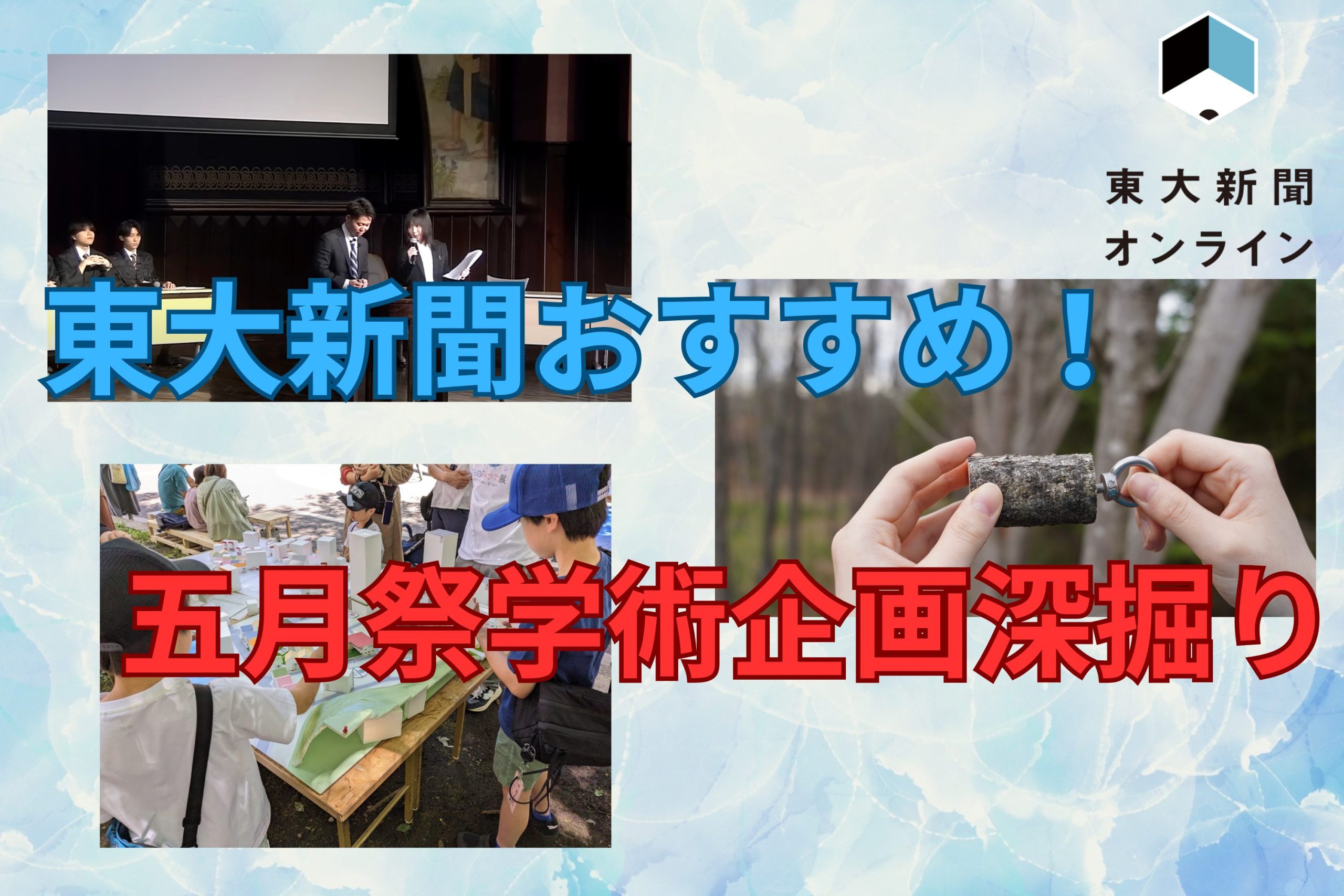
後期課程の学部の多くがある本郷キャンパスで開催されることから、五月祭は東大のもう一つの学園祭である駒場祭よりもアカデミックな色合いが強いと言われる。五月祭来場者におすすめの学術系企画を取材した。(取材・平井蒼冴、写真は各企画提供)
【法律相談所】カスハラ加害者に法的責任は問える? 「法律相談所模擬裁判」

東京大学法律相談所は、五月祭で「砂城」と題しカスタマーハラスメントをテーマにした模擬裁判を大講堂(安田講堂)で上演する。模擬裁判の今年のテーマはカスタマーハラスメントによる被害とその責任の所在について。ハウスメーカー従業員が業務中の一つのミスをきっかけに顧客から執拗(しつよう)で悪質なクレームを受け、うつ病を発症、悪化して自死する。その両親が、加害者である顧客に対し、不法行為責任を問う損害賠償請求訴訟を起こすという設定。裁判の論点は、カスタマーハラスメント加害者にどこまでの範囲で法的責任を認め得るか、自死という結果に関する責任をどう評価するかにある。
東京大学法律相談所は法学部生有志が民事の法律相談を行う団体。週3回法律相談に応じる他、夏季休業期間中には遠方に赴いて相談活動を行っている。法律相談活動に並行して、法律相談所は例年五月祭で模擬裁判を実施している。刑事と民事を毎年交互に扱っていて、今年は民事の回だ。初めて模擬裁判を実施した1948年から数えて今回で77回目となる、今年で98回目を迎える五月祭の中でも歴史ある企画だといえよう。
法律相談所には法学部の3年生と4年生が所属しているが、裁判劇を演じるのは3年生だ。4年生は裏方として劇を支え、演者12人を含め全体で約200人が活動に加わる。準備は昨年の11月ごろから始まり、演者が練習を始めるのは4月から。参加した動機はさまざまで、法律の勉強ができるから、劇で取り扱う社会問題に関心があったからといったものがある。
劇を作る上でこだわっているのは、法律面での精緻さだ。先輩たちから、判例の分析などを通して法律面でよりリアリティーを追求するよう言われてきたそうで、実際の裁判への再現度が高くなっている。それに加え、近年は取り扱う社会問題への洞察も深めようと努める。
法律相談所の学生は証人尋問や判決の言い渡しなど、裁判における各種手続きへの造詣を深められる。机上の空論になりやすい、大学の講義における理論や知識を実社会にもつなげられる。このことが法律相談活動の役に立つ効果につながる上に、現行の法制度と社会通念の隔たりを認識することで法律に対して批判的な視点を養える。
企画の責任者を務める清野恭(たかし)さん(法・4年)は現実の人間関係や社会的な価値を裁判という手続きで捉えきるのは難しいので、法という一つの物差しに基づいて判決を出す行為それ自体について来場者に考えてほしいと話した。もちろん劇としても面白く、「誰でも楽しめる劇ですので、ぜひ気軽にお越しください」と話した。
【東京大学鴨田ゼミ】 獣害、伝染病… おもちゃから考える日本の林業 「東大の木で! 森を感じる工作体験」

東京大学鴨田ゼミでは工学部14号館で「東大の木で!森を感じる工作体験」を出展する。企画では木材にボルトをねじ込むことで鳥の鳴き声を再現する道具、バードコールの制作体験を行う。この他、ゼミで学んだことについてのポスター展示なども行う予定だという
東京大学鴨田ゼミは、鴨田重裕准教授(東大大学院農学生命科学研究科附属演習林)が前期教養課程で開講している複数の全学自由研究ゼミナールや全学体験ゼミナールの受講生のうち有志が集まった団体。各ゼミナールの活動場所は伊豆や秩父、千葉とさまざまで、それぞれに特色ある学びの舞台が用意されている。学園祭企画は、各ゼミの活動を通じて得た体験や知見をもとに学生が自分事として発信をすることを目的とし、ゼミ活動の一環として重要な位置付けがされている。
バードコールを山に持っていき音を鳴らすと、鳥が集まることもあるといい、森を感じるのにふさわしい企画といえよう。バードコールの材料にもこだわる。材料はほぼ全て東大のキャンパスや演習林で採集した。基本枯れた木から採集したというが、ここには価値が無いとみなされ普通なら捨てられてしまうものにも、視点を変えれば使い道が生まれるのではというメッセージがある。材料として選んだ樹種は、ミズナラ、クスノキ、ユーカリなどいくつかあり、それぞれに選んだ理由がある。例えばミズナラに関しては、日本の森林は近年「ナラ枯れ」(ある虫がナラの木に入り込み病原体に感染させることで、ナラの木を枯死させる伝染病)の深刻な問題が進行している。日本の国土の約7割を森林が占めるが、森林に大きな問題が起きていることをほとんどの日本人が知らないことへの問題意識が、材料に込められているという。
発信したいことをまとめたポスター発表も必見だ。企画の責任者、斉藤光祐さん(法・3年)は企画で特に伝えたいこととして、日本で林業が「もうからないから」と放棄されてきたことを課題に挙げる。斉藤さんによると、人と自然とのコミュニケーション手段だった林業が放棄され人間と獣の緩衝地帯となっていた里山が劣化した結果、獣害が広がっていったという。さらに、千葉県のスギの林に広がる溝腐(みぞぐされ)病(幹に溝ができそこから木が腐り溝が大きくなる伝染病)を例に挙げ、里山が放置されることにより病気の木が排除されず林全体に病気が広がる問題も起きていると指摘する。
このような問題がありつつも、従来の林業を復活させるのは簡単ではない。それどころか、林業を斜陽産業として切り捨てる態度の人も多い。そこで、来場者に日本の林業の現状を知ってもらい、この複雑な問題について一緒に考えていきたいという。
「私も、森や林業にはなじみがなかったのですが、ゼミで見た光景に絶句したことが、企画の原動力になっています。日本の森や林業は様々な課題を抱えていると言われますが、同時にさまざまな可能性も持っていると思っています。日本の未来の森、未来の林業はどうなっていくのかということについて、この工作体験を通じて少し思いをはせてみませんか」と斉藤さんは話した。
【工学部都市工学科】 すごろくで都市開発を考える「私と都市の工差点」

工学部都市工学科では工学部14号館で「私と都市の工差点」を出展する。渋谷や日本橋で行われている再開発事業を模し、都心部における第一種市街地再開発事業の構想段階から実際に完成して客が入るまでの流れをすごろく形式で体験するゲームがメインだ。さらには揚げパンを販売し、そこで出るごみを使った投票企画も行う。程よい長さの時間で参加できる企画が多く、来場者が楽しみやすいのが特徴。都市模型の展示のほか、工学部14号館前の通路にはストリートファニチャー(ベンチなどの街路に置かれるものの総称)の設置も行う。これらの企画を通して、来場者に都市をより身近に感じてもらえることを目指すという。
都市工学科ではまちづくりや都市計画についての講義や、実際に関東近郊のまちを題材にそのまちがどうあるべきかを考える演習を行っている。さらに、都市計画を学ぶには実際にまちづくりに参加することが必要だという認識の下、長野県小布施町や東京の上野、本郷などでストリートファニチャーを設置するなど、実践活動も行っている。
かつて都市工学科は例年五月祭に企画を出展していたが、コロナ禍で一度途絶えてしまったという。しかし、昨年から再び出展。好評だったため、今年も昨年とは企画名を変えて出展することにしたという。
昨年は都市開発に関する制度に沿ったルールで、積み木を使って都市開発を再現するゲームを実施。好評だったものの、50分ほどかかってしまった。今年はその反省も踏まえ、10〜20分ほどでプレイできる手軽なすごろく形式のゲームを出展する。
準備は2024年度Aセメスターが終わる1月末から始まり、企画が固まったのが2月から3月ごろだという。企画に参加する木村栞莉さん(工・4年)は「揚げパンの模擬店などどなたでも参加いただけるものから、ワークショップや展示など都市に詳しい方も楽しんでいただけるものまで、幅広く企画を用意しています。ぜひ工学部14号館にいらしてください」と話した。










