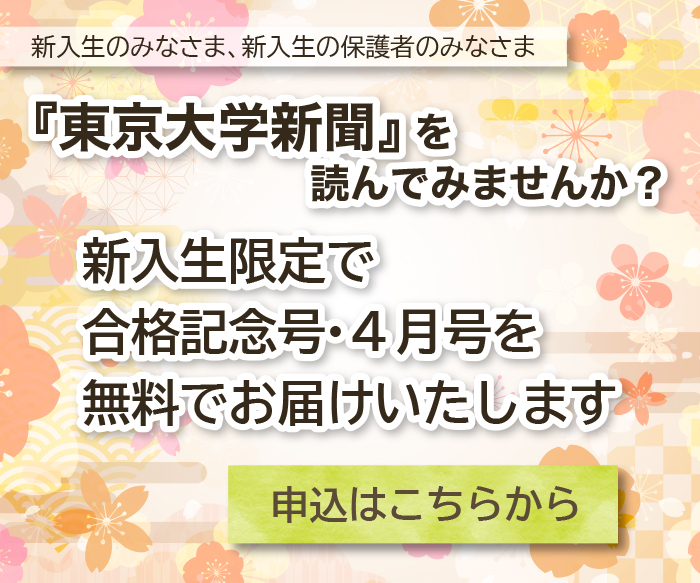駒場祭で賑わったキャンパスの片隅で、物語を紡ぐ声がある。新しく動き出した劇団ねよんごは、現代口語劇『長靴で浅瀬まで』を上演する。繊細な感情のゆらめきを描くその舞台について、劇団ねよんごを主宰し脚本を手がける朝比奈さんに話を聞いた。(取材・木下太陽)

駒場祭の小空間に、新たな劇団が旗を掲げる。その名は「劇団ねよんご」。「ねよんご」の名は、西アフリカのブルキナファソなどで話されているモシ語(モレ語)で「夜」を意味する言葉に由来している。今年発足したばかりの劇団で、旗揚げ公演となる『長靴で浅瀬まで』を上演する。メンバーは16人。中心となるのは、以前から学内の劇団で活動していた学生だ。主宰の朝比奈さんは、1・2年次に所属していた劇団で脚本を手がけてきた経験を持つ。その同期を中心とした関係者に声をかけ、新しく結成されたのが、劇団ねよんごだ。仲間とともに「もう一度、自分たちで新たな舞台をつくりたい」という思いが、この旗揚げへとつながった。
感情の波を描く
旗揚げ公演のタイトル『長靴で浅瀬まで』は、思い付きから生まれたものだという。駒場祭委員会への申請上、早い段階で題名を提出する必要があり、「とりあえずこのタイトルでいこう」と決めたところから、物語の構想が始まった。だが、偶然の産物であった題名が、やがて作品世界の核となるモチーフへと育っていく。
「波が寄せて返す浅瀬に立つ長靴。その中にじわじわと水が入り込んでくるそんな情景から、感情の浸食というイメージが浮かびました」
長靴を満たす海水は、人の心の奥へゆっくりと染み込む絶望や希望の比喩として描かれる。ファンタジーの要素を含みながらも、舞台はあくまで現代。登場人物たちが交わす日常的な会話のなかに、静かに心の波が立ち上がる。観客は、どこにでもある言葉のやりとりの奥に、かすかな痛みやぬくもりを見出すことになるだろう。
朝比奈さんがこれまでに手がけてきた作品は、いずれも独自の世界観をもつ脚本だった。会話劇が中心だった以前の作風に対し、今回は身体の動きや空間の使い方に焦点を置いた現代口語劇として構成されている。ふと足を止めた通行人が「なんだか面白そうだな」と思って立ち寄れるような、開かれた作品を目指したという。
駒場祭公演には、通常の劇場公演とは異なる制約が多い。会場となる駒場小空間(駒場Ⅰキャンパスにある多目的ホール)は複数の団体で共有するため、舞台設営や撤収の時間が限られており、大掛かりな舞台装置を組むことは難しい。照明や音響設備も他団体と譲り合いながら使用する必要がある。そうした中で、劇団ねよんごのメンバーは工夫を重ねた。
宣伝用のチラシ制作にも手間がかかったという。モチーフである長靴を撮影するために、海岸まで出向き、海辺に長靴を置いて撮影。泥で汚れた長靴を洗い直しながら何度も撮り直したそうだ。その1枚には、作品世界の空気を象徴する静謐(せいひつ)さが宿る。限られた環境の中で、どのように作品の雰囲気を伝えるか。その工夫の積み重ねが、作品全体の完成度を支えている。

役者とスタッフが織りなす総合芸術
出演する俳優は5人。そのうち2人が固定の役を演じ、残る3人はアンサンブルとして複数の役柄を行き来する。状況や感情の変化を、セリフだけでなく身体の動きや舞台上の配置で示す構成だ。観客は登場人物が入れ替わる瞬間に、まるで波のような連続と断絶を体感することになる。
「さまざまな役を入れ代わり立ち代わりで演じたり、特定の役に縛られずに舞台上に出てきたりするので、状況での演出や衣装選びは難しいです」
舞台上で演じる俳優だけでなく、照明・音響・衣装など裏方のスタッフも経験豊富なメンバーが多い。特に照明や音響は、場面ごとに繊細な変化を加え、感情の波を視覚・聴覚の両面から立てる。「役者の演技はもちろんですが、裏方の仕事にも注目してほしい」と朝比奈さんは語る。
舞台となる駒場小空間は、その名の通り小規模な劇場だ。しかし、制約は表現の幅を狭めるものではない。むしろ、ここでしかできない演出が生まれる土壌になっている。
「この劇場の構造を逆手に取った、ちょっとした仕掛けをしてみました。見れば多分『あっ』と思ってもらえると思います」
観客との距離が近い空間だからこそ、息づかいや視線、微かな照明の揺れまでもが物語に溶け込む。舞台と観客席の境界がゆるやかに溶け合う瞬間、劇団ねよんごの世界が立ち上がる。
劇団ねよんごにとって今回の公演は、まさに出発点である。限られた時間と舞台の制約の中で、それでも独自の世界を立ち上げようとする姿勢には、演劇そのものの原点に通じる熱がある。