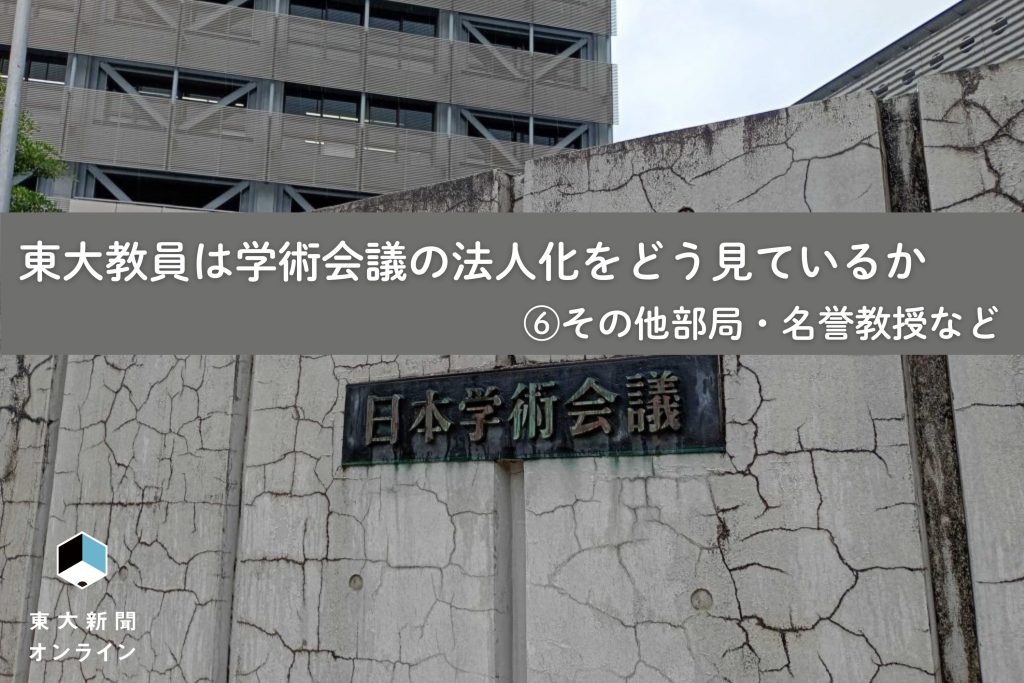
東大には多くの日本を代表する研究者が存在し、東大教員にも日本学術会議の関係者が存在する。5月に衆議院本会議を通過した政府による日本学術会議法人化法案は、6月11日に成立に至った。東大教員は今の情勢をどう見ているか、メールでアンケートを実施した(期間:5/7〜5/26、回答人数:163人)。
ここではアンケートに寄せられた自由記述のうち、これまでに含まれなかった部局の教員、及び名誉教授によるものを原文のまま掲載する。他の部局については記事末尾を参照。各設問とその集計結果についても順次公開。
※学術会議の法人化に関しては、6月10日付で発行の『東京大学新聞』6月号に特集記事を掲載しています。そちらも併せてご覧ください。(お買い求めはこちらから)
・社会科学研究所 教授(現在学術会議の連携会員)
頼まれるままに連携会員になってしまって初めて分かったが、学術会議という組織の現状には大いに問題がある。政府の対応には問題がありそうだが、私自身が学術会議の存在意義について疑問を感じているので、昨今の政治的な論点について関心が持てない。
・社会科学研究所 佐々木彈教授
一般報道では必ずしも強調されていないが、今般の学術会議法人化案は、2004年の国立大学法人化のときのような「表札の架け替え」に留まらず、国家権力が学術会議内の人選に口を出すという露骨な実質的介入の計画されている点が問題の核心にある。国立大学のときのような文字通りの「法人化」だけであれば、教職員が公務員から法人従業員となり労働者としての権利が保障されるという副産物もあった。今般の学術会議「改革」は、単純な「法人化」のみならず人選への政府介入を許す(つまり菅政権の任命拒否暴挙を事後的に正当化する)という「おまけ」の附いている点で大変深刻な「改悪」となっている。
・大学院公共政策学連携研究部 教授
会員の選考課程が不透明。 デュアルユースに対しての姿勢など安全保障環境の変化を踏まえているとは考えにくく硬直的。 税が投入される組織である以上、政府に対して一定の説明責任を持つことは当然。
・エグゼクティブ・マネジメント・プログラム室 小野塚知二特任教授(現在学術会議の連携会員)
学問の自由を大きく損なう危険性のある法案であり、有害かつ不要な内容ばかりなのでぜひ廃案にしてほしいと考えています。会員任命拒否以降の一連の騒動について、日本のメディアの報道が鈍く、国民の多くにことの真相が伝わらないまま、こうした重大な改悪がなされようとしていることにも大きな懸念があります。
・部局無回答 教授
現在の学術会議が役割を果たしているとは思えないが、現行の政府案も賛同できるものではない。
・部局無回答 准教授
政府の姿勢やそれに賛成する言説を見ていると、しばしば学術会議の姿勢や志向性への反発から、変化を起こそうとしているように感じられる。学術会議の現状に様々な意見があったとしても、そのことと、ナショナル・アカデミーとはどのような要件を満たす機関であるべきなのかとは、切り離して考えるべき。同時に学術会議側も、構成員が研鑽してきた「知」をベースに、独立性・自立性のある機関として保たれる意義を感じてもらえるような取り組みを続ける必要があるだろう。
・名誉教授(過去に学術会議の会員または連携会員)
従来の日本学術会議での会員選考のやり方は、過去の経緯を踏まえて大変合理的で工夫されたものでよくできたものであり、また、社会的に必要な状況の中で、会員も連携会員もよくやってきたと思う。多くの提言を出して学術の社会的な役割を十分に果たしてきたと思う。私自身は、東日本大震災後の復興のあり方や今後のエネルギーや原子力の利用のあり方、学術の社会的な役割などについても真摯に議論をして、多くの提言を提出してきた。このような役割の成果については、会員選考や予算について政府からの独立性と十分な支援が必要である。今回の法案による改訂により、今までのような学術の社会的な役割を十分に行うことが大変疑問である。先進国の中でも文教予算や研究の予算が十分でもなく、その中で、軍事研究に誘導し、軍事研究をしなければ研究資金が確保できない状況は、例えば天文学や地球物理学のような一見、軍事と関係ない領域まで浸透しており、特に若い研究者が研究を続けるために、軍事研究に手を染めなければならないような、大変危惧されるような状況にある。その中で、若い基礎科学の研究者が軍事研究に安易に手を染めることなく自由な研究ができることが、今後の未来社会で必要なことであり、そのことに対しても、今までの学術会議は真摯に取り組んできた。しかし、今回のような組織改訂によって、そのことができなくなることは、社会にとっても、若い研究者にとっても困ったことになる。しかし、なかなかこのことが十分に社会に浸透していないのが残念である。このような意見が、実名を伴って公開されても全く構わないが、私自身は退職しており名誉教授であるので、掲載は不適切ではないかと思う。名誉教授でもいいということで改めて意見を表明することを求められれば、実名で発言することには問題はない。
・佐藤学名誉教授(現在または過去に、学術会議の役員または部長)
日本の学問の発展のためにも、学問研究の国際連帯のためにも、政府から独立したアカデミーは絶対必要です。アカデミーの解体を導く法案は学問の良識において廃案にしなければならないと思います。
・保立道久名誉教授(過去に学術会議の会員または連携会員)
学術会議は大学とともに学術の中心を構成する職能的組織であって、大学と同様に学問の自由の下に時の政府や政治諸勢力から独立しているべきものです。学問は社会の諸職業の専門性と密接に結びついているものです。学術の専門性を尊重することは、社会の諸領域のもつ専門性と自律性を尊重して社会が組織されるための重要な条件です。政府の行っていることは、日本社会における諸職業の専門性と自律性をいよいよ軽いものする動きといってよいものであり、現代社会ではあってはならないものだと思います。
・名誉教授
政府の考え方は、科学者の国会として、科学者の総意を結集、形成できる組織という考え方がない。
・品田悦一名誉教授
学術会議の修正要求に「必要ではない」と答えたのは、修正では不十分で、廃案にすべきだと思うからです。
・小森田秋夫名誉教授(現在または過去に、学術会議の役員または部長)
政府は、現行制度のもとで学術会議が行なっている自主改革を尊重するという態度をとり、予算の拡充によってそれを支えるべきである。学術会議には社会への発信を強化することが求められ、政府にはその科学的助言に真摯に耳を傾けることが求められる。
・田中純名誉教授
研究資金についての質問などは、在籍時の経験および客観的認識により回答した。政府の言う「独立性・自立性」は学術界の主体的判断をむしろ奪うための方便であり、この種の論理のすり替えは大学のガバナンスをめぐって繰り返されてきている。大学「改革」を主導してきた内閣府のメンバー(上山隆大氏など)は安保政策にもコミットしており、学術会議関連の法案がそうした動向とリンクしていることは明白である。任命拒否を撤回させ、その責任をクリアにしないまま、政府案に追随することは学術界として認めるべきではない。学術会議自体の改革はあくまで学術界全体で考えるべきことだろう。
・大沢真理名誉教授(現在学術会議の連携会員)
今回の法案は、学術会議や学界全体に対して、「問題意識や時間軸」を政府や社会(ほぼ経済界と同義)と「共有」することを求める動きの一環である。それらの「共有」の質や度合いが、研究資金の獲得に影響することも予想される。政府与党の「時間軸」はおうおうにしてごく短く、「問題意識」は大きく揺れ動く。自分の研究が軍事にはかかわらないと考える研究者であっても、それらを「共有」しようとするために研究がゆがむ恐れがあると、危惧しなければならない。
・高橋宗五名誉教授
政府は学術会議にお金は出すが口は出さない、が原則であるべきです。政治家や官僚は「学問の自由」(日本国憲法第23条)が何を意味する分かっていないのではないか。
・柴垣和夫名誉教授(過去に学術会議の会員または連携会員)
学術の世界は、「少数意見は必ずしも新しい真理とは限らないが、新しい真理は必ず少数意見として登場し、それが論理的首尾一貫性と実験ないし実証によって次第に新しい多数意見を形成してゆく」世界です。そのような学術の世界に、多数決原理による既存の多数意見で運営される政治権力によって影響を与えようとするのは、社会の将来的発展を遅らせ妨げることになります。
【他の部局についてはこちら】










