
『まなざしのレッスン』(東京大学出版)などで知られ、日本の西洋美術史研究をけん引してきた三浦篤教授(東大大学院総合文化研究科、昨年当時)が4月で退任した。日本人が日本で西洋美術を研究する意味をどう見出してきたのか。常に社会とのつながり、そして世界とのつながりを模索し続けた意図はどこにあったのか。30年以上にわたる研究生活を振り返る。(取材・撮影:宮川理芳)
複製図版と書籍に導かれて
━━西洋美術史研究の大家として知られる三浦先生ですが、東大入学時には既に西洋美術史をやろうと思っていたのですか
いえ、そんなことはありません。将来についての明確な展望は全くありませんでした。しかし今思えば、西洋美術への関心の萌芽はある一枚の絵にあったように思います。40 年前のことです。母校の島根県立大田高校の図書室で、画集をぱらぱらとめくっていた時でした。レオナルド・ダ・ヴィンチ作『岩窟の聖母』という絵に目が留まりました。しかし気になったのは聖母ではなく、天使の顔です。何という微妙な表情だろうか、と感銘を受けました。来るキリストの受難の運命を予感して、諦念と優しさに満ちた表情にやられてしまったのです。これが西洋絵画との最初の出会いでした。
ただしこれも今振り返ればという話で、当時それで西洋美術史を専門にしようと思ったわけではありません。西洋美術を知ることと美術史学がどのようなことをする学問かを知ることは別ですから。その意味では、高階(たかしな)秀爾先生の『名画を見る目』(岩波書店)という本に出会ったことが大きかったと思います。美術史研究の何たるかを知りました。過去の作品の良さ・面白さは、現代の目で見ても分からないことがありますが、当時の社会に与えたインパクトなど資料を調査することで、描かれたときに本来持っていた意味が読み解けるようになります。謎解きのようなある種の知的な面白さがありました。田舎の高校生でしたから、このように研究する道があるのだとこの本で初めて知ったわけです。
阿部良雄先生との出会いも大きかったですね。阿部先生はボードレール研究で知られる方ですが、私は『西欧との対話―思考の原点を求めて』(河出書房新社)や『群衆の中の芸術家―ボードレールと 19 世紀フランス絵画』(中央公論社、当時)と出会い、絵画を「研究」する意欲が強くなっていきました。卒業論文は阿部先生に師事し、修士論文は高階先生に師事しました。ですから、私の美術史学との出会いは本物を見た衝撃ではなく、複製図版と書籍によるものだったんです。こうして考えてみると、私もまた明治以来の日本における西洋文化受容の末端にいるのだと実感します。

━━研究対象にマネを選んだのはなぜですか
19世紀フランス絵画を選んだのは阿部先生の影響です。実は当時ベラスケスにも強い関心があったのですが、第二外国語でフランス語を選択していたので、スペインの画家であるベラスケスよりもフランスのマネの方が良いだろうと思いました。スペイン語を選択していたらベラスケスを選んだかもしれません。後にマネとベラスケスの間に親交があったことを知りました。どことなく同質の、辛口のリアリスムとも言うべきものがあるように感じます。
マネは分かりそうで分からない、謎めいたところの多い作品ばかりです。今でも100%理解できたとは言えない部分があります。他の絵画との違いは、様々な要素が複合的に絡み合っているという点。マネは古典的教養を兼ね備えながらも、宗教絵画ではなく当時のパリを描き出すことに関心がありました。また、裕福なブルジョワジーの息子として、何不自由ない身分の中であえて画家という道を選んだ特異な人物でもあります。そもそも「ブルジョワジー」という単語一つ取っても、どのようなものか現代の我々には想像できないですよね。画家自身の複層性が作品にも反映されているのでしょう。
二重のまなざしの揺らぎの中で
━━大学院進学後、パリ・ソルボンヌ大学に留学します。当時の指導教員による指導とパリでの調査が後の研究にも大きな影響を与えたそうですね
19世紀では主流だったアカデミズム絵画を研究していた先生に、アカデミズム絵画と印象派の間のダイナミズムを教えていただいたことで、両方を相対化できたのは本当に良かったと思います。日本にいると印象派至上主義に陥りがちですが、異端だけでは理解できないのだと痛感しました。また、日本ではどうしても現物を見られないので図版や人の書いた論文をもとに研究するしかありませんが、それは学術研究というよりは評論です。
フランスでは、本物の絵を自分の目で観察し、また国立図書館に毎日のように通って一次資料を探し、ある一つの絵について、当時の評価から出展歴、購入歴、画家の当時の人間関係、モデルの人生…と徹底的に「全て」を調べました。調査に穴がないか見極める感覚を養う良い訓練にもなりましたし、全てをブルドーザー的に調べたことで「日仏の美術交流」に関する思いもよらない資料を見つけることもできました。
資料の重要性というのは他の資料との関係性の中でしか分からないものです。徹底した調査を行って初めて、資料の持つ意味や重みや新しいことが見えてくるのだと骨身に染みて分かりました。しかしこれでは無限に広がっていってしまう。だからテーマというものが必要なのです。ただしどの程度の対象期間・範囲が妥当かということもまた調査によってしか見極められない。調べては修正し、を繰り返して何度も立ち返るしかありません。テーマを確定するだけで何カ月も、時には1年間費やしたことさえあります。

━━留学時の調査を経て「19世紀の価値観を内在化する」ことができるようになったとのことですが、どのような感覚なのでしょうか
留学時は、19世紀のフランスという別世界に自らを浸していたような感覚でした。19世紀の文化や社会を知るほど、当時評価された作品の素晴らしさも理解できるようになるのです。印象派を評価する現代の価値観とは違う 19世紀の価値観が自分の中に芽生え、作品を見るとき両方の視点を行き来できるようになりました。これが留学の最大の成果と言えるかもしれません。以降この二重のまなざしをもって、現代と 19世紀のはざまの中で研究してきました。
━━帰国から数年後、東大教養学部で初の美術史の専任教員となり、以来約30年にわたって美術史研究の面白さを伝える「西洋美術史の見方」を開講してきました
研究を始めた頃、世間では「美術史学など遊学だ」という見方が一般的でした。しかし、美術史学とは歴史学であって、緻密な実証の上に組み立てられる学問です。私は美術史学を人々の間に根付かせることを自らの使命として、駒場での授業を毎年やってきました。授業では、自分の足で美術展に行き、ある作品について書く 4000字のレポートを課しました。多いと思うかもしれませんが、言語化することで作品の見方を肉体化し、意識的に絵を見ることができるようになります。作品の見方が分かれば、美術展も「きれい」という感想一つで終わらず、もっと面白くなるでしょう。芸術を身近な楽しみとすれば生活が豊かになります。美術を縁遠いものと考える人は多いですが、専門家でなくても、入口さえあれば楽しめるものです。
30年で1万人前後の学生が受講してくれましたが、たとえ 10人に1人でも美術ファンとなって周りにその面白さを伝えてくれれば、その輪は広がっていきます。日本文化の底上げにつながればという思いでやってきました。美術史と人文科学の運命は同じです。近年ますます人文科学を軽視する声が強くなっているように感じますが、授業を通じて少しでもそうした流れに抗うことができたならば幸いです。
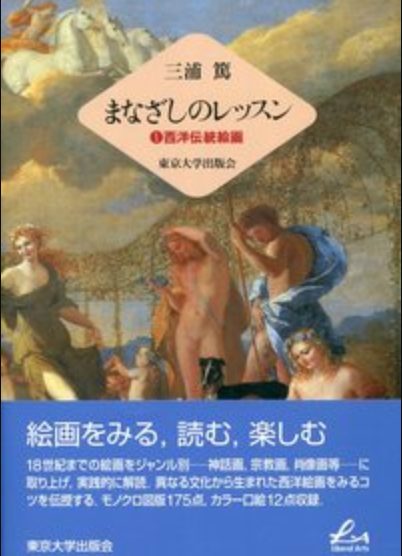

━━2000年代から国際交流を推進し、海外の研究者を日本へ呼んだり自ら世界各地に赴いたりしています。何かきっかけがあったのですか
これは大学側のサポートが増えたことが大きいです。フランス美術の研究ですからもっと海外に出向きたいという思いはありましたが、予算の関係上なかなか難しかったんです。もちろん海外の大学や美術館との交流はありましたが、展覧会の開催がメインで、一過性のものでした。それが 00年代後半になってアカデミアの世界でも一気に海外交流を推進する波が押し寄せて、積極的にできる環境が整いました。その波に乗った形です。
ただやはり苦労も多く、向こうは英語やフランス語を母語としていて、当然日本語は話せません。同時通訳も付けましたが、相互理解は同一言語でなければなかなか進みません。言語の不均衡があると対等の学術交流はできないと思いつつも、フランス美術を専門にする者としては不満も言えませんし(笑)。明治以来の日本は常に、文明も社会も西洋化することで発展してきたという歴史があります。未だに「学ぶ」という姿勢が払拭(ふっしょく)されていません。
私の専門は 19 世紀のフランス美術ですから、日本では日本語で西洋美術研究を行いますが、海外ではフランス語で発表するという苦労があります。そこで、私はある意味で両面作戦的な道を取りました。ジャポニスムの研究をしていることを生かして、日本のことをテーマにした研究をフランスで発表するのです。フランスの研究者が研究しない分、非常に貢献度は高い。どちらが良いという話ではなくて、向こうの土俵で本格的に西洋美術をやることも一つの道ですが、日本に関係したテーマで彼らの知らないことを発表することも一つの道だと気付いたのです。
最近は西洋の研究者は気が付かないような視点、日本人の感覚や分析視点から研究するという手がないかと模索しています。日本人として西洋美術を学ぶ意味が次第に分かってきたのでしょう。最初は西洋の研究者と同じようになるのが目標でした。しかし自分が日本人である以上、日仏の美術交流という、あまり人のやっていないことをやるのもまた大きな意味のあることだと考え始めました。
「クロスエリア」から「クロスジャンル」へ
━━日仏交流という「クロスエリア」研究だけでなく、近年は芸術の垣根を越えた「クロスジャンル」研究にも精力的に取り組んでいます
19世紀の画家たちの交友関係を調べていると、当然ながら彼らは画家たちとだけ交流しているわけではなくて、詩人、作家、音楽家、作曲家、演劇人などさまざまな芸術家たちと交流していたことが分かります。これまで、絵画と文学の間の影響関係はある程度研究されてきましたが、形として残らない音楽や演劇との関係は研究しづらかったんです。楽譜や台本は残っても本質的に一過性のものですから。しかし文学・美術・音楽は明らかに 19世紀において緊密に連携していたわけで、ここに関心を持つようになりました。
現時点における集大成は、昨年末から今年初めにアーティゾン美術館で行われた「パリ・オペラ座―響き合う芸術の殿堂」という展覧会です。総合芸術としてオペラ座を捉え、諸芸術との多様なつながりをテーマとしました。
━━同じく 00年代から社会との連携も進めて来ました
これも大学の大きな目標として掲げられていたものでした。大学で美術史の研究をしていると、どうしても社会の中で孤立してしまいます。「よく分からないことを研究している先生」と見られて、大学の狭い世界の中に閉じ込められるのは嫌でした。社会に対して人文科学がいかに重要なものかを広めたいという思いがありました。私はごく普通の家庭出身でしたし、自分の両親にとって全く訳の分からないことをやりたくなかったんですね。分かりやすく書くことで社会に還元したい、どうすれば内容のレベルを下げずに良質な易しい日本語で伝えられるかを、教員になって以来ずっと考えてきました。
美術史には展覧会という他の学問分野にあまりないツールがあり、これを介して社会の相当数の人々と関われるという強みがあります。展覧会は時に何十万という人々に見てもらえるという点で、本やテレビの特集番組を凌駕(りょうが)します。これまでいくつもの展覧会を監修・企画してきましたが、私は最新の学術成果を盛り込むと同時に興行としても成功させたいと考えてきました。
━━今後の研究の展望についてお聞かせください
まだまとめきれていない美術史研究を3、4冊の本として形にしたいです。それから、さらにもう一歩踏み込んだクロスジャンル研究をやっていきたいと思っています。本という形でなくても、芸術の諸分野をつなぎ、クリエイターやメディエイターを巻き込んで、学術と創造の統合を行う場を作りたいですね。
━━研究を志す東大生に何かメッセージをお願いします
まずはいろいろなことを学べる幸せを自覚してほしいです。東大は本当に恵まれた環境です。貪欲に学んでいってください。それから、好きなこと、これなら続けられると思うことを見つけたあとは、質を上げることを大事にしてほしいと思います。仕事にするなら、好きというだけでは説得力がありません。他者からの客観的な評価があって初めて仕事として認められるのです。厳しいようですが、最後は収斂(しゅうれん)させることが重要です。

三浦篤(みうら・あつし)元教授 97年パリ第4大学で博士課程修了。博士(美術史・考古学)。06年より東大大学院総合文化研究科教授、23年退職。東大駒場美術博物館館長。主要著書に『近代芸術家の表象−マネ、ファンタン=ラトゥールと 1860年代のフランス絵画』(東京大学出版会)、『往還の軌跡—日仏芸術交流の 150年』(編著、三元社)など。監修した展覧会に「ラファエル・コラン展」(1999年)、「モネからセザンヌへ−印象派とその時代展」(2002年)など










