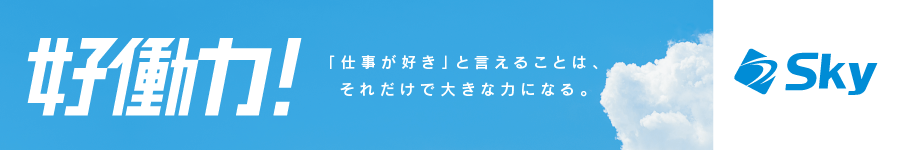鳥取県八頭郡智頭町。面積の93%を山林が占めるこの町に、全国各地から人が訪れるベーカリー&ビアカフェ「タルマーリー」がある。この店のオーナーは渡邉格(わたなべ いたる)さん。東京で生まれ育ち、高校卒業後フリーター生活を経て4軒のパン屋で修業した。2008年に千葉でパン屋を開業するが東日本大震災を機に岡山県真庭市へ移住。さらに麹菌を採取するために智頭町へ移転した。『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』の著者でもある。
腐る経済、聞き慣れないこの言葉は本のタイトルにもなっているように、タルマーリーの事業の軸をなす大きなテーマである。便利で人も多い都会を離れ、お世辞にもアクセスがいいとはいえない小さな田舎町で事業を営むのはなぜなのか。そして渡邉さんの持つ経営哲学とはどのようなものか。著書の内容にも触れつつ、話を聞いた。

田舎で働く面白さ 菌から始まる地域内循環
――渡邉さんがタルマーリーで力を入れていることは何ですか?
うちの特徴は、里山の空気中から菌を採取して色んな農産物を発酵させることです。パンは小麦を、ビールは大麦を発酵させたものです。人工的に培養された菌を使わず昔ながらのやり方で培養するので、それに必要な条件として綺麗な自然環境があります。ずっと菌を採取し続けるために森と里山を綺麗にし、頂いた恵みを自然界に還元することに力を入れています。
――自然界に還元するとは具体的にどのようなことをしているのですか?
まずは経済的に還元するところから始めています。熱源を薪に変えて、たとえばオーブンは智頭の材木屋さんの端材をペレットにしたものを用いたペレットオーブンを使用しています。また、智頭の林業家から薪を買って薪ストーブの燃料にしています。個人としては微々たるものですが、取り組みを発信すると真似する人も増えてきて、これが広がるとそれなりの意味が出てくると考えています。
――林業をサポートしているのですね
林業と関わりを持つと水も空気も綺麗になります。里山から菌を採取するためには里山を綺麗にしてくれる林業家に対価を支払い経済的に循環させることが大事です。また、この辺りでは植林にも取り組んでいますが、鹿や猪が多く若い芽を食べてしまう。そこでカフェではジビエも食材として使います。いまは隣町の八頭町で取れた猪を使った猪バーガーを出しています。
――都市部から田舎に出て来られました。田舎で働く面白さはなんでしょうか
仕事中心の生活ですが、仕事の中に本気になれる遊びがあるので没頭することができます。自然と繋がった仕事は失敗も多い分飽きることがありません。そして自分の思想を活かした事業ができていることも魅力だと思います。たとえば地域内循環を目指したいというのも思想の一つです。都会では仕事と遊びは分断されがちですが、ここでは人生の時間全部が自分のものになったような実感があります。

思想を活かした事業を―。熱のこもった渡邉さんの言葉には揺らぎない信念や哲学のようなものを感じられた。ここからは渡邉さんが持つ貨幣観にも焦点を当てつつ話を進めたい。
腐る自然、腐らない不自然
――思想のお話もでましたので、本の内容にも触れつつ質問します。本のタイトルにもある「腐る経済」ですが、腐るという表現にはどのような意味が込められているのでしょうか?
実は30までろくに働かずに生きていたこともあり僕自身も腐っていました。ただ自然界において腐るということは有機物を土に返すことで、栄養分の分配を行い再生して循環するという仕組みに組み込まれています。物事を一歩離れてみると腐ることはそんなに悪いことではなく、持続可能という中に必ず入ってくる現象なのです。
――本の中では腐らないもの、として貨幣をあげています
腐る、あるいは発酵させて土に返すという行為から外れて腐らないものは何かというとまさしくお金です。ミヒャエル・エンデの言葉を借りると、お金は錬金術的に自己増殖します。その結果人は利益を追い求め、食品も洋服も安いものが好まれます。するとその過程で個人の技術は軽んじられ機械による大量生産に取って代わられます。するとみんながお小遣い制になり使える金額が限られてくるので生活費を下げようとします。マルクスが給料は生活費で決まると著書である資本論で述べているように、人々の生活はどんどん息苦しい物になります。
地方で事業を起こすには?仕事を与えられて生きている人へ
――私もスーパーでは安い食材を選んで買ってしまいます。資本主義、が問題なのでしょうか?
お小遣いが決まってるので安いものを選ぶのは仕方ないですね。何も崇高に生きろという話じゃなくて仕事を与えられて生きている人が多い現代の社会システムにも問題点があると思うのです。手仕事の価値を高め、下がり続ける食の値段を上げるにはマルクスの言葉はヒントになります。しかし共産主義がうまい手段とも思えません。大事なことは個々人が生産手段を取り戻すことです。本の中では小商いという言葉を使っています。
――小商いにはどういった可能性があるのでしょうか?
お金の使い道を投資に変えることができる、たとえ高くても意味のあるもの、巡り巡って自分の事業にも意味の有ることにお金を使えるのが事業主の強みです。今の日本で事業主と呼ばれる人は12%くらいしかいない。その他の会社からお金をもらっている人は投資というより消費になるのでこれじゃないとダメだという徹底感が少ない気がします。田舎で自然環境と一体化した小商いを作り、消費じゃなくて投資に向かうお金の使い方をみんなでしながら循環させていきたいです。
――田舎で事業を起こすために必要なことは何でしょうか?
まずは技術を磨くことです。自然から得て何百年も続いてきた技術、例えば宮大工の技術とかを身に付けるといいと思います。技術といってもレシピ通りのものではなく観察力を持って身に付け、自然界との繋がりを探しながら仕事を作り出すという時代がまた来るのではないかと思います。
――私の周りでも地方に対する関心が高い学生や、地方での就職を考えている学生が多くいます。そういった学生に伝えたい事があれば教えてください
急がば回れ、です。確かに地域は面白いけど地域にすぐ入って町おこしするのは農業で言うところの化学肥料のようなものです。町おこしの中心は崇高な理想でも、楽して儲けたい人が群がることもよくあります。誰も真似できない技をもった人が本来は町を創るべきでしょう。今の社会では目的持ったら最短距離を走りたがる人が多い。みんなが自分の時間を切り売りして労働力を売っているからまずは自分の時間を取り戻すことが重要です。取り戻すためには急がば回れ、ゆっくり技術を身に付ければいいと思います。

ミヒャエル・エンデ『モモ』から考えるお金の話
渡邉さんの話でも触れられた、ドイツの児童文学作家であるミヒャエル・エンデ。彼は、「お金を作り出し増やしていくのは錬金術のやり方と極めて似ている。錬金術は鉛から金を作りだそうとするが、ありふれたものに価値を与える点で、通貨を印刷し利子がそれを増やしていくという資本主義経済の考えに通ずる」と述べている。(『エンデの遺言』)
ミヒャエル・エンデと聞いて多くの人が思い出すのは、エンデの代表作である『モモ』だろう。本国ドイツだけでなく日本でも根強い人気があり発行から40年たった今もなお多くの人々を魅了し続ける。あらすじはこうだ。
ある町の円形劇場に住み着いた身寄りの無い少女モモ。モモには人の話にじっと耳を傾けるだけで、人々に自信を取り戻させるような不思議な力が備わっていた。貧しくとも心豊かに暮らす人々の前に、ある日「灰色の男たち」が現れる。「時間貯蓄銀行」から来た灰色の男たちは、時間を節約して、時間貯蓄銀行にその時間を預ければ、利子が利子を生んで人生の何十倍もの時間をもつことができると主張する。彼らの言葉に誘惑された街の人々は、時間を奪われ余裕のない生活に追い立てられていく。そして気がつくと人生の意味をも失っている。モモは盗まれた時間を取り戻すために、英知の象徴である不思議なカメ、カシオペイアとともに灰色の男との決死の戦いに挑む。
『モモ』は、忙しく働き続ける現代人に時間の本当の意味や豊かさとは何かを考えさせ、生き方を見つめ直すきっかけとなる物語である。しかし、エンデはある対談の中で以下のように述べている。
「じつは『モモ』の書評などで褒められてもひどく外面的表面的な理解しか示されてないと思うことはあるのです。(中略)。私としてはもう少し先のところまで言っているつもりなのです」(子安美和子著『エンデと語る』朝日新聞社)と。エンデの言う、「もう少し先のところ」とは一体何を指すのだろうか。
ドイツの経済学者ヴェルナー・オンケンは、エンデとの手紙のやり取りを通して、「モモ」の裏側に潜むテーマに確信を持ち「経済学者のための『モモ』入門」という論文を著した。オンケンはその中で、以下の様な論を展開した。
灰色の男たちは、不正な貨幣システムの受益者にすぎない。その貨幣システムは、本来、人間に備わっているものではなく、自然界の外にあって、貨幣を〈凍結〉させる機能をもつものである。(中略)。自然に適合した貨幣システムが実現して、灰色の金利生活者たちが利子を通じて人間から時間を盗むことができなくなってしまえば、彼らは、人間存在としてではなく、不正なシステムの受益者として、”安楽死”–ケインズ–を受け入れなければならない。(『経済学者のための『モモ』入門』 1999 Werner Onken 宮坂英一 訳)
自然の摂理に逆行するように増殖する貨幣。私たちは知らず知らずのうちに灰色の男たちの言いなりにはなっていないだろうか。もしくは私たち自身が灰色の男になっているのだとしたら…。
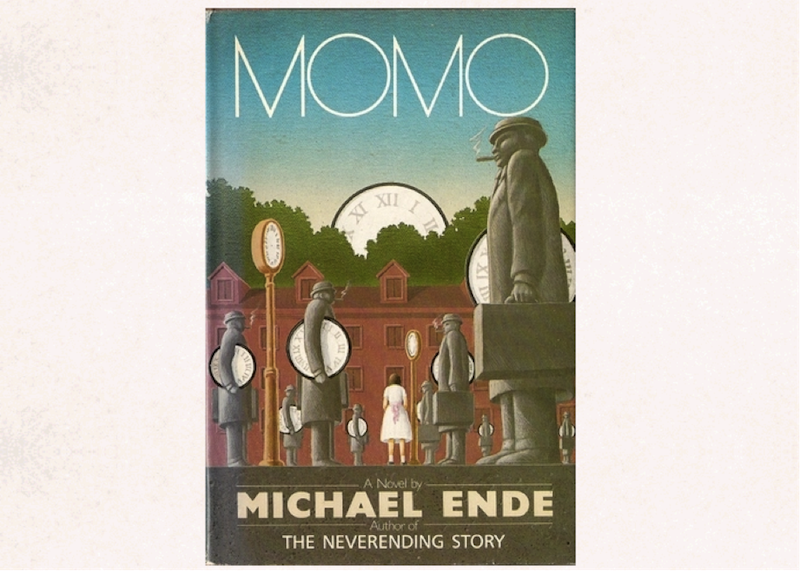
渡邉さんの目指す「腐る経済」とは何か
渡邉格さんは著書の中で私たちを取り巻く貨幣システムについて以下のように述べている。
時間による変化の摂理から外れたものがある。それが、おカネだ。おカネは、時間が経っても土へと還らない。いわば、永遠に「腐らない」。それどころか、投資によって得られる「利潤」や、おカネの貸し借り(金融)による利子によって、どこまでも増えていく性質さえある。これ、よく考えてみるとおかしくないだろうか? この「腐らない」おカネが、資本主義のおかしさをつくりだしているということが、僕がこの本で言いたいことの半分を占めている。(『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』 講談社 p74)
そんな渡邉さんがタルマーリーで挑戦し続けているのは、「菌」の声を聞き、菌が喜ぶような素材を選び、素材を活かしたパンやビールを作ることだ。そのような「菌の声」に基づく「菌本位制」のパン作りをするならば、安く大量に作るという「腐らない経済」とは決別し、「パンを正しく高く売る」必要がある、という。
それでは、私たちはどのようにすれば経済を「腐らせる」ことができるのだろうか。
渡邉さんは、毎日のおカネの使い方を見直すことも、経済を「腐らせる」一つの方法だという。自分たちが信じられる商品をつくり、サービスを提供する人に対して「正しく高く」おカネを使う。「利潤」をつくり出そうとするひとたちではなく、環境を整え、土を作るための仕事をしている人たちにおカネを使う。場が整い、「菌」が育てば、食べ物は発酵へと向かう。人も菌も作物も、生命が豊に育まれ、潜在能力が十二分に発揮される経済のかたちこそが、渡邉さんの目指す「腐る経済」なのだ。
革命は辺境の田舎町で、静かに動き始めているのかもしれない。
(文・取材 久野美菜子)
タルマーリー
営業時間 午前10時~午後4時 (定休日 火曜・水曜・木曜)
〒689-1451鳥取県八頭郡智頭町大字大背214番地1
電話 0858-71-0106
http://talmary.com/
〈参考文献〉
渡邉格 『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』(講談社 2013)
ミヒャエル・エンデ 『モモ』(岩波文庫 2005 )
河邑 厚徳 『エンデの遺言 ―根源からお金を問うこと』(講談社+α文庫 )