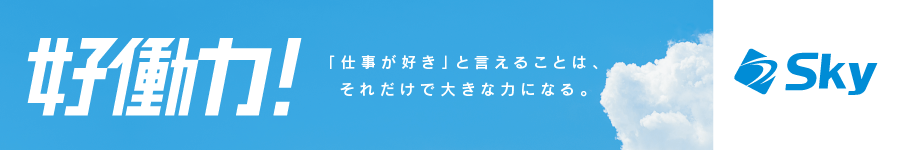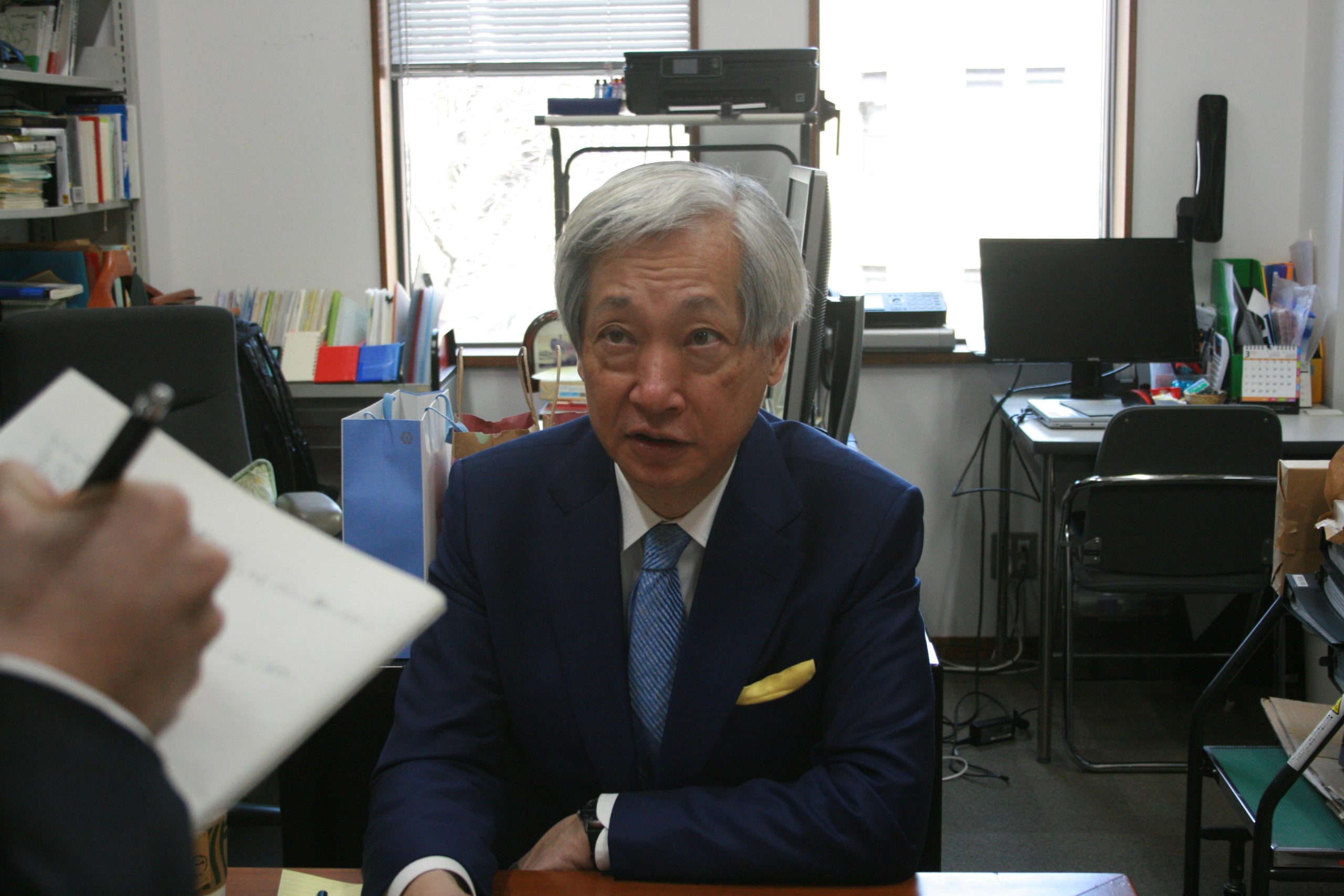東大で30年以上国際政治研究に携わり、東南アジアのナショナリズム、民主化から国際秩序に至るまで活発な議論を展開してきた藤原帰一教授のロングインタビューを2回に分けてお届けする。前編では、藤原教授に自身の学生生活や研究内容の展開、現地調査での経験などについて聞いた。
(取材・円光門、撮影・中井健太)
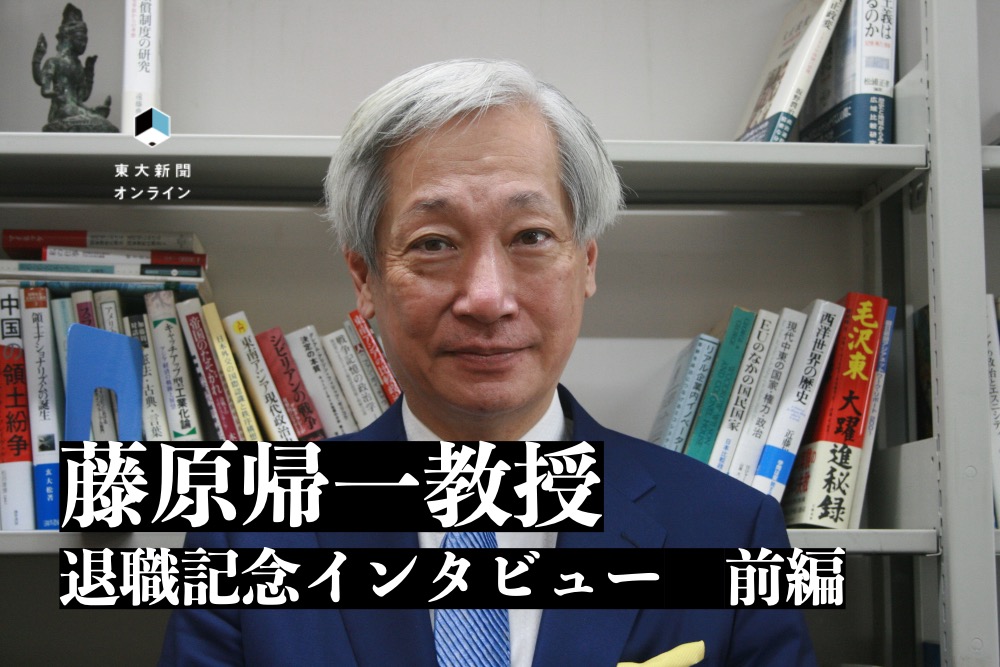
【インタビュー後編はこちら】
──1975年に東大に入学しました。入学直後はどのようなことに関心を持っていましたか
文科Ⅰ類に入学しましたが、最初は文学部への進学を考えていたんです。2年次にはアメリカ文学の大橋健三郎先生のゼミに参加させてもらっていました。
──法学部への進学を決めたのはなぜですか
あまり深く考えていませんでした。文化系では文Ⅰ、文Ⅰなら法学部に進学するという流れが当時は今以上に主流だったので、進学したんだと思います。お給料を稼ぐ仕事を見つけなくてはならない、そのために法律の勉強をしよう、くらいの判断でした。
──法学部の授業はどうでしたか
実際に民法や刑法などの授業を受けてみて、それなりに面白いとは思いましたけれど、「これを自分が職業にするのだろうか?」という疑問はあったんですよね。そんな中、3年の冬学期に履修した坂本義和先生の国際政治の授業が面白かったので、ゼミも取ってみることにしました。
─そのゼミを履修して学者になろうと思ったのですか
当時、学者は特殊な恵まれた環境にある人がなるものだと思っていましたから、そういうことはあまり考えていませんでしたが、大学院に進学しても必ずしも研究者になることはないと思ったので、進学について坂本先生のところに相談に行きました。すると先生は、君は研究者になりたいんですかと聞いてきたので、私は思わず、あ、はい、その研究者になりたいんです、と答えましたね。成績はと聞かれて成績表を見せたら、憮然とした顔をしていました。優は2/3以上はあったんですけど(笑)。
──就職する道も考えましたか
やはり、食べていけないのではないかという心配があったのと、皆就職活動していた時期に自分だけ何もしていないことに寂しさを感じていたというのがあって、朝日新聞の入社試験を受けました。合格したのですが、入社前の講習会で合格者と顔合わせをした時に、皆さん何というか、ちょうど東大に入学したての学生のような偉そうな喋り方をしていて、自分はこんなところにいられないなと思うようになったのです。その講習会の期間中に大学院の合格発表があったものですから、入社はお断りすることにしました。もっとも、大学院に入ったら同じように偉そうな人ばかりだったので、しまったと思いましたね。
──大学院ではどのような指導を受けましたか
研究は指導されるものではなく、自分でするものでした。先生のお手伝いをする場面はありましたが、ゼミ以外で「指導」と呼べるものを受けたのは、研究室に入った初日のご挨拶と、それからずっと先、修士論文の題目届を持って行った時の2回です。
初日にご挨拶に伺った時は、どういう授業を履修するか申し上げました。政治思想のゼミはあるかと先生が聞くので、佐々木毅先生がプラトンの授業を担当されますと答えると、先生は、それはいい、その授業を取りなさい。藤原君はちょっと早とちりする性格だから、じっくりと考える必要があるでしょう、と言うのです。
修士論文の題目届を持って行った日は、どういう論文を書くつもりか一生懸命説明したのですが、坂本先生はお忙しい方だったので次から次へと電話がかかってくるんですね。それで電話から戻ってきたら先生は一言、うん、書いてみるまで分からないね、と。私は、あ、これは落とす気だなと確信したので、そこから根性が据わって論文を書くことができました。
──修士論文ではアメリカ統治期のフィリピンにおいてモロ民族が創造される過程を研究しました。どのようにしてこの研究テーマに至ったのですか
今も相変わらずそうなんですが、当時の自分にとって一番よく分からなかったのがナショナリズムの問題でした。「ネーション(民族・国民)とは何か? 」「ネーションというアイデンティティは存在するのか?」「なぜネーションは武力衝突を引き起こすのか? 」という疑問だらけの状況だったのです。そんな中、ちょうどフィリピンでイスラム教徒とキリスト教徒の対立が広がり、モロ民族解放戦線のラディカルな武力路線が展開されていたので、それを調べ始めました。でも調べて調べても「モロ」とは何かということが全然見えてこない。それで「モロ」というアイデンティティが形成される過程に着目することにしたのです。
──ナショナリズムという問題に関心を持ったのはなぜですか
私は元々アメリカからの帰国子女で、アメリカに住んでいた時も日本に帰国してからも、周囲から違う人という目で見られていました。日本って何? という、その時に抱いたアイデンティティへの疑問がナショナリズム研究につながったのだと思います。
──修士課程修了後、82年から留学します。留学先に米イエール大学を選んだのはなぜですか
当時、東南アジアについて面白い研究をしているアメリカの政治学者は2人いました。一人はコーネル大学のベネディクト・アンダーソン、もう一人がイェール大学のジェームズ・スコットです。コーネル大学には他にも著名な政治学者が大変多く集まっていましたし、イェール大学は更にすごくて、ロバート・ダールやホアン・リンス、アルフレッド・ステパンがいる。現代のアテネのような場所でした。
この2校に絞って出願したところ、2校とも合格して、フルブライト奨学金もいただくことができたので、どっちにしようかなと迷っていました。それで、先輩の先生にご相談したら、そんなのコーネルに決まっているじゃないかとおっしゃったので、つむじを曲げてイェール大学を選びましたね。
──イェール大学では主にどのような研究を行いましたか
私は当初、フィリピンのマルコス政権における戒厳令の施行と韓国の維新体制の成立──どちらも72年の出来事ですが──という事例を取り上げて、脆弱な民主主義体制が崩壊し権威主義体制へと移行する条件について考察するといういかにも博士論文らしい研究計画をイエール大学に提出していました。ところがこれには問題がありました。民主主義体制の崩壊に関しては当時すでに研究がかなり進んでいましたし、今度は逆の問題設定、すなわちラテンアメリカの軍政崩壊の事例をベースにした権威主義体制の崩壊に関する研究が盛んになっていったという時期だったのです。しかも、フィリピンでもマルコス政権の崩壊がそろそろ起こるのではないかという動きが実際に出てきました。
──その矢先、83年にベニグノ・アキノ議員が暗殺されます
当時のマスメディアは、アキノが暗殺されたからマルコス政権の崩壊は時間の問題だろうということを言っていました。私は、いやいや、そうはならないだろう。これだから素人は困るといった昂然(こうぜん)たる態度をとっていたのですが、現地調査に行った時に私が目にしたのは、それまでのフィリピンとは全く違う光景でした。空港の入国審査官が私に向かって”Please tell the world what is happening in our country”(わが国で起こっていることを世界に伝えてもらいたい)と言うのです。頭がおかしくなったのかと思いましたね。何というか、フィリピンの人たちが皆ハイになっているようでした。
これが、私が初めて見た、権威主義体制が崩壊し民主化が実現していく光景でした。衝撃を受けました。私がそれまで書こうとしていたのはいかにも博士論文らしい形になっているのだけれど、それよりもずっと面白いことが今起こっている、でもどう捉えたら良いのか分からない、という状況でした。
ですから、論文のテーマをがらりと変えてしまったわけです。これまでとは真逆の、民主主義体制の成立、つまり権威主義体制の崩壊の方に軸足を移しました。書き上げるまで随分と時間がかかったので、最終的にはイェール大学の博士論文としてではなく、当時の所属先であった東大社会科学研究所の助手論文として提出することになりました。自信作ではないですが、やって良かったなと思っています。
──現地調査でのインタビューを基にした論文を多く書いてきましたが、インタビューの技法はどのようにして習得しましたか
体系的に習得することがなかったので、本当に手探りでしたね。最初はそもそもどのような人にインタビューしたらよいのか分からないという状況だったので、現地のジャーナリストやアジア経済研究所の研究員、商社の駐在員などからお話を伺って、インタビュー候補者をリストアップするという作業から始めました。それから候補者に丁寧な手紙を送って、電話でフォローしました。自分は信頼できる人だという安心感を相手に与えなくていけないからです。
インタビューをさせていただけることになっても、次に問題となるのは、本人が本当のことや大事なことを話すとは限らないということです。相手が明らかに間違ったことを言っている時に、それを指摘して喧嘩になるのはアウトですが、私はこれをやってしまったことがあります。そうすると相手はもう黙ってしまってインタビューが成り立たなくなってしまうのですね。友好的に接しながら求めている情報を相手から引き出すというのは本当に難しいことなのです。
──東大社会科学研究所の助手になるちょうど1年前の83年に、後のナショナリズム研究に大きな影響を与えたベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』が刊行されました。この著作についてはどう思いましたか
ショックでした。自分が細々とやってきた問題について、予想しなかったほどの幅の広さと深さでナショナリズムについて表現が与えられていたのです。驚いたし、ジェラシーも感じましたね。こういう人がいるんだったら、僕が学者なんかする意味ないや、というくらいの気持ちになりました。
当時日本では、ナショナリズムは古臭い研究テーマだと考えられていたんです。ナショナリズムについて私が報告するたびに、そんな古いことばかりやっていたら就職できないというリアクションだったんです。ですから、日本では『想像の共同体』に対する反応は初期の頃は肯定的なものではありませんでした。ただ、結果的にはその後の議論をひっくり返すような、大きな変化を呼び起こしたのだと思います。
──民主化研究やナショナリズム研究のようないわゆる比較政治に留まらず、国際政治に関する議論も多く展開していますが、比較政治と国際政治の関係についてどう考えますか
私自身「比較政治と国際政治を区別することに意味はない」と常々言い続けてきました。とはいえ、あるディシプリンが作られると、そのディシプリンの中の研究を踏まえて研究をするのでなければ、そもそもジャーナルには載りません。ですから学際や領域横断が必要なんだという一般論を実践するのはとても難しいことなんですね。
個人的には、国際政治と比較政治が分かれてしまえば学問研究が痩せてしまうと思いますし、さらに言えば、比較政治と地域研究の境界線も正当なものだと思わないです。一番重要なのは、考える問いがあるかどうかということに尽きるのであって、その問いに対してプロフェッショナルなアプローチをとらなければならないということですから。ただ、建前としては皆さん同意されるのですが、実際に研究活動でそうした境界の横断を進めようとするのはなかなか困難だと思います。
【インタビュー後編はこちら】