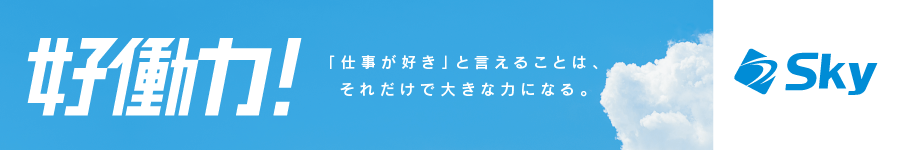本記事では、2020年に没後50年を迎え、近年その著作が再び評価されているところの三島由紀夫、特に三島文学の金字塔である遺作『豊饒(ほうじょう)の海』四部作について、4回に分けて語る。第2回の今回は『豊饒の海』第二作『奔馬(ほんば)』。第一作『春の雪』において、松枝清顕(まつがえきよあき)は死んだ。本多に「今、夢を見ていた。又、会うぜ。きっと会う。滝の下で」と言い残して。
『豊饒の海』第二作『奔馬』
『奔馬』は、清顕の死後18年が過ぎた昭和7年の東京が舞台である。本多は38歳になり、青年時代の理屈っぽい性格が表れたかのように、彼は裁判所で判事を務めている。ある日、本多は来賓として招聘(しょうへい)された剣道の試合で、剣の名手で無骨な肉体美を持つ、18歳の飯沼勲という青年に出会う。実は彼は、かつて松枝家の書生であり清顕の教育係でもあった飯沼茂之の息子であった。
その後、本多は高宮神社の麓にある滝の下で、勲と偶然再会する。そこで本多は、勲の脇腹にある3連のほくろを目撃する。そうして彼は、勲こそが清顕の生まれ変わりであると直感するのである。
勲は、昭和初期の日本下層社会の疲弊を案じ、それをもたらした政財界の腐敗に怒っていた。明治初期、日本の西洋化と武士階級の没落による「日本精神」の衰退を憂いた、尊王攘夷派武士の反乱である「神風連(しんぷうれん)の乱」に、勲は心酔していたのである。
神風連の思想や行動を特徴づけるのは、その純粋性であった。神意を見極める「宇気比(うけい)」と呼ばれる占いを絶対視し、例え現実に勝ち目がない状況でも、宇気比の神意が反乱を命ずれば、それを覆そうとはしなかった。また、舶来物である電線の下をくぐり抜けることはせず、反乱においても鉄砲を持つ政府軍に対して、日本刀のみで戦った。当然ながら反乱は完膚なきまでに失敗し、生き残った者もみな自刃した。
勲はこのような神風連の純粋性をもって、金権に冒された日本を浄化する反乱を起こそうと、友人と政治結社を結成した。彼は純粋な動機と行動を欲した。反乱が成功し、自らが金や名誉欲にまみれた汚い権力者となるよりは、むしろ反乱が失敗し、自らの行動と思想が汚れぬまま自刃することを欲したのである。
しかし、彼は父親の主宰する右翼政治結社にも財界との癒着があることを知り、大きく失望する。また、勲が協力を請うた「志士」とされている軍人らも、実は信念より自己保身に走る俗物であった。そのような中でも、清顕を通じて父茂之と親交があり、勲とも文通をしていた本多に対しては、勲は一片の純粋性を嗅ぎとるのであった。俗世の我欲や保身から超越した、純粋性を。
勲らは蔵原武介(ぶすけ)や新河亨(とおる)をはじめとする政財界要人の暗殺計画を引き続き練っていたが、突然の密告により計画はついえてしまう。勲は逮捕され、本多が裁判官を辞職して弁護を請け負うことになった。勲が暗殺しようとしていた政財界の要人、とは、実は父茂之が金銭援助を受けている人物であり、計画を密告したのは他ならぬ茂之だった。本多らの尽力と世論の同情により、勲は刑を免除される。しかし純粋な行為を欲していた彼は、小手先の弁護で自らの崇高な目的と純粋性が汚されたと感じ、かえって鬱屈(うっくつ)としてしまう。そのような失意の中、家に帰り酒に酔った勲は寝言を言う。「ずっと南だ。ずっと暑い。……南の国の薔薇の光りの中で。……」
その後、勲は単身で蔵原武介の暗殺を決意する。蔵原の神道を愚弄(ぐろう)するような姿勢を、やはり見過ごすことができなかったのである。彼は蔵原の別荘に侵入し、短刀で殺害を遂げる。辛うじて現場から逃げた勲は、追手が迫る中、夜の海の崖で自刃する。
彼の思い描いていた理想、すなわち、日の出の断崖の上で、昇る日輪と輝く海を見ながら、気高い松の木のもとで自刃すること、それは叶わなかった。しかし、勲が刀を腹へ突き立てたその瞬間、日輪は彼のまぶたの裏に昇ったのであった──。
本作では、前作で挙げられた「禁を犯す優雅」「死」に加え、三島文学における美の側面がもう一つ出てくる。すなわち「純粋性」である。勲は本多が直感した通り、清顕の生まれ変わりであり、前作中において清顕が付けていた夢日記の内容と、今作中における勲の行動が一致したことからも、それは証明された。清顕が聡子への全霊の愛の中死んだように、清顕の生まれ変わりは日本と天皇への全霊の愛の中死んだのである。しかし、清顕には顕著に現れなかった「純粋性」という美が、勲には現れている。勲にとって真に重要であるのは、ある政治体制の実現なぞではなく、純粋性のなかで美しく生き、美しく死ぬことなのである。
そしてここにも、勲の思想の裏に、三島の哲学が透けて見える。三島が市ヶ谷駐屯地で総監を人質に立てこもり、バルコニーでの演説の後に自刃した「三島事件」については、彼の行動を滑稽だと冷笑する人が多い。今年死去した石原慎太郎も、まさにその例である。しかし、三島と勲が同様の思想を持っていたとしたらどうだろうか。三島は、野次馬の自衛隊員らに対して自衛隊建軍の本義や憲法改正、自衛隊によるクーデターなどを説いた。ところが、神風連の精神に敬意を払ってマイクを用いなかった彼の声はほとんど届かず、さらにその演説は現場の自衛隊員の罵声にかき消された。しかしながら、それでよかったのである。あの理智的で論理的な三島が、自衛隊によるクーデターを実現できると妄信していたはずがない。彼は、理屈をこねるが何も行動せず、人生の所々で遭遇する圧倒的な美の瞬間を、指をくわえて見ているしかない醜い男、つまり本多のように老いていきたくなかったのだろう。純粋性のうちに美しく死ぬという三島の絶対的な理想において、決起の成否や後世の「理屈上手」な老人の誹(そし)りはどうでもよかったのである。
総監室の片隅で、自らの腹に刀を突き立てた三島由紀夫──そのまぶたの裏には、きっと赤々とした日輪が昇っていたはずだ。【三】
【連載】
【関連記事】